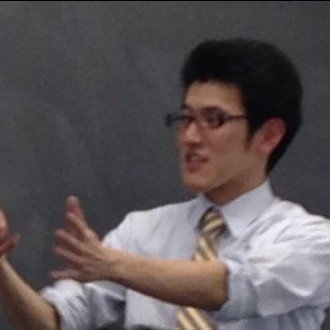記事一覧
企業とサステナビリティー:トリプルボトムライン
持続可能な開発に関する社会的要請が高まるにつれ、企業はサステナビリティーに関する活動をビジネスに統合するようになった。その中で、特に特徴的なのはコンサルタントであるElkington (1997) によって提示されたトリプルボトムラインという考え方であろう。
彼は、利益という財務上のボトムラインにのみに焦点を当ててきた事業のスタイルから、経済ボトムライン(経済性)、社会ボトムライン(社会性)・環
持続可能な開発の歴史的流れ(1990年代から現在)
1990年代に入ると、1987年に提唱された「持続可能な開発」を踏まえた国際会議が開かれるようになる。1992年に環境と開発に関する国際連合会議(UNECD、通称地球サミット)がブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された。
この会議において、持続可能な開発に向けた新しいグローバル・パートナーシップ構築を目的とする「環境と開発に関するリオ宣言 」と、その実現に向けた「アジェンダ21 」、「生物多様
持続可能な開発の歴史的流れ(1960-1980年代まで)
持続可能な開発の起源をたどるとするならば、Malthus (1798/2008) の人口論にまでさかのぼることができるが、持続可能性に関する大きな動きが生まれたのは、Carson (1962) が「沈黙の春」を出版してからといえる。
彼女はDDT が環境に悪影響を与えることを説き、環境保護の思想に大きな影響を与えた。この頃の日本は、いわゆる四大公害病が表面化してきた時期であり、1967年に公害対
持続可能な開発とは何か
人類は従来のままの経済成長を続けることができるのであろうか、あるいはそれを目指して良いのであろうか。経済成長は、環境問題や社会問題を多く引き起こしてきた。とりわけ、先進国と発展途上国との間の経済格差は大きく広がり、従来の経済モデルが正しいものであったのかは見直す必要が出てきている。
このような従来の価値観に対する疑問から生まれたのが、「持続可能な開発」という考えである。持続可能な開発とは「将来世
SDGsフォーラムに参加してきた:須藤先生の講演
ビーコンプラザで行われたSDGsフォーラムというものに参加してきた。
主催は公益社団法人日本青年会議所九州地区大分ブロック協議会。
ドクター論文がコーポレート・サステナビリティーをテーマにしたもので持続可能な開発にはもともと興味があったこと、そしてAPUの須藤先生が公演されるということで楽しみにしていた。
SDGsとは、持続可能な開発目標 (Sustainable Development G
非倫理的な行動と心理学の実験:スタンフォード大学監獄実験
二つ目の心理実験は1971年にスタンフォード大学で行われた実験である (Haney et al. 1973; Zimbardo 2007)。この実験を行うにあたり、スタンフォード大学の地下に実験のための刑務所が作られた。
実験の目的は、看守と受刑者の間に生じる心理的効果を観察することで、刑務所という空間においてこの制度が行動に与える影響をまとめることである、とされていた。
実験の参加者は新聞広
非倫理的な行動と心理学の実験:ミルグラム実験
ここでは、非倫理的な行動の研究として最も有名な心理学の実験を紹介する。一つ目の実験はアメリカのイエール大学の心理学者、スタンリー・ミルグラムによる実験である (Milgram 1974; Milgram 1963)。この実験は人が他者に服従してしまうメカニズムを解明しようと試みたものである。具体的な実験手順は以下の通りである。
この実験は、教師役、生徒役、実験監督者の3名によって進められる。まず
腐った樽:倫理的意思決定に影響を与える状況要因
人が倫理的意思決定をするか否かは個人要因のみに依存しているわけではない。むしろ、素晴らしい人であっても状況によっては非倫理的な行動を起こす可能性もある。すなわちその人が置かれていた状況が非倫理的な行動を促す(腐った樽)、ということである。よって、ここではこうした状況要因を整理する。
第一の状況要因は倫理的風土 (Ethical Climate) である。倫理的風土とは、何が受け入れられ、何が受け
企業の社会的パフォーマンスと財務パフォーマンスの因果関係
最後に、企業の社会的パフォーマンス (CSP) と財務パフォーマンス (CFP) の因果関係について説明する。
二つの変数の間に相関が認められたからと言って、それが因果関係を示すということにはならない。つまり、CSPとCFPが正の相関をしていたとしても、CSPが原因となってCFPに影響を及ぼす、という論理を導き出すことは難しい。
このような因果関係を説明するためには、1. 二つの変数間の関係が
企業の社会的パフォーマンス
企業が社会的責任の原則に基づいて社会的即応性のプロセスに基づいて行動した結果を、企業の社会的パフォーマンス (Corporate Social Performance, CSP)と呼ぶ。
Wood (2010) はCSPを大きく三つに分けている。一つは人々や組織への効果である。すなわち、企業が社会からの期待に応えることによって、人々の生活や自らの組織に対してどのような影響を及ぼしたのか、という視
企業の社会的即応戦略とそのプロセス
企業の社会的責任に関しては、主として規範的側面から従来議論されてきた。すなわち、企業はどのような存在であるべきなのか、企業は株主の利潤の最大化のみを考慮すればよいのか、といった点である。しかし、こうした議論は実際の企業の行動に対するインプリケーションが乏しかったといえる。すなわち、どのような時に企業は社会的責任を果たすような行動をとるのか、ということが明らかになっていないのである。こうした反省を受
もっとみる他のアジアの国々のCSR(中国及びインド)
中国においてCSRが注目されるようになったきっかけとして、胡錦涛政権における「和諧社会」の実現というスローガンが掲げられたことがあげられる。和諧社会とは、調和のとれた社会を意味し、江沢民時代の経済成長の代償としての不平等や格差を是正する、ということが目指された。とりわけ、和諧社会の実現のために (1) 都市と地方のより親密な関係を築くこと、(2) 省エネルギーと環境に対する意識を持つこと、(3)
もっとみる