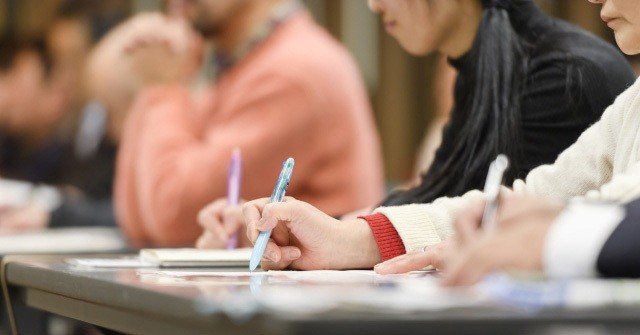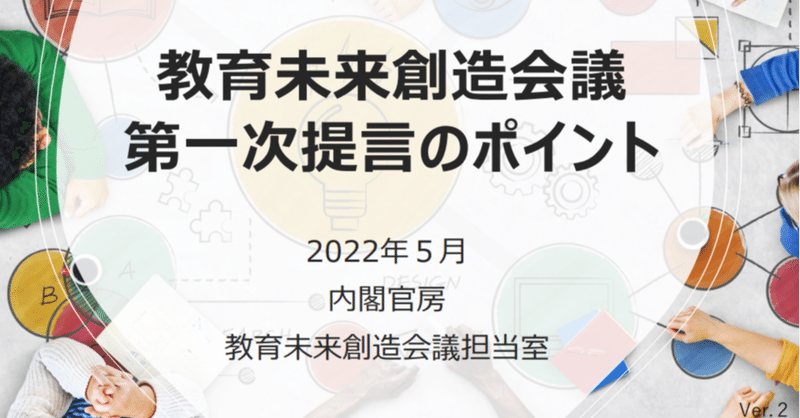#大学改革
大学のリカレント教育に残された道はこれしかない。徹底的に個人に寄り添った”学び直し”について考える。
最近、教育未来創造会議の第一次提言について詳しく内容を聞く機会がありました。このなかで「学び直し(リカレント教育)を促進するための環境整備」が、大きなテーマとして挙がっていたこともあり、リカレント教育について改めて考えてみて、何となく自分のなかで整理ができたので、一度まとめてみたいと思います。
まず、本提言でも言及されているのですが、日本人は諸外国に比べて「日本の企業は学ぶ機会を与えず、個人も学
大学にとって起死回生のきっかけになる!? アフターコロナに生まれるだろう、大学と学びの新常識を考える。
新型コロナの蔓延によって、急速にオンライン学習が普及しはじめています。大げさでも何でもなく、おそらく現在、人類が誕生して以来、最も多くの人がオンライン学習をやっているのではないでしょうか。大学に関していうと、オンライン授業用にコンテンツをつくるだけでなく、学生たちが受けられるように資金や機器の援助にまで取り組んでいます。
この一連の出来事は一過性のものなのか、それとも今後も続く変化のきっかけなの
これからのホームカミングデーはウェブ開催!?今こそ大学と卒業生との関わり方を変えるときだと思う。
前回、関西学院大学の卒業式特設サイトが教育機関の心意気を感じて良かったという記事をまとめました。調べてみると、ほぼ同じタイミングで(卒業式だから当たり前ですが…)、いくつも魅力的な卒業式特設サイトがありました。これらサイトを見ながら思ったのですが、もしかしたら、今回のタイミングは、大学と卒業生との関わり方を変える絶好のタイミングになるかもしれません。今回は、これについて書いてみます。
大学と卒業
埼玉の取り組みに学ぶ、大学の授業という“源泉掛け流し”の知的コンテンツを、どう有効活用するか。
大学とは、見ようによっては授業という名のコンテンツの集合体と捉えることもできます。そして、そうであるなら、このコンテンツの質をいかにして上げるか、また有効に活用するかが、大学の存在意義や価値と直結しているといっても、そう間違っていないのではないでしょうか。
今回は、この授業の有効活用法で面白い取り組みを見つけたので、それについて取り上げたいと思います。まずはどんな取り組みなのか、記事をご覧くださ
大学の在り方を根本から変える! 大学4年間を“学び続けるための最初の4年間”だと捉え直す。
大学関連の仕事をしているとリカレント教育の重要性が年々高まっているのを感じます。18歳人口が減る大学にとって、社会人学生は新たな財源になるし、国はできるだけ多くの人に効率よく働いてもらいたい。人材が流動化し、実力主義になってきている世の風潮とも合致している。すべての思惑が合っているんだから、そりゃあ重要だと、みんなが言うのも頷けます。
でも、これだけ求められているのに、リカレント教育が盛り上がっ