
ヤドカリ放浪記2013〜焼山寺-もみじ川温泉編〜
11月5日
AM3:54
道の駅温泉の里神山

なんか知らんけど前日より更に早く目覚めた寅の刻の夜明け前
星が綺麗だ
この日、訪れる予定の寺をナビに入力してルート作成
ちょいとマッタリして五時前に行動開始です
AM5:12
焼山寺

本尊は虚空蔵菩薩の四国霊場第十二番礼所
弘法大師開基の寺なり
その昔、この山一帯は毒蛇の棲む魔域で暫し悪行を災いなし付近の人々を虐げていた
大師は魔境こそ仏法鎮護の霊域であると摩廬山に登った
大師の開創を恐れた魔物達は山を火焔として聖者の行を阻み妨げたが大師は恐れず印を結んで敢然と登り続けると業火はみるみる消え衰え大師の法力により天変地異を絶ち楽土として甦った
そこで山中に一宇を建立して焼け山の寺と名付けた
故に山号を摩廬山と呼ぶ
摩廬とは梵語で水輪を意味し火伏せに因んだ山号である
今も尚、山上に毒蛇を封印したと伝わる岩窟があり、その岩頭に三面大黒天を刻んで建立したと伝えられる
現在三面大黒天は寺内故に安置され日本三体の一つとしてその霊験は遠近に聞こえる
境内には国主・蜂須賀より寄進の霊鐘があり国家鎮護の為、勅願の御綸旨を下し、寺宝として保存されている
これより一km登れば奥之院に至り、護摩壇や求聞持の窟・せり割り岩・閼伽の水・五葉の丸・杖立の峰など弘法大師ゆかりの遺跡・名勝が観られる
そんな寺に闇の中訪れるとまずは不動明王の下から湧く水で喉を潤す
更に別の不動明王像と慈母観音菩薩像・涅槃釈迦如来等十三仏が出迎えてくれる
とりあえず夜が明けるのを待ってから参拝
AM6:39
杖杉庵

本尊は地蔵菩薩の四国八十八箇所霊場番外札所
遍路の元祖とされる伊予国浮穴郡荏原の長者・衛門三郎が弘法大師に逢う為に逆順で四国を二十一周する
そしてついにこの地で力尽いたその時、弘法大師が現れ、衛門三郎の今生における悪業の果報が尽きたので来世の望みを言うように語りかけ、衛門三郎は「来世は国守に生まれ善政を施したい」と願った
弘法大師は小石に衛門三郎再生と書いて左手に握らせると衛門三郎は笑って亡くなったという…
弘法大師は衛門三郎の亡骸を埋め墓標として形見の杉の杖を建てる
するとその杖は根付いて大杉となった
これに因んで杖杉庵と称する
AM6:53
サンクス徳島神山町店

流石はお遍路上にあるコンビニ
弁当の数半端ありません
サンドとピルクル購入して朝食にする
AM7:05
雨乞の滝入口

雨乞の滝まで800m
途中に何ヵ所か滝があるらしい
物凄く美しくて綺麗な渓谷を眺めながら急坂を登る
AM7:08
うぐいす滝

駐車場から徒歩二分で観れる素晴らしい滝
次の滝に向かうまで大小数々の名も無き滝が楽しめる♪

AM7:17
不動滝


その名に恥じぬ豪快な滝
滝上に岩で囲った祠があったから不動明王を祀ってるかと思ったらタヌキの置物が祀られていていた

何故?
AM7:22
地獄淵
駐車場から雨乞の滝の中間地点
さほど地獄と言うほどでもない
転けた
AM7:25
もみじ滝

大きな岩で遮られているが恐らく5mほどのこの滝
AM7:28
観音滝

不動滝にも勝る豪快な滝
滝壺が綺麗♪
AM7:30
雨乞の滝

日本の滝百選に選ばれている他、四国のみずべ88カ所・とくしま88景・とくしま水紀行50選等にも選ばれている名瀑
雄滝と雌滝の二つの滝からなる夫婦滝で雌滝の方が豪快且つ迫力のある滝
落差は45mあり三段に分かれて流れ落ちる
一方、雄滝は落差27mの直下型
悪くないが嫁滝が凄すぎる
なので嫁滝に打たれる


凄いパンチ力!!
最高に気持ちヨカでした♪
AM8:27
大日寺

鮎喰川の畔に建つ第十三番礼所
本尊は十一面観世音菩薩
弘法大師が大師ヶ森で護摩修法をしていると空中に大日如来が現れ、一宇建立のお告げを受けた為、大日如来の姿を刻んで本尊とし寺名もこれに因んでいる
ところが後に一宮神社の別当寺になった為、一宮寺とも呼ばれ栄える様になる
本堂は天正年間に焼失
現在の堂宇は明治期に再建
明治の神仏分離により一宮神社に納められていた十一面観世音菩薩がこの寺に移され本尊となる
元々の本尊であった大日如来は脇侍仏として祀られている
AM8:32
一宮神社

阿波國一之宮なりし神社
祭神に大宜都比売命・天石門別八倉比売命を祀っている
神仏分離令が下される迄は十三番札所の大日寺と一体化していた
空気の澄んだ静かな神社だ
AM8:35
一宮城址

徳島県内で最大級の山城
本丸は北城に属し明神丸等の曲輪は南城に属した
山麓には居館があったと言われている城
現在は東山渓自然公園とある
勿論散策する
AM8:38
経筒出土地

明治40年、北側斜面下の神宮寺跡を開墾中に12世紀頃のものと思われる銅製の経筒が出土
釈迦入滅後、仏教の教えは次第に衰え日本では1052年より末法の時代に入ったとされ将来弥勒仏が現れる時まで有り難いお経を残そうと筒に入れて理納したものだとか…
AM8:44
竪堀

斜面に縦に造られた堀
あまり堀とは気付かない(´・ω・`)
AM8:45
曲輪

原っぱ
本丸まで残り三百m
AM8:46
湧水

本丸まで残り二百mの地点に湧く湧き水
城の周辺では所々に小さな湧き水が見られる
この湧水は最近のものらしい
AM8:49
堀切

上の明神丸から続く尾根を鉈で切った様に切り崩し造られた
堀切によって才蔵丸は孤立した曲輪となっていた
AM8:51
虎口

城郭や陣営などの最も要所にある出入り口
AM8:52
展望台

一宮市一望
鮎喰川も見える
正面にはさだまさしの小説の舞台にもなった眉山も一望
うん、見晴らしは良いが本丸跡ではないな
少し体力回復♪
本丸まで目指すとまた竪堀があり、門跡に出る
AM8:56
明神丸

標高140.9mに位置する二の丸にあたる曲輪
本丸との高低差は3.4mで本丸より明神丸が東北にあることから眺望がよい
此処からも徳島市一望
鮎喰川も淡路島も一望…
さっきの見晴らし台と同じ景色だな
井戸があった
AM8:59
帯曲輪

曲輪の側面や城の周りを帯状に細長く囲んだ曲輪
本丸と明神丸を結び城を守る大切な要所となっている
AM9:00
本丸跡

1338年小笠原宮内大輔長宗によって構築
城主は小笠原・一宮・長曽我部を経て蜂須賀至鎮に渡る
1615年一国一城令により廃城
天然の地形を利用したのみならず構造もすこぶる精巧堅固で阿波の名城の一つに数えられている
AM9:08
釜床跡

城の炊事場跡
北の斜面は石垣で築かれ本丸下の釜床には石組が一基残っていたが以前は数基並んでいたらしい
AM9:16
蔭滝

上手の貯水池から流れ落ちる細く緩やかな滝
貯水池は周囲の曲輪とこの岩壁によって固に守られていた
採石場の跡でもあったらしい
AM9:35
常楽寺

釈迦入滅後この世に現れ群衆を救済すると言われている菩薩弥勒菩薩が本尊の第十四番礼所
四国霊場で唯一の未来仏
弘法大師がこの地で修行をしてると弥勒菩薩が多くの菩薩と共に現れ説法を行った為、大師がその姿を霊木に刻み堂宇を建立し本尊として祀る
岩肌剥き出しの境内が素敵♪
神木の上に南無大師遍照金剛が祀られていているのが可愛い
AM9:50
国分寺

第十五番礼所で本尊は薬師如来
阿波国分寺跡
国分寺とは741年の聖武天皇の勅旨により尼寺と共に全国に建立された官立寺院
阿波国分寺跡は1978年以降の発掘調査で金堂から延びると想定される回廊跡や築地跡・寺域を画する溝などが確認された事から、かつては西に塔を配置し金堂・講堂などが一直線に並ぶ東大寺式伽藍配置を有し現・国分寺を中心とした方二町におよぶ範囲に存在していたと考えられる
現在境内の隅に残る塔心礎は寺の南西、塔ノ本が字名が残る水田の中から出土したと伝えられ東門・西門・北門・坊等の字名が現在も残っている
出土遺物の一部は徳島市立考古資料館で収蔵・公開されている
AM10:07
坂東商店
酒・煙草etc…
蜜柑が一袋百円だったので購入〜♪
甘くて旨ぇ〜
AM10:12
慈眼寺

第十四番礼所・常楽寺奥之院
常楽寺の寺領に位置し、本堂には十一面観世音菩薩を御本尊とし、脇仏に弁財天・昆沙門天を安置している
本堂の東側に生木地蔵尊のお堂がある
そんな奥ばった場所にはなくて楽にお参り出来る
AM10:24
観音寺

第十六番礼所で本尊は十一面観世音菩薩
左右に寄進者の名を刻んだ石柱が並ぶ町中の寺
山門を潜ると目の前に本堂があり、その右手に大師堂が建つ小さな寺
縁起によれば聖武天皇の勅願によって開基されたと伝わる
その後、816年に弘法大師がこの地を訪れ等身大の千手観世音菩薩を刻んで本尊とする
更に鎮護国家の為に毘沙門天と悪魔降伏の意を込めて不動明王を刻み脇侍として安置したと言われる
16世紀後半、長宗我部勢の兵火により寺は全焼…
いい加減にしろよ長宗我部って感じだ
以降衰退の一途を辿っていた江戸時代初期に藩主蜂須賀の支援で再建した
AM10:40
井戸寺

第十七番礼所
本堂の中央には本尊の薬師如来が鎮座する
その左右に三体ずつ少しポーズの違う薬師如来が鎮座する

合わせて七体が本尊として七仏薬師如来と呼ばれ鎮座している珍しい寺
元は妙照寺と呼ばれ天武天皇の勅願道場として開基
弘法大師が刻んだというカヤの一木造の六尺余りの十一面観世音菩薩等を安置
水不足に苦労する村人を哀れみ大師が錫杖で一夜のうちに掘ったという伝説の面影の井戸ある
水に映った自身の姿を石に刻んだ日限大師も祀られている
また井戸を覗いて自分の姿が映らなかったら死ぬらしい
更に霊水を汲ませてもらえるらしくたまたま持っていたステンレスボトルに汲む
境内に黒猫が居て癒される斜面に縦に造られた
やっぱ猫良いわ♪
AM11:14
徳島城址

1585年豊臣秀吉の四国平定の大功により阿波一国を賜り、1586年に一宮城から吉野川河口付近の中洲に位置する標高61mの渭山に築城した渭津城を修築して徳島城とし藩政の中心地とした城
山頂の本丸や東二の丸・西二の丸・西三の丸からなる詰の城部分と本丸御殿が置かれた麓の御屋敷と呼ばれていた部分からなる戦国時代を思わせる縄張りであった
城山に築かれた山城と城山の周囲の平城からなる連郭式の平山城
日本百名城の一つである
現在は徳島中央公園として整備されている
AM11:16
舌石

水路沿いの石垣面から突き出ている石
屏風折塀の支柱石で塀の一部を屏風の様に折り曲げて堀川の方向に突き出させたもので、この折塀に鉄砲や矢を撃つ為の穴を設ける事で正面のみならず側面方向への攻撃が可能となり城の防御性を高めていた
旧寺島川沿いには約32m間隔で六個の舌石が残っており、全国的にも類例の少ない貴重なものであるらしい
AM11:23
太鼓櫓跡

現在はラジオ塔が建っている
1933年にラジオ普及の為に建てられたもの
大日本駆逐艦追風記念マストも建つ
AM11:28
下乗橋

城内の堀に架けられた太鼓橋で殿様の住む御殿への正面出入口にあたる
この橋を渡ると桝形が設けられ石垣や門によって厳重に守られていた
橋の前で駕籠などの乗り物から降りて歩いた渡った事からこの名が付いた
別名・小見付橋
1869年花崗岩製になり更に1908年に現在の水平の橋に改造された
AM11:34
鷲の門

徳島城正門
徳島城の巽に位置する表口見付門でその造りは脇戸付きの薬医門であった
幕府に鷲を飼うからと申し立て建造したところからこの名称になった
廃藩置県後、城郭の建造物は取り壊され唯一残された鷲の門も1945年の徳島大空襲により焼失
現在の門は1989年市制百周年を記念して復元されたものである
AM11:44
月見櫓跡
幕末まで残っていたらしいが今は何も無い
AM11:47
旗櫓跡
不明門の上にあった櫓
跡地っていうだけ
AM11:48
数寄屋橋

徳島城の鬼門にあたる門が旗櫓の下にあった数寄屋門
別名・未明門とも呼ばれ城内の凶事の際以外に開かれる事のない門だった
その数寄屋門の東側、堀に架け渡されたのがこの橋
現在は当時と同じ木製の太鼓橋が架けられている
AM11:52
城山の貝塚

約2300〜4000年前の縄文時代後期から晩期を中心とした岩蔭・洞窟遺跡
公園内には三つの貝塚が存在するらしい
1922年に鳥居龍蔵博士等によって発掘調査が行われ、二号貝塚でハマグリ・カキ・ハイガイなどを主体とした厚さ60〜100cmにもおよぶ貝層が確認
縄文時代後期の土器片や、ほぼ完全な屈葬人骨一体を含む三体分の人骨の出土
城山の貝塚は当時の人々の生活や自然環境を知る上で貴重な遺跡として徳島県における考古学調査の先駆けとなった遺跡として評価された
市指定文化財である
PM0:00
文学博士鳥居龍蔵先生記念碑

鳥居龍蔵博士は明治3年徳島市東船場の煙草問屋に生まれ小学校中退後、独学自立を志し苦学勉励の末、東京帝国大学人類学教室の助手・講師・助教授に進む
この間に台湾・シベリア・モンゴル・中国・朝鮮半島・樺太・千島列島の調査研究を行う
明治39年、モンゴル王の招きを受け夫人と共に幼児を抱いて内外モンゴルを踏査する
大正10年、東京帝国大学より文学博士の学位を授与される
同12年帝国大学を辞して鳥居人類学研究所を設立
大正の末、上智大学文学部長・国学院大学教授に迎えられ昭和11年には外務省文化使節として南米インカの調査
昭和14年から12年間北京燕京大学教授に招かれ研究に没頭
帰国後昭和28年1月14日、82歳で永眠
英独仏中蒙語に通じ著書百余冊という偉大な功績を学会に残された世界的学者
死後名誉市民を追贈される
現地案内板より
PM0:02
子供平和記念塔

世界の平和がいつまでも続くようにと願って建てられた塔
塔に埋め込められている石は徳島の子供の呼び掛けに応じた全国の小中学生やアメリカの子供達から送られてきた特色のある石や化石が使われており、その中には今上天皇から贈られた石も含まれている
PM0:06
弁天池

城山南麓に残る古池
かつては池一面に蓮が植えられていたので蓮池とも呼ばれた
この池の中央に築出した所に七福神の一人である弁財天を祀る社が建つ
南畔から朱塗りの欄干の付いた木橋が架かっていた為この名が付いた
PM0:14
東二の丸跡

三層の天守が設けられていた
一般的に天守閣は城郭の最上部に建てられるが徳島城では本丸から一段下がった二の丸に置かれた
天守閣の一階は七間四方と大きかったが天守台はなかった
PM0:16
本丸跡

標高61mの城山山頂に置かれた曲輪で山城部分の中では最も面積が広く重要だった
中央に置かれた御座敷と城山の管理人であった御城山定番の詰めた御留守番所の他、弓櫓や東西の馬具櫓・武具櫓・火縄櫓が設けられてた
櫓は戦いの際には防御施設になる
藩主は城山麓の御殿で暮らし城山に登る事は稀だったがこの御座敷にも藩主専用の部屋があり台所もあった
本丸の出入口は東西の門が使われていたが北口には御座敷の建物で隠された非常時の脱出口・埋門があった
PM0:34
西二の丸跡

西二の丸には鉄砲櫓と帳櫓
PM0:35
西三の丸跡
西二の丸西方に位置する
木材櫓と平櫓が設けられていた
現在は水道配水池が設置されている
PM0:38
8620系式蒸気機関車

大正12年から徳島の町やのを走り山や谷を巡り汽車ポッポの愛称で親しまれてきた
昭和44年7月22日の徳島〜小松島間の運行を最後に鉄道からその姿を消した
四十六年間数多くの人達に利用され鉄道沿線はもとより徳島全域の産業・経済・文化の発展に大きな役割を果たしす
市は昔を偲び懐かしいその勇姿を徳島中央公園に永久に残している
PM0:45
蜂須賀家政公銅像

蜂須賀公が入国後、藍・塩等でそれまで阿波にはなかった産業を取り入れ新しく製塩・製藍工業を起こし盛んに日本中に売り広めた
また全国でも有名な阿波踊りも家政公時代に始まったと伝えられている
戦前は野太刀と長槍を持った甲冑姿の蜂須賀家始祖・蜂須賀小六正勝公の銅像が建っていたが戦時中に供出されてしまい1965年に現在の銅像に生まれ変わった
PM0:51
徳島市立徳島城博物館

徳島中央公園内にある博物館
此処に日本百名城印があるというので立ち寄る
休館日だった…orz
こう云うところは休んじゃ駄目だと思う(´・ω・`)
PM1:03
東駐車場
此処でも日本百名城印を捺せるというので立ち寄るが印を手に持ちダラダラ話し込むババア💢
手から奪い取り、捺す
ババアはどおしてこんなに迷惑なんだろう
┐(´д`)┌ヤレヤレ
PM1:33
恩山寺

第十八番礼所で本尊は薬師如来
本堂は山の中腹にあり、石段を上がると大師堂、更にその上に本堂がある
聖武天皇の勅願により行基が厄除けの薬師如来を自ら彫って本尊とし諸人の災厄を除く道場となった
この寺は元々女人禁制
弘法大師がこの寺で修行していた折、母の玉依御前が遥々訪ねてきたが逢えなかった
そこで大師はママの為に一七日間、滝に打たれ修行し、女人解禁の秘法を納め晴れてママと再会
ママはここで髪を切って出家
以来寺号を母養山恩山寺とした
PM1:59
立江寺

阿波の関所寺とも呼ばれた第十九番礼所
本尊は延命地蔵大菩薩
聖武天皇の勅願により行基開山
白鷺に導かれこの地に来た行基は聖武天皇の妃・光明皇后の安産を祈願して一寸八分の金の延命地蔵大菩薩尊を刻み本尊とした
その為、後に子安地蔵として広く信者を集める様になった
弘法大師が訪れた際、本尊が余りに小さいので紛失を心配し、六寸の地蔵菩薩を刻んで胎内へ納めた
創建当時は現在のやや西側、清水の奥谷にあったが十六世紀後半のやっぱ長宗我部事件で焼失
蜂須賀家により現在地に採光とされ元の寺は奥の院となった
PM2:25
道の駅公方の郷なかがわ

国道55号沿いにある道の駅
裏は屋台村的なエリアでたこ焼きが12個で350円だったから買ってみた

うん…安いだけあるわw
PM3:06
道の駅ひなの里かつうら

県道28号上にある道の駅
よってネ市なる大きな物産館あり
道の駅内にある喫茶はモーニングやってるらしい
うん、巡礼用だね♪
もう少し遅かったら泊まっても良かったな
(ノω`*)
PM3:32
鶴林寺

鶴が本尊を運んだと伝わる二十番礼所
本尊は地蔵菩薩
お鶴さんとも呼ばれるこの寺は山頂までの道程は八十八ヶ所中でも難所に数えられる四km余りに続く急勾配の参道
桓武天皇の勅願により弘法大師が開基
大師がこの寺を訪れると本尊降臨杉の上で二羽の鶴が黄金の地蔵菩薩像を護っていたという

そこで三尺の地蔵菩薩を彫り、胸の中に一寸八分の黄金地蔵を納め本尊とした
寺名はこれに由来し、周囲の山々の雰囲気が釈迦が説法した場所インドの霊鷲山に似ている事から霊鷲山宝珠院という山号が付けられた
そんな鶴伝説で山門にも阿吽像では無く、鶴像が祀られている
寺の各所にも鶴像は見られる
また石垣美しい寺だった
PM4:31
太龍寺

西の高野さんとも呼ばれる二十一番礼所
本尊は虚空蔵菩薩
桓武天皇の勅願により開基した寺
本尊は弘法大師が彫った
江戸時代は阿波屈指の名刹として繁栄
仁王門・護摩堂・本堂・多宝塔など立派な伽藍が整う
中でも求聞持堂は若き空海が虚空蔵菩薩に願って、すべての経典を暗記する修行をした霊場として名高い
今も虚空蔵菩薩の真言を何万遍と唱える荒行を納めに来る修行者がいるらしい
そんな西の高野さんは標高600mの山頂付近に構えている寺で焼山寺・鶴林寺と並ぶ阿波三難所の一つで最難所…
本当は翌日ロープウェイで登ろうと思ったら、たまたま通った道から太龍寺まであと3.7kmの看板を見て急遽予定変更
しかし道は険しいわ
駐車場からまた一km歩くわでバタバタお参り

やっぱり翌日ゆっくりと参拝に来ればよかったとかなり後悔する
最後に持仏堂の龍天井を見て駆け足で車に戻る

鳴龍って日光だけかなって思ってたけど意外とあちこちにあるんだね
PM4:59
道の駅わじき

国道195号沿いにある小さな道の駅
営業は十七時までと書いていたから慌てて太龍寺のお参りを済ませて、事故りそうなほどヤドカリ的にとばしてやって来たが、まだ閉める様子もなくのほほんと話し込んでいた
脱力するw
良い道の駅だ♪
PM5:09
道の駅鷲の里

本来なら此処でP泊して翌日此処から太龍寺へお参りに行くつもりだった広い道の駅
巡礼者がロープウェイから帰って来るから十七時二十分と中途半端に開いているので無事スタンプを捺す
PM5:30
全日食相生店
たまに見かけるチェーンスーパー
酒類も売ってる
缶酎ハイと酒の肴に惣菜等を購入
PM5:54
道の駅もみじ川温泉
宿泊施設が道の駅化した温泉道の駅
以前にも来た事あるはずなのだが全く記憶と違う
とりあえずひとっ風呂浴びるが浴室も記憶と違う…



リニューアルしたの?
とりあえず体はサッパリしたが気持ちはスッキリしない
PM7:00
ヤドカリ帰還
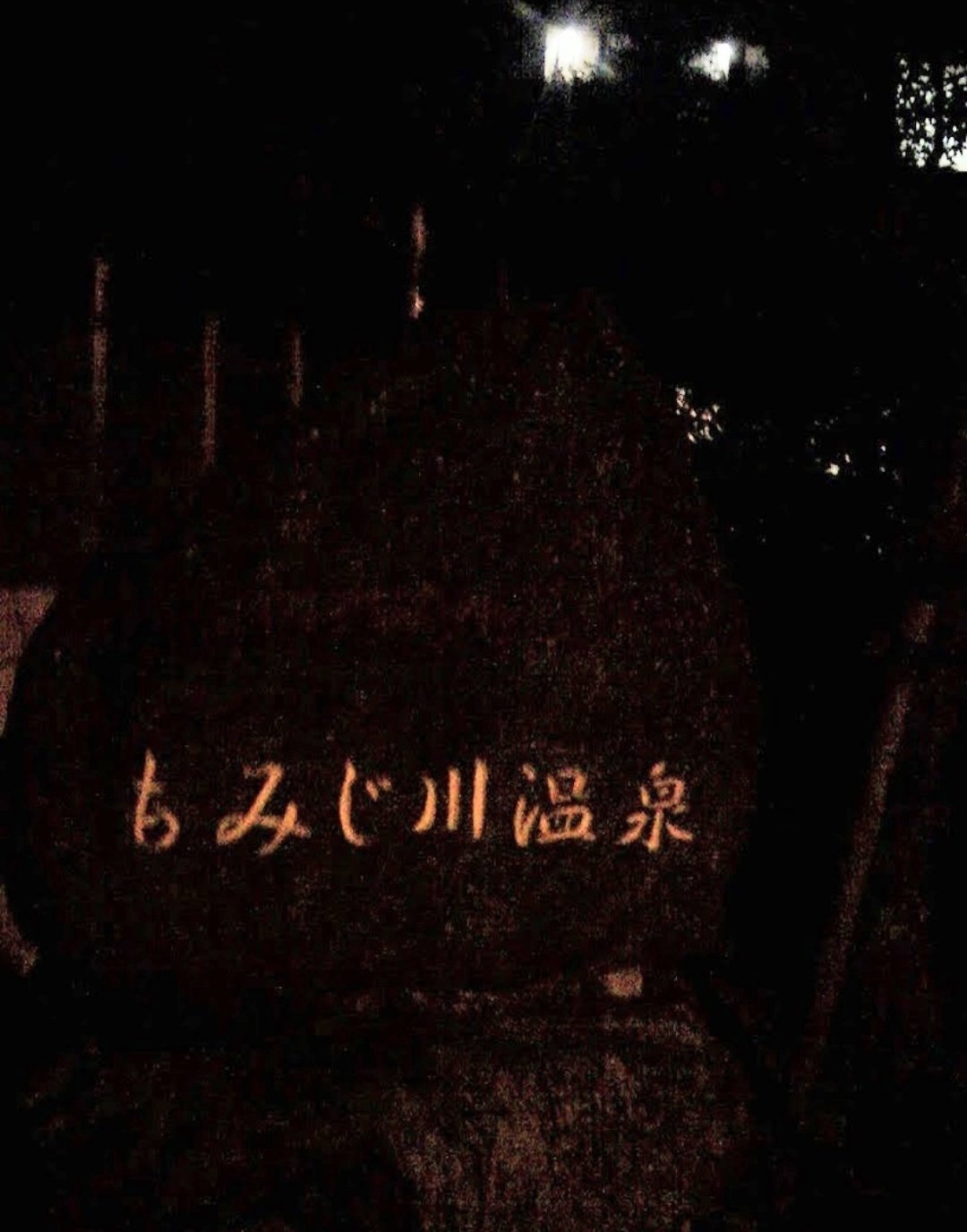
車に戻ると見覚えのある車が…
四国霊場巡り初日にP泊した道の駅第九の里にもいた鹿児島ナンバーのワゴンだ
俺は寄り道しながらなのに同じペースとはw
とにかく車内に戻って晩酌
最近ハマっている納豆で晩酌
それにしてもよく観て周ったな〜
霊場参りに滝巡り、道の駅巡り、城巡り♪
よくもまぁ〜こんなに周ったわ(*´ω`*)
よろしければサポートよろしくおねがいいたします クリエイターとしての活動費にしたいと思います
