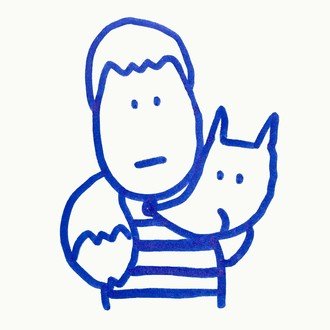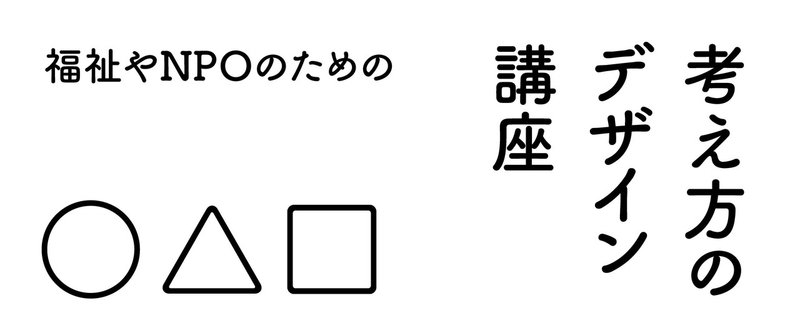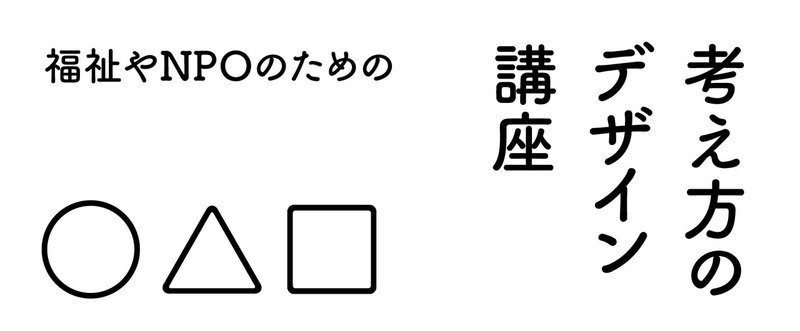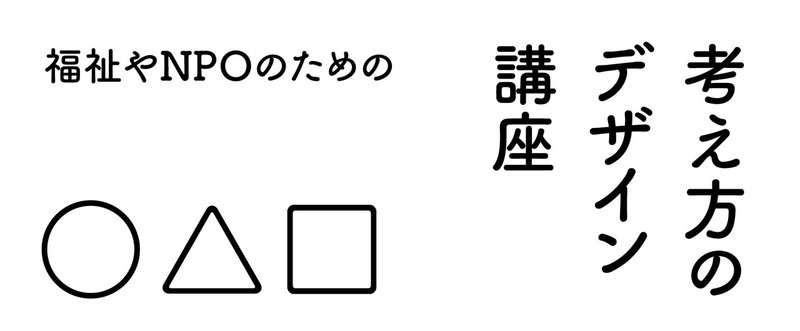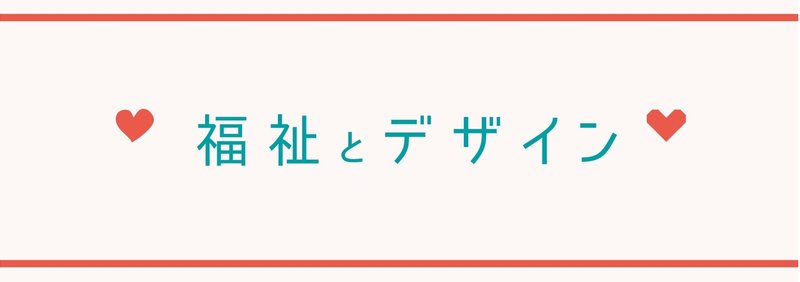
デザイン教育の講師とデザイナーをしながら障害福祉事業所の理事兼支援員。生活介護のアートプログラムや精神当事者むけのワークショップ、NPO全般のスタッフ研修や企画アドバイザーをした…
もっと読む
- 運営しているクリエイター
#福祉支援
【告知含む】福祉事業所を対象に、デザイン相談ができる「福祉とデザイン サポートカフェ 播磨」をスタートします。
障がい福祉事業を「デザイン」でサポートする。「福祉とデザイン サポートカフェ」を播磨地域で開設します。https://www.facebook.com/fukushitodesign/
今回、場所は、姫路二階町商店街のNPOビル「レウルーラ二階町」 1Fのワーキングスペースにて、月に1-2回から、相談日をスタートさせていきます。
初回は10/15(土)を予定しており、料金は1事業所につき¥15
福祉・NPOの進展に必要な「決裁権」
よりよいアイデアや企画が生まれても、
福祉やNPOの決裁権がそれを阻む事があります。そうならないために、
公的機関や地域福祉に決裁権のある
団体・役職・担当者のような人々にこそ
「イメージ力」を鍛えて欲しいと思います。
世間では
「新しいことをやってください」
「いままでにないものをやってください」と
口をそろえて求められますが、
「いままでにないこと」は
容易にはイメージできないものです。
企画の骨子は「背景」です。
企画の骨子は「背景」です。
「背景となるきっかけ」がなければ
物事を思いつくということができません。
それは個人的なことでかまいません。
課題が与えられたから考えたのではなく、
自分の中に何か思うことがあったり、
表現したいことがあったり、
小さい頃の記憶があったり、
問題意識を感じたり、
単に好きでたまらないものがあったり、
なんとなく気になることだったり。
それが、「背景」であり、
そこ