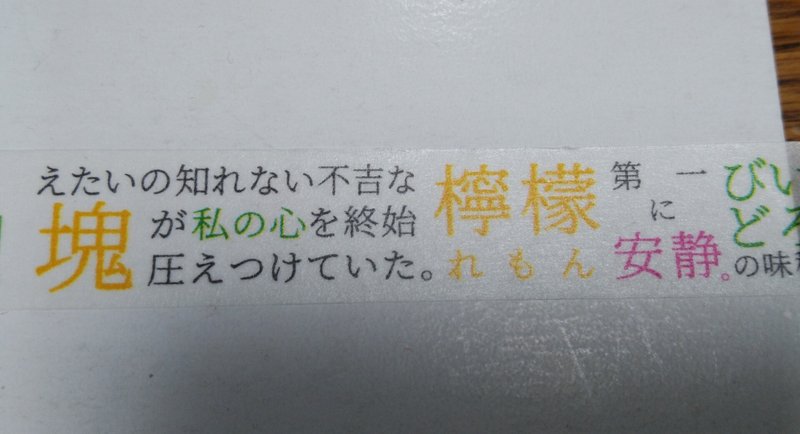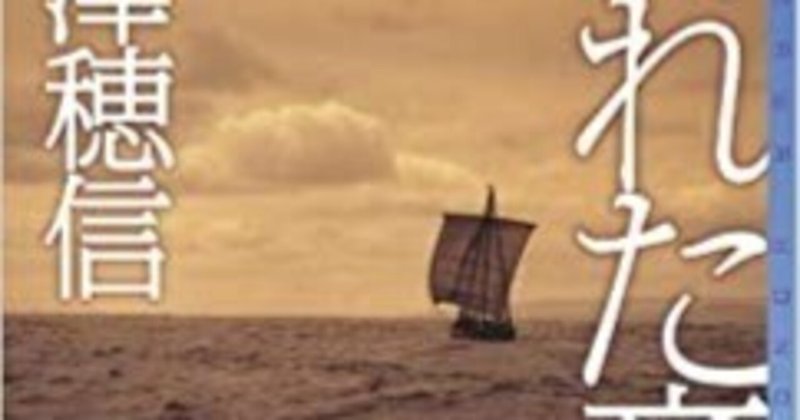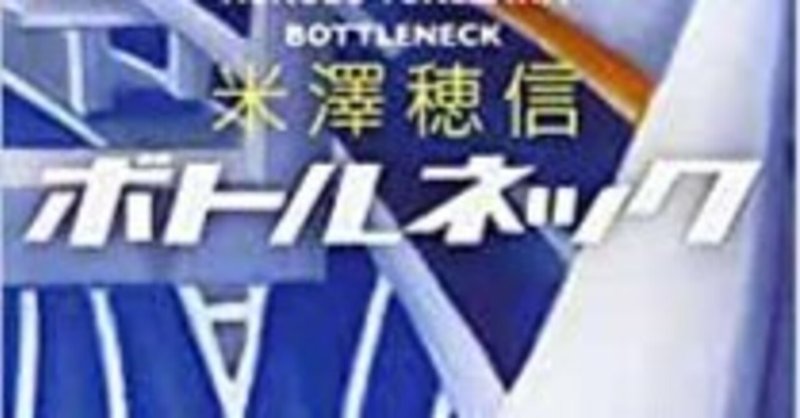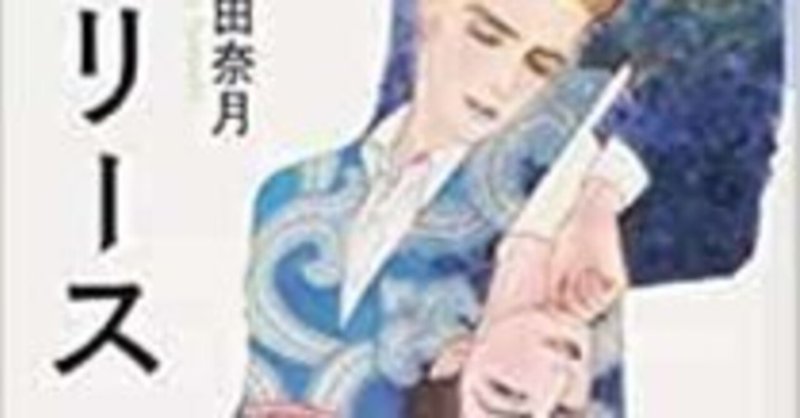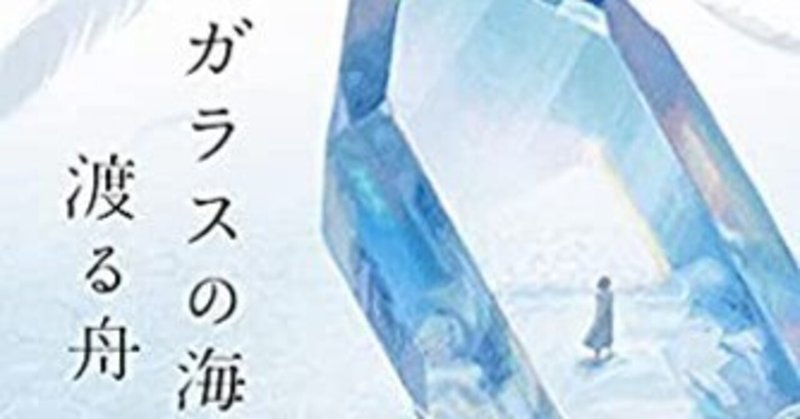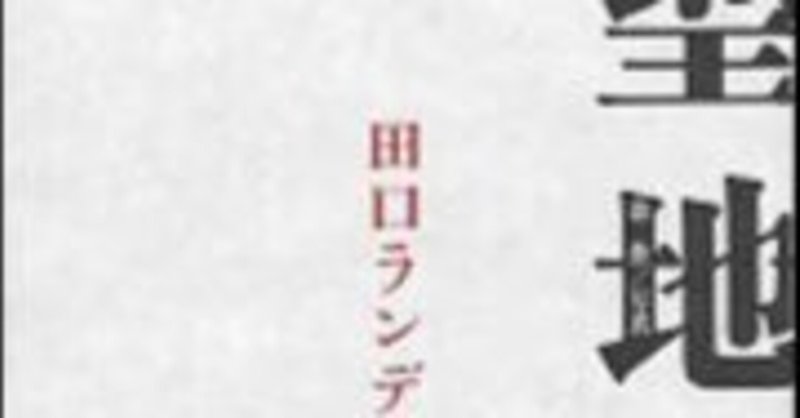2022年9月の記事一覧
『オリーヴ・キタリッジの生活』『オリーヴ・キタリッジ、ふたたび』(毎日読書メモ(416))
エリザベス・ストラウト作、小川高義訳『オリーヴ・キタリッジの生活』(ハヤカワepi文庫)、『オリーヴ・キタリッジ、ふたたび』(早川書房)を読んだ。
昨年、『オリーヴ・キタリッジ、ふたたび』が刊行されたときに北村浩子が「週刊文春」に大変魅力的な評を書いていて(魅力的、というか、評者がどれだけこの物語が好きか、という愛に溢れていた)、初めてこの本の存在を知ったのだが、1冊目の『オリーヴ・キタリッジの生
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂15』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(415))
廣嶋玲子・jyajya『ふしぎ駄菓子屋銭天堂15』(偕成社)、今回も一気読み。ネタバレあるのでまっさらな気持ちで読みたい方は注意。
14巻の終わりで、六条教授のやり方に疑問を持った、元研究員関ノ瀬さんが紅子にタレコミ。六条教授の研究所は銭天堂をつぶそうとしている、と紅子の科白の中で明記されている。
14巻では具体的なやり方は書かれていなかった、銭天堂を陥れようとするやり方、それは、偽の魔法グッズ
弓削尚子『はじめての西洋ジェンダー史』(毎日読書メモ(413))
新聞で紹介されていた弓削尚子『はじめての西洋ジェンダー史 家族史からグローバル・ヒストリーまで』(山川出版社)を読んだ。大学でのジェンダー史入門の講義録を元に、西洋(主にフランス、イギリス、オランダ、ドイツ辺りを中心とした地域)における家族史、家族の構成員それぞれの家族の中での役割、性別とジェンダーによる、世界の歴史の中での役割、そしてグローバル・ヒストリーを取り扱い、世界の連関性の中での西洋のジ
もっとみる『ふしぎ駄菓子屋銭天堂14』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(412))
廣嶋玲子・jyajya『ふしぎ駄菓子屋銭天堂14』、先が気になってまたすぐ読んでしまった。(ちょっとネタバレ)この巻でもまだ、六条教授は紅子と直接対決していない。届くようで届かない敵(敵なのか?)の攻略法をあの手この手で考え、潜伏捜査続く。
幸運のお客さまたち自体は、その六条教授の策略により、悪い影響を受けることはない。しかし、六条教授たちのばらまいた小銭が確率高くその日の幸運のお宝になるのは何故
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂13』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(410))
廣嶋玲子・jyajya『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』、12巻から現れた新キャラ六条教授が、銭天堂にとってどんな敵となるのか、気になって、続けて13巻を読む。表紙の紅子はちょっとおすましさん、だけど逆光でちょっと妖しい翳が。
六条教授は、紅子やよどみのような超常的存在ではない。だから自分自身が銭天堂に辿り着けたこともないし、研究所のスタッフたちも銭天堂に行けていない。しかし、人海戦術で、大量の小銭を用意し
藤谷治『あの日、マーラーが』(毎日読書メモ(409))
藤谷治『あの日、マーラーが』(朝日新聞出版)を読んだ。2011年3月11日(金)、未曽有の混乱下にあった東京で、予定されていた演奏会を開催した、ホールとオーケストラと指揮者と、105人だけやって来た観客の物語。
錦糸町のすみだトリフォニーホールで、ダニエル・ハーディング指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団が、ハーディングのミュージック・パートナー就任記念演奏会としてマーラーの交響曲第5番を演奏。
寺地はるな『ガラスの海を渡る舟』(毎日読書メモ(408))
寺地はるなが昨年発表した『ガラスの海を渡る舟』(PHP研究所)を読んだ。寺地はるなの小説に出てくる登場人物たちは、所謂機能不全家族で暮らしていた訳ではないが、家族相互のコミュニケーションの前に大きな壁が立ちはだかっている、そんな印象。読んでいてとても息苦しい。
舞台は大阪。祖母が持っていた土地に、祖父がガラス工房を作り、作品を作って売ったり、ガラス工芸教室を開いたりして生計を立ててきた。祖母が亡
田口ランディ『聖地巡礼』(毎日読書メモ(407))
過去の日記を読み出したら、なんだか懐かしいやら興味深いやら。忘れていたことなども色々思い出す。通勤の電車の中でせっせと読書をしていた時期だった(まだ携帯電話をどっぷり見ちゃう習慣はなかったから、今よりしっかり読書していたと思う)。この時期にかなり読んだのが田口ランディだったな、と懐かしく思い出す。
田口ランディ『聖地巡礼』(メディアファクトリー)に取り掛かる。屋久島とか、天河弁財天とか、水につな
リュドミラ・ウリツカヤ『ソーネチカ』とT.E.カーハート『パリ左岸のピアノ工房』、新潮クレストブックスの歓び(毎日読書メモ(406))
【ちょっと追記】もう少し先の日記に『パリ左岸のピアノ工房』についてもう少し書いてあったのでそれも足してみた。
過去日記より。リュドミラ・ウリツカヤ『ソーネチカ』(沼野恭子訳、新潮クレスト・ブックス)と、T.E.カーハート『パリ左岸のピアノ工房』(村松潔訳、新潮クレスト・ブックス)の感想。
ここに書いてある感想だとあんまり感じ取れないかもしれないが、『パリ左岸のピアノ工房』は、わたしが21世紀に入
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂12』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(405))
1ヶ月ぶりに、廣嶋玲子・jyajya『ふしぎ駄菓子屋銭天堂12』(偕成社)。前巻でよどみとはお別れ出来たようで、この巻ではよどみも怪童も現われず。平和な日々?、と思ったら、紅子の痕跡をつけ狙う謎の紳士六条登場。SNSとか口コミとかをつてに、銭天堂の商品を使って何か超常的な効果を得た(良くも悪しくも)幸運のお客さまから、買ったものについての聞き取りを行っている。でも本人は銭天堂にもたどり着けないし、
もっとみる