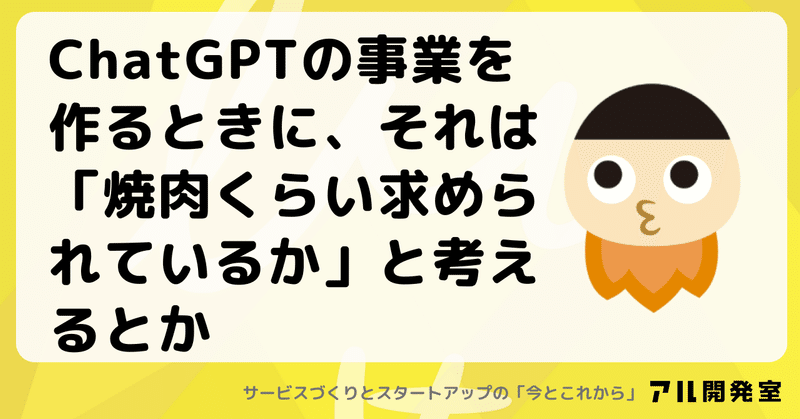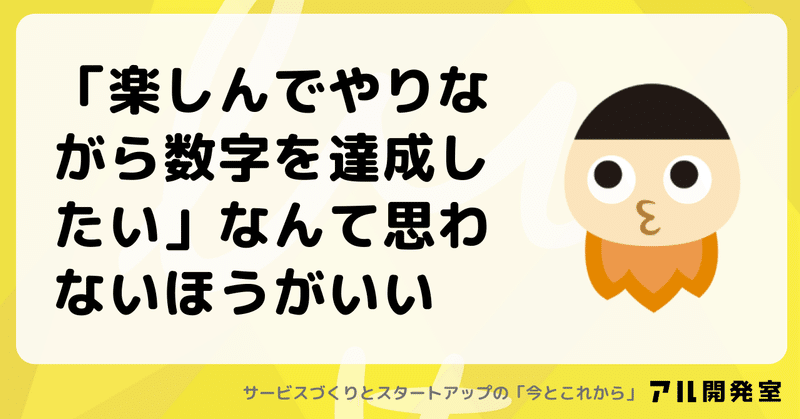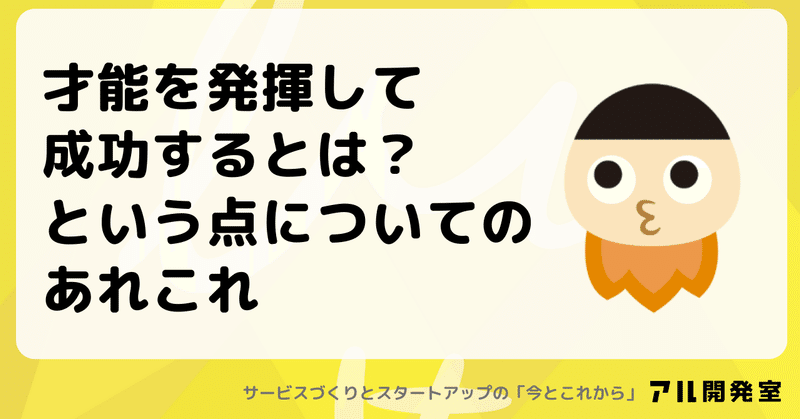2023年5月の記事一覧
「遅咲きの偉人」に夢を見るな【キンコン西野】
1日でも早く学び、1日でも早く勝て
今日も最新刊『夢と金』の深掘りをしていきたいと思います。
今日は少し耳の痛い内容になりますが、312ページの「1日でも早く学び、1日でも早く勝て」をピックアップ。
ここでは、『20代で生まれた差は、一生埋まらない』と書いているんですね。
これ、ガツンとくらった人が少なくないと思います。
「20代で生まれてしまった差が何故埋まらないのか
#045 組織・社会が劣化する構造的要因について
こんにちは。今日はアムステルダムまで来ています。昨日の夜中についていま朝の7時。これ書き終わったら朝食食べます。組織と社会の劣化要因について少し考えたことを。
歴史家のチャールズ・P・キンドルバーガーは、彼の著書「経済大国興亡史」において、ポルトガルやスペインなどの大国が衰退した理由の一つとして「社会的な新陳代謝の停滞」を挙げています。権益が既得化して社会システムの上位にある人がこれを独占するよ
ChatGPTの事業を作るときに、それは「焼肉くらい求められているか」と考えるとか
こんにちは!
今日、投資家の人と話していて、たしかになー!と思ったことがあるので共有します。
昨日の引き続き「ChatGPTを使って事業をつくりたいんだけど?」というのに使えるかなーと思って書いてみました。
それは「飲食店をやるときに、めちゃくちゃに個性的なものを出すところよりも、焼肉みたいに人気があるものを提供し、そのやり方とかを変えたほうがいいケースってあるよね」ということです。
結論
#037 「役に立つ」から「意味がある」への価値シフト
記事タイトルにある『「役に立つ」から「意味がある」』という提言を最初に明確な形で提出したのは、2019年に上梓した著書「ニュータイプの時代」においてでした。思い出してみれば、このアイデア、仕事をサボって夕方にバーにいった時に「なんでバーの酒類はこんなにあるんだ?」という問いに答えを出そうとして思いついたんですけど、その話はまた別のタイミングで。
「役に立つ」と「意味がある」
このメッセージはい
「楽しんでやりながら数字を達成したい」なんて思わないほうがいい
こんにちは!
今日、Twitterのサブスクのほうで「Twitterを楽しみながら、もっと多くの人に見られるようになるにはどうしたらいいのか?」というのを質問されました。
これを見て、「なんか最近、楽しみながら、という条件が必須になっている人いるな?」と思ったので、ちょっと書いてみます!
結論結論からいうと、最初から「投稿を楽しみながら数字を達成していこう」みたいに思っていると失敗しやすいん
才能を発揮して成功するとは?という点についてのあれこれ
こんにちは!GW明けでお久しぶりです!
というわけで今日は「才能がある人というのはいったい全体、どういう人のことなのか?」ということについて、最近つらつらと考えていたので、それについて共有します!
才能がある=はじめからできる人ではない才能がある人とは何か?というのを考えたときに、マンガとかでいうと「はじめてやったときから、すごい才能を発揮してめっちゃすごい」みたいな感じで描かれることが多いと
#022 キャリアの滑落死を避けるための三つのポイント
キャリアはよく登山になぞらえられて語られます。では、登山において最も重要視されるのは何でしょうか。それは「生きて帰る」こと。これに尽きます。ところが、キャリアに関する論考の多くは「いかに速く登るか」、「いかに高く登るか」といった論点にフォーカスするばかりで、肝心かなめの「いかに生きて帰るか」「いかに滑落を防ぐか」といった論点がなおざりにされている感があります。
僕は前著の「仕事選びのアートとサイ