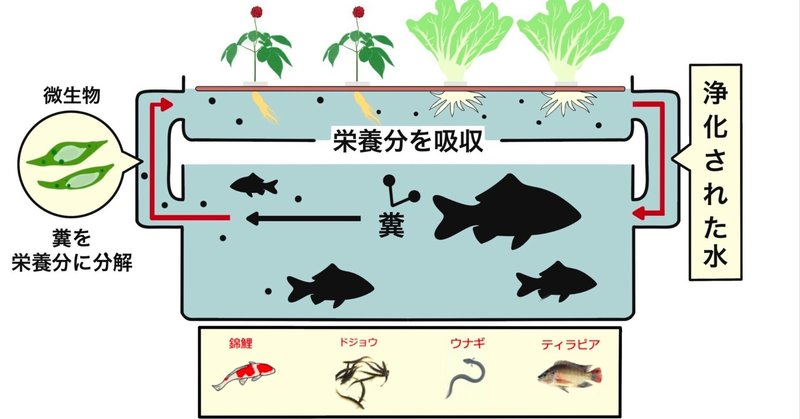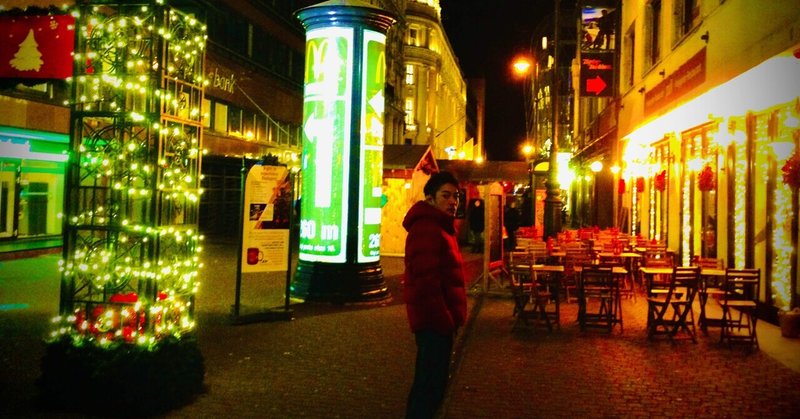記事一覧
「ゼロリスク社会」の罠 佐藤健太郎 著
近年になって組織運営において「コンプライアンス」の項目は特に敏感に取り扱われている。社によっては社内にコンプライアンス専門の部門が設置され、どの企業もコンプライアンスの遵守を徹底している。コンプライアンス違反が明るみになり、メディアからのバッシングを受け、一般消費者の客離れが起きてしまうといった問題もいくつも発生している。
そうした一企業が起こした不祥事がメディアによって拡散され、不祥事の程度の
勤勉は美徳か? 大内伸哉 著
労働について昨今の状況も踏まえながら改めて再定義した本だった。正直私にとってはそもそも勤勉を美徳とも思っていないし、雇用契約も会社に忠誠を誓うことで会社に生活を保障してもらおうとする制度と捉えている。ゆえに被雇用者の立場にたったこの本にはあまり共感することは少なかった。しかし労働の起源や根本的な概念について学べたのは良かった。
人生の中で一番長く使う時間を幸せに過ごす
これは人生の幸福度を上げ
自助論 S.スマイルズ 著 竹内均 訳
この本の原著は1858年に刊行されていて、著者のスマイルズがさまざまな視点から数多くの賢人を例に挙げ、そこから学びを得るといった具合の内容になっている。この本を通して改めて実感したのは、人の考えは人の性格によってそれぞれだし、持って生まれた環境、時代背景によっても移り変わる。しかし決して変わらない信条、思想、哲学も同時に確かに存在していて、それこそが現代までに語り継がれる財産であり、本のタイトルを
もっとみる「私」のための現代思想 高田明典 著
「私」という存在を哲学的に、現代的に解釈、再定義した本だと言える。哲学とイメージすると本質的でありつつ、かつ抽象的な概念を今までイメージしていた。ゆえに現実世界と哲学とをリンクさせることは難しいように思えたが、現代社会にも多くの気づきを与える一冊だった。
特に印象に残っているのは、人間にとっての正しさの定義である。著者によれば、人は「正しくあろう」とする存在だと言う。ここでいう正しさとは何か、こ
「命令違反」が組織を伸ばす 菊澤研宗 著
さまざまなプロジェクトを回す上で合理性は常に意思決定の検討材料となる。合理的であることは経済性に優れていて、時間の捉え方がインスタントになった現代社会において非常に重要な要素だ。そうした時代においてそもそも合理性とは何なのかを別角度から見つめる1冊だった。
太平洋戦争における日本の敗戦を現代のビジネスでの教訓とする書籍は非常に多い。特に『失敗の本質』は太平洋戦争での敗因分析をもとにしたビジネスの