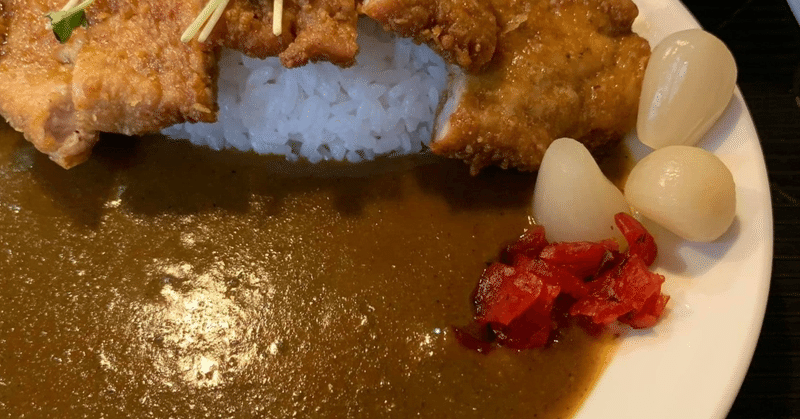#夏目漱石
三島由紀夫から見た夏目漱石の読者
三島由紀夫、安部公房だけではない。これまで見てきたように谷崎潤一郎も漱石の評価は低いし、太宰治に関しては「俗中の俗」と漱石を切り捨てている。三島由紀夫のこの発言も、夏目漱石というすでにこの世にない作家の死してなお消えない過剰な人気に対する反発の表れだ。
しかも芥川龍之介までスタイルは鴎外に近接し、漱石文学から何を継承したのかということさえ曖昧なので困る。
この三島由紀夫と安倍公房の対談は
シンプルな読みに向けて
これまで私は夏目漱石から谷崎潤一郎までのいくつかの作品について、何か書いてきた。それを「新解釈とは言えないまでも私なりの感想のようなものをまとめてみました」とでも書いてしまえばいささかでもお行儀が良かろうものを、私は「宇宙で初めての新解釈です」と云わんばかりに書いてきた。これはどう考えても私なりの感想のようなものではない。現に、『途上』のからくりにさえ、誰一人気が付いていなかったのではないか?
もっとみるやがて色んなことが解らなくなる 『虞美人草』における「大森」の意味
大岡昇平の漱石論を読みながら羨ましかったのは、大岡昇平が『それから』や『彼岸過迄』に描かれる電車や駅の位置関係に関して実地の記憶を持っていることだった。当然『それから』や『彼岸過迄』が書かれた後も電車や駅は日々変化していたので、大岡昇平の記憶は夏目漱石が見ていた電車や駅そのものではない。しかし今の新橋駅と漱石の作中の新橋の停車場が別の駅であると知識としてではなく感覚として知っていること、昔の中野
もっとみる夏目漱石作品と芥川龍之介の生活 夏目さんにしてもまだまだだ
皆さん、あの『こころ』の「私」のところへ「芥川」を置いてみてください、と『芥川龍之介の文学』で佐古純一郎は書いている。これが近代文学1.0における根本的なミスの事例であることは指摘するまでもなかろうか。佐古純一郎は芥川龍之介は漱石文学を継承したというストーリーを持っていて、そのストーリーに芥川作品を無理やりはめ込むつもりなのだ。だから芥川が漱石に対して感じていた畏怖や圧迫感をすがすがしい敬愛に置
もっとみる