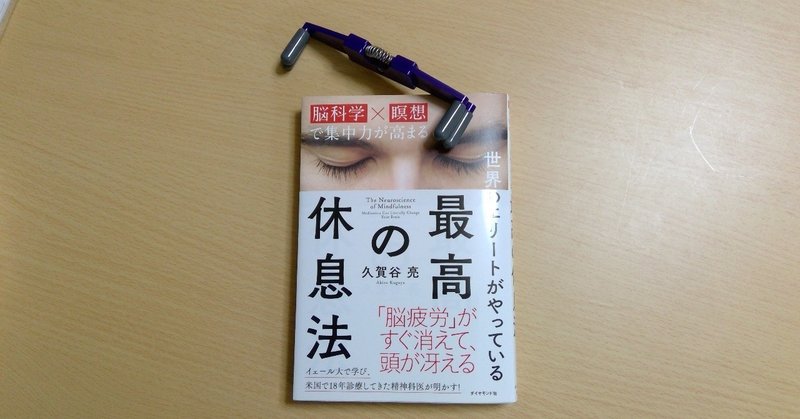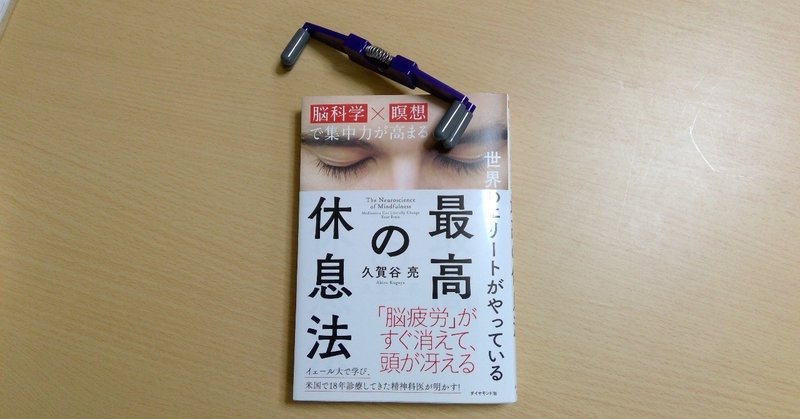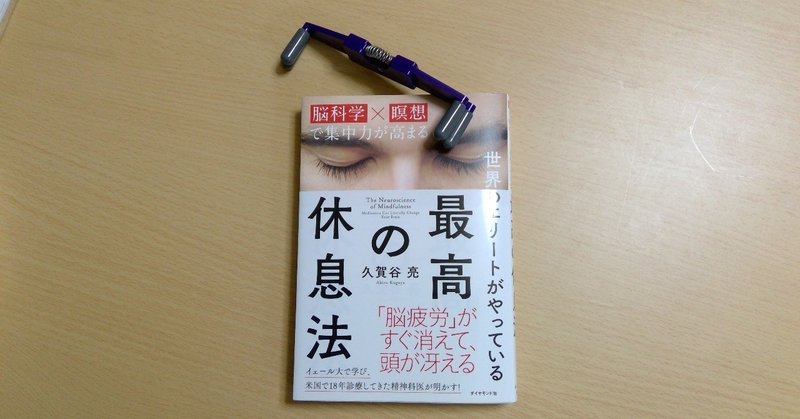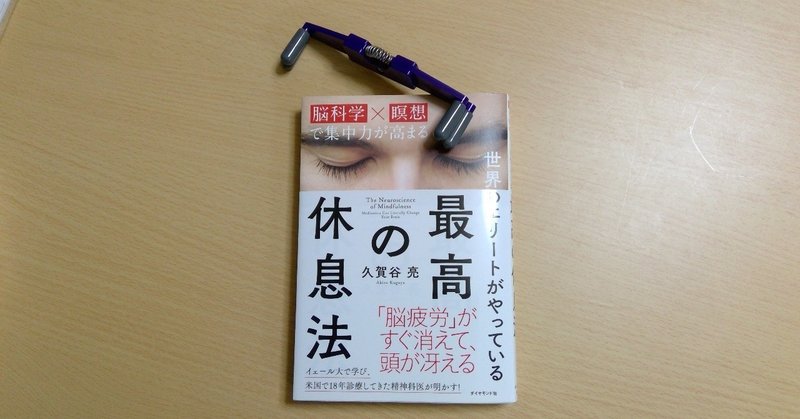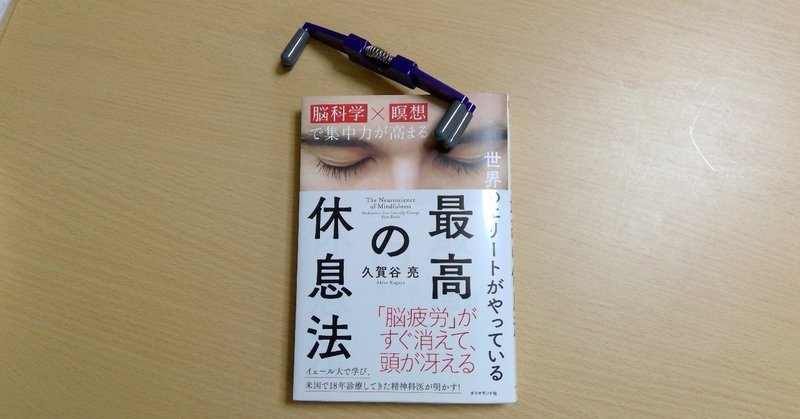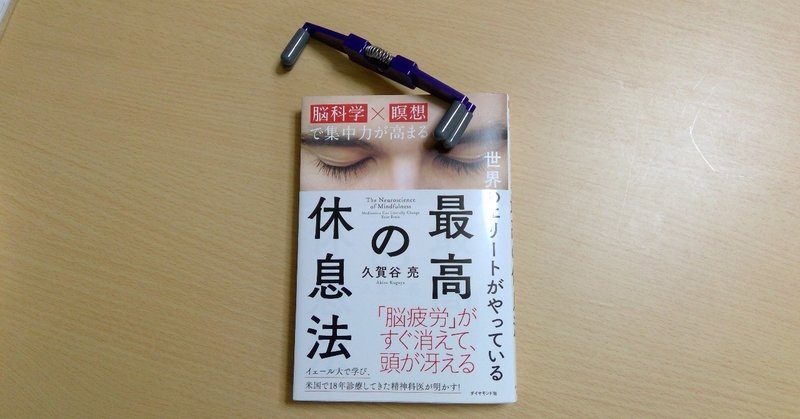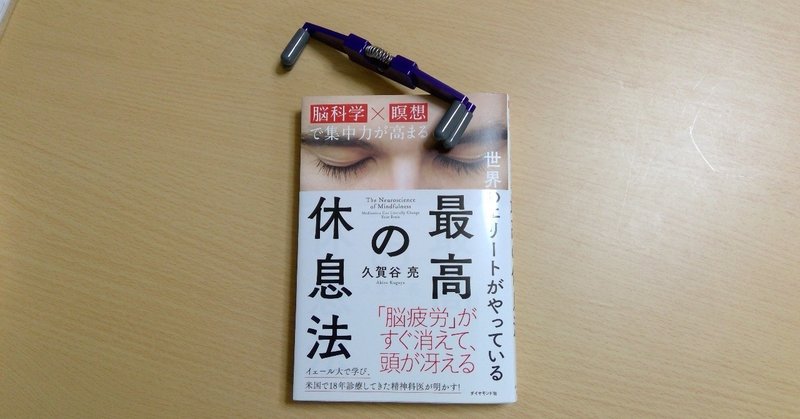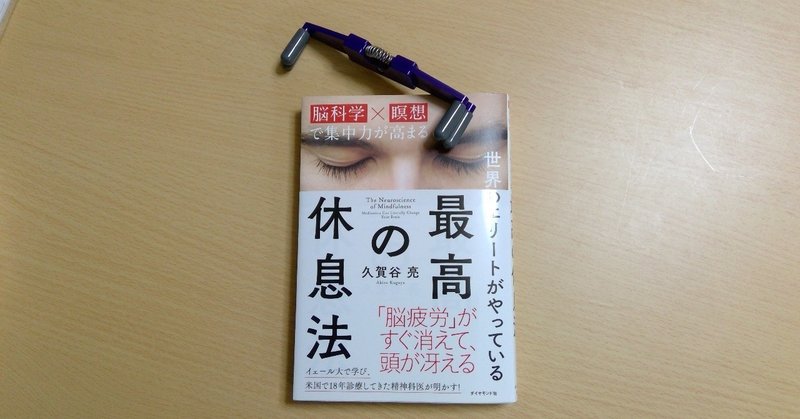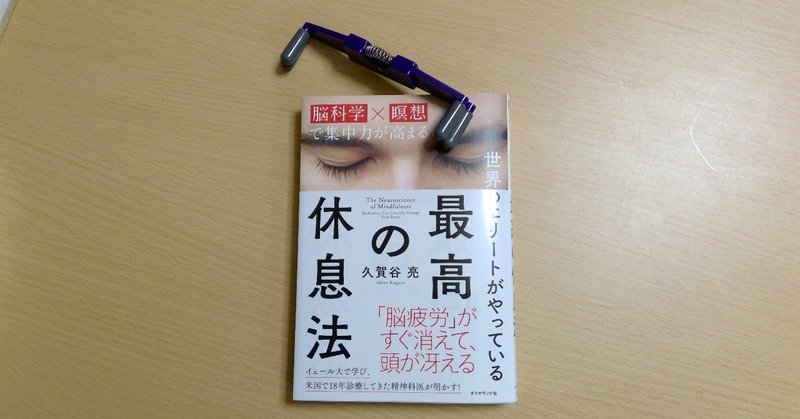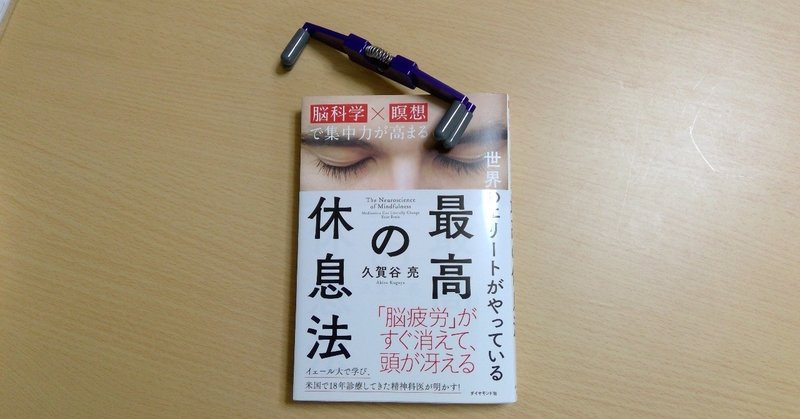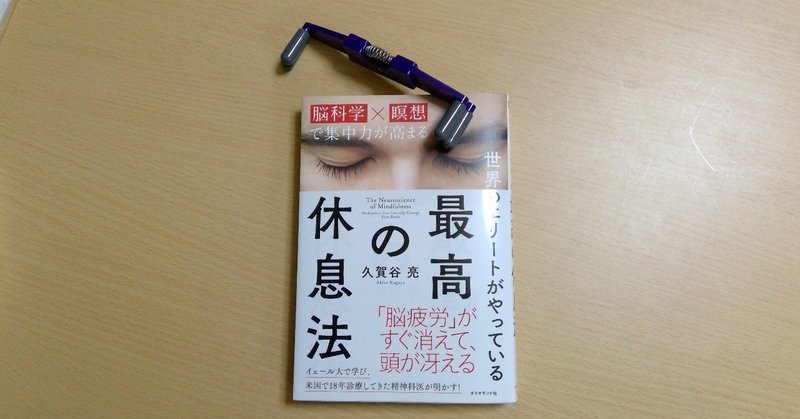2018年10月の記事一覧
「最高の休息法」を読んで 23 脳内のうるさいサルを追い出す
ベトナム出身の禅僧で、世界的なマインドフルネス指導者であるティク・ナット・ハンは南フランスにプラム・ヴィレッジというマインドフルネスの研修所をつくりました。そこで行われる研修プログラムには丸一日を休息の為だけに使うレイジーデイ(lazyDay=怠ける日)が設けられています。
何も予定をいれずに、各自が歩行瞑想や軽い読書をしたり、家族へ手紙を書いたりすることになっています。
週末に「思いっきり休む
「最高の休息法」を読んで 22 思考のループから脱したいとき「モンキーマインド解消法」
頭の中にさまざまな雑念が渦巻いている「モンキーマインド」の状態では、脳のエネルギーが膨大に浪費されどんどん疲労が蓄積し睡眠の質も下げてしまいます。
そんなときはまず雑念そのものに対する「認知」を変えましょう。
繰り返しやってくる思考に「名前」をつけるとループに陥りにくくなります。
ポイント
・「雑念=電車」、「自分=プラットホーム」のような認知行動療法的アプローチが有効
・「自分」と「自分の考
「最高の休息法」を読んで 20 ブリージングスペースとは
ストレスは脳内の現象ですが、慢性化すると身体に様々な影響を及ぼします。じんわりとした身体のだるさや肩こりのような症状から、激しい腹痛、胃腸の炎症までさまざまです。
ストレスによる身体への影響に気づき、それを脳(前頭葉と偏桃体の関係性)から改善していく方法があります。
前頭葉が抑え込めないくらい偏桃体が過剰に活動すると、交感神経に作用して激しい動悸や過呼吸などの身体症状が引き起こされます。これが
「最高の休息法」を読んで 18 食事をしながら脳を休める
ムーブメント瞑想に似た方法として、食事瞑想もご紹介します。
食事という当たり前な行為をしているとき、私たちは「いまここ」を忘れがちです。そんなときに役立つのが食事瞑想。
なかでもよく使われるのがレーズンエクササイズ。1粒のレーズン(もちろんレーズンでなくても大丈夫。)を意識の錨として利用する方法。
まずレーズンをよく観察します。
はじめてレーズンを目にした子どものように、手のひらに乗せてじーっ
「最高の休息法」を読んで 17 ムーブメント瞑想を日常に
マルチタスクに由来する自動操縦状態を解除し、リラックスと集中とを同時に高めるうえで有効なのがムーブメント瞑想。こちらは呼吸ではなく自分の身体の動き(ムーブメント)を意識の錨にする方法です。
グーグルの社員研修プログラムSIYでも実践されている典型的なムーブメント瞑想に歩行瞑想があります。
最初はできる限りゆっくりと、亀のようなスピードで歩きながら
・脚の筋肉や関節の複雑な動き
・手の動き
・足が
「最高の休息法」を読んで 16 マインドフルネスとフロー(ゾーン)
マインドフルネスと集中力との「結び目」になっているのがフローと呼ばれる状態です。
フローとは心理学者のミハイ・チクセントミハイが提唱した概念であり「リラックスした状態にいながらも対象に浸りきってすさまじい集中力が発揮されている状態」の事を言います。
一流のアスリートなどが世界的記録を出すときにも、このリラックスした集中状態を体験するといいます。スポーツなどでの場合、ゾーンという言葉が使われたり
「最高の休息法」を読んで 15 自動操縦状態の危険さ
過去や未来に意識が奪われていると、脳が疲弊するという話をしました。
もうひとつ知っていただきたいのが、私たちは日常生活で「自動操縦状態」にあるということ。
食べる、歩く、歯を磨く、電車や車に乗る、など。
私たちは日常のさまざまな行為のほとんどを「意識することなく」こなせています。それほど注意を払ってなくても、飛行機の自動操縦モードのように目の前のタスクを処理しているはずです。
では、肝心のパイ
「最高の休息法」を読んで 14 気が付くと考え事をしている、そんな時に「ムーブメント瞑想」
気が付くと考え事をしている・・・そんな時に役立つ
ムーブメント瞑想
これは
・集中力、注意力の改善
・フロー状態の実現
に役立つほか、脳を疲労させる「自動操縦状態」を脱します。
現代はマルチタスクの時代。
誰もが「何かをしながら」別の事をやっている日常的な所作の中で「自動操縦モード」になっている時ほど頭には雑念が浮かびやすくなります。
これが常態化すると注意力・集中力が低下しかねません。
グ
「最高の休息法」を読んで 12 マインドフルネスの核心は「Let it go(あるがまま)」
・このやり方であっているのでしょうか?
・1日何分やれば?
・やはり半年は続けないとダメ?
この先にも何度か繰り返しますが、マインドフルネスに「こうしなければ」というルールはほとんどありません。
とにかく徹底的に実用重視!でいきましょう。
「身体の感覚や呼吸に意識を向ける」という点以外は、どれだけ自分なりにアレンジしても大丈夫です。たとえば
イスが苦手なら正座でもOK
座禅に慣れている人はあぐ
「最高の休息法」を読んで 10 瞑想において雑念は当たり前
瞑想中、おそらく1分もしないうちに心の中に雑念が浮かんでくるかと思います。
仕事の事や家族の事、もしくは「あーお腹減ってきたな。このあと何食べようかな」とか「あーまだ終わらないかな。今何分くらい経ったのかな」とか。
脳内ではDMNが働いているので、それはまったく自然なことなんです。
「私って雑念だらけの人間で、すぐに他の事を考えてしまってダメなんです」
マインドフルネスを体験した人の中にはこん