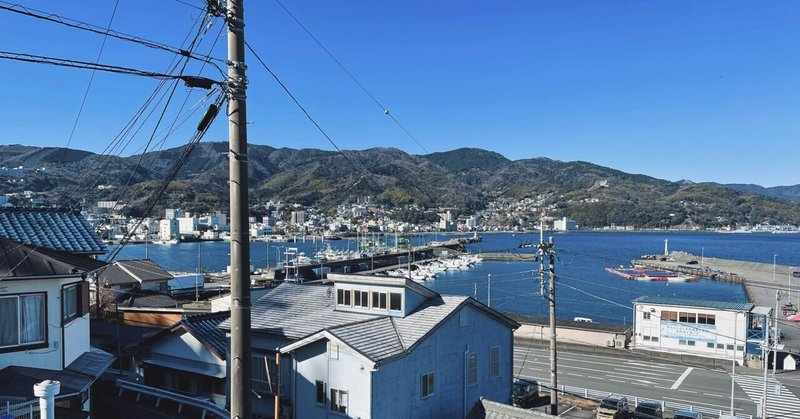#とは
創作とは何かと対話すること
私は一人でいることを全く苦に感じない。道端でご近所さんと世間話したり、干物屋のおじちゃんと話したりで充分満足できる。だから家族も友達もいない街へ移住できたのだろうけど。一人っ子なこともあり、一人の時間を過ごすサバイバル術みたいなものを幼少期のうちに会得したらしく、むしろ友達付き合いは苦手な方だった。ツアーミュージシャンになってからも旅の道中は一人だったし、どこかへ属したいという気持ちも全くない。一
もっとみるゴールのない芸術作品を目指して
藤森愛として活動14年目を迎えた(昨年は間違えて12年目と言ってたみたい)。今でもこうして藤森愛という看板を出して活動できているのは、たくさんの支えがあるからなのだと年月を重ねるごとに強く、深く感じる。
芸術ごとを続けていくのは難しい。なんでもそうだろうけれど、特に芸術は生きていくために必要なものとしての優先順位は圧倒的に低い。生きていくためには絶対に必要だ!という人もいるかもしれないけれど、芸
現代社会での自分なりの幸福論について考えてみる
観葉植物たちが無事に冬を越えられるかを心配している。ベンジャミンは部屋が寒すぎたのか、半分ほど葉を落としてしまった。パキラは冬眠させているからあまり変わっていない。他の植物たちは冬の日差しでもニョキニョキと成長し、新芽を生やしたものもある。植物を通してたくさんのことを学んだ。水をあげるタイミング、日差しとの距離、土に混ぜる肥料の種類、植え替えの時期など、それぞれの植物に合わせて環境を用意する必要が
もっとみる創作することは体の機能の一部
新しい机を買った。机自体を斜めにすることができるため、姿勢が前かがみにならない。先日、腱鞘炎になってしまったため何かを改善しなければと思い、まずは姿勢を直してみることにした。だから作業部屋には、大きな机が2つ並んでいる。1つは音楽やWEB系の作業をするため、今回買った斜めの机は絵を描くためだ。
ふと、高校生の頃の自分を思い出した。絵も描きたいし、音楽もやりたい。けれども進路は一つに絞らなければな
芸術は感想の押し売りではない
どこにいるのか、毎朝自分と確認する。今は真ん中にいるらしい。とても平穏で、静かな世界が流れている。真ん中の世界を知ったのはこの街へ来てからだからまだまだ新鮮で、知らないことも多い。家事や事務作業などのできることは増えるけれど、感情は少し鈍くなっている気がする。薬を飲むことによって真ん中を維持させて、感情が振り切れないようにしているのだからそりゃそうか。真ん中にいると創作ができなくなってしまう不安が
もっとみる文章を書くことは発見の連続
朝寝坊してしまい、昨日は文章を書けなかった。書けなかった日は頭の中で文章が渋滞している感じがして、なんだかソワソワする。夜に書いてしまうと、脳みそが覚醒して寝つきが悪くなるから朝書くようにしていて、朝のラジオ体操のような役割になってきている。私にとっての文章は脳内整理みたいなもので、散らかった部屋を片付けている感覚に似ている。頭という部屋の中に散らばっている文字を収納棚に収まるように選んだり、入れ
もっとみる