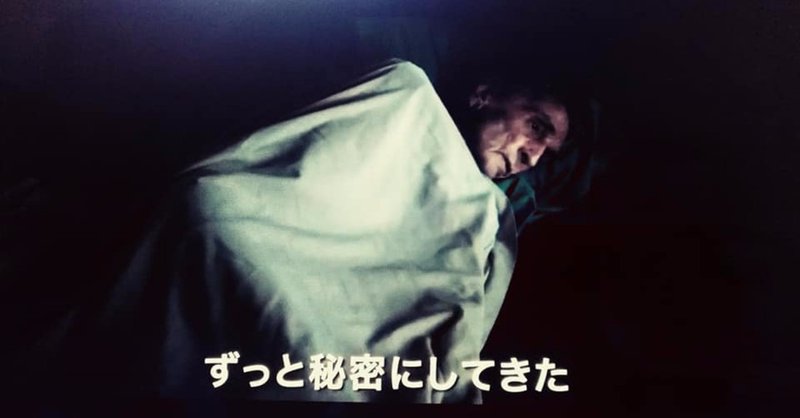#24節気72候
寒露:第51候・蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)
晩秋ともなると、夜にあれほど鳴いていた虫たちの声が減る。
蟋蟀戸にあり、
虫の数が減って、合唱だった歌が独唱となり、その歌が侘しくさせるのだろう。
秋も、彼らの生も残り僅か。
離れていくから名残惜しい。
恋情は燃えるが、それを振り払って、引き剥がして生きていく。
「あき」はそうやって「あきらめていく」とき。「飽きる」も語源だともされるが、いずれにしても距離が「空いて」いく。
自分の何
大暑;第35候・土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)
大暑 土用
土はますます黒くなる
しかし 東京のど真ん中だと 土の上に立つことは ほとんどない
蝉の幼虫も アズマヒキガエルも アスファルトで轢死体になって よく見つかる
恵まれたことに 氏神様の境内にある小さな畑で藍を育てる機会をここ数年いただいている。
藍染に使う蓼藍だ。
今年は土も入れ替えて 被さって日陰を作っていた椎なども剪定してもらって明るくなった 肥料も概ねひと月ごとに与
大暑;第34候・桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)
氏神さまの赤坂氷川神社には、徳川吉宗公が一ッ木にあったとされる氷川神社をこの地に遷座(1730年)して以来の拝殿が残っています。総欅造り、朱漆塗りの拝殿は、関東大震災や東京大空襲を奇跡的に免れて創建時のまま残っています。
正面の壁間には桐と鳳凰が描かれています(写真は赤坂氷川神社のサイトより拝借)。古来中国では、聖天子(徳のある優れた王)が即位すると、瑞兆である鳳凰が現れると伝えられてきたといい
小暑;第31候・温風至(あつかぜいたる)
都心の氏神様の杜で蝉の声をこの夏初めて聴いた 境内の小さな畑では藍が青の滲んだ緑濃い葉を広げてきた
月桃の花も咲いた
この日はまっすぐ南下し 三浦半島へ向かった お庭の現場の下見
今まで馴染みがなかった土地だけど
「半島」という響き 海に迫り出しているというだけで魅力的だ
しかも地質学的にかなりユニークな土地 何十億年も前に差し込まれたフィリピン海プレートと太平洋プレートによる鬩ぎ合い
小暑;第32候・蓮始開(はすはじめてひらく)
鎌倉地方での仕事の合間、ちょっと余裕ができたので思い立って、、、いや何を思ったか覚園寺へ。その名前しか咄嗟に出てこなかった不思議。
どうしてこの日この時間にこの場所だったのか。
僕はほぼ一人で仏様やこのお山と向き合った。
仏様の多くは蓮台座つまり蓮の花の䑓にお座りになっている。この世で得業を積み、清らかな心で成仏すると極楽の蓮華の上に転生化生するという。
このイメージはあまりに美しい。
芒種;第25候・螳螂生(かまきりしょうず)
冷房が効かないので
窓を開けて車を走らせていると
どこからやってきたのか
蟷螂の子がフロントガラスを斜めに翔けていく
たった一匹
梅雨入り前の途方も無く広い空を眼下に
二つの鎌を立て
身を反らせて
三角まなこはみどりの粒で
あんなにも軽々とあらわれて
もう会えない
花を活ける仕事をしていると
稀に蟷螂の卵が付いている枝がある
捨てられないのでバルコニーなどに保管しておくと
小満;第22候・蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)
生まれ育った地域はかつて養蚕がとても盛んな土地柄で、小学生の頃は隣もお向かいも裏の家も田畑と養蚕を営んでいた。
隠し部屋のようになっていて使うときだけ降ろす階段が、土間続きに設えられていて、それを不思議な感覚で登った記憶がある。登ると蚕室は囲炉裏や寝室のある一階の上ほぼ全てという広さで、そんな板張りのガランとした「お蚕さん」の蚕室に何度か入れてもらったことがあるけど、何百匹といる蚕が草を食む音に
立夏;第20候・蚯蚓出(みみずいづる)
分解者の代表 蚯蚓。特にこの時期、彼らの役割を改めて思い出す。
場所は世田谷ものづくり学校。
ぽくぽくと土を耕してくれて、年々土は豊かになっていく。
人の手は最小限にしている都市では珍しい場所。足元に広がっている見えない営みが命を支えている。
蚯蚓もまた死んだら次の命の場所になる。