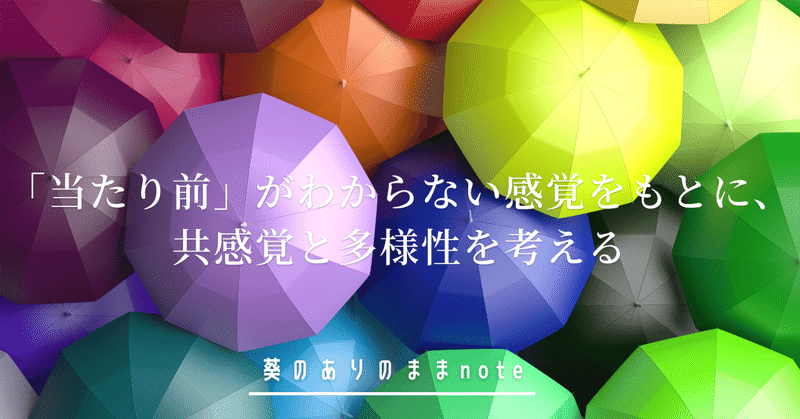
「当たり前」がわからない感覚をもとに、共感覚と多様性を考える
先日、聴覚に関する共感覚についてああでもないこうでもないと思考整理を行っていたが、
その中での私の仮説として、
聴覚過敏があるのに、小さな共感覚の反応した音を拾って来れない。ということは普段から聴こえてくる音を拾う場所と、共感覚で反応する「音」というものは全く別の箇所から反応しているのだろうか。
というもので着地した。が、あくまでも仮説だとその時も付け加えている。
この話を先日、川﨑先生にしたところ耳が聴こえている情報と共感覚での聴覚の反応が違うのはそりゃーそうだというニュアンスの返答がきて、そのまま次の話に流れていった。
この仮説は仮説ではなく、当たり前に考え付くことだった。
(もちろん解明されていない為仮説ではあるが)
この試行錯誤してやっと導いた「共感覚の聴覚は普段の音を拾うことと別なのかも」ということに気付くということが、共感覚者にはとても困難だということがこのやりとりでよくわかった。
前回は写真は視覚情報だけかもしれない、と曖昧表現を使ったがそれもわからないのだ。
共感覚というのは、ただの感覚に過ぎない。
なんとなく目に入ってくるもの、手で触れるものに対して、その感覚があることに疑問を持つことはあるだろうか?
ふわふわしたものに触れたら、柔らかかった。
その感覚に疑念をいだくことは?
おそらくないだろう。それが当たり前なのだから。共感覚者もそれと同じだ。
ふわふわしたものに触れたらやわらかく、色が見えた。
ここまでが共感覚者の疑念を抱かない当たり前の感覚の動きで、これが共感覚ではないかなどと考える当事者はなかなかいないのだ。
情報が少なく、私は自分の体験をもとに文献を調べながらなんとかかんとか仮説を立ててはみるが、あくまでも仮説で終わったり、また1から考え直しだということも何度も何度もある。
正しく伝えていきたいからこそ、このように仮説を立て、共感覚者がどのように自覚していけばいいか、苦しいことから逃れられるかを考える。
先日先生と話したことではこの、「当たり前だと思っていることに気付けなく、当たり前だと感じているものが違うことがある」ということが大きな衝撃だった。
これは、今世間で多く取り組まれている多様性を考える時に必ず出てくるであろうキーワードだ。自分には当たり前、だけどそうでない人もいる。それはなにもおかしくなくて、理解できなくても、自分はそうではなくても、受け止めていこう。それが昨今の流れだ。
誰かの当たり前は自分には違って、だけどをそれを受け入れられる、そんな社会であるように、その中に共感覚も入れられるように。
次に私に出来ることは何か?それを絶えず考え続ける。
山口葵
▼共感覚についてのマガジンはこちら▼
▼BeautyJapan2022グランドファイナリスト山口葵の応援方法▼
公式Facebookページへのいいね&フォロー

Facebookのフォロー

応援よろしくお願いいたします。

文章を楽しく書いている中で、 いただくサポートは大変励みとなっております。 いただいたサポートは今後の創作活動への活動費等として 使わせていただこうかと思っています。 皆さま本当に感謝いたします。
