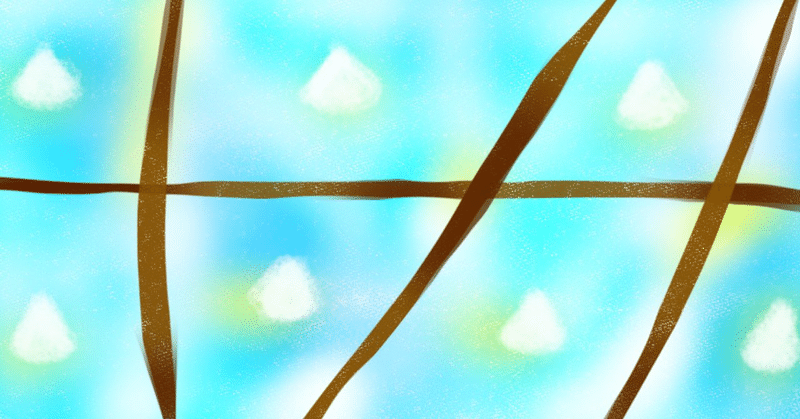#創作大賞2024
六言六蔽。優れた人徳が備わっているのに、結果がついてこないのはなぜか―『論語』
人の役に立ちたい。
困っている人を助けたい。
世の中に貢献したい。
強きをくじき、弱きを助けたい。
どんなに正義漢が強く、どんなに人徳に厚くても、それをうまくいかせないことがあります。
それは、自分の能力を自在にコントロールする知恵や術が備わっていないから、ということが多いのではないでしょうか。
あるいは、経験が足りないのに、頭でっかちで意識だけ先走ってしまう。結果、パフォーマンスを存分に発揮で
人はなぜ不正をするのか。止めることはできないのか。その3―荀子の「性悪説」
人の本性は「悪」である
なぜ人は不正をしてしまうのか。
それは、もって生まれた性質と、どう関係しているのか。
企業において、弱い立場にある社員が、組織的な圧力に屈して、自らの良心に反して、不正に加担してしまう。それを防ぐには、どうすればいいのか。
古代中国の人間観、思想をおさらいすることで、組織において立場の弱い人が不正に加担してしまう理由を探るシリーズ。第3回。
孟子の「性善説
投稿するのは何のため?
何のために投稿をするのでしょうか。
何のために書くのでしょうか。
ふとそれを記事にしてみたくなったのは、このところ、「投稿について書かれたみなさんの投稿」を目にすることが多くなったせいだと思います。
もちろん、なぜ投稿するのかを、必ずしも明文化する必要はないと思っていますが、記事にあるみなさんのお考えが、それぞれとてもおもしろくて──では、わたしはわたしなりの「何のため?」を、この機会に探ってみ
他人のせいにしても、何も解決しない。自分の内なる声に素直に従う―『呻吟語』
書が下手なのは、筆のせいでも、紙のせいでもない
失敗したときやモノゴトがうまくいかないとき、ついつい他人のせいにしてしまいます。政治や世の中がよくないからだ、と不満をぶちまけて、やり過ごすこともあります。
そこに一面の真理はあるにしても、正義をふりかざしたからといって、ましてや世の中のことをいくら憤っていても、問題は解決しません。
かえって、あの人はいつも正義漢ぶっているけど、不満をぶ