
ニジマスが1回の産卵のみのキングサーモンの卵を産める様に、細胞移植!資源確保へ。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
サケは、多くの人に愛される食材だと思います。キングサーモンは、和名で「マスノスケ」と呼ばれ、寿司やステーキで食されています。脂の乗った厚い身が特長だといいます。
サケは多くの食卓に並ぶ食材の1つだと言えますが、実はあるデメリットがあることが分かって来ました。
キングサーモンやベニザケなど北太平洋を回遊し、日本や北アメリカなど故郷の川に戻って産卵するサケ類の仲間(タイヘイヨウサケ属)のほとんどは、生涯に一度しか繁殖せず、産卵後に雄雌共に死んでしまうといいます。
そこで、一度しか産卵しないキングサーモンに代わり、今代用されつつ研究が進んでいるのが、ニジマスです。
サケは一生に1回しか産卵しませんが、ニジマスにサケの細胞を移植することで、サケの卵を繰り返し産ませることに成功できたと、魚類発生工学が専門の東京海洋大学の吉崎悟朗教授などの研究チームが明らかにしました。
高級食材であるサケの養殖の効率化や遺伝資源の保存や保護などに役立つと期待が持たれています。
論文が2024年4月24日、科学誌[サイエンス・アドバンシズ]にて発表されました。
今回は東京海洋大学が行っている、研究の概要について紹介したいと思います。
東京海洋大学のニジマスを使った研究の概要

キングサーモンは成熟まで3~7年要し、産卵や精子など受精は一生で1回だけ行います。その反面、同じタイヘイヨウサケ属で、キングサーモンやベニザケと一緒でも比較的原始的な、小柄なニジマスは6~7年の生涯で産卵や受精が毎年できます。精子や卵の基になる「生殖幹細胞」が、ニジマスの身体内には何年も残るのに対し、キングサーモンは1回で消失してしまいます。
今回、研究チームはニジマスの産卵能力を活かして、キングサーモンの卵が得られるかを実証実験をしました。稚魚は雌では2歳、雄では1歳で性成熟し、サケの「生殖幹細胞」が作られる様になりました。
吉崎教授など研究チームは、ニジマスとキングサーモンの精巣や卵巣を比較しました。ニジマスが繁殖した後も「生殖幹細胞」を維持しているのに対し、キングサーモンは使い切っていました。
その結果、オス27匹中10匹も1~4歳の4年続けて精子を作り続け、メスは24匹中5匹が、2~4歳の3年に渡り毎年卵を作り続けました。
そこで、ゲノム編集で自身の卵や精子を作れなくしたニジマスの稚魚に、キングサーモンの精巣から、卵や精子に分化する「生殖幹細胞」を取り出し、生まれたばかりのニジマスに対し移植しました。成長させた「代理親」のニジマスは、キングサーモンのDNAを持つ精子や卵を作り、それを交配させて稚魚もできました。移植した「生殖幹細胞」はその後も維持され、代理親は翌年以降も毎年、キングサーモンの卵や精子を作り続けました。
ニジマスは1~2年で成熟すると、キングサーモンの遺伝子を持つ精子や卵を毎年作り続ける様になりました。ニジマスはサケの精子や卵を毎年作り続け、4歳になるまでに作る「生殖幹細胞」の総数は通常のサケと比較して、卵はおよそ5倍の5000個程度、精子ではおよそ2倍の1兆個程度に増加していました。移植した「生殖幹細胞」によって作られる卵や精子の量や回数は、代理となる親魚に制御されることが明らかになりました。
小型のニジマスを代理親にすれば毎年繁殖できるため、短い期間で安定的な養殖ができる様になります。
サケの養殖では毎年、大量の親魚が必要になります。今回の新しい技術でニジマスを代理の親魚とすることで手間を減らし、これまでの実証実験よりも短い期間で次世代の個体を得られるメリットもあります。一般的に魚の品種を開発するためには5世代の交配が必要とされ、15〜20年程度要しますが、新しい技術を使うと5〜10年程度に短縮できると見込まれています。
吉崎教授は、「キングサーモンは数年かけて成熟させても、一度卵や精子を取って終わりですが、ニジマスなら飼育も簡単で、1年目から繰り返し繁殖できます。養殖の果たす役割がこれからますます大きくなる中で、ニジマスを親にして別の魚を産み出すという新たな養殖スタイルが誕生したかもしれないです」と主張しました。
「『生殖幹細胞』を凍結保存すれば、絶滅の危機に瀕しても、遺伝的に同じ魚を復活させることが可能です。希少性の高い高級魚などの養殖技術や品種開発に応用できれば、安定的に美味しい魚を供給できるやり方になり得えます」と説明しました。
参考:ニジマスにサケの卵繰り返し産ませることに成功 東京海洋大学 NHK NEWS WEB(2024年)
この東京海洋大学の新しい技術は、それ以外の魚にも適用することが可能です。
2007年に、東京海洋大学の研究チームは、5年程度、冷凍保存していたニジマスの「生殖幹細胞」をヤマメに移植して次の世代のニジマスを作ることにも成功していて、これらの技術を組み合わせることで、ヤマメにニジマスの卵を産ませたことをきっかけにアジやコイ、サバなどでもそれぞれ遺伝的に近い仲間同士だと適用できることを確認した以外にも、クサフグという小型のフグに高級魚で知られる大型のトラフグを産ませることにも成功しています。
将来的には絶滅危惧が指摘される魚の「生殖幹細胞」を保存し、別の魚に卵を産ませることで種を保全していくことにも役立てられると考えています。
魚類育種遺伝学が専門の、北海道大学の教授の男性は、
「キングサーモンの卵や精子が安定的に得られる新しい技術で、養殖に大いに役立ちます。産卵回数が『生殖幹細胞』ではなく、代理親で決まることも意義深い発見だと言えます」
と述べました。
吉崎教授は、「新しい養殖スタイルになり得ると思っています。高級サケの品種改良を進めていきたいです」と語り、これから、より多くの種類の魚での適用を検討している以外にも、産卵のメカニズムを左右する「生殖幹細胞」に関してさらに詳細に解析していくといいます。
サケは好きな魚
私は子どもの頃、家族と回転寿司屋さんに行くと、いくらしか食べていませんでした。私は結構偏食で、いくら以外なら、いなり位しか食べていませんでした。
典型的な好きなものだけを食べて、飽きることがないので、食べ続けても全然大丈夫な人間です。
ずっといくらだけが回っているわけではないので、お店の人に「いくらを下さい」と、オーダーしたり。
しかしそんな日々に変化が現れます。サーモンの登場です。
どこで初めて食べたか忘れましたが、サーモンを食べた時、「こんなに美味しいものがあるなんて」と、一瞬で虜になりました。
回転寿司で、いくらは割と高めな皿であることから、サーモンを食べる数が増えました。
サケも地球沸騰化の影響で北海道ですら、獲れる量が激減しているらしいですし、東京海洋大学の今回の研究成果は、大いにこれから役に立つ研究だと思いました。
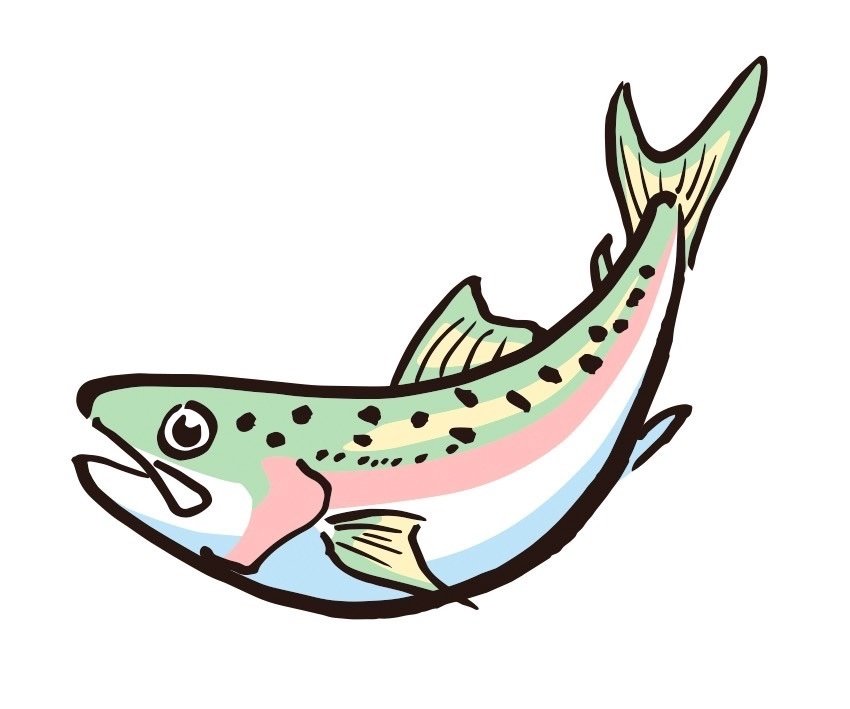
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
