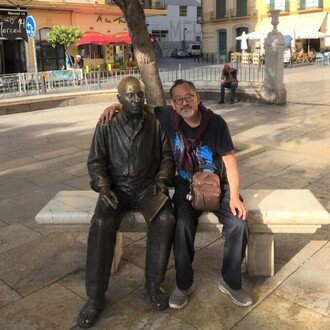2022年12月の記事一覧
<書評>『白と黒の断想』
瀧口修造著 2011年 幻戯書房
日本のシュールレリストの第一人者である瀧口修造が、評論家として、20世紀に活躍した写真家を中心に、ピカソやダリなどの著名な芸術作品も含めて、個々の作品とその短評(解説)をまとめたもの。そして、ところどころに瀧口が作った、それぞれの作家をモチーフにした、シュールレアリスムのイメージあふれる詩編が散りばめられている。
書名となった「白と黒」とは、全ての写真や美
<ラグビー>2022~23シーズン、大学選手権準々決勝の結果、リーグワン第二週結果、インターナショナルラグビー関連(2023年からのルール変更等)
(どうでもよい「話の枕」です。関心ない方は飛ばしてお読みください。)
先日衛星放送で『オズの魔法使い』(1939年アメリカ、日本公開は1954年)を観た。もう83年前となる古い作品であり、今ならCGを屈指するところを書き割りのセットで撮影している他、シンプルな合成映像を使っているので、「古く稚拙な映画」と一笑する若い人が多いと思う。しかし、逆にその古い技術でしっかりと作られているからこそ、異
<映画評>アメリカングラフィティ
今やハリウッドを代表する監督になっているジョージ・ルーカスが、1973年に公開(日本は1974年公開)した、1950年代後半のアメリカ中西部の田舎町(しかも住人はヨーロッパ系ばかりで、有色人種は中南米系が少しいるだけ)の中産階級の高校生を主人公にした物語。
当時のヒット曲をメドレーで流しながら、名DJのウルフマン・ジャックも登場させて、「懐メロ+王道の青春群像」ドラマにしている。『スター・ウ
<書評>『イタリア・ルネサンスの文化』
『イタリア・ルネサンスの文化』ヤーコブ・ブルクハルト著 柴田治三郎訳 中公文庫
原本は1860年、文庫は1974年。
1.普通の書評として
著者は、歴史を勉強するものにとっては、いわずとしれた大家である。また、フリードリッヒ・ニーチェとも親交のあった学者で、19世紀末のキリスト教思想に対する批判精神を持っている。そうした雰囲気は、本書の対象であるイタリア・ルネサンスの文化の担い手であった、当