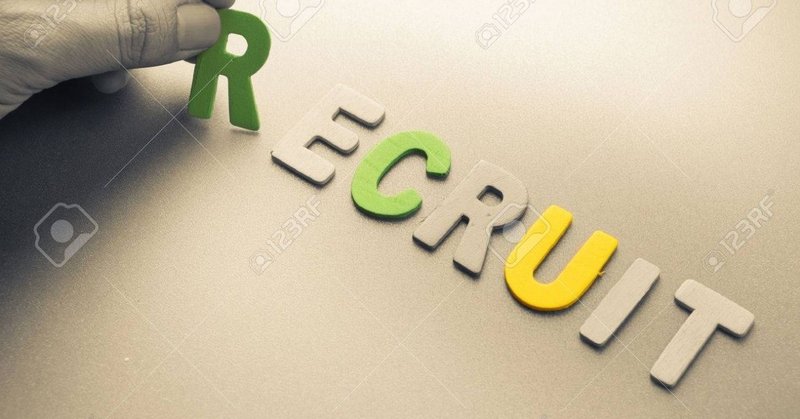
リクルートの強さの真髄は、「心理学×経営にある」
「人を育てる」
「圧倒的に成長できそう」
「社会を変えていくような新しい取り組みを行っている」
「仕事に対するモチベーションが高い人が集まっている」
「新しい事業を生み出している」
などのイメージがあるリクルート。
上記のようなイメージを持つリクルートは、人/組織に対して世間からは、肯定的な評価を得る事が多い。
「勢いのある営業のイメージ」も強いリクルートだが、それだけメンバーをやる気にさせているのはいったいなんなのか。
世間的には有名ではないかもしれないが、リクルートの基礎を作った方々は心理学出身が多い。
創業者の江副浩正氏、創業メンバーであり、組織活性に関する施策の中心にいた大沢武志氏はいずれも、東京大学教育学部教育心理学科出身。
心理学の学術的な実証結果を参考にしながら、人組織へ深い洞察を行い、人事制度設計や風土情勢を設計している。
そこで今回は、人材開発の名著でありリクルートの神髄であるとも言われている、以下の書籍について、今後役立ちそうなTIpsをまとめていきたい。(これから、本 NOTEをどんどん更新していく予定)
※HR分野の著名な方がお薦めする書籍に、だいたい紹介されている。
▽心理学的経営とは
「人には建前と本音がある」
「合理的なシステムに対して非合理的な人間の行動」
「表のマネジメントに対して裏のマネジメント」
というようないわゆる合理的な人間像ではなく、ありのままの人間に対する理解を中心に企業経営を考える経営手法。
合理化/効率化された官僚組織への懸念を持ち、人間行動の本質は、ノイズや無駄な情緒を含む感情が基底にあると捉える。
例えば、効率性/専門性を求め、分業すること、システマティックに指揮命令を整える事により、人は働きやすくなるのか。生産性が上がるのかという点に大きな疑問を提示している。
それよりも、本音や建前をありのままに受け入れる事に重きをおき、「べき論や建前論でひとは動かない」とし、実際に人間がイキイキとモチベーション高く行動するにはどうすればよいのか。
そのメカニズムやその背景をありのままに理解することを重視する。
▽モチベ−ションに関する理論
心理学的な経営では、これまでの産業心理学を中心に、以下のような理論からモチベーション向上を捉える。
a.内発的な動機付け(ハーズバーグの二要因理論)、
b.職務特性モデル(ハックマン=オルダム・モデル)を基底にしている。
aの内発的な動機を形成するために、業務に対して自分なりのやり方で取り組ませる。
チャレンジし自分で統制しながら達成感を味わい、報酬を得る。
リクルートでは、仕事の報酬は仕事という文化があり、成果を上げるとさらに責任の重い仕事を任せてもらえる。
また、同僚や上長からのFB、表彰制度や日々の上司との定例、挑戦を奨励する風土などが巧みに整備されているという。
bについては、職務特性モデルを意識して、業務をメンバーに期待を添えて任せている。
※①、③、⑤は上司とのコミュ二ケーションの中から、②、④は仕事の進め方である。
①スキルの多様性:仕事を達成するためにどのくらいスキル/能力を求められるか。
②タスクアイデンティティ:課業の一貫性。始めから終わりまで携わる事ができるか
③有意義性:仕事の意味がどれほどあるか。組織/社会への影響範囲。
④自律性:仕事の結果に対する責任意識に直結。自分の考えや意思によりどれだけ段取りを決められるか。
⑤FB;自分の仕事の結果成否を確かめる事ができるか。
上記を踏まえて、特に下記3つが若手メンバー向けの内発的動機付けには特に大事だという。
①自己有能性 :自分が仕事を通して自己効力感をもてるか
②自己決定 :業務の計画から実行まで自分が主体として進めていけるか
③社会的承認性:同僚や上司から自分の仕事が認められるか
上記のような観点で、メンバーと接する事ができること。
業務を切り分け、メンバーに期待を添えて業務を渡す事ができるとモチベーション向上に寄与する。
少しでもキャリアの参考になった、転職活動に参考になりましたら、ポチっといただくと励みになります。
