
執着の源である”言語”を「心の解放」のために転用する -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(3)
『精神の考古学』 第五部「跳躍(トゥガル)」の冒頭、中沢氏は師匠から授けられた言葉を紹介する。
「ケツン先生のような精神の探究者にとっては、ふかふかの椅子に体を沈め、目の前にスクリーン上にくりひろげられる光の劇をただ受動的に眺めて、いたずらに感情や思考を刺激されているのが「ベスコープを見る」ことにほかならない。それと同じように、トゥガルのヨーガを通して自分の目の前に展開している光の運動を、それがいったい何なのかという正確な理解をもたないままに陶然と眺めているだけでは、映画を見るのとなんらかわりがない。この光のヨーガはゾクチェンの哲学と結びつくことによって、はじめて心の解放のための強力な方便(手段)となりうるのだ。」
ベスコープというのは映画のことである。映画を見るのはとても楽しい体験である。感情を喚起され、いろいろなことを考えさせられる貴重な機会である。
中沢氏がネパールでチベット人の先生のもとで取り組んだ修行にも、「光の運動をみる」ヨーガが含まれている。このヨーガで光が見えることと映画を見ることとは、視覚が動くという点ではよく似た体験である。
「光を見る」ことを「心の解放」のための方便にする
ここで中沢氏のお師匠さんは、映画を見る体験と、修行で光の運動を体験する経験とのちがいを強調する。修行で、瞑想の中で光を見ることは、あくまでも「心の解放」のための「強力な方便(手段)」として用いられることである。
ヨーガ、あるいは瞑想に入って「光」を見るということは、ある程度訓練をすれば(あるいは訓練をしなくても発熱や過呼吸で意識が変容した状態になれば)案外だれでも体験することができるという。実はこれを書いているわたし自身、子どもの頃、病気の発熱でうなされながらそういうのをみたことがある。これについては下記の記事で簡単に紹介しているのでご興味あればどうぞ。
こういう「みえる」は、ただ見えたというだけでは、「見えているなあ」「ふーん」「へえー」という、あくまでも感覚というか、印象というか、それだけでは言葉にならない。見終わって「ああおもしろかった」と思うか「ああ怖かった」と思うかは人それぞれだと思うが、いずれにしても感想を言うとすれば「不思議だった」くらいのものである。これだけでは「心の解放」とは程遠い。特に、
見ているわたし / 見られている不思議な対象物
というこの対立・分別は、瞑想状態から意識を取り戻した瞬間にはっきりと際立ってしまう。さらにその「見られている不思議な対象物」を「おもしろい」とか「こわい」とか「神」とか「悪魔」とか、何でも構わないが対立する価値の二極のどちらかに振り分けて「いい」とか「わるい」とか、二つに分けてどちらかを選ぶ分別評価・合否判定をすることもできてしまう。
と・・、そういうことをやって止まない分別心こそが、妄念を生み、妄念への執着に人を追い込み、そして苦しめる、というのが仏教の考え方である。分別心を離れる、二辺を離れる、ということが「心の解放」であり、そのために修行する。

* *
「みる」ための哲学
この「みえる」を「それがいったい何なのかという正確な理解をもたないままに陶然と眺めているだけでは」修行にならない。
「みえる」を「心の解放」のための「方便」として活用するためには、「見るものと見られるもの」、「主体と客体」、「光と眼」といった”光を見ること”にまとわり付く分別=二項対立が、いわば現れたり消えたりを繰り返しながら脈動し、対立する二極が分かれつつも分かれない、分かれているでもなく分かれていないでもない、という状態で美しく振動する様を明晰に意識化=言語化できる必要がある。
そうした”分かれているでもなく分かれていないでもない”を整然と説くことができるための論理性(両否の論理、レンマの論理)、カオスがそのままコスモスである「カオスモス」の論理を鍛えた上で、この論理でもって、「みえる光」が「いったいなんなのか」を”理解”し、解いて=説いていく。
++
この論理性を獲得するために、修行者はまず、光の瞑想に入る前に、その「哲学」を学ばなければならない。ここから言語による修行、井筒俊彦氏の言葉を借りれば「意味分節修行」といったことを修することになる。
修行としての意味分節
その哲学とは、言語の論理性を日常のそれとは全く違うモードに励起する、極めてシンプルでありながらあり得ないほど破壊的で創造的なアルゴリズムである(アルゴリズムをマンダラと呼び変えてもいい)。
言語を、わたしたちが物心ついたときからなんとなく使っている日常の信号伝達的コミュニケーションの手段としての姿から(記号とその意味内容をぴったりとくっつけておくコードが社会的に共有されて定まっているべきだ、というところに”みんな”が同意しているような領域から)、ふわりと浮かび上がらせて、いや、剥離させて、その破片たちを深く深く沈み込むような…、瞬間的に床が消えて、どこまでも落下しながら、ああ、ここは宇宙なのだ、上/下の分別はあってもいいしなくてもいいのだ、という感じにまで励起していくような・・・。それを瞑想ではなく、言語そのものによって、言語の論理性が崩壊するようなしないようなぎりぎりのところで組んでいく。そういう哲学、言語的思考を方便とする道があるのだ。
というわけで、すこしページを戻って、『精神の考古学』の152ページから、言語を「心の解放」のための方便に組み替える方法をみていこう。

「心」と深く向き合う
「セムニーはたえまなくセムに変容してつぎつぎと妄想が湧いてくるが、思考を停止してセムニーの中にしっかり止まりなさい[…]」
「セム」と「セムニー」のちがいに注目して考えてみよう。
セムとセムニーの混成体
中沢氏は『精神の考古学』で、私たち人類の心は「セムとセムニーの混成体」であると書く。
「人間は生と死がくりかえす輪廻する世界を生きているが、その状態をつくりだしているおおもとは、身体と言葉と思考をとおして絶え間なく活動している心(セム)の働きにある。しかしこの心は純粋な心性(心そのもの、セムニー)が変性したものであり、このセムとセムニーの混成体として、人間の心作用は動いている。」
人の心はセムとセムニーの混成体である。
セム・分別心
まず、セムとは、分別心、分別=対立する二極・二辺を”切り分ける”働きが連鎖する動きである。
このセムの働きによって私たちは身体と言葉と思考において、
生/死
有/無
静/動
同一性/差異
心/物
主体/客体
主観/対象
といったありとあらゆる分別をつけて、二項対立関係を立てる。
ここで、生/死を分けては生だけを選び取ろうと執着し、そこから有/無を分けて有だけに執着し、そこから有を欲し、欲したもの(欲望の対象)を自動的に発見して自分のものにするような仕組み(感覚〜識)が固まっていって迷う、というのがいわゆる十二支縁起である。
人は分別する心によって、ほんらいそれ自体としての実体はないはずの二項対立する諸項たちをそれ単独で取り出して、自分のものにしようとしては、それが叶わぬことを思い知らされて苦悩する。このことから身体と言葉と思考は、密教では三つの「毒」、三毒とも呼ばれる。
セムニー・分けるでもなく分けないでもなく
セムニーとは、分別するセムがそこから生えている場所であり、分別するようなしないような動きをみせるところである。セムニーを「セムニーとはXのことであります」というように、いずれかの実体としての項(つまり分別心が分節した項)に言い換えることはできない。セムニーのことを言語でもって言おうとすれば、仮にレンマの論理(Aでもなく、非-Aでもない)でもって、対立するはずの二極が絡み合いつつ分離し、響きあいつつぶつかり合い、共振しつつずれる、混じり合いつつ分かれている、といったようなことになる。
* *
人間は、このセムとセムニーの「混成体」としての「心」でもって、ものごとを分別・差別する。そしてそれとまったく同時にふと思いついて「分けるでもなく分けないでもない」と覚ったりする。

「セム」はこの絵で言えば、一つ一つの結晶構造である。
一方「セムニー」は結晶が育つことを可能にしているこの洞窟そのものである。
とイメージしてみてはどうだろうか
セムニーは遠く離れていない
それ自体として「何であり、何ではないか」を言葉で分別して説明することはできないのが「セムニー」であるが、このセムニーは私たちの日常の分別心・セムと切り離され隔絶しているわけでもない。
このセムニーは、セムが微妙に「?」という感じになるところで、原初的な文字のようなもの、音声のようなものとして、私たちの感覚に捉えられる姿を現す。
しじまの微振動、鳥たちの歌
「音声化されたセムニーまたは存在の振動は、日中は鳥たちの歌をとおして、夜は「しじま」の微振動をつうじて、音声の「紐」で私を世界につないでいた。」
セムニーは「音声化」される。
つまり繊細な空気の振動となって、私たち人間の心身を震わせる。
昼間なら鳥たちの歌を「とおして」、夜なら「しじまの微振動」を「つうじて」、行者である中沢氏の三密(身体・言語・心)と共鳴する。
鳥の歌や、夜のしじまの「微振動」を、音声化されたセムニーとして聴く耳を育てること。これを読んでいて、中沢氏の以前の著書『ミクロコスモスII 耳のための、小さな革命』を思い出した。
「私はまだゾクチェンの正行を始めていなかったが、心(セム)の動きが自分の中に生じた瞬間に、その心の動きをセムニーに即座に溶解させていく要領をつかみ始めていた。」
日々忙しなくしていると、セム(分別心)に分別の材料を提供するための器官として習慣づけられている「耳」であるが、同じ耳が、音声化されたセムニーの振動を聴き取ることができるように、いわば励起されると、セムニーから生えてきた瞬間のセムの動きを聞き取り、束の間分別を働かせては、不意にセムニーへと溶けていくセムの動きをも聞き取るようなことができるという。
妄想を分別して私たちを苦しめてやまない「セム」が、実は鳥の声や夜のしじまの微振動と共鳴する”セムニー”と異なるものではないこと。セムは「即座に」セムニーに「溶解」できるということ。そう覚った心は、なんと自由であることだろう。
これを中沢氏は「意識が二チャンネルに分離して」いる状態とよぶ。
「このような意識状態で[…]山道を歩いていると、とても不思議な体験をするようになった。自分の意識が同時に作動している二チャンネルに分離して、いっぽうのチャンネルではこれまでどおりの外の世界を見ているのだが、もう一方のチャンネルでは青空のような空をみている。[…]「色即是空空即是色」の奇妙な体験が持続されるようになっていた。」
「これまでどおりの外の世界を見ている」、つまり分別心でもって、他ではないあれがある、他ではないこれがある、という具合に「それではないもの」から諸項を分別している。それとまったく同時に、その分別された諸項が「空」、色即是空の「空」であることをみている。
分別されたあれこれは「色」である。
そしてそれがそのまま「空」である。
空か、それとも色か?!
空と色を二つに分けて、空がホンモノで、色がニセモノ、といった分別をしない。まさに色即是空空即是色。
+ + +
現象をつくりだすゲシュタルト(形態)に関する
”情報”
ここで「空」は、分別心(セム)と異なるものではないし、もちろんセムニーと異なるものでもない。
「空である心はリクパに内蔵された力の充満する原空間であり、この原空間には現象をつくりだすゲシュタルト(形態)に関する情報がたっぷりと詰め込まれている」
「空」は「心」と異なるものではなく、「現象をつくりだすゲシュタルト(形態)に関する情報」が格納された「原空間」ということになる。
ここに「情報」という言葉が用いられていることに注目しよう。
情報というのはバイナリ(0か1か)の情報理論がそうであるように、煎じ詰めれば二項対立を分別して、どちらを選ぶか、ということを重ね合わせていくことである。
分けては選び分けては選びする”情報処理”により、あれこれの「色」、つまり人間にとっての感覚的で経験的な「物事」たちそれぞれが、他ではない何かとして姿を現す。
ここで「リクパ」というのは、原初的な心(セムニー×セム)に「自発的に生起する本来的な意識」である(p.154)。心(セムニー×セム)はガッチリと固まって静止しているモノではなく、動いているような動いていないようなコトである。この心の動き方、振動の仕方のようなことが、まったくのランダムではなく、あるパターンを描くようにリズミカルに、テンポよく(?)脈動し、つまりある一定の波長(周波数)を示しており、そしてどうやら、この波長を複数重ね合わせて共振させたりさせなかったりできるところで「情報」を分節することができるようになる。
極めてシンプルなオン/オフの二状態しかとらないスイッチのようなしくみでも、これを複数連ねて、束ねて、並列にして、フィードバックループを組んで、そしてネットワークにしておくと、あいまいさを考慮しながら次なる状態を予測し、予測と実際の状態を比較しながら新たな曖昧さの中でまた次の状態を予測し、という具合のいわゆる「意識」、セムの分別識の定まった姿も生まれ始めるのであろう。
+
この分節するようなしないような「深み」から、安定的に定まった共振状態としての「セム」的分別識が立ち上がってくる(いや、煮凝ってくるというほうがいいか)プロセスのことを思わずに、分別”された”後に残されたものをみて、「Aが端的にそれ自体としてある」とか、「非Aはない」とか、「Aが好きで非Aが嫌い」とやると執着、妄分別になり、迷い、苦しむ。

多層パーセプトロンとしてシミュレートするAI
(AI生成)
*
情報処理=分別され終わったAや非Aをありありとリアルにながめつつ、それが、「心(セムニー×セム)」に内臓された「現象をつくりだすゲシュタルト(形態)に関する情報」から始まったもので、このAも非Aも、A /非Aを分けることができるとコード化する情報も、なにであれ”空”と異ならない、と観じ、感じることができていると、まさに「意識が二チャンネルに分離」した状態になる。
ついつい分別してしまう
セムとセムニーは別々に異なる二つのものではなく、あえていえば同じひとつのことの異なる姿である。もちろんここで「同じ」といえば差異/同一性という分別が思考に紛れ込んでくるし、「ひとつ」といえば一/多の分別が思考に紛れ込んでくるが、だからといって言葉を使って考えたら「ダメ」ということでもない。ダメ/ダメじゃないというのも分別である。
このように私たちの心は、特に言語で理路整然と思考しようとすると、ついつい「分別」をやってしまう。その最たるものひとつが、主語と目的語の分別、主/客の区別、認識している自分の心と認識の対象との区別である。
「現象と戯れているときは、主客の区別はないが、それを自分の心とは別の対象だと思った瞬間に、セムニーのセムへの頽落が起こってしまう。」
二つに分けるでもなく分けないでもない”セムニー”が、はっきりと二辺を”分け終わった”かのように凝り固まる時、セムニーはセムに頽落する。
「心は空でもなく、有でもない、心(心そのもの、セムニー)とはどこか別のところに根拠があるのでもなく、支えをしている土台も存在しない。心はどこにも依るべきところのない無底の原空間に生起し、そこにあり続け、そこに溶融していく。[…]サンサーラとかニルヴァーナとか言われているものも、この無底の原空間に現象しているのであるから、ゾクチェンパはそれにすら執着してはならないのである。」
ここで注意するよう書かれているのは、「セムニー」とは”それ自体として本質的に何であるか”とか、「空」とは”それ自体として本質的に何であるか”とかいうことは、問いようがないし、分別しようがない、ということである。
セムニーに、それを支える「土台」はあるともないとも言えない。
土台というのは、
土台 / 上物(うわもの)
この二項対立を分別・分節するセムの働きによって区切り出された項である。心で蠢いていることを、心の表層たるセムの表面に走った分割線たちで囲まれたある区画に言い換えて、「分かった!」となることはできない。
あるいは
ニルヴァーナ / 非-ニルヴァーナ
この二項対立もまた、分別・分節するセムの働きによって区切り出された項である。「ニルヴァーナ」(涅槃)という言葉をつかもうとして、それ自体にこだわるようでは、それこそ分別して執着するサンサーラであって、ニルヴァーナどころではないということになってしまう。
分けるでもなく分けないでもない”本来清浄”
とはいえもちろんこうした「他ではないそれ」としての名前があるセムの表層の小さな”区画”ひとつひとつが、セムとセムニーの混合体の動きが描いた波紋のような現象形態であり、それが「空」と”異なるものではない”ということもおさえておこう。中沢氏は、ある文献を引いて次のように書かれている。
「粗大な思考であれ、繊細な思考であれ、どんな思考が心に湧いてきても、それは法身の広大な広がりの中に生起したものとして、生起と同時にすでに自己解脱している。法身においては空と色とは分離されないのである。」
「すでに自己解脱」というところに注目しよう。
解脱している / 解脱していない
この二辺を分別して、そこに「よい/わるい」の分別を重ね合わせて、「解脱してるのがイイんだよ」「解脱してないのがワルイんだよ」と思考判断するようなことは分別心ならではの所業である。では、このような分別心は「ダメ」なのかといえば、分別心は善なのか、それとも悪なのか、どちらか選べ、というのはまさに分けて固めようとする分別心〜妄念である。
「法身」は、解脱している/していないの二辺からも解かれ、これを脱している。
心に湧いてくる思考。
分かれているような分かれていないような微妙な脈動を感じ取る繊細な思考であれ、「うまいか?おいしいか?どっちだ」というような粗大な思考であれ、分別したり分別しなかったりすることは、ことごとく「法身の広大な広がりの中に生起したもの」であり、それ自体としては”自己解脱”している、つまり”分別しているでもなく、分別していないでもない”ことである。
そしてこのことこそ「如来蔵」の思想、さらには空海でいえば「即身成仏」の思想を可能にする論理につながっていく。
「心のおおもとである法身が純粋きわまりなく、いかなる妄想にも煩悩にも汚されることがないことを、直接体験しようとする」
心の「おおもと」である法身は、それ自体として「純粋」であり、分別心が区切り出した項が(この区切り出すコト自体は良くも悪くもない)乾燥して固まってしまったようなものである妄想や、その妄想へのこだわりとしての煩悩に「汚されることがない」。
この汚れなき純粋な清浄性を「直接体験」するために、例えば「頭蓋骨を蹴破ってセムニーに飛び出していく」という意味の「トゥガル」という名で呼ばれるヨーガなど、いくつものヨーガ(瑜伽)の行を修していくことになるのである。
*
言葉をほぐして法身と共鳴させる
この法界の清浄性を直接体験することができるためには、まず言葉を、放っておくとついつい分別した二極を”それ自体”に固めて、求めたり、厭うたりさせて止むことのない言葉を、ほぐしておく必要がある。
中沢氏は『書かれないタントラ』というタントラの一説を紹介されている。
『書かれないタントラ』
あらゆるタントラは説かれないものである
語られないものである
記号(区分)のない空間に出て行ってしまっているものだから[…]
あらゆる伝授はおこなわれることがない
考案(企み)のない空間に
出ていってしまっているものだから
追求も束縛もできないのである
対象世界はなく
心はなく
文字表現はない
それゆえに
どんなタントラもなく
どんな伝達もなく
[…]
あらゆる言葉を超えて
この空にはかたるべきなにものもないのである
「かたるべきなにものもない」というのがポイントである。
良いというのであれ、悪いというのであれ、どちらを選んだとしても、それはかたったことになる。例えば、「言葉は妄想の元だから”悪い、ダメ”」と断じるわけでもない、ということである。
良い / 悪い
OK / ダメ
好き / 嫌い
こういうのもなんとまさかの分別である。
こうなるとぐるりと転じて「言葉はダメなんだ、悪いんだ」などということも必要がなくなる。もちろんそう言うコト自体は一向に構わないのだけれども、言いながら、二辺に分別して片方だけを選んで、そこにとどまろうとして苦しむなら、それは妄念である。
言葉は、よいものか、わるいものか、どっちだ?
という問い方に対して、どちらかを選ばないといけないような気がすることが妄念なのである。だから「言葉は良いモノではないが、ワルイモノでもない」というようなことをスラスラと言えるようになっておくとよい。そのような「二辺のどちらか不可得であるようなないような不可得」なことを言う時、言葉は、人の言葉は、声は、法界とシンクロ=共鳴する”三摩耶”になりうる。

(AI生成)
二辺を”離れる/離れるない”の二辺を
離れるでもなく離れないでもなく
法界の清浄性を直接体験するために大切なことは、ありとあらゆる分別を超えることである。
すなわち、分別する/しないの分別さえ、超える!
中沢氏はここで『リクパのカッコウ』という書物の言葉を紹介する。
「世界の多様性は二元論を超えているが個体は概念がつくる概念構成から自由である。世界に「まさにかくのごとき」と確定したものなどなくすべての現象はあるがままに善である。存在は自ずと完成しているから努力して何かを得ようとする病を断って無努力のうちにとどまるのが、私の教えである。」
セムによって分別され、二辺に分たれたあれこれは、ほんらい無自性であり、そして「善」である。
”分別する/分別しない”
といったことからして、分別である。”分別することが悪で、分別しないことが善”などと言うのも分別に分別を重ねて固めた妄想分別である。
そして
善/悪
これもなんと、分別なのである。
上の引用には「あるがままに善」と書いてある。ここは気をつけて読んだ方が良さそうである。同じことであるが「存在は自ずと完成している」ともある。
この「あるがまま」の「善」は、善/悪の二項対立の一方に切り出された”善”ではない。それ自体として善でもなく悪でもない、という言い方の方が論理的に適っているのかもしれないが、このような言葉を「セム」で固まっている心で読んでしまうと”善でもない”に引っ張られて、「ああ、悪でもいいんだ」などと分別して迷う可能性もあるので、言葉でいうなら仮に「善」とおいておこう、ということになろうか。
ある概念をそれではない概念と分別することことによって切り分けられた二項対立から自由になること。自由といっても、不自由と自由を分別して対立させる必要もない自由である。
法界・心・空は、これ本来清浄で、二辺のどこにも止まらないという点で自由なのである。この本来自由に振動しているはずのことを、人間の分別心は、粗大に二つに分けて、あちらがダメで、こちらイイ、とやる。
このような二辺を離れるということは「存在は自ずと完成しているから努力して何かを得ようとする病を断って無努力のうちにとどまる」ことである。
これについて中沢氏は「ゾクチェンとは絶対的な肯定思想である」と書かれている。
「世界は空であると同時に、個体性をそなえた無数の現象をたえまなくつくりだしている。世界は空であり有なのである。心(セム)はこれらの有を概念によってとらえようとする。しかし概念は二元論によっているので、こうした概念構成によっては、世界に満ち溢れる個体性をつかまえることはできない。思考分別が働く瞬間、セムニーはセムに頽落してしまう。世界の実相は人間の心からはいつも自由であり、いっさいの概念に縛られることなくその自由のうちに戯れている。」
いっさいの概念に縛られることなく、自由のうちに戯れる。
ひとつ前の引用で「努力して何かを得ようとする病」というところに注目しよう。倫理的に非難されるようなことを画策している人を「悪い欲望に囚われている」と断じることは容易い。しかし一般的には「よい」とされていることを必死に頑張って求めているひとに「You、それも執着かもしれないよ」というのはかなり申し訳なくて、言いにくい。
しかし、どれほど常識的に「良い」とされる言葉の連鎖で巻かれていても、それが”二つに分けられ、他方を排除し、一方だけ選ばれたもの、そちらだけが選ばれ続けるべきだとされたもの”であるかぎり、ひとはそれに妄執し、それを失うことを恐れ、迷うことになる。
「人はより良いものを求めたり、悪きものを排除しようとしたりする心の病気を患っている。この病気に冒された心は、向上改善を求めて努力に励もうとする。しかし存在世界はあるがままにして、自ずから完成し成就しているのであるから、努力するほどに実相から遠ざかっていく。だから苦行も、瞑想修行も、ゾクチェンにおいては必要のないものである。無為のまま、無努力のままにとどまりまさい。そうすれば自然に、心は菩提心に、セムはセムニーに変じていく。『リクパのカッコウ』はそう語るのである。」
良いものを求めること。
悪きものを排除しようとすること。
それを「心の病気」だなどと言われると、ギョッとしてしまう方も少なくないことだろう。
しかしここでいう「心」が「セム」すなわち分別心であり、分かれているでも分かれていないでもない法界に、いきなりズバッと切れ目を入れて、「こっちがいい、あっちがわるい、イイものだけを選べ、悪いものは破壊せよ」と命じる言葉をアタマの中に憑依させてぐるぐると回しているのだと知れば、なんというか凶器を振り回して興奮している人が、家のなかに入ってきたような「落ち着け落ち着け」という感じに気づくのではないだろうか。
そうして、「あれっ?そういうふうに分けても分けなくてもいいよね?」と言いながら、その”興奮しているの”を「まあまあ」と座らせて、お茶の一杯でも飲んでもらって、という感じになる。幸にして、そう言うのにどこをどう切り刻まれようとも、実は何もどうにも切れていないのであるから、「こちら」は無傷である。そうしてのんびりしているうちに、”興奮しているの”もまた、すべてと異なることのない「空」から生じた影の一つだよね。と言う具合になり、追い出す必要もなく、いるのだかいないのだかよくわからない、いい感じになる。「無為」「無努力」である。
ここで「無努力」と聞いて「なるほど!努力したらダメで、努力しないのがイイんだ!」と思う方がいるとしたら、それは何度も書いている通り、二つに分けて、片方をいい、もう片方を悪いとする、分別と執着である。
「あれをすべき」/「これをすべきではない」
努力はだめ / 無努力がいい
とするのも、それもまた分別である。
「心(セム)がつくりあげている現象の世界は、あるがままの実相においては、概念がつくる相対的な良い悪いを超えて、つねに絶対的に善なのである。分別思考を働かせないでいるとき、世界はあるがままに善である。」
「分別思考」を働かせずに「概念がつくる相対的な良い悪いを超」えたところで、「絶対的」な肯定であり、「絶対的」な善ということを直接経験する。
ここでふと思い出すのは、松長有慶氏が密教の重要経典である理趣経について解説された下記の文である。
「もっと大事なのは、日常性を超えてしまえということです。といって日常性を否定しているわけではないので、そこを誤解しないようにして下さい。善悪の善を否定して、悪だけを取り上げようとしていると誤解されると、分別になってしまいます。あれが善いかこっちが悪いかということになりますから、密教ではそういう分別を否定します。[…]自分と大日如来が一つになるということは、そういう小さな倫理、へ理屈を捨てろということなのです。こういうふうに思い切った書きかたをしているので、漢訳するときにはそのまま訳せなかったのでしょう。「たとえ」と仮定法に訳し変えてしまっています。原文はもっと問題を鋭くつきつけています。」
これは理趣経の「一切蓋障 及 煩惱障 法障 業障 設廣積習 必不墮於地獄等趣設作 重罪消滅不難…」というところの解説である。おやっ?!これは?!と思われた方は、ぜひ下記の文献を購入して読んでみるとよろしいかと存じます。
「あれが善いかこっちが悪いか」もまた「分別」であり、そういうところから離れた善、「非-悪」としての善ではない、絶対的な”善”にありのままに共鳴できるようになりたい、というところである。
これを「そのまま訳せなかったのでしょう」というところがおもしろい。
* *
分別思考するのではなく直接経験する。
この直接経験の「対象」のようなことは、何か特別な、現世を離れた遠いところにある手の届かない何かではなく、目の前に広がる「心(セム)がつくりあげている現象の世界」である。
「ゾクチェンが無為や無努力を主張するのは、心(セム)が虚構している現実世界の覆いを破断してみれば、そこに自然のまま初めから完成をとげているセムニーが赤裸に露出してくるのを、誰しもが見届けることができると考えるからである。現実界はその赤裸なセムニーの原初の空間の中に現れる法界の戯れである。」
「心(セム)がつくりあげている現象の世界」を、分かれつつ分かれていない、分かれていないでもなく分かれているでもない蠢きとして感じる、共鳴する、そういう身体、言葉、イメージのモードを、表層言語の固まった分別思考で抑え込まないということが大切である。
ここでは「心(セム)がつくりあげている」諸現象もまた「法界の戯れ」のひとつの姿である。「妄想によってつくりだされているこの現象世界は、法界の戯れとして、あるがままにして完全」である(p.166)。
そうしたところで、現象世界と法界とが異なるものではなく、現象世界のあれこれ、仮に分別されて見えているあれこれもまた、善悪を分別するまでもなく「あるがままに善」なのであると知ることになる。
*
さらに『金翅鳥の飛翔』というテキストから中沢氏が引用するところを読んでみよう。
「心が働きかける対象は存在しない、無思考であることが正しいダルマの道である。[…]真如についての瞑想などおこなっても、なにも得ることはないし、解脱に執着するのは、この道ののぞむところではない。」
真如「について」の、”について”に注目しよう。なにか”について”というとき、そこにはその”なにか”が対象として存在しているはずだとう意識が入り込む。そして対象が存在するということはその対象を「ある」とか「ない」とか、「ほしい」とか「いらない」とか分別する「主体」もそこに入り込んでいることになる。
対象 / 主体
そして主体が対象を「得る」ということが問題になる。
得られるか、得られないか。どうすれば得られるか、どうしていると得られないのか、などなど。
「獲得される対象はないし、そこから精髄が湧いてくるわけでもなく[…]心が働きかけることなく、変化をつくりだすことなく、自性のあるがままにいれば、すべての願いはすでに満たされている。」
対象化された真如とか、対象化された解脱とか、”そこから精髄が湧いてくる”なにかとんでもなく素晴らしい対象物というのは、そういう対象とその対象を求める主体とを分別したところに区切り出される妄想である。
そのような対象を欲望し執着したのでは「心の解放」は程遠い。
分別をすることから主体と対象が分かれ、主体が対象に、”とてもつもなく素晴らしい対象”に執着することがはじまる。
冒頭に書いた話を思い出してほしい。
光をみるヨーガで、なにか非日常的なすごいものが「みえる」かもしれないが、それをここでいう「対象」として、欲望したり、執着してしまったのでは、「心の解放」からは程遠い。そのような執着の凝固をほぐすことができるようにしておくために、二辺を離れることができる言語的意識の修行(としての「哲学」)が不可欠なのである。
*
そしてここからが仏教の、というか密教系の仏教の、きわめておもしろいところである。ありとあらゆる分別、二項対立から離れる時、
ある / ない
真 / 偽
清浄 / 不浄
神 / 悪魔
この世 / あの世
そして
二つに分ける / 二つに分けない
などなどといった極めて基本的な二項対立もまた、どちらか一方だけを選べるものではなくなる。
二辺を離れるでもなく離れないでもなく
特に最後の「二つに分ける/二つに分けない」の二極からもともに離れるというのが強烈で、こうなると「分けるのがダメで、分けないのがいいんだよ」とも言いようがなくなる。
あとに広がるのは、
分けるような分けないような、
分かれているような分かれていないような、
分けるでもなく、分けないでもない
の宇宙である。
それこそ「変化をつくりだすことなく、自性のあるがままにいれば、すべての願いはすでに満たされている」宇宙である。
そこでは「すべて」が、通常の意識によって分別されるあれこれ、自己と他者、主体と対象、ありとあらゆることがはっきりと分かれたまま、分かれていない、しかし分かれている、けれども分かれていない。
分かれる/分かれないの両極の間を振動しているような様子が言語意識の線上に浮かび上がってくる。
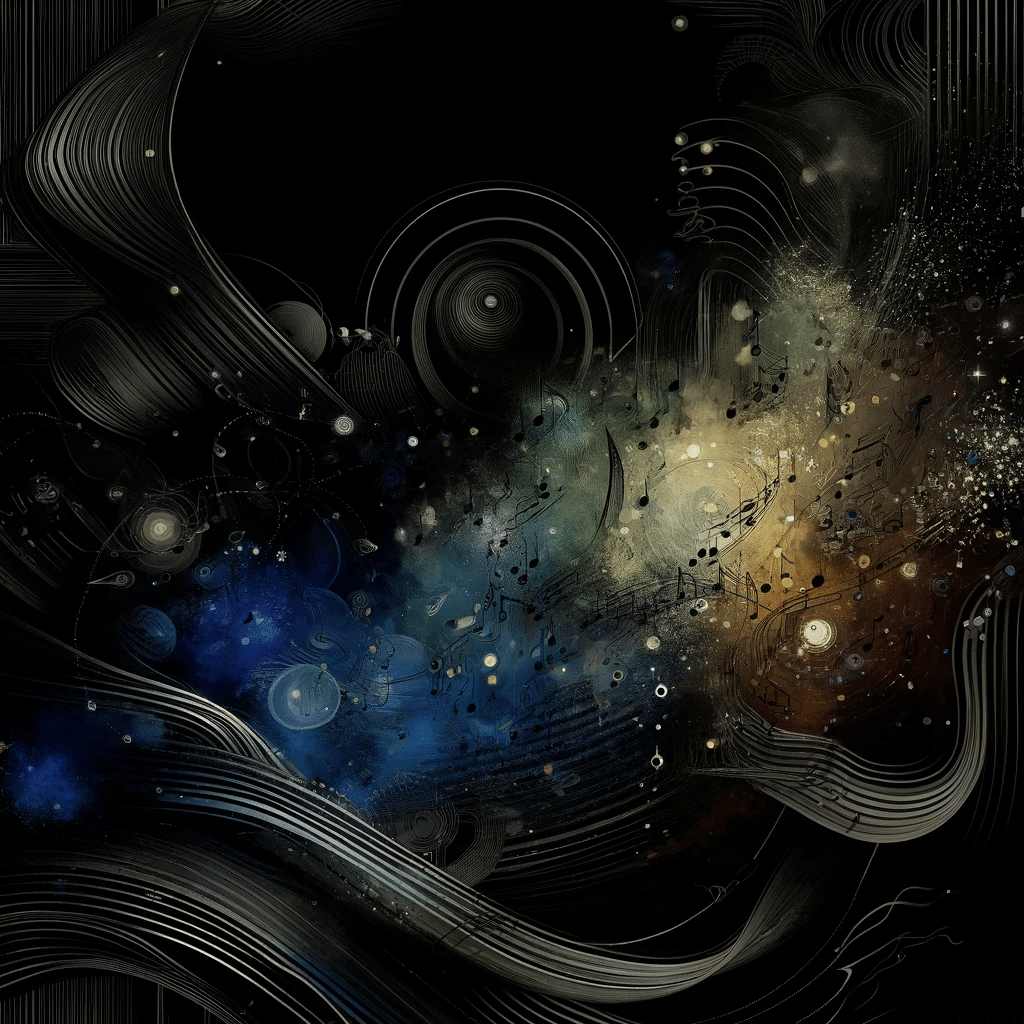
(AI生成)
まとめ
上の引用に続けて、中沢氏は次のように書かれている。
「私は記号の絶滅の向こうに出現する、人間の心の赤裸な姿を見届けるために、ここへやってきた。[…]しかしゾクチェンでは単純に記号による思考分別を絶滅させるのではない。それを空に自然に湧き上がる雲のように受け入れ、同時に無化するのである。」
「記号」を「対象」として、撲滅すべき「対象」として、破壊すべき「対象」として、そこに照準を合わせて修行に臨んだ若き中沢氏は、いわば敵と味方のようなことを二つに分けて、
記号 / 心の赤裸な姿
||
破壊する / 育てる
強いて書かせていただくならば、上記のような「分別」をしておられたといえようか。
*
それに対してゾクチェンの教えは「記号による思考分別」を「空に自然に湧き上がる雲のように受け入れ、同時に無化する」ことを説く。「記号による思考分別」が”破壊すべき対象”として対象化されていない。
記号は、あるもでもなくないでもない、よくもなくわるくもない、あろうがなかろうがどちらでも異なることがない、湧き上がると同時に無化され、無化されるが同時に湧き上がる、という徹底した”二辺を離れる”思考。
この論理によって、言葉が、記号が、「心の解放」の道を歩むための「方便」として使えるものへと、突如変容させられるのである。
このように変容した言葉でもって分別するでもなくしないでもない意識を明晰に、光を見て、風を感じて、鳥の声を聴く。そうすると人間の心は、妄想分別の再生産装置であったときと全く同じメカニズムで動きながらも、光や風や鳥の声と共振し、大宇宙そのものの脈動と共鳴することができるようになる。
「金翅鳥が大空に翼を広げて飛翔していくように、自性は拡散することもなく、個体に凝縮することもない。大海のように初めからそれはあり、そこにさまざまな存在者が出現する。菩提心である原初仏の活動域には生死もなく、すべてがかくのごとく如実に存在する。大きく翼を広げた金翅鳥は、虚空にすら執着しない。」
虚空と言った瞬間に、虚空/非-虚空が分別されて、虚空がすばらしくて、非-虚空は嫌なものだ、という分別が効いてしまう。そういうΔ虚空には、執着しない。
離れる、と言った瞬間に、離れる/離れないが分別されて、離れるのが良くて、離れないのがダメだ、という分別が効いてしまう。そういう”Δ離れる”には執着しない。
二辺を”離れる/離れるない”の二辺を離れるでもなく離れないでもなく。
異なるが同じ、同じだが異なる。
異なること異ならないことは、異なるが異ならず、いわば共鳴している。
などと分節言語で強いて言うならばそういう具合になる。
+
なぜそんな面倒でややこしく、大変なことをするのか?
その答えは、例えば下図のような「光」を「みた」時に、これを転じて分別心(セム)の底を破ってセムニーに飛び込むための”方便”として自在に動かすことができるフィールドを開くために、言葉もまた”方便”として励起するため、という感じである。

分かれていないが分かれている
関連記事
*
この記事が参加している募集
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
