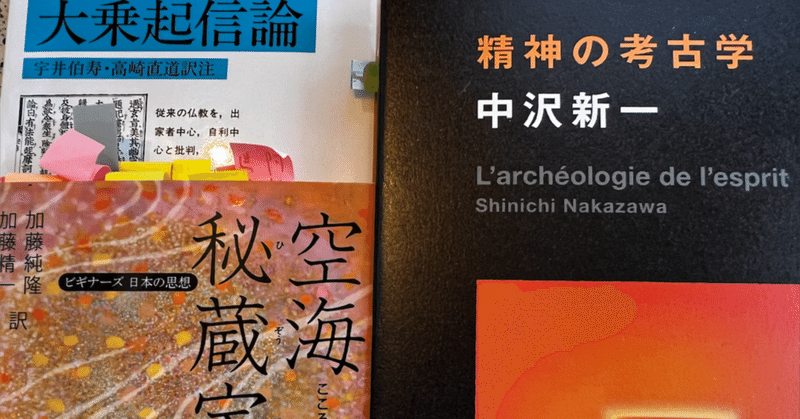
詩的言語/サンサーラの言葉とニルヴァーナのコトバの二辺を離れる -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む
しばらく前のことである。
「人間は、死ぬと、どうなるの?」
小学三年生になった上の子が不意に問うてきた。
おお、そういうことを考える年齢になってきたのね〜。と思いつつ。
咄嗟に、すかさず、大真面目に応えてしまう。
「死ぬと、どうなるとか、どうならないとか、いうことはないよ」
生と死の二項対立を四句分別する。
念頭にあるのはもちろん空海の「生まれ生まれ生まれて、生のはじめに暗く
、死に死に死に死んで、死のおわりに冥し」である。
こういうのは子どもには”はやい”、という話もある。
が、はやいもおそいもない、というか、はやからずおそからず、「どちらを選ぶべきか」という類の分別心による分別に汲々としている場合ではない。
それこそまさに「くらい」である。
*
質問してきた本人といえば、「死ぬ」と、なにか大変なことになるんじゃないかと思っていたらしい。ところが、拍子抜けするような答えが返ってくる。「(なんだこの親、質問の意味がわかってないんじゃないか? あたまがちょっとお留守なんじゃないか?)」という表情をしているのが良い。
あるいは「死ぬと、悪魔に貪られるぞ!嫌ならきゅうりをしっかり食べて光の要素を浄化すべし」と言っておけばよかったかもしれない。ちなみにきゅうりの話は下記の記事に書いているのでご参考にどうぞ。
ちなみにマニ教の「きゅうりやスイカを食べること(=過度に結合したかと思えば、過度な分離へと振れる)」と「どうなるでもなく、どうならないでもない」という四句分別とは、まったく別のことを言っているようで、実は、まったく同じことを言っている。このあたりの事情に「あかるく」ありたいものである。
どちらの方便を選ぶと良いかは、これは訊ねている方の機根次第ということになろう。詳しいことは上の記事に「β脈動するスイカとβ結合する」の話として書いているので、ご興味ある方は、ご参考にどうぞ。
さて、生/死。
人間の「心」は、日常的経験的感覚的には、「知性と感性」という「分別=二つに分けて片方を選ぶこと」に邁進して止まないように動いている。
生/死
この区別された両極もまた、人間が言語的に「生に対する死とは何か?それはすなわち然々である」うんぬんと思考している限り、”分別された二項関係のうちの一方”である。生/死を分けて、この二項対立関係を、さらに別の二項対立関係に置き換えていくことが、通常「死ぬとこうなります、ああなります」といった話の持っていき方になるだろう。
生/死
||
a/非-a
||
b/非-b
||
…
||
x /非-x
死ぬとどうなるのか?
という問いが、もし仮に、
「死ぬと非-aになります」、
「死ぬと、非-bになります」、
「死ぬと非-xになります」式の言い換え=二項対立の置き換えを、どこか特定の置き換え先に固定することをもって「答え」としようとしているのであれば、それは死を過度に厭離したり、逆に死を過度に欲したりする妄想分別と執着につながるので苦しくなるよ、というのがブッダの説くところであろう。
* *
仏教でいえば、生/死に限らず、何であれ、この”二つに分けて片方だけを選ぼうとする”ことが、人間の心の「知性」や「感性」といった部分がついついやってしまう妄分別であり、執着のはじまりである。
生 / 死
ある(存在) / ない(非存在)
含む / 含まれる
変化する(なる)/変化しない(ならない)
主 / 従
増える / 減る
同じ / 異なる
こういうありとあらゆる二項対立、私たちの経験と感覚と知覚と意識を貫いて構造化している基本的な二項対立もまた、これまたすべて”二つに分けて片方だけを選ぼうとする”と執著を生じることになる。
知性や感性が「他ではない、これ、それ」と同定して取り出して、数を数えたり、並べたりできる項は、すべて分別するということが動いた後の、切り取られた何かである。
二つに分けるでもなく、分けないでもなく
ここで「どうなるでもなく、どうならないでもない」ということを体感するためには、手を変え品を変え、自分に適合したやり方で、この二つに分けて固める心をほぐして、やわらかくしてみる手がある。
中沢新一氏が『精神の考古学』に記されている修行はまさにそのようなこととして読むことができる。
「[…]私は、周囲の世界にたいする自分の知覚が変化しだしているのに気がついていた。ボトルの中の水を見ても、牛が草を食べている原っぱの土をみても、そこにある物質の中に自分の知覚が滑り込んでいってしまうような、奇妙な感覚である。「元素」の音声を聴く訓練に集中したおかげで、さまざまな物質はそれぞれに特有の波動を持っていて、それらの波動は四つの基本的な物質の音声の合成としてできていると感じるようになった。」
いきなりここだけ引用されても意味不明かもしれないが、詳しいことは『精神の考古学』をぜひ読んでいただくとして、ヒントになりそうなところだけを選んで、精読させていただこう。
四大へ、自分の感覚で「滑り込む」
人は、適切に訓練を積めば、「水」や「土」といった「物質」へ、”自分の感覚”が「滑り込む」ような「感覚」を感じることができる。
通常、水とか土といえば、ものとしてそこに転がっており、「私」とは何の関係もない、私とははっきりと分けられた何かという感じがするところであるが、元素の「音声を聴く」という感覚の組み替えにより、物質を「音声」として、振動として聴く、つまり”聴いているワタシ”の身体と共鳴させることができるようになる。
そうなると、
感覚しているワタシ / 物質
という日常的な分別がゆるみ、感覚しているワタシもまた物質であり、物質もまた感覚をしているワタシと深く繋がり共振しており、互いにはっきり区別できるものではない、という感じがしてくる。
この”物質”について、中沢氏は次のように書かれている。
「四大(ないし五大)元素は科学が明らかにできる物質構造をあらわしているのではなく、存在の基底材であるダルマダーツ(法界)の音声化されたゲシュタルト(形態)をしめしている。」
四大というのが四大元素として表現される「物質」である。
それはいわゆる自然科学が観測測定する「物質構造」のことではなく、”ダルマダーツ(法界)の音声化されたゲシュタルト(形態)”である、という。
「三昧法螺聲 一乗妙法説 経耳滅煩悩 當入阿字門」を思い出すところである。
法界が音声化
ダルマダーツ(法界)というのは、分別の手前、分別以前、ありとあらゆる二項対立のはるかに手前の、分別に対して言えば”無分別”の動き、分けることと分けないことが分かれているでもなく分かれていないでもない「霊性」の動きである。前回の記事では「/」として記述したものである。
「四大は[…]三様態を内蔵する、存在の示す四種類の基本的波動をあらわしている。そのため四大の声を聴くことをつうじて、人間はダルマカーヤ(法身)、サンボガカーヤ(報身)、ニルマナカーヤ(応身)の三様態がむきだしの状態で相互変容を起こしている現場に、実態的に立ち会うことができる。」
このいくつもの「/」の動きがもつれ、からみ、共振するところに、ある「波」のパターンのようなものが強度を増して反復されるようになる。そしてそこに「物質」として人間が感覚できるような大きなパターンが、そうでないところから区別できるようになる。
この際、「人間」もまた「/」の共鳴状態のひとつのあり方であり、あれこれの「物質」もまた「/」の共鳴状態の一つのあり方であり、どちらの共鳴状態もまた、同じひとつの異なることのない「/」たちの振動が渦巻くところ(法界)から立ち上がり、生えている。
四大の声が渦を巻いて響きあう
「四大の声が渦を巻いて響き合っているこの空間こそ、ゾクチェンが開こうとしている心的空間に他ならない」
人間の「心」もまた、”四大の声が渦を巻いて響き合っている”もののひとつであり、「心」が感じたり認識たり分別しようとしたりする「物質」もまた”四大の声が渦を巻いて響き合っている”ものたちである。
と、このように書いてみるものの、あまり余計なことを確定的にいうのは回避したいところである。
「四大の声を聴くヨーガがひらくこのような原空間は、恐ろしく複雑な構造をしている。それを言語の「ロゴス」的仕組みによって表現することは不可能である。」
おいドラえxん、真実は「波動」なんだよな!
おいのびx!真実は「シンクロ」なんだよな!
などという時、しばしば私たちはついつい「波動」なるもの「シンクロ」なるものを非-波動、非-シンクロと分別して、波動の方がホンモノで、非-波動はニセモノ、などと白黒つけてしまう。
波動 / 非-波動
||
ホンモノ / ニセモノ
言葉で考えると、いつでもどこでもすかさず、二つに分けて、片方を選ぶ、執着が始まる。そうしてこの執着を強固に反復しようとして、いつの間にか白を黒だといったり、黒を白だと言ったりもする。
そういうわけでこの”四大の声が渦を巻いて響き合っている”を、ロゴス的な言語、「AはXで、非-Aは非-Xである」式の言い換えを線形に連鎖させるやり方で”表現”することは困難である。
「ゾクチェンの四大の声を聴く瞑想は、[…]火の中に、不断に渦巻き状の全体運動を続ける、西洋的「ロゴス」とは別種の知性的なるものを見出していった。私はのちにそれを「レンマ的」な知性として再発見することになる」
ここでふと思い出すのは、かのジャック・ラカンが『精神分析の四基本概念』で書いている次の一節である。
「シニフィアンとシニフィエの関係を間の横線で表す分数をいわば信用しすぎているのです。[…]慎重さを欠いた危ないやり方でこの横線を操作することは決してできません[…]何らかの論理的欠陥を生むことのないシニフィアンそれ自身への関係などありえないからです。」
ここで言われている「分数」の「横線」というのが、「/」のことに近いような気がする。「/」という線は、任意の所与のΔ1とΔ2(シニフィアンとシニフィエといってもいい)を二次的に分母と分子の位置に引っ張りこむような代物ではない。そうではなくて「/」はありとあらゆるΔに先行している。先行しているというか同時発生している。「/」が走ることによって、その両側に初めて二つの位置が析出される。しかもこの「/」お行儀のいい一本線ではなく、無数にもつれ絡み振動する”線たち”のうちの小さな線分である。
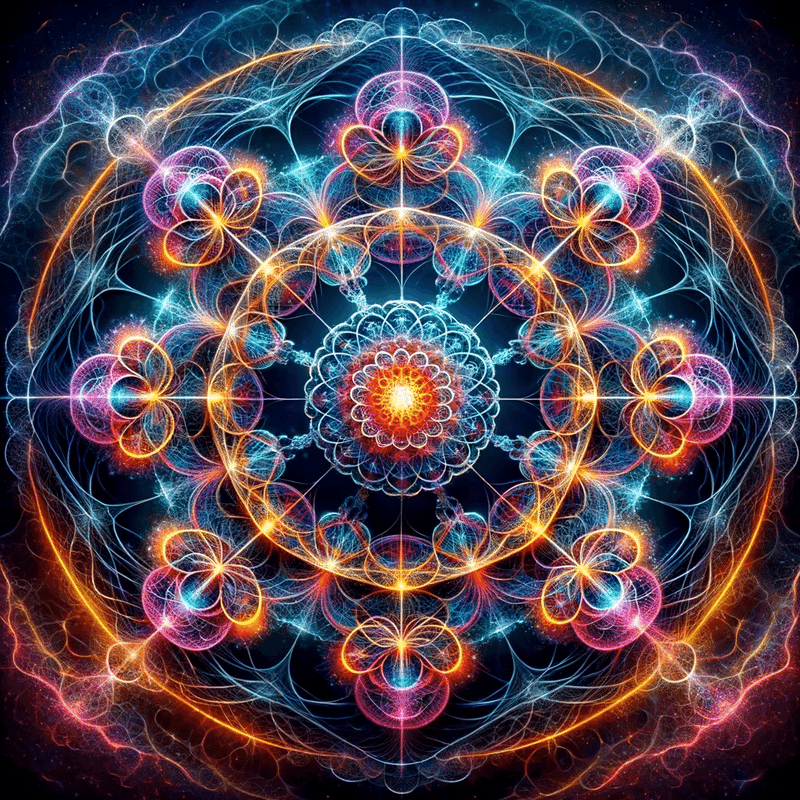
共鳴し、共振する
動的構造としてのレンマの言語の姿
ここで”渦を巻いて響き合っている四大の声”を前に、人間の「声」は沈黙せざるを得ないのかと言えば、必ずしもそういうことはない。
言語を、”二つに分けて片方を選び、その選ばれたものたちを一列に並べていく操作”(これが「ロゴス」であろう)とは別の仕方で編み、組んでいくことで、”渦を巻いて響き合っている四大の声”と共鳴し、共振する動的構造を、言葉の響きの上に仮設的に建立することもできる。
人間の「心」では、”四大の声が渦を巻いて響き合っている”のと直接響き合っている、というか、この四大の声の渦とまったく異なるものではない深いところと、その上澄みから生えて表層を覆った構造体のようところとが、多重になっている。後者がロゴスであり、このロゴスを転用して前者をシミュレートしたものがレンマである、ということになろうか。
「人間は生と死がくりかえす輪廻する世界を生きているが、その状態をつくりだしているおおもとは、身体と言葉と思考をとおして絶え間なく活動している心(セム)の働きにある。しかしこの心は純粋な心性(心そのもの、セムニー)が変性したものであり、このセムとセムニーの混成体として、人間の心作用は動いている。」
ロゴス、あるいはかっちりと分節されたものたちを一列に並べた姿をした言語と、その言語の固定生を強烈に支持している前五識と記憶された経験のイメージたちからなる心の相を「セム」という。
これに対して「それ」を直接記述することはできず、レンマの論理でかろうじてシミュレートできるようなできないような”四大の声が渦を巻いて響き合っている”のと異なることのない深い深い心の相を「セムニー」という。
人間は、このセムとセムニーの「混成体」としての分節システム=「心」でもって、ものごとを分別し、差別し、二つに分けた片方だけを選ぼうとして汲々としたり、不意に「分けるでもなく分けないでもない」と覚ってみたりしながら生きている。
*
この分別システムである”セム”と、分別するでもなく分別しないでもない”渦の響き合い”のようなセムニーの「混成体」の組み方がいろいろある。
例えば、空海が「十住心論」に整理している「心」というのも、まさにこのセムとセムニーの「混成体」のことである。
心、セムとセムニーの組み方にはいろいろあり、その数は数えきれない(無量)のであるが、仮に大きくまとめて十に整理してみた、というのが十住心論である。
仏教では有情を、神、阿修羅、人間、餓鬼、畜生、地獄の六つのカテゴリーに分ける。それぞれの存在カテゴリーの心作用は、それぞれのセムの構造の違いによって条件づけられている、と考えるのだ。」
十住心論の第一住心「異生羝羊心」をさらに細分化すると、地獄、餓鬼、畜生、そして人間の「心」が区別される。それらの心の違いは「セムの構造」の違い、すなわち、”渦の響き合い”のようなセムニーが動き回っているところから、縺れ上がってきたいくつかの毛玉のようなものをキツく縛ってまとめていったところに、いくつかの「異生羝羊心」のバージョンが形を定めていく、といったイメージである。そして「人間」の「心」もまた、その一つなのである。
「それぞれの存在は、自分に与えられたセム構造の内部から、世界のことを捉えている。有情は各自のまわりに、各自のセム構造に適した世界のあり方を「仮想」して、その仮想世界の中で「世界」というものを体験するのである。そのために同じ空間の同じ場所が、すべてに満ち足りた神々には快感を与えてくれる「神の世界」と見える(仮想される)のに対して、神々に対する嫉妬に満ちた阿修羅たちの目には、憎らしい不平等の「世界」と見える(仮想される)のである。」
人間を含む存在たちは、”自分に与えられたセム構造の内部”に、外界=世界についてのシミュレーションモデル(「仮想世界」)を生成する。
そこで、例えば人間のような者にとっては、”この世界”は、自/他が、食うか/食われるかで争っているフィールドに見えたりする。しかし世界がそのような殺伐とした世界”である=”として仮想される””のは、人間の”心”が
自/他
食うか/食われるか
強/弱
生/死
といった二項対立を分節しては片方だけを選び続けようとするシンプルなシステムとして自動化してしまっているからであり、もっと別の「心」のあり方でもって分節したり、しなかったりすることも、できる。
いや、「できる」はずなのだが、なかなかできない。
ここに言葉がでてくる。
言葉のかたち
「ようするに人間のセムは言葉によって構造化されているのである。私たちが自分のセムと内的対話をおこなうときも、自分の内部で紡ぎ出される言葉の糸を追っている。言葉は時間の流れにそって伸びていく線のような構造をしている。そのためセムの内部で言葉が発動するたびに、時間の流れが確かなものとして整序されていく。人間のサンサーラはつねに言葉とともにあるのだ。」
人間の「心」はただ固定的分節システムとしての「感性と知性」を動かしているわけであるが、このモードに巻き取られた言葉は、
Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ
という、線形の「糸」、「伸びていく線」のような形になる。
さらに言えば、時間や空間という、物事が順番に並んでいるという世界の見え方自体が、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δという線形を配列していく言語の力で作り出されている可能性もある。
ところが、おもしろいことに、人間はこの言語を”ブリコラージュ(日曜大工のように用途を転用流用)して、「感性と知性」の分別システムを、捨て去ることなく、転用し、「霊性」あるいは「レンマ」の論理、”分けるでもなく分けないでもない”渦の共鳴と共鳴するモードに励起することもできる。
これを中沢氏は「ニルヴァーナの原空間」において「変容」を受けた言葉のあり方と書く。
「それならば、ニルヴァーナの原空間で、その言葉はどんな変容をうけることになるのか。そもそもニルヴァーナに言語活動はあるのか。あるとしたら、それはセムニーの活動に制限を加えるものであってはいけない。時間の流れにしたがって事物を線形に並べることで、サンサーラの言葉はニルヴァーナの言葉に制限を加えているからである。いちどきにすべてを表現できる言葉でないと、ニルヴァーナの言葉にはなれない。そうなると、詩的言語はサンサーラの言葉とニルヴァーナの言葉の中間にあるということになる、天使の言語活動があるならば、やはりそういうものだろう…」
ニルヴァーナの原空間の言葉は、”分けるでもなく分けないでもない”渦の共鳴と共鳴するモードに励起された言葉とは、
・いちどきにすべてを表現できる言葉
・線形に並んでいるようで並んでいない言葉
である。
サンサーラ(つまり生/死を分けて、生まれ生まれ生まれて…死に死に死に死んで…の輪廻)の言葉とニルヴァーナの”コトバ(β脈動)”の”中間”というのが重要である。サンサーラとニルヴァーナを分けて、「サンサーラはダメで、ニルヴァーナがイイんだよ」、とやりたくなるのは、まさに人間の妄想分別である。
「詩的言語」は、「天使の言語活動」は、ニルヴァーナでもなく、サンサーラでもない、知性と感性と霊性の”あいだ”で、おもしろがる、自受法楽する。
一見、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ、という姿をしてままの言語でもって、下図のような渦たちの共鳴状態と共振する。

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析している神話の語りなどは、対立する二極の過度な結合から過度な分離への急転換、そしてまた過度な分離から過度な結合への急転換を語ることで、まさにΔ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δという線形配列の姿をした言葉でもって、上のマンダラ状の脈動を再現しようとするとてつもないものなのであった。
そういえば、近日、中沢新一氏によるレヴィ=ストロース論『構造の奥』が刊行される予定である。楽しみで仕方がない。まだ読んでいないがすでにおすすめである。
さて、ここで冒頭の「生/死」 の話にかえってくる。
「人間はこの言葉によってつくられる仮想現実を介して、生物に必ず訪れる生老病死というリアルと直面する。そのために、動物たちは自分の死を恐れたりしないのに、人間だけは言葉がつくる「私」というものがあるために、自分の死を恐れることになる。生物的な死とともに「私」が消えてしまうことを、仮想的な「私」は認めることができないからだ。ブッダはこの問題に取り組んで、仮想的な「私」の滅却に至った。その状態がニルヴァーナと呼ばれるものである。」
人間にとっては「生/死」の分別、生と区別される限りでの死も、死と区別される限りの生も、どちらも”言葉によって作られた仮想現実”である。
つまり死というのは、
生 / 死
の対立の一方の項であり、
非-死 / 死
である。これはすなわち、
非-死 / 非-非-死
である。
死とは何か、死ぬとどうなるのか、という「問い」を言語でもってたてて、それに言語でもって答えるということはつまり、
非-死 / 非-非-死
の対立関係に、何らかの任意の二項対立
非-x / 非-非-x
を重ね合わせるということをやろうということである。
非-死 / 非-非-死
||
非-x / 非-非-x
* *
そうであるからして、「死ぬとどうなる?」という問いに対して、
「
非-Δ1/非-非-Δ1
||
非-x / 非-非-x
という分別は、してもしなくても、いいんじゃない?」
というのが私からの答えになるわけである。
「私」とか「ある」とか「ない」とか、「生」とか「滅」とか、「増」とか「減」とか、ありとあらゆる”Δ”は、「仮想的な」Δである。
そういう仮想的なΔを「滅却」すること。
Δ死-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ終わり-Δ-Δ-Δ-Δ「私」の-Δ滅却
ここで注意しよう。「滅却」というのは、ある/なしの二極の「なし」の側に放り込むというのではなくて、あるようなないような、”あるでもなくないでもない”に、いわば知性と感性の側からみれば「宙吊り」にする。
ちょうど、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』の基準神話に登場する、「鳥の巣あさりの兄弟」、ハシゴで木に登ったら、ハシゴを外されて、降りようがなくなってしまった主人公のようにである。
もちろんこれを「宙吊り」と「表現」されて「ああなるほど」と思えてしまうのが知性と感性の分別識、サンサーラの心だということはお忘れなきよう。
二項対立関係の対立関係を固めることをするでもなくしないでもないのが、ニルヴァーナ、となる。
そしてそのニルヴァーナとサンサーラ(生/死を分けて、生まれ生まれ生まれて〜暗く、の輪廻)との「中間」に広がるのが、”八不”の言葉、レンマの論理で振動する二項対立(以前の記事で使った用語でいえばβ脈動)たちである、ということになる。
いま仮に、
Δ/Δ
||
Δ/Δ
という具合の分節システムである「セム」としてのいわゆる”私(我)”の肉体が「死に」=八識のもつれが解かれたとしても、「セムニー」そのものはまったく無傷というか、そのままである。そういう「セムニー」のことを、この”セム”でもって観じるために、詩的言語、ロゴス的に対立する二極の間を過度に分離したり過度に結合したりするレンマのコトバが手がかりになる。
つづく
>つづきはこちら
関連記事
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
