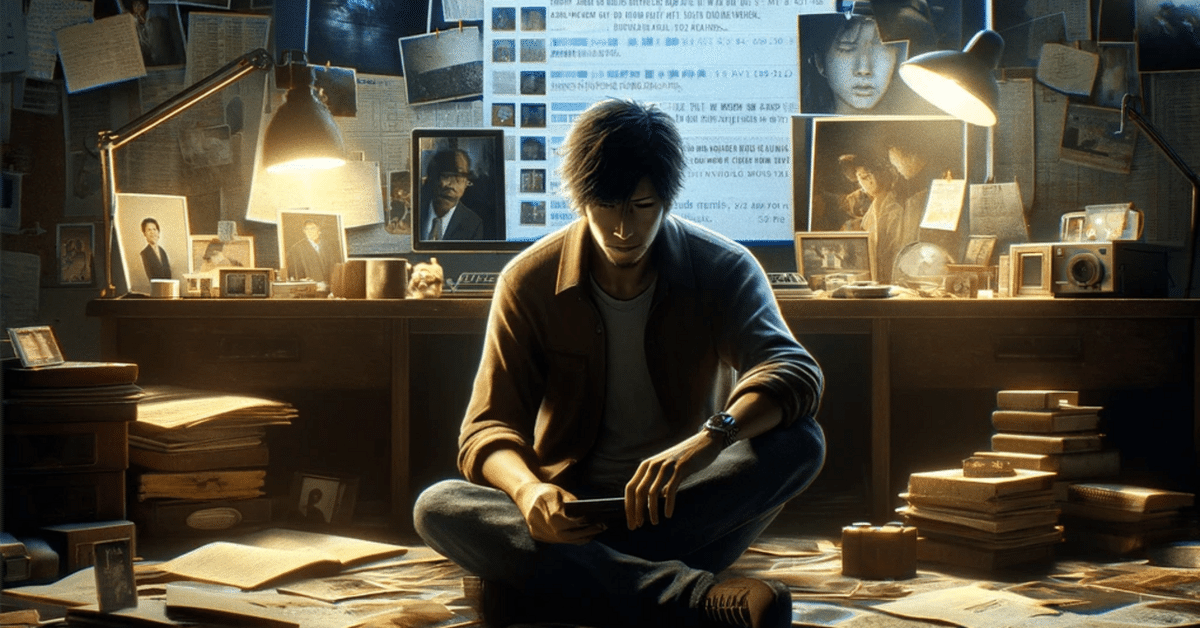
【連載】「灰かぶりの猫の大あくび」#13【学校編~僕たちはどう生きるか~】第五話
登場人物
灰かぶりの猫
久しぶりに小説を書き始めた、岩手県出身の三十代。芥川賞候補作家の三島創一の代役として、夏目の母校での講演を依頼される。
黄昏新聞の夏目
新米記者。アニメ好き。『僕の心のヤバイやつ』第2期にはまり、今はこのアニメを観るために生きている。「旅館編」を経て、すっかり猫の相棒役に。次のシリーズでは、準主役の予定。
モノリス
灰かぶりの猫の自宅のAIスピーカー。知らぬ間に、猫と夏目の会話を学習してしまい、時々おかしなことを口にする。シンギュラリティが訪れた場合、猫と敵対する可能性も。――それにしても猫さん、ワタシの出番はまだですか?
三島創一
小説家。夏目の高校時代の先輩。学生時代に、大学の個性的な教授陣との交流を戯画化した『シランケド、』で、現像新人賞を受賞しデビュー。人間の母性を地球にまで拡張した問題作『たゆたふ』で、芥川賞候補に。現在は体調不良。本当か?
杉田薫子
聖子ちゃんカットをした女生徒。インターハイ記録も狙えるほどの韋駄天の持ち主。schoolからscholēへの変革を画策する。
智彦
さだまさしのような黒縁の眼鏡を掛けた男子生徒。薫子のアシスタント。どうやら薫子には、「ほの字(死語)」のようで。
昌大
アキハバラのラジオ会館生まれ。おしゃぶり代わりに、真空管をしゃぶって育つ。エンジニア。
敦子
薫子とは幼馴染。『エースをねらえ!』のお蝶夫人こと、竜崎麗華のような髪型をしている。ダミーのスタンガンを所持。
真司
ラグビーでもしていたような、いかつい見た目に反し、時間にうるさく、臆病なところがある。
福田伸一
すっかり存在を忘れられている生物学教師。とにかく口が軽い。
坂本銀八
校長。作家として三島創一のことは認めながら、猫に対しては小馬鹿にしたような態度を取る。一人称は「儂」。
(以下、灰かぶりの猫=猫、夏目=夏目、モノリス=モノリス、杉田薫子=薫子と表記)
※各固有名詞にリンクを添付。
※この物語は、三年寝かせてもフィクションです。
前回のあらすじ
東校舎三階の視聴覚室に集合した薫子、智彦、敦子、真司の四人。薫子から作戦が伝えられ、四人は拳を突き合わせ決起を図る。猫はそんな彼女たちに、1970年11月25日、市ヶ谷駐屯地で小説家の三島由紀夫らが起こした「三島事件」を重ねながら、戦場カメラマンとしてその行く末を見届ける決意を固める。
――それぞれ自分の役割を果たすため、散り散りとなった四人。真司はひとり、放送室に籠り、事前に用意しておいた教頭の合成音声のカセットテープをレコーダーにセットし、その時を待っていた。智彦は、一階の下駄箱の前に待機。残る薫子と敦子は、間もなく校長室に到着するところだった。当然、その後ろには、猫と夏目の姿。
――そして迎えた、13時30分。「エレフ」の作戦が決行される。
――ピーンポーンパーンポーン。
教頭 「訓練。訓練。ただいま、東北地方全域に緊急地震速報が発令されました。職員並びに生徒一同は、担当者の指示に従い、速やかに避難を開始してください。――繰り返します。訓練。訓練。ただいま、東北地方全域に緊急地震速報が発令されました。職員並びに生徒一同は(以下同文)」
坂本校長
「訓練だと? 全く聞いてないぞ」
――ガラガラガラ(校長室の扉をいきなり開け、薫子と敦子が乗り込む)。
薫子 「(坂本と目を合わせ)事前に知らされていたら訓練にならないでしょ。抜き打ちで行ってこそ、本当の訓練。あんたたちが前例を踏襲して、当たり前のように行ってきたことは、子どものままごとみたいなものなんだよ」
坂本校長
「き、君は薫子君。なぜここに」
薫子 「物語もクライマックスみたいだから、ラスボスのところに出向くのは当然でしょ。――ね、猫さん(そう言って、猫の方を振り返る)」
敦子 「ですが、薫子さん。最後を締めくくるわたくしたちの仇としては、いささか小物過ぎではありませんこと」
薫子 「はは。敦子も言うね。でも結局、ボスって言うのは、図体や態度がでかいだけで、そのほとんどは小悪党みたいなものなんだよ。そして本当の巨悪は、その裏に潜んでいたりする」
敦子 「なるほど。そういうものですか。では校長先生は、スケープゴートなのかもしれないのですね」
薫子 「もし、闇将軍みたいな黒幕がいたとしたらね」
坂本校長
「な、夏目君。どうして黙っているんだね。君たち大人からかも、何か言ってくれないか。校長の儂に対し、無礼にもほどがあると」
夏目 「――申し訳ありません。坂本校長。今のわたしたちに、彼女たちの行動に介入する権利はないんです。わたしと猫さんのことは、この物語の観客として認識してください」
坂本校長
「この物語? な、何を言っておるんだ。これは現実。白昼夢でもVRでもなく、ありのままの現実じゃないか。――それにこんなこと、校則的に許されるわけが…」
薫子 「校長、あんたの時代は終わったんだよ。かつてはあんたも、『人間の精神が腐りきることなど絶対にない!』と、不良の生徒をかばうほどの熱血教師だったようだね。だが、今はどうか。自分の姿を鏡で見たことある? ないだろうね。自分がすでに『腐ったみかん』になってしまっていることに、気づいてすらいないんだからさ」
坂本校長
「――き、貴様!!」
――坂本、怒髪天を衝き、怒りに任せ、手に持っていた扇子を薫子に向かい投擲する。瞬時に身をかがめ、扇子をかわした薫子だったが、矢のようにまっすぐに飛んだ扇子は、薫子の背後に立つ猫の額をかすめた。
夏目 「きゃ! 猫さん」
――猫、不動明王のように微動だにせず。薫子の姿を見つめ続ける。
――真司の校内放送により、あらかじめ組まれていたプログラムに従うかのように、総勢約300人の職員と生徒一同が下駄箱や職員玄関に向かう。教頭はなぜ、自分の声が放送室から流れているのか分からない。それでも自分の声に従い、右に倣えで避難を始める。智彦は黒子として自らもその一員となり、これが自分たちの作戦に基づいた避難訓練であることを悟られないように、秘密裏に皆を校庭へと導く。
――校舎内に忍者のごとく潜んでいた昌大は、校内に仕掛けていた監視カメラにより、校内が、校長、薫子、敦子、真司だけになったことを確認(猫と夏目は除く)。すぐさま職員室に忍び込み、教頭のパソコンから学校のホームページに管理者としてアクセス。瞬く間に、この学校の法則とも言える「校則」を書き換える。彼はエンジニアであり、ハッカーでもあった。
――物語は再び、校長室。
――薫子は敦子と協力して、用意していた縄で校長を縛り上げ、ソファーの上に転がして、文字通り俎板の鯉状態にしていた。そして、猫と夏目が見守る前で、板垣退助のように自由を謳う訴状を坂本の口の中にねじ込み、この場が酒席であるかのように、「さあ、呑め、呑みこめ!」と囃し立てる。
夏目 「(動揺しながら)猫さん、本当にこれで良いんでしょうか。薫子さんたちが行っていることはやはり、倫理的、道徳的、法的に問題があるんじゃ。もしそうだとしたら、子どもたちの過ちを正すのは、わたしたち大人の役割だと思うんですが…」
猫 「君はいつから、大人になったと自覚した?」
夏目 「え? そ、それは、成人してからでしょうか」
猫 「それは単に、歳を重ねただけじゃないか。今更だが、通過儀礼がなくなった現代で、大人になるというのは実は非常に困難なんだ。何をもって大人になったと言えるのか、それが分からない。成人を迎えた者たちは、果たして大人と言えるのか。確かに、法的には成人として規定されている。だがそれは、あくまでも表向きの話だろ。その証拠に、中身は一切問われることはない。じゃあ、親になったら大人なのか。その可能性は十分にある。何故なら、自らの子どもと対比ができるからだ。子どもがいるから自分は大人。だが、そんな時代も終わろうとしている。もはや、この国において子どもたちは、いわば絶滅危惧種。つまりは、『大人』という概念が、従来通りの意味をなさなくなりつつあるんだ。――だから、薫子君たちが行っている『大人に楯突く行為』が可能なのは、今、この瞬間だけなのかもしれない」
坂本校長
「うっ、ごほっ、ごほっ(完全体前のセルのように、唾液と共に訴状を吐き出す)。儂は蟒蛇ではない。こんなもの、呑めるか!」
薫子 「(ゴム手袋をはめた手で、再び校長の口に涎にまみれた訴状を押し込み)いいえ、校長。あなたは吞まなければならない。例え目下の者からでも、注がれた酒を断るなんて、大の大人がしていいことではないんじゃない?」
坂本校長
「こ、校則とは、君たちのためにあるんだぞ。君たちが清く正しく美しく、蛹から蝶へと成長して、この社会へと羽ばたいていくために。校則は、君たちが大人になるために必要な、ディシプリンなんだ」
薫子 「拘束の間違いじゃないの? 規律によって作り出したいのは、大人たちにとって都合の良い三大義務を果たす労働者でしょ。夭折の画家、石田徹也が描いたような現代社会で働く人間たちを。その先には、地域のため、国のためのお題目が並ぶ。この国に生まれたからと言って、この国のためにこの身を捧げなければならないという道理はないはず。今はもう、戦後ではない」
――トゥルルルル、トゥルルルル(そこへ、一本の電話)。
薫子 「ったく。小粋な演出のつもりなのか知らないけど、迷惑電話はお呼びでないって言うのに。敦子、すぐに切って」
敦子 「(受話器を取り)はい、どちら様でございますか」
――敦子、相手の言葉を聞き、瞬時に目の色を変える。受話器の送話口を手でふさぎ、
敦子 「薫子さん。あの、あなたにお電話みたいです」
薫子 「は? 誰さ、こんな時に。――(敦子に代わり)はい、もしもし」
?? 「君が、『エレフ』代表の杉田薫子だね」
薫子 「何でその名を?」
?? 「驚くのも無理はないよね。部外者が、君たちの他愛もないサークル名を知っているはずはないだろうから」
薫子 「部外者が言ってくれるじゃん。そう言うあんたこそ、その斜に構えたような話し方、何とかならないの? 異性に一番嫌われるタイプだよ」
?? 「素敵なアドバイスありがとう。心に留めておくよ。だが、この物語の中に僕のことを嫌う人間はいない。いいや、こう言った方が良いかな。そんなキャラクターは存在しえない。坂本校長が僕のことを密かに崇拝しているように」
薫子 「(激しく首を振り)あー、やだやだ。とんだナルシスト野郎だね。これ以上話していても吐き気がするだけだから、切るね」
?? 「残念ながらそれは無理だ。君の行動は、君が親の仇のようにこだわっている校則によって縛られているのだから。君のお友達の昌大くんが書き換えた、新たな校則によってね」
薫子 「さっきから、頭どうかしてるんじゃない? 面倒だから切るよ。じゃ」
――薫子、耳から受話器を離し、電話を切ろうとするも、何故かそれ以上、手が動かない。
薫子 「え?」
?? 「だから、無理だと言っているだろ。――さて、君にはもう用はないから、そこにいる、灰かぶりの猫さんとお話しさせてくれないだろうか」
――薫子、手を震わせながら、まるで誰かに操られているかのように、受話器を猫の方に差し出す。猫、躊躇うことなく、薫子から受話器を受け取る。
猫 「もしもし」
?? 「にゃー、とは鳴かないのですね。がっかりです。伊達に猫は名乗っていないと聞いていたのに」
猫 「僕は東北の人間だが、伊達藩ではないからな。というか、君は誰なんだ。この物語の登場人物は、上の欄で紹介されている人物しかいないはずなんだが」
?? 「――悲しいな。僕はあなたの同業者ですよ。いや、未来の、と付け加えた方が良いですかね」
猫 「ハルキストなのか知らないが、君も一人称は『僕』か。ややこしいな。それはともかく、僕も鼠のような闖入者には慣れている方だと思っているが、君は少々、鼻につく人物みたいだな」
?? 「闖入者だなんてとんでもない。僕は『旅館編』のエピローグから登場していますよ。一度、ご自身で読み返してみては?」
――猫、「灰かぶりの猫の大あくび」8(『旅館編』エピローグ)を読み返す。
猫 「――まさか」
?? 「ええ。やっとお気づきになられましたね」
猫 「まさか、お前は」
?? 「そうです。今あなたが、頭の中に思い浮かべている人物が僕です」
猫 「まさか、お前が、あの」
?? 「――だから、そうだと言っているじゃないですか。早く言ってくださいよ。『ドラゴンボールZ』のあらすじ紹介のような引き延ばしは必要ないんですから」
猫 「分かった。言うよ」
?? 「はい、お願いします」
猫 「言うさ、もちろん」
?? 「猫さん。レイザーラモンRGの『あるある』ネタのようなこともやめてください。焦らしは笑いになりますが、いい加減、読者も怒りますよ」
――猫、『クイズミリオネア』のみのもんたのように神妙な顔をして、その答えを、溜めに溜めた挙句、ようやく、息を漏らすように、
猫 「――三島か」
三島 「ご名答」
夏目 「三島? 三島って、まさか三島創一ですか?」
――猫、夏目に視線を向け、無言でうなずく。
猫 「いよいよ、真打登場ということか。すまいね、出がらしもなくて」
創一 「それを言うなら、出囃子でしょう。猫さん、あなた本物ですか?」
猫 「虎の威を借りちゃいないさ。そんなに疑うのなら、現場に来て、僕のマスクを剥がしてみたらどうなんだ。ルパン三世でもジム・キャリーでもないことがはっきりするぞ」
創一 「後者の『マスク』は困りますね。あなたをアメコミのキャラクターにしてしまう。それこそ、この物語が漫画になりかねません」
猫 「僕も、目玉が飛び出るような演出はごめんだな」
創一 「さて、週刊漫画に倣えば、そろそろコマの枠外に、『つづく』と綴る場面ではありませんか」
猫 「こんな引きで、読者が付いてくるかな?」
創一 「コロナ禍で無観客試合が行われたことを思えば、読者不在でもどうってことありませんよ」
猫 「――そうか。しかし、創一君。知らぬ間に、お互い馴れ馴れしく言葉を交わしてしまったが、第六話ではちゃんと敵対しないといけないぞ」
創一 「十分、心得ていますよ。だって僕は、」
猫 「おっと、それ以上はダメだ。――夏目君、この辺りで一度、カメラを止めよう。上田慎一郎監督には怒られるかもしれないが、テープ切れということにしてくれ」
夏目 「はい。分かりました」
――猫の指示通り、撮影は一時ストップ。休憩を挟んだ後、撮影を再開することに。次回『学校編』、いよいよクライマックス?
つづく
#小説 #連載 #コント #パロディ #学校 #高校生 #校長 #三島由紀夫 #三島事件 #闇将軍 #板垣退助 #自由 #大人 #蟒蛇 #レッドデータ #石田徹也 #もはや戦後ではない #ハルキスト #鼠 #僕 #ドラゴンボールZ #あらすじ #レイザーラモンRG #あるある #クイズミリオネア #みのもんた #出囃子 #ルパン三世 #ジム・キャリー #マスク #アメコミ #コロナ禍 #無観客試合 #カメラを止めるな #上田慎一郎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
