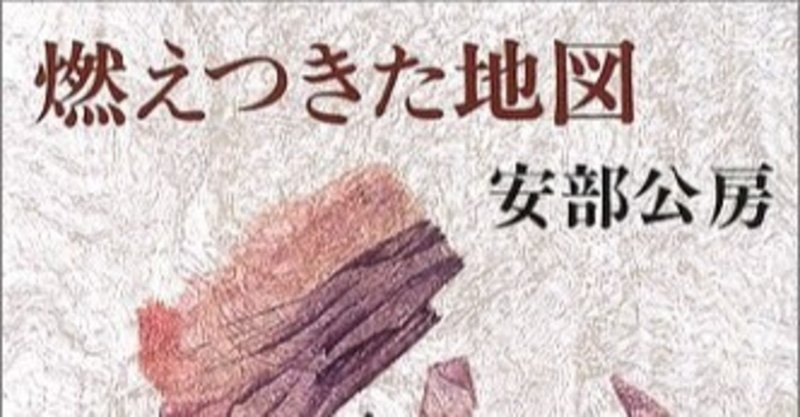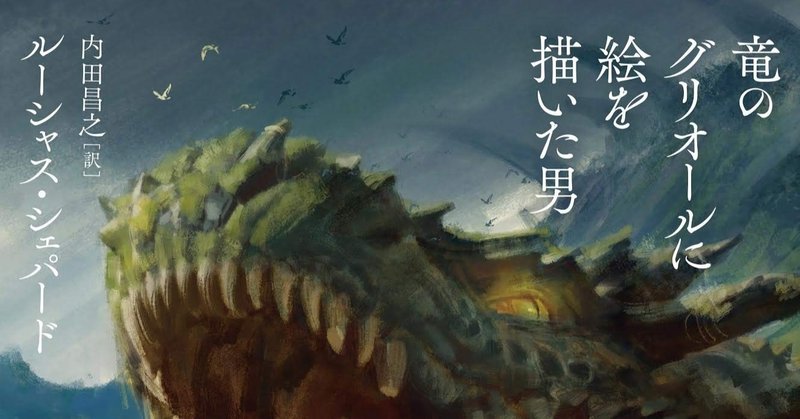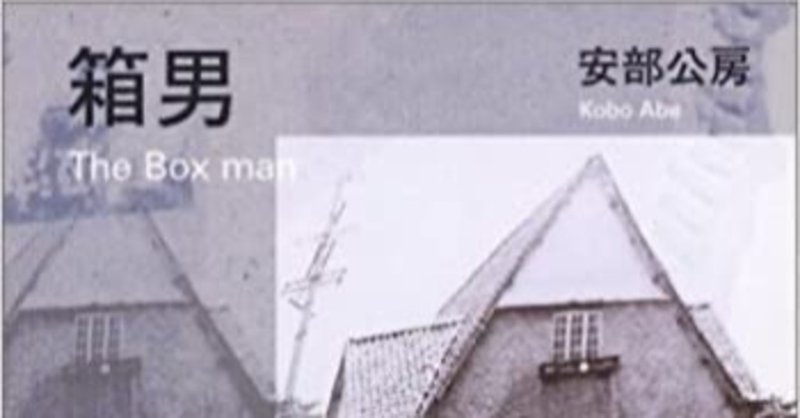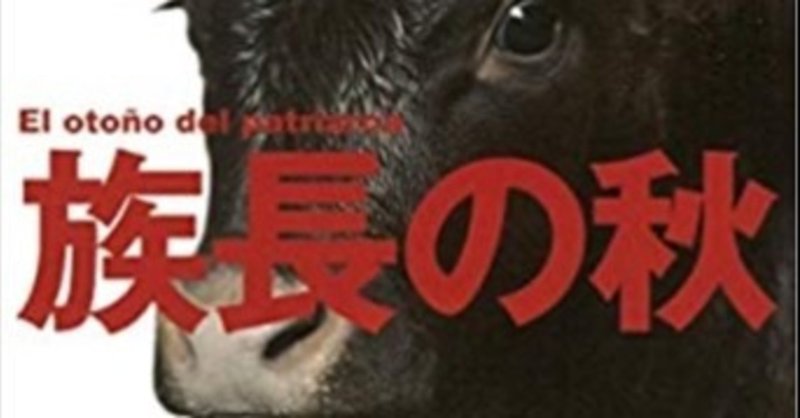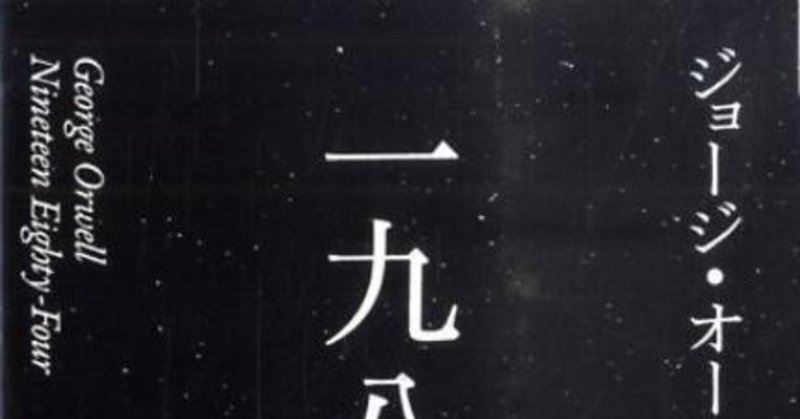#読書感想
「ヴィンダウス・エンジン」(十三不塔)感想
止まっているもの全て見えなくなるという「ヴィンダウス症」。唯一の寛解者であった主人公キム・テフンは、成都の都市管理AIに組み込まれ、「ヴィンダウス・エンジン」の歯車となる——。中国を舞台に描かれる、清と濁の共存する近未来都市は、どこかエロティックな印象をもたらした。個人が超常的な力を得ることへの憧憬を刺激し、上質なエンタテインメントを提供する。
そんな本作に見受けられる構造として、ある種の対比、
ブンゲイファイトクラブ批評 グループC
★点数★
「おつきみ」 3点
「神様」 5点 →勝者
「空華の日」 2点
「叫び声」 4点
「聡子の帰国」2点
★総評★
六枚という短さで、人間の感情を表現するというのはなかなかに難しいことだと思う。作中に描く場面を大きく広げ、個々の人間が薄まっているような印象を受けた。私は物語を大きく分けるものの一つとして、「人間」と「それ以外」を考える(単純な二元論にはならないが、便宜上)。読後感
ブンゲイファイトクラブ一回戦Bグループ感想
・「今すぐ食べられたい」中原佳
食べられたい牛と食べたくない人間の倒錯した悲劇。世界に平和をもたらすだろうその美味と、(観光客がおらず沐浴する人もなくただ死体を焼いている)戦争に近い状態だろう人間界とが、対比される。誰も牛に手を出さず、ガンジスに流してしまうという結末からは、ある種のメッセージを読み取ることができるだろう。寓話だろうか。
・「液体金属の背景 Chapter1」六〇五
組織に腐
ブンゲイファイトクラブ一回戦Aグループ感想
・「青紙」竹花一乃
死へ赴くことを強要される「赤紙」とは対照的な、自ら生を選択する「青紙」の物語。非常に風刺的であると同時に、「自由」への批判が読み取れる。選択は幸福をもたらさず、そもそもハリボテに過ぎなかった。
・「浅田と下田」阿部2
男湯に入る女生徒浅田、家族の元から逃走する浅田の父親。「規範からの脱出」が描かれ、しかし彼らは、帰ることを強制される。脱出することを望まず、母親が嫌な顔をし
第一回かぐやSFコンテスト最終候補作感想
候補作品は以下のサイトで公開されている。
①「Eat Me」
現実に居場所を失って、図書館に魂を、社会に肉体を捧げる、主人公。成長する学校図書館に就職する者たちは、例外なく「マザー」の内部に吸収されて、今度は吸収する側に回るだろう。繰り返される永遠。図書館という名の永久機関。強制と支配の社会(物質世界)から、逃れるための図書館(精神世界)の姿が垣間見える一方で、社会に居場所をなくした人間は、社