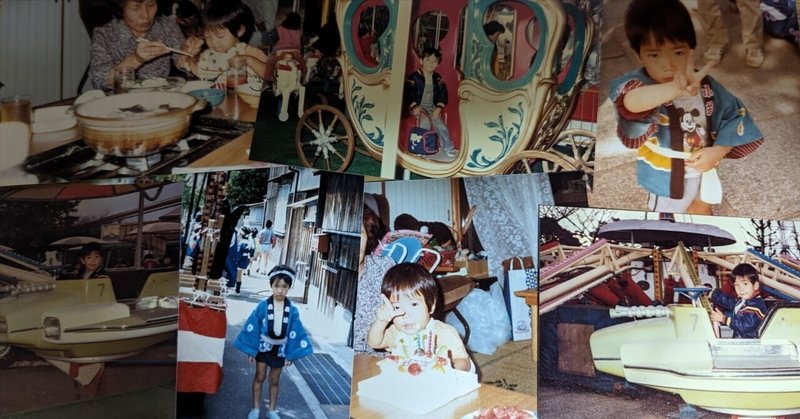
【連載小説】息子君へ 233 (45 俺はかわいそうだと思われたかった-4)
俺は子供の頃からずっと、あのひとと友達になりたいと思って誰かに近付くということをしなかった。ひとがたくさんいるところにいて、みんなのことを眺めていても、あのひとと仲良くなりたいとなんとなく思うことすらなかったんじゃないかと思う。そういうことは、なりゆきでそうなることで、仲良くなりたくて仲良くなるようなものではないような感覚がずっとあった。女のひとのことはそれだけだと難しいなと大学時代に思ったのだろうけれど、それは完全に女のひとに対してだけだったのだと思う。
俺は知らないひととも気楽に話せたし、初対面での印象は悪くなかったのだろうし、新しくどこかの集団に入るときに嫌な態度を向けられて苦労したりした経験はなかった。かといって、誰かに対していかにも相手と仲良くなりたいという態度でひとに近付くということは、自分で気持ち悪かったし、したことがなかったのかもしれない。女のひとに対してすら、自分から近付きはしても、そこまではっきりと仲良くなりたそうな態度は取れたことがないのだと思う。こんなノリでお喋りさせてほしいというノリで話しかけて、相手にそのノリに応じてもらえるように頑張るというような接し方がまともにできたことがなかった。自分の中での相手との現状の距離感として自然な感じで、露骨に好意的にならずに、普通な範囲の態度で接して、うまく話が弾んで興味を持ってもらえたらいいなというような接し方でしか女のひとに近付くこともなかった。
一対一の関係で、女のひとという比較的他者性が強い相手にすらそうだったのだ。ノリを押し付けられることも、自分からノリを押し付けることにもしっくりこないままでいたせいで、そういうことに不慣れだったのだろうし、そう考えると、俺はやっぱりノリに合わせる難しさにつきまとわれた人生を送ってきたんだなと思う。
もうちょっとでそうでなくなれていたかもしれないタイミングというのは自分にもあったはずなのだろうとは思う。けれど、もうちょっとのときもあっただけで、本当に俺はずっと集団のノリみたいなものにまともに乗れないままで生きてきたんだなと思う。
高校の頃は多数派グループで居心地よくしていたけれど、多数派的じゃないひとが異様に多くて多数派になっていただけで、実際、十数人ぐらいのゆるいグループだったけれど、集団の力学みたいなものはほとんど働いていないグループだったし、みんな思い思いにお互いを面白がって、好き勝手なことを言い続けていて、同調圧力的なものとしてのいつものノリをみんなでなぞる感覚はかなり希薄だった。
大学のクラスでも、人数的には一番多数派のグループにはいて、そのグループにしても変わり者が多い集団ではあったけれど、高校の頃のグループに比べれば、多数派的な立ち位置で生きてきたひとがそこそこ混じった集団だった。そこでは個別のひととは喋ったけれど、集団でいるときはそれほど喋らなかった。喋って嫌がられるのを感じていたわけではなかったけれど、みんなが喋っているのを前にしていて喋ることが思い浮かばない感じはしていたし、発言が求められている感じがしていないのは感じていたから、仲のいいひととはああだこうだと喋っていたけれど、そういうひと以外と喋るときも、みんなと喋るときも、普通には喋っていたけれど、自分からはあまり喋らないひととして集団の中にいたような気がする。
大学でも、サークルの仲間とは、自分が中心人物だったのもあってかなり喋っていたし、二十歳過ぎくらいの一番躁的だった頃は、サークルの仲間といるときに、人生で一番集団への一体感を当たり前のように感じて、集団でいるときには自分が消えかかったままになって、それがいい気分であるような状態になっていた。それでも、それが落ち着いてからは、みんなが楽しそうにしているときは、その邪魔をしないようにという感覚になっていることが増えてきて、集団の一体感に溶け込むために、一体感をなぞりにいくのが億劫になっていった。噛み合っていて、みんなと同じような温度の気分でいれば、みんなと同じノリでいなくてもいいという気持ちだったのだと思う。二十歳以降で俺は急激にものの感じ方が変わったし、その中で、やっと一対一ではなく、集団ではしゃげる仲間と一緒にいられるようになったのに、また自分にとっての適度な他人との距離に戻っていったということだったのだろう。仲間は裏で俺がよそよそしくなったとか、下の名前で呼んでくれなくなったとか、悲しんでいたらしい。それを聞いて、俺だって距離感が変わってしまう前の方が一緒に騒いでいる高揚感は大きかったし、心が傷んだけれど、仲間を仲間としか思っていないからできるノリよりも、仲間でありつつ他者としてちゃんと確かめていられるような間合いで接している方がいいと思ったし、それを聞いてからも距離感を戻そうとはしなかった。自分から大事なものを失くしてしまったような気持ちもあったけれど、自分の感じていることを黙らせておかないと、浮かれたことはできなくて、その頃くらいから、俺は浮かれるよりも、目の前のことに感じていることに自分でしっくりくることの方がはっきりと心地よくなっていったのだと思う。
きっと、ひとは集団として協調して行動しやすいように、集団内にいると、みんなに同調してその一体感で心地よくなろうとしてしまうようにできているのだろう。自然と心が半分止まるようになっていて、それによって自分の心の動き方とはギャップのある集団のノリにすんなり一体化できるようになっていたりするのだ。それは他人の感情への共感能力とか、自然と他人に同調してしまう度合いの強さとも関連してはいるのだろう。けれど、それとは別の要素として、集団を意識したときに、自分への意識が途切れるくらいに、自分ではなく集団とかその場が主体であるかのような感覚に切り替わる機能があって、その機能の働き方にも個人差があったりするのだと思う。
俺はそういうことが少し苦手な気質で生まれついてきたのかもしれない。そして、少し苦手な程度で特に困ったこともなくきていたのに、同居人や彼女と毎日のように長い時間一生懸命話し込んでいるうちに、自分が何を言いたいのだろうかと、自分の気持ちを自分で確かめている習慣がついてしまったし、ちゃんとお互いの伝えたいことが伝わっているのか、相手の気持ちをしっかり確かめようとする習慣もついてしまって、自分の気持ちも、そこにいるひとりひとりの気持ちも感じようとしすぎるようになってしまったのだ。それによって、ふとすると集団の雰囲気に壁を感じたり、集団の騒ぎ方への嫌悪感にとらわれやすくなってしまったし、その嫌悪感も自分の気持ちだからと、その気持ちをちゃんと感じようとしてしまって、その気持ちを確かめれば確かめるほど、人間が集団になったときの心の動きが暴力的でいい気になりたいだけの悪意的なものに思えて、自分が集団に対して気持ち的に入り込まないようにしていることが正しいことに思えるようになってしまったということだったのかもしれない。
多くのひとは、みんなが楽しいかのような顔で楽しそうにしていれば、みんなで楽しく過ごせていると感じてしまえるのかもしれない。建前というか、その場でそういうことになっていることを、本当にそうであるかのように思って生きていられるようになっていて、頭の中で楽しいと思っていたら、実際にはいろんな気持ちがあっても、自分は今楽しいとしか思っていないかのように他人に話しかけることができるし、楽しく話せてさえいれば、どれだけ話していても、自分は本当はそういう気持ちなわけではなかったと気付くこともめったになかったりするのかもしれない。
そんなふうにして、多くのひとは、実際にはお互いに細かな不快感や嫌悪感を行き来させていても、それなりに楽しく喋れたと思っていられるし、お互いに友達だと思っていられるし、仲がいいとすら思っていられるのかもしれない。むしろ、友達だと思って接していれば、相手がやってくれたことや言ってくれたことは、全て仲のいい友達が言ってくれたこととして受け取って、相手のリアルタイムの感情の動きは気にしないでいられるのかもしれない。友達だけじゃなく、上司でも、後輩でも、恋人でも、誰に対しても、このひとはどういう相手で、このひととはこういうものだからという以上には、相手の小さな気持ちの動きをいちいち気にしないものなのかもしれない。現実として気持ちを行き来させているのではなく、関係性を確かめ合うようにして、お互いがこの関係性をどう思っているのかということを大雑把に伝え合っているというのが、ひとと一緒にいるときの基本的なあり方だったりするのかもしれない。
だとすると、俺はずいぶん勘違いしていたということになるのだろう。俺は向かい合ったときに肉体的に感じるものだけが実在していると思ってきたのだ。
もちろん、俺だって集団内の序列はどこにいたって常にリアルタイムに感じ取って、みんながそれを踏まえてどういうつもりで誰をどんなふうに扱っているのかを感じ取っているし、自分でもそれを踏まえてひとに接している。それでも、感じるのだから仕方ないだろうと、その場でみんなになぞられているパターンは建前としか思わずに、それぞれの心の動きをその場の現実として受け取ろうとしていた。どういう話の流れなのかはわかっているうえで、いつでもそれぞれのひとを、そうは言っていても一言では言えないいろいろな気持ちがあるのだろうと思いながら眺めていたのだ。
きっとそれは二十歳くらいでものの感じ方が大きく変わる前からそうだったところなのだと思う。大学の同級生の女のひととお茶していたとき、正田君はいつもグレーって感じだよねと言われて、よくわからなくて聞いたら、白黒はっきりしたこと全然言わないよねと言われて、自分では独断的に突っ込んだ話をしている方だと思っていたからびっくりしたことがあった。その場ではわからなかったけれど、少しして、確かに俺は、ああでもないしこうでもないということばかり言ってはいるんだなとは思った。
俺にそう言ったひとは、今思えば発達障害的な傾向がなくもなさそうなひとだったし、素直なひとではあったし、かわいいひとだとは思っていたけれど、自分の頭の中を生きている度合いの強いひとだとも思っていた。だから、当時にしても、白黒はっきりしないと言われて、自分がおかしいのかもしれないと思ったりはしなかったし、白黒はっきりしたことしか喋らないとしたら、その方がおかしいのだと思っていた。
みんな生きていていろんな気持ちになっているし、自分が何を思っているのかということだって、そんなに単純に言葉にできるものではなくて、自分の気持ちもわからないまま状況に流されてばかりいるのだ。それを目にしているのだから、みんないろいろ思うし、みんなそれぞれにどうしてもそう思ってしまうことがあるものなのだろうという以外に、思うことはないはずだろう。
目の前にあるのは、それぞれの肉体で生きている、ばらばらな人間のそれぞれの感情なのだ。どういうパターンだから何と言っておくのが無難だとか、それについては何が正論ということになっているとか、今言うと面白いのはこれだからとか、嫌なやつの話だから自分も嫌だった話をしておこうとか、友達だから慰めてあげようとか、恋人だからすごいねとほめておこうとか、そういうことの全ては、目の前のひとがどんなふうに自分の中で気持ちを動かしながらそこにいるのかとは関係がないことなのだ。
けれど、どうしたって、ひとというのは、すぐに目の前の肉体がどんな気持ちでそこにいるのかを感じていない状態になってしまうものなのだ。
俺はこの手紙のようなもので、人間というものがどれほど集団の中での自分の地位をよいものにするというモチベーションでしか行動していないものなのかということを書いてきたけれど、それがどうしてなのかわかっただろう。
集団に一体化しようとする本能が強いひとからすれば、そういう感覚はただ当たり前のものでしかなくて、わざわざそれについて何か思ってもしょうがないことなのだろう。けれど、俺はそうではないし、君は俺の身体を引き継いで生まれてきている。君だって、俺と同じような違和感にとらわれ続けてしまうかもしれない。その違和感を小さい頃の君が素通りできたとしても、君がいつか、わかってあげたいとか、わかってほしいという気持ちで一生懸命に他人を関われる時間を過ごせるようになったときには、君の肉体が自分の気持ちや相手の気持ちを感じ取り続けてしまうせいで、君は自分の思いたいことだけを思ったまま、何も感じていないかのようにひとと接することができなくなっていくのかもしれない。
そうしたときに、君にとっての世界は変質するし、そこから君はどうしてなんだろうと思い続けることになるのかもしれないんだ。君だって、どうしてみんなはあのひとのちょっと嫌なところが気にならないんだろうとか、どうしてあのひとも集団でいるときはああなんだろうとか、自分だって集団の中で楽しくやっているときには、自分らしさとは別のものを当たり前に自分の中に浮かび上がらせてしまっているとか、そういうことを考えてしまうようになるのかもしれない。そして、それがどういうことなのかをイメージしようとするときには、集団の中の人間というものがどういうものなのかを自分なりにイメージできるようになっていく必要がある。その助けにこの手紙がなればいいなと思う。
俺にとっては、集団と同一化できなさというものが、俺の人生を貫いている中心的な原理のようなものになってしまった。
それは自分でも不思議なことだったりする。俺は生まれつき警戒心とか不安感が少ない方だったのだろうし、小さい頃からひとと接するのを避けるわけでもないし、ひとりになりたがったりするわけでもなかったし、個人と個人として関わるのならいつでも楽しんでいられたのだ。上下意識とか排除の意識がそれなりにしっかりと働いてしまっている集団の中にいて何かをするときに気持ちが入り込めないというだけだった。
逆に、俺がそれなりに素直で漠然と相手に合わせているだけでひととすんなり関われるような気質だったから、集団でうまくやるのが難しくなっていったというのもあるのかもしれない。俺はひとりで自己完結したがるよりは、むしろ、他人との関わりの中に自分を確かめていたし、楽しければいいという自己満足ではなく、ひとに働きかけることの充実のために生きていようとするようになっていった。ただ、ひとと楽しくやるということの方向性が偏っていたというのはあったのだろう。俺は相手の気持ちを感じるとか、自分が自分であることを大事にしすぎていて、そのせいでみんなと楽しくやれている感覚を最大化できるように自分をチューニングすることをしないままになりすぎたというのはあったのだと思う。
他人との間に関係性ができていくということを、俺はどういうことだと思ってきたのだろう。いい時間を一緒に過ごしたことで、お互いが絶対に自分のことを軽く扱ったりしないと信頼し合ったうえで、いろんなひとといろんなことをできたし、いろんなひとと一生懸命になって仕事をできた。いい時間を一緒に過ごしたことで、傷付けられることはないと信じられることで向けられる顔を向けてもらえるようになったりはしてきた。俺はそういうものをうれしく思ってきたし、そういう関係にたどり着くことができたそのひとたちとの過去に対してよかったなと思う気持ちはたくさんある。
けれど、誰とどんな関係になれたからって、自分の中でその関係の重みが変わるわけでもなく、そのうちにそこを通り過ぎていくというだけだったのだし、いつだって俺は、自分が自分であることを感じようとしているばかりではあったのだろう。何かを感じて、何かを思って、何かをすることにしか意味がないと思っていたところはあったのだと思う。何をするわけでもなく、ただ喋っていれば気がまぎれるとか、一緒に楽しいものを見ていれば楽しい気分になるからとか、そういうことのために他人と時間を過ごす必要性を感じていなかったのだろう。
それだって実家で暮らしていたときからそうだったのだろう。ちゃんと喋るならちゃんと喋りたいし、ちゃんと面白くしようとするならそうしたいけれど、親とテレビを見ながら話しているみたいに、漫然とそれらしく楽しいっぽい感じで過ごすだけなら、一人でゲームをしていればいいと思っていた。今だって、ゲームをしなくなっただけで、何かに何かを感じられるわけでもなく、ただだらだらしたことをするだけになるなら、そのひとと一緒に過ごすよりは、ひとりでやれることをやっていればいいと思っているのだと思う。
親といて安心したり落ち着いたりするひともいるのかもしれないけれど、俺は思春期以降は実家のひとたちと一体感のようなものを感じたことがほぼなかったんじゃないかと思う。親が自分のことをまともに感じてくれているとは思っていなかったし、親と何を喋っても、気持ちを動かされることのない上滑りするだけの何かにしかならないし、一緒にいて気が楽ではあったのだろうけれど、何を思っても口に出す気もなくぼんやりしているだけだったようにも思う。実際、実家を出てから、親に会いたいとか、親の声を聞きたいと思ったことは一秒もなかったけれど、それは大人になった俺にとって、親は俺が感じたい何かを感じさせてくれるわけではない存在になってしまっていたからなのだろう。
俺はただ感じようとしていただけだったのだと思う。感じようとしていたから、実家にいるときのように、ひとがいても、そのひとたちが特に何を思っているわけでもないと、その場に感じるべきものがなくて、ぼんやりするしかないことが苦痛になってしまっていたのだ。
もちろん、それは俺の感じ方が間違っていて、家族というのは、目的もなく一緒にいるというか、一緒にいることが目的となっている集団で、友達のように何かをするために集まっていたり、集まっているのだから何か面白いことをしようとする集団ではないのだろう。
俺だってそれくらいはわかっていたのだとは思う。けれど、わかっていても、そこにひとがいるのに何も感じないのは違うんじゃないかと思っていたのだろう。自分の側には思うことがなくはないのに、思ったことでは接することができないことに、つまらない場所だなとは思っていたのだ。そういう意味では、子供のことをちゃんと見守ってあげて、ちゃんと話し相手になってあげるような生活をしたいと思うようになっていった俺が、自分の実家のような家庭を作りたいとは思ったことがなかったのは、あまりにも自然なことだったのだろう。
集団があって、関係性があって、それに付き合わされるということが、俺はいつも億劫だったのだろう。パターンだけがそこにあって、目の前の相手が今この瞬間に感じていることや思っていることに反応するのではなく、存在しないものを期待されたり、駆け引きされたりするのがずっと居心地が悪かったのだ。
だからこそ、セックスフレンドのひとは気が楽だったのだろうし、付き合っているひととは同棲したいと思わなかったのに、友達とは何年も一緒に住んでいたのだろう。何も期待されていなくて、楽しくやれることで楽しくやることしか求められていなかったから安らいでいられたのだ。未来がない関係というか、なぞるべきイメージがないというか、今笑えていたり、今セックスして気持ちよければそれでいいというだけの空っぽな時間が俺には心地よかったのだ。
それも身内意識の薄さからきたものだったんだろうなと思う。他者として関わっているのなら、相手に何も期待していないのが普通で、その場で感じて思ったことを返すだけだから、敵意を向けられれば敵意を返すけれど、そうでなければ、相手がどうであれ、めったに腹が立つことはなかった。逆に、一対一の関係だったとしても、相手に二人の集団という意識を持たれると、ちょっとした気持ちの動きが鬱陶しく感じられてしまったりすることもあった。
恋人を自分にとって特別な存在だと思っているようで、いろんな関わったひとたちの中で最も深い関係というだけで、他のひとたちとは別種類の特別な存在とは思っていなかったというのも、そういう問題だったのだろう。俺はひとに甘えられなかったし、寄りかかれなかったけれど、それだってそういうところからきていたのだろう。
俺にとっては、誰もがどういう関係であれとりあえずは他人で、誰のことも、自分のことを守ってくれたり、かばってくれたり、助けてくれてもいいはずの存在だと思っていなかったのだと思う。
自分は誰かを助けたり支えたりできるときにはそうしようとしていたけれど、それは俺がそうしたくてしているだけで、そういう関係だからしないわけにはいけないと思ってやっていたことはめったになかったのだろう。むしろ、いつも、そこまでの関係じゃないけれどとか、そこまでしなくてもいいんだろうけれどと思いながらやっていたように思う。そして、その反転として、誰かに対して、自分を助けてくれてもいいはずなのにと強く思うことができなかったというのもあったのだろう。
頼りたいという気持ちがないわけではなかった。頼ることを求めてもらえなかったというだけだった。自分が辛かったり、悲しかったりするたびに、このひとは俺から寄りかかられたくはないのだろうというのを確かめて、寄りかからないですませていた。
例外は同居人だった男だけだろう。本当の意味で俺と対等な関係として、上からも下からも見ずに、まっすぐに俺を見てくれて、俺が辛かったり悲しかったら嫌だと、当たり前のようにして、はっきり嫌だとだけ思って接してくれていたのは、そいつだけだったのだろう。他のひとからすれば、俺はどこかしら接しにくいひとで、辛さとか悲しさのような感情を充満させている状態の俺にはできれば関与したくないと無意識に思っていたのだろうと思う。
付き合っている相手には、たまには無理をして寄りかかってみたこともあった気がする。けれど、俺の感情が少し落ち着くのに付き合ってくれたという程度で、俺の悲しさとか苦しさに触れようとしてくれて、それに気持ちで反応してあげようとはしてくれなかった。
関与することと、見守ったり寄り添ったりすることの間には、大きなギャップがある。対等で、他者として関われて、かつ、気持ちを押し付けてくれることが関与には必要で、そのためには、友達とか恋人とか家族として相手を見ている以上に、ひとりの人間として相手を見ていないといけなくて、俺は付き合っていた相手とは、そんな関係にはなれなかった。
最初から諦めていたわけではなく、対等な存在として、関係性としてではなく、俺の気持ちに気持ちで関わってくれる相手になってくれるのかもしれないと思いながら付き合ってはいたつもりだった。けれど、結局は、彼氏彼女なんて、彼氏としてしか扱ってもらえない形式的な関係なんだなと悲しくなるというのを繰り返しているばかりになったのが俺の人生だった。
次回
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
