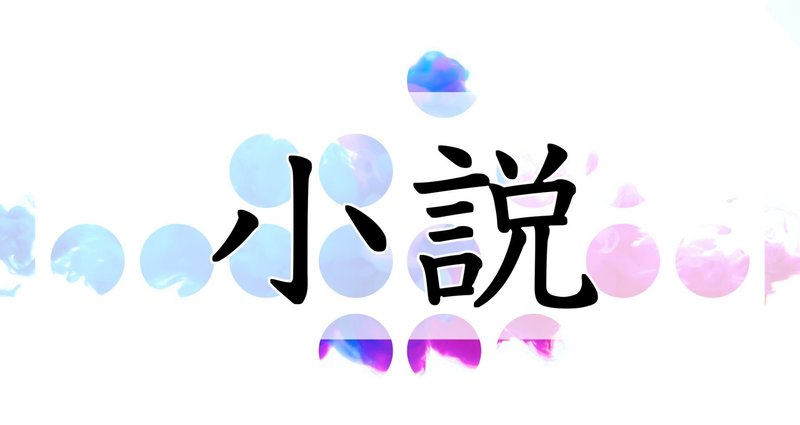#忘年P
ささど「花火とその余熱」前編
「今年もたのしかったね、塔也くん」
関野遥が僕に笑みを向けながらそう言った。余裕を湛えた、世界の全てにーー彼女の認識する世界そのものに――慈愛を注ぐような、そのような笑顔だった。慎ましい美しさが遥を包み込んでいる。しかし、その姿は僕を幸せにはしてくれない。
大晦日の午後一一時三〇分、僕と遥は山奥の国道上にいる。道路自体は綺麗に舗装されているが、ガードレールを境界として、その先には暗い山肌が広が
虫我「サンタ証明の途中式」前編
「次は、如月四条、如月四条」
ある冬の一夜。大学生である僕は、その送迎バスの最終便に一人揺られていた。
「……」
十二月二十四日の夜。生憎僕にとってクリスマスは聖夜ではなく、何気ない日々のその一員にしか過ぎない。
僕は窓を、その中にうつる世界を見る。夜の暗闇に照らされるキャンドルのような街並み。宝石のような街灯。腕組みして歩く二人組。笑顔の絶えない家族連れ。それは、クリスマスと形容するにはぴ