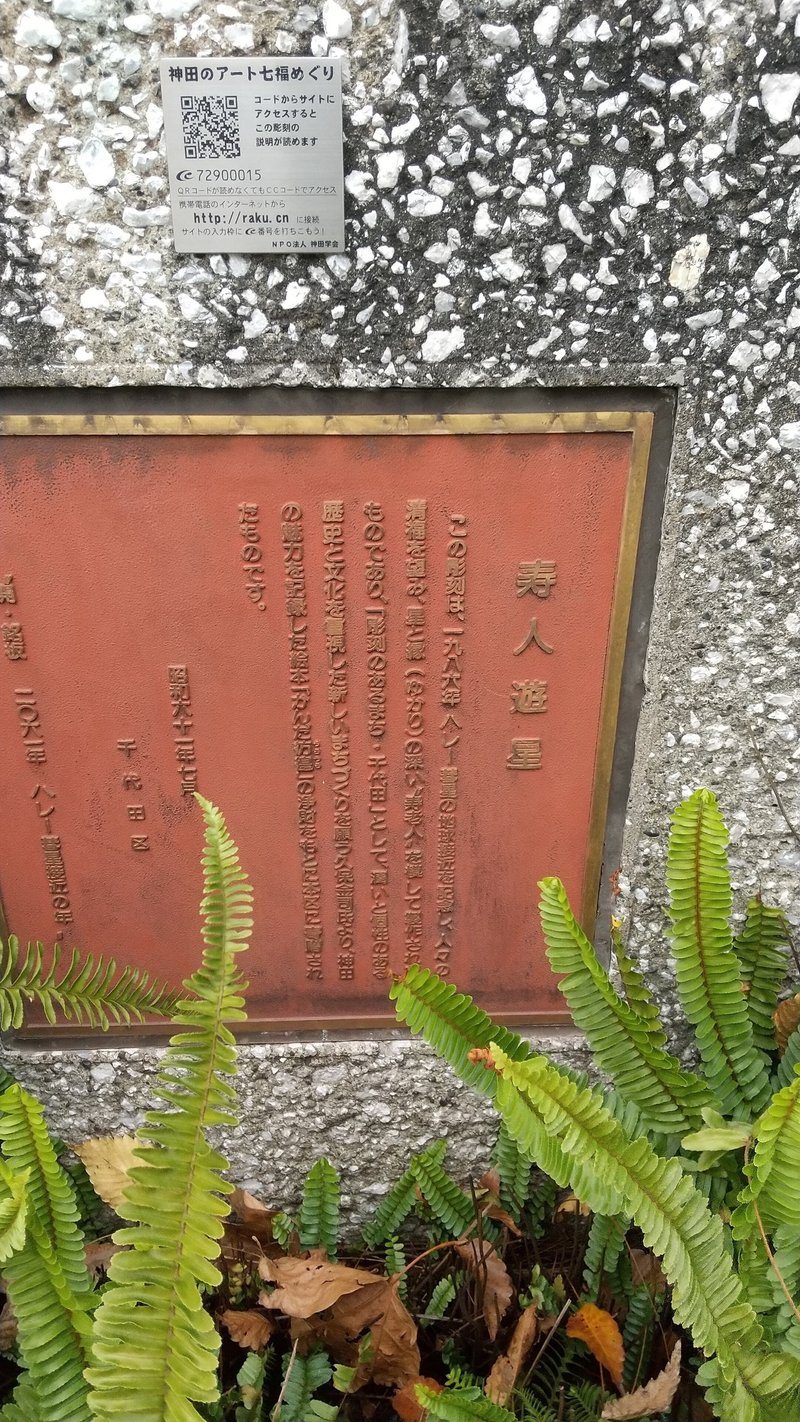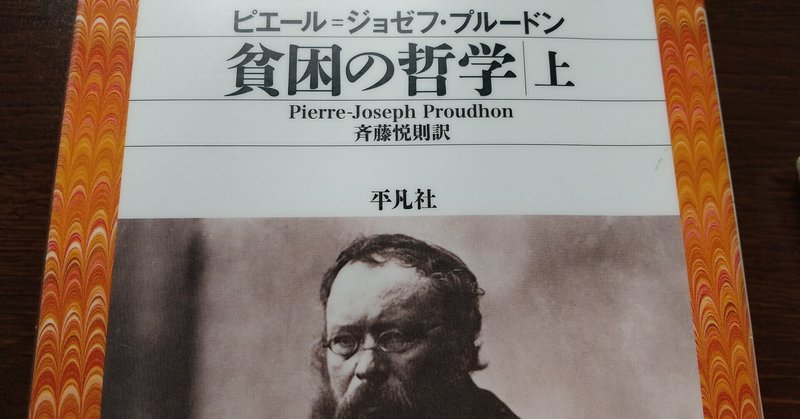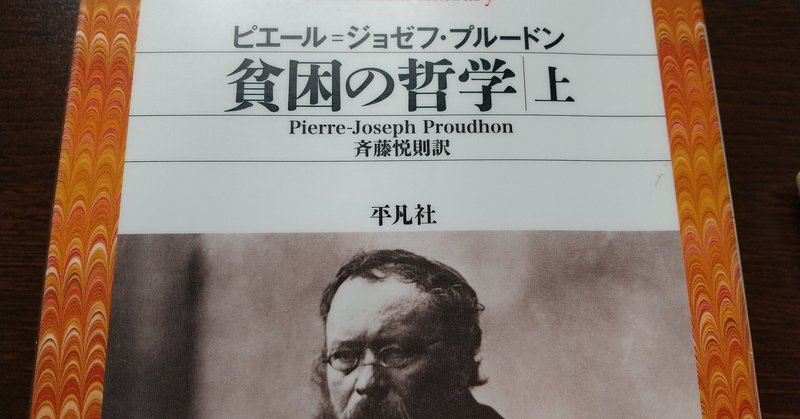#note新エディタ
【読書録】井筒俊彦『イスラーム哲学の原像』
宣言通り、読書録を久しぶりに更新しようと思う。
だが、読書録って、こういう系の記事を書いたことのある人はわかるだろうが、その場で読んでその場で書くという感じより、だいたいひと月前までの以前の蓄積から、引っ張り出して再生するという感じの方が近い、その場でいっぺんに読むというのは、自分が相手にしているような本だと難しい。今急に書こうと思っても、その以前の蓄積というのがなければ、急には立ち上げられな
【読書録】アレクサンドル・ジノヴィエフ『カタストロイカ』
西谷修『不死のワンダーランド』のなかで、共産主義国家の資本主義化運動について解説しているところで、この著者の名が出たので、あまり政治批評家の読み物みたいなものは読まないんだけれども、いい機会だと思って図書館で借りて表題の本を読んでいる。
最初の方は、大戦後のソ連の政治情勢など知らないから、全然ついていけなかったのだが、なんとなくわかってくるとともに、そんなこと以上に、ソ連、現在ではロシアとされ
【読書録】西谷修『不死のワンダーランド』の総評
総評というと偉そうだけれども、今まで部分的にしか触れてこなかったこの本の全体について、少なくとも個人的に考えてみる必要を感じた。
とはいえ、この本の全体的なメッセージは明快だ。なんとなくの感触でしかないが、私たちは第二次世界大戦、そしてナチスドイツのユダヤ人殲滅作戦などを機に、生と死という価値が変わった。不死といえば聞こえがいいが、わたし自身として死ぬすべは奪われてしまった。私が生きている間に
【読書録】西谷修『不死のワンダーランド』
この本を読み続けて、たぶん一年かそこら経つ。以前に述べたように、最近の時間経過が自分の感覚とだいぶ違っているため、そこのところは自信がない。が、今年読み始めたということはない。去年のいつごろかかもしれない。とにかく、長さと読みやすさの割にはずいぶん時間がかかってしまった本を、ようやく読み終えることができそうだ。
そういうわけで、西谷修『不死のワンダーランド』、最後の手前の章の「民主主義の熱的死
【読書録】豆腐色戦記(白)
封筒は茶色、豆腐色は白を塗布しろと。
ふうろいとに憑りつかれておる。もともとは、ドゥルーズの『千のプラトー』を読んでいて、狼男の章を読んだ時に、元ネタを読んでおくべきだと考えて開いたフロイト全集だったが、そこから逸れるようにして開いた西谷修の『不死のワンダーランド』にも、「〈不安〉から〈不気味なもの〉へ」と題して、またしてもフロイトを読めと促される。フロイトならもう読んだよ、と、「夢判断」を
【読書録】フロイトから逃れたつもりがフロイトに戻ってくる
気分転換というか、少し気ままに本が読みたくなって、あるいは、つい今しがた本の整理をしたからという物理的な動機もかかわってくるのかもしれない、とにかく西谷修の『不死のワンダーランド』を読み始めた。いや、前に半分以上読みかけていて、放っていた。こんな本はたくさんある。あまり途切れ途切れに本を読むのはよくないと決め込んでいたけれども、割合悪くもないかもしれない。本の種類による。ある種の散漫な意識に貫か
もっとみる【読書録】フロイト全集14 2 フロイト節
フロイトの書いているものを、内容を理解し、感じる為に飲み込まなければいけない、フロイト節のようなものがある。
一つは、無駄にではないだろうが、回りくどいこと。いや、半ばは無駄なんじゃないかと思う。「私はもしかしたら読者の疑念を招いてしまうかもしれない、それは……」という感じの、エクスキューズが多く、厳密でありすぎることに読んでいると疲れを覚えてくる。
もう一つは、多く感じるところかもしれない
【読書録】フロイト全集14 晩年の信仰
フロイト全集14巻、有名な『狼男』分析を読むつもりで読み始めたけれども、とりあえず月報を読んでいる。
あまりよく知らない、いろんなジャンルの偉い先生方の、論評がつづく。
その中、月報の最後の文章、濱田秀伯という人の、「ジャネとフロイト」という文章の中で、知っている人は知っている、『ヒステリー研究』という、フロイト初期の出世作みたいな研究本を共同制作した人について触れていて、この人、フロイトと
【読書録】レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』2
しかし同時に、人類が自らに言いきかせるべきだと思うのは、人間とその環境との最良の均衡に人類が到達できるのは、あらゆる科学の成果を用いることによってでしかないということです。それ以外に、われわれがそこに到達方法はないでしょう。(……)科学の成果だけが、たとえ僅かの程度にではあっても、何か似通ったものを再構成することができるからです。
(本書、30ページ)
彼らが予見しているのは、自分たちが処理する
【読書録】悲しき熱帯1
読書は続けていたが、久しぶりの読書録となった。思ったより進んでいないことは事実だ。どうということはないけれども。
中央公論社、中公クラシックスではない、単行本で出た、日本語での初出化はわからないが、版の、レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』を読み始めた。坂口恭平が、彼の独特の行動をはじめる、その原動力の一つとなったのが本書だと言い、また中沢新一がことあるごとに参照している研究者でもあるから、期
【読書録】ロベール・パンジェ『パッサカリア』の詳しい感想
前に、『パッサカリア』を読み終えたと書いたけれども、本当に、ただ読み終えたとか、どれくらい読んだ、としか書いていなかったので、さすがに中身に少しは触れようかと思う。
ロベール・パンジェ。フランスの、前衛的作家の一人。活躍していたのは、おそらくひと昔前だ。ロブ=グリエ、サミュエル・ベケットと交流があった、といって伝わるだろうか。まさに同時期に生きていて、彼らの小説を息を吸うように読んで、そしてそ
【読書録】プルードン『貧困の哲学』3
事実が先なのである。美しく整えるより前に、広く探求しなければならない。
(プルードン『貧困の哲学 上』平凡社ライブラリー)
ページ数をメモし忘れた。上巻の前半には違いない。
学問を始める際に、それがどんな形を成しているのか考える、またそれを成形しようとするのではなく、まず事実となることを集めよ、という文脈で語られている。
これが、小説にも言えることなのではないかと思った。
小説を書く際に
【読書録】プルードン『貧困の哲学』2
そこで私に言わせてもらえば、普遍的な理性とは、昔のひとびとが神と呼んだものを近代的な用語であらわしたものにすぎない。ことばはあたらしくなった。しかし、それでものごとがわかったのだろうか。
(プルードン『貧困の哲学 上』平凡社ライブラリー、18p.)
「理性=神」とは、よく聞く話ではあるが、改めてグッと来た。フランス革命のときに、神を廃棄し理性を信仰するといって、「理性の祭典」なる祭りをやって色々
【読書録】プルードン『貧困の哲学』
全くの偶然から、この本を手に取った。少し噂は聞いた気がするけれども、どういう哲学者というイメージもなかった。
著者略歴を見てみる。
十九世紀を生きた、貧しいが独力で学問し、トルストイに『戦争と平和』を書かせた哲学者。
なるほど。わかったつもりになる。
数ページ読み進めてみた。この時期の哲学者に向かって言うのは酷だが、今の所、全くキリスト教的世界に向けてしか喋っていないと感じる。中国に対し