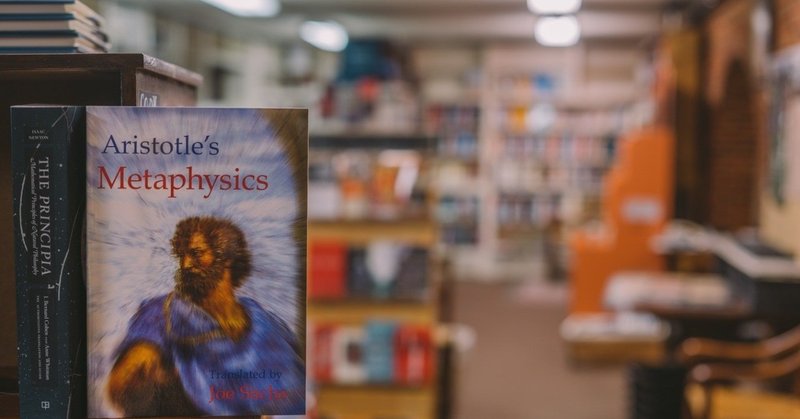
斎藤哲也氏の『試験に出る哲学』を読む
■斬新な企画で勝った
▼「桃始笑(もも はじめて さく)」という季節になったが、4月から大学生になる人や、今年20歳になる人に、おススメしたい本を紹介する。
▼卓越した編集者として知られる、斎藤哲也氏の『試験に出る哲学』(NHK出版新書)。昨年話題になった新書の一冊である。
まず、発想が斬新である。過去20年ほどのセンター試験「倫理」の問題を読み込み、そこから20問を厳選して、古代ギリシャから「近代批判」の時代まで、西洋哲学をおさらいしよう、というものだ。
一読して、この内容は文庫に詰めると窮屈で、単行本だと締まりがなくなる、新書ならではの好企画だと感心。しかも、どの哲学者についても水際だった編集である。筆者が10代のころにこんな本があったらよかったのに、と思った。
▼哲学を学ぶことで、今、目に映っている時代が違って見えるようになる場合がある。本書には、そういうきっかけが詰まっている。ここでは四つ挙げておこう。適宜改行。
■ソクラテスが刑死した背景
▼一つめ。ソクラテスの時代。
〈ソフィストとはソフィア(知恵)のある人を意味しますが、前5世紀のアテナイでは、報酬と引き換えに教養や弁論術を教える職業教師のことをソフィストと呼びました。
彼らは、自然哲学者のように万物の原理を探求するのではなく、もっぱら政治の場で人々を説得するための弁論テクニックの教授に意を注ぎ、多額の報酬を得ていました。
ソフィストに共通する価値観は、プロタゴラス(前490頃~前420頃)の「人間は万物の尺度である」という言葉に象徴されます。つまりソフィストたちは、何が正しく何が正しくないかは、個々の人間の尺度しだいという相対主義的な価値観にもとづき、人を上手に言いくるめられるような説得のテクニックを市民に売り込んでいったのです。
「正しくあることではなく、正しく思われることをこそ望むべきである」(グラウコン)、「〈正しいこと〉とは強い者の利益になることにほかならない」(トラシュマコス)など、普遍的な正義など歯牙(しが)にもかけない彼らの主張が浸透するにつれ、アテナイ市民たちは、富や権力、名誉ばかりを追い求めていくようになりました。〉(39頁)
▼これがソクラテス刑死に至る背景である。今、ソフィストはいるか、いないか。
■ベーコンの「市場のイドラ」
▼二つめ。ベーコン。本書は平田利之氏のイラストがどれも素晴らしいが、この項も、ベーコンの唱えた「四つのイドラ」が、イラストを見ただけでパッとイメージしやすくなっている。
ベーコンは人間が囚(とら)われる偏見を「四つのイドラ(幻影)」に整理した。「種族のイドラ」「洞窟のイドラ」「市場のイドラ」「劇場のイドラ」だが、最も厄介なのは三番目の「市場のイドラ」である。
〈流言やデマを信じたり、抽象的な概念をもてあそんだりする際に、市場のイドラは生じます。〉(113頁)
▼400年前の指摘は、現代にそのまま当てはまるか、否か。
■カントの「定言命法」
▼三つめ。カント。この章も、カントの哲学を最小限度の分量で、まさに「要約」されている。カント自身の有名な「定言命法」について。
〈汝の人格および他のあらゆる人の人格のうちにある人間性を、いつも同時に目的として扱い、決して単に手段としてのみ扱わないように行為せよ。(『道徳形而上学言論』)(中略)要するに、他人を手段としてのみ扱ってはいけない、ということです。〉(162-163頁)
▼人は人を「手段として」扱わざるを得ないが、手段として「のみ」扱ってはいけない、というところがミソだ。不朽(ふきゅう)の一言だと思う。
他人を手段としてのみ扱う人は増えているか、減っているか。
■ハイデガーの「ダス・マン」
▼四つめ。現代に近づいて、ハイデガー。(ここから後の太字は引用者による。)
〈つねに周囲の他者やモノに気遣いを向けている人間は、自分に固有な本来的なあり方を忘れて、周りに合わせるだけの状態に陥ってしまうとハイデガーはいいます。
ハイデガーにとって、本来的なあり方とは、与えられた可能性のなかから自分自身の生き方を選び取り、自らの存在をその都度噛(か)みしめるような状態をいいます。
それに対して、日常生活に埋没して、周囲に流されるような状態に陥ることをハイデガーは「頽落(たいらく)」と呼び、誰であってもいいような非本来的なあり方を「ダス・マン」と名づけました。「ダス・マン」は「ひと」「世人(せじん)」「誰でもない人」などと訳されます。
ハイデガーは「ダス・マン」のあり方として、くだらないおしゃべりや、物珍しいものに飛びつくだけの野次馬的な好奇心などを挙げています。〉(224頁)
▼インターネット時代になって、「ダス・マン」は増えたか、減ったか。おそらくこの統計はとれない。「誰でもない人」に陥った人本人は、まさにこれこそ自分ならではの行為だと思いながら、「くだらないおしゃべり」や「物珍しいものに飛びつくだけの」日々を生きているからだ。インターネットの中でも、外でも。
■二つの時代
▼巻末の哲学史と哲学者のブックガイドも素晴らしいものだ。本書で言及されているが、このブックガイドには載っていない、二つの「時代」について触れておきたい。
時代が変わると、「それ以前」の時代の常識は消えてしまう。しかし、テキストなどが残っている場合、「それ」の前と後を見比べることで、歴史の面白さ、思想の面白さを痛感することができる。
■アリストテレスとイスラム圏
▼一つは、アリストテレスとイスラム圏について。「12世紀ルネサンス」と呼ばれる物語だ。
〈6世紀に東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌスが異教禁止令を出したことで、哲学研究者たちは追放の憂き目にあい、アラビアの地に逃れていきました。
このとき、アリストテレスの文献も一部を除いてほとんどが流出していった。そのため、アリストテレスの遺産はもっぱらイスラム圏で継承されていくことになったのです。
しかし、11世紀末に十字軍運動が起こり、イスラム圏との交流が活発になったことで、アリストテレスの文献がイスラム圏からヨーロッパ世界に逆輸入されていきます。
ここでキリスト教神学は、アリストテレス哲学をいかに受容するかという課題に直面します。というのも、イスラム圏から伝わったアリストテレス哲学には、キリスト教の教義と衝突する内容が含まれていたからです。〉(93頁)
▼西洋にとってイスラム圏は恩人にあたるわけだ。
この時代の「知のドラマ」を見事に描いたのが、リチャード・E・ルーベンシュタイン氏の傑作『中世の覚醒』である。かなり分厚い本なのだが、なんと文庫化した。
■17世紀の「科学革命」
▼もう一つの時代は17世紀。いわゆる「科学革命」だ。斎藤氏の手腕が水際立っているのは、「オッカム」から「科学革命」までの300年の流れを、たった新書2頁弱で要約してしまうところだ。
〈神学の世界では、14世紀のフランチェスコ会士ウィリアム・オッカム(1285頃~1349頃)が、トマス・アクィナスとは異なる、神学と哲学を明確に分離する思想を展開しました。
これは、いわば信仰と理性の役割分担を明確にすることにほかなりません。
単純化すれば、神の問題は神学が担当するが、現世の自然研究は哲学(理性)が担当できる。そのことは結果的に、理性の活躍範囲を押し広げることになり、近代科学の土壌を準備していきます。
また、14世紀~16世紀にかけてイタリアから広がったルネサンスも近代科学と密接なつながりがあります。
たとえば、ルネサンス期に確立された遠近法は、絵画の空間を人間の視点から主体的に再構成するものであり、その構成は数学的な計算にもとづいています。
実際、遠近法を駆使したレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519)は、数学や力学にも精通し、「工学は数学的科学の楽園である」という言葉も残しています(『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』下巻、杉浦明平訳、岩波文庫)。
こうした神学の変化やルネサンスを背景にして、17世紀には、天動説から地動説への転換、ガリレイやニュートンらによる力学の基礎の確立など、その後の世界に決定的な影響を与える研究が次々と生まれていきました。これが17世紀の「科学革命」と呼ばれるものです。〉(106-107頁)
▼「12世紀ルネサンス」と、17世紀の「科学革命」の二つをクローズアップしてみたが、いずれも「キリスト教との対話」が大きなテーマになっていることがわかる。
本書は全編にわたって、西洋哲学にとってのキリスト教の意味が見え隠れする。この短い本で、驚くべき編集の力量だと思う。
▼ちょっと哲学を学んでみたい、と思った人は、まず本書を手にして、巻末のブックガイドから「次の一冊」を吟味するのがいい。
(2019年3月13日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
