
445.私たちって、良かれと思い、ついつい人に親切にしてしまう。でもね「いらぬ、おせっかい」の場合もあるようだ。
(6)人生を好転させる方法
1.いらぬ、おせつかい
私たちって、良かれと思い、ついつい人に親切にしてしまう。
親切って、間違いはなく、親切が足りない世の中だからこそ、それが必要なことなんだけれど、ときとして、それは「いらぬ、おせっかい」の場合もあるようだ。
例えばね、「相手が親切を望んでいる場合」と、「相手が望んでいない場合」がある。もちろん、それでも親切は悪いことではないけれど、問題は相手側にもあると思う。
ある女性がcoucouさんにとても親切にしてくれた。
何も頼んでいないのに、まるで姉さん女房のように手取り足取り説明をしてくれるんだ。coucouさんに説明がなくとも、知っている場合であっても、相手に悪意があるわけがないので、そのまま親切をいただくようにしている。そして、親切にされるたびに「ありがとう」と感謝するようにしているんだ。
その女性はね、注意してみていると、coucouさんだけ特別に親切をしてくれるのではなく、他の人たちにも親切丁寧にお手伝いをしている。
でもね、それを良し、と思わない人もいるようで、煩がる人もいる。
それも自然なことだけれど、相手が望んでいないのだもんね。
でも、その煩がれた女性はとても悲しそうな顔をしていた。
人はそれを身から出た錆のような、親切の押し売りのように思うかもしれないけれど、「悪意のない善意」「人を思う純粋な気持ち」からなのだから、ただ素直にありがたく感謝すれば良いのだけど、実際は嫌われてしまうようだ。(おかしいよね?ありがとうって言えばいいだけなんだから)
coucouさんはどちらが正しくて、どちらが悪いというよりも、「してもらう側」が常に感謝の気持ちを持つことの方が大切だと思うんだ。
coucouさんの場合は「偉大なる一方的なおせっかい」の持ち主だからそう思うのかもしれないけど、「おせつかい」というものは現実には大変なことなんだよね。
それはって、良く思われない場合が多いからなんだ。
また、注意しなければならないことは「おせつかい」と「気づかい」はとても似ているもので一見区別がつかない部分もあるけれど、どちらも悪意からでなく好意から出ているもの。
どっちも大切な人間関係のものだけれど、こんな場合は自分でも気づかないまま「悪意」に変わる場合がある。
例えば、相手が悩んでいたとしても、困っていたとしても、「一人で考えたい」「一人で見つめたい」「そっとしてもらいたい」と思っているときは、善意は悪意に変わる恐れがあるよね。
せっかくの善意が「いらぬ、おせつかい」となってしまう。

2.そっとしておく
人って、誰でも一人でいたいとき、誰にも会いたくないときがあるよね。
「もう、ほっといてくれ!」「一人にさせてくれ!」というとき。
こんなときに親切にされても余計に苦しくなり、それこそ相手を追い詰め傷つける場合もある。
ある意味、一人きり、「孤独」はその人を冷静にさせて、心を落ち着かせる場合がある。でも、それでも世の中では「ほっとけない」「突き放せない」人も多く、それが結果として逆効果となる恐れがある。
世の中、「そっとしておく」ことができない人も多く、せっかく好意で、善意で助言しているのだからと、さらに拍車をかけておせっかいし続ける人もいる。(お世話好きの人たち、ほっておけない人たち)
これは家族間、兄弟、友人関係、職場でも同じだよね
確かに仕事の場合は利害が発生するんだから仕方がないかもしれないけど、それ以外のプライベートな付き合いでも互いが「そっとしておく」ことができないためにトラブルとなる場合が多いと言えるかも。
よくいう、「そっとしておいてあげてください…」という場合だよ。
この「そっとしておく」という考えは「おせっかい」ではなく、相手をおもいやる「気づかい」になるのさ。
とかく、「おせっかい」って、自分の思うとおりにしたいためのおせっかいも多く、「気づかい」と「おせつかい」は一見似ているけど、まったく違うものだということがわかるよね。
相手は真剣に考えているのに「ああすればいい」「こうすればいい」と言いづければ相手にしてみればいい迷惑の何者でもない。
「ああすればいい」「こうすればいい」というのはあくまでも助言の一部あり、押し付けるものではないもんね。
このように「おせっかい」の大半は注意しないと押しつけとなったり、傲慢となったり、自分の知識の方が上で相手を低く見てしまう人に多く、「自分の勝手な正しさの押しつけ」ともいえるかもしれないよね。
だからといって、「おせっかい」「気づかい」は悪いものではないよ。ましてや相手が好意で助言や協力をしてくれているわけですから本来は感謝してあげなければね。
一度助言して、相手がそれ以上望んでいないのなら、二度目、三度目の助言は「押しつけのおせっかい」に変わってしまうからすぐにやめる。
望まれていない場合は「ほっておく」「そっとしておく」だよね。

3.わかって欲しい人々
私たちのまわりには「わかって欲しい人々」がたくさんいるよね。
でもね、私たち自身も「わかって欲しい人々」の一人なんだよ。
ツィッターやフェイスブックなどのSNS投稿などはその最たるもので、「一億人総わかって欲しい人々」のように思える。
私のことを知ってほしい、
あなたのことを知りたい、
あなたと出会いたい。
SNSを通して分かり合う人々との出会いを待つ。
メールやラインなども同じ、人と繋がっていることで安心をする。また、すぐに返信が来なければ見捨てられたかのように不安に陥る、わかって欲しい人々となる。
勝手なもので「いつでも、どこでも、いつまでも自分のことを見ていてほしい…」という現われのような気がするのはcoucouさんだけなのかな?
でもね、それって、すべて幻想で、SNS上、現実の人間関係においても「自分のことをわかってくれる人など、どこにもいないんだよ!」こんなことを言うと反論もあるだろうけれど、つまり、そのような人は存在していない、と思うことも必要だと思うんだ。
これはね、家族も、兄弟姉妹、友人、職場でも同じ、「100パーセント自分を理解する者は存在しない」。
どう、あなたは100パーセント自分を理解してくれている人はいる?
そう、もちろん、いないよね。
それだけ人間の心(精神)は複雑怪奇なもので、自分が自分のことすら理解できないのに相手を理解できるなど不可能に近いということがわかる気がする。
でも、せめて半分、50パーセントや30パーセント、20パーセント、10パーセントの理解はあり得えるよね。
また、すべてのSNS上の繋がりや現在の人間関係には当てはまらないかもしれないけれ、中には心底信頼できる相手、両親や、妻や夫、兄弟や友人(親友)などはいるはずさ。
つまり3人から5人いてくれれば、
それだけで贅沢な幸せなことかもしれないよ。
遠くのSNSの友人よりも身近に理解する人がいれば、それだけで人生は好転するはず。つまり、それが幸せだといえると思う。
身近にそのような人がいない人は、とても不幸かもしない。
人間の幸福、不幸のすべては人間関係から起こるものだから、信じれる、信じられる人が傍にいないというのはとても不幸なことかもしれませんね。

4.家族だからわかって欲しい
「親しきなかにも礼儀あり」という言葉がある。
実は、親しければ親しいほど、この「礼儀」というものが忘れられてしまう恐れがあるんだ。
そんなことはない、家族というものは長い間の歴史があり、互いは理解しやすい関係で、当たり前だ。それに礼儀など必要はない、という人もいる。
でもね、家族というのは互いが依存しあう関係があり、別な言い方をすれば「甘え合う関係」、良い言葉で言えば「許し合う関係」なのだけど、現実は甘え合うことによって、甘やかされることによってこの「親しきなかにも礼儀を見失いやすい」関係になりやすく、家族でなくて夫婦や兄弟姉妹、友人なども同じ「甘え合う関係」になってしまう恐れがあるものなんだよね。だから余計に注意が必要な気がする。
もし、本当に「親しきなかにも礼儀あり」ならば「許し合える関係」になっているはずなのだけど、甘えは許す関係にはならなくなってしまう。
甘えているから許せなくなるんだ。
甘えているから相手のせいになるんだ。
甘えているから「礼儀」を失うんだ。
この「礼儀」を保てる人たちには「信頼関係」があり、それが「許し合う関係」となるはず。つまり、「わかって欲しい」という一方的な関係にはならない距離が保てるからなのさ。
「親しきなかにも礼儀あり」の人間関係は、ここに、
人生を好転させる秘密がありそうですね。

coucouさんです~
みなさん~
ごきげんよう~
coucouさんはね、一時期、俳句の句会に参加していた。
この句会の面白さはね、毎月1回か2回、市の施設をお借りして約90分ぐらいで俳句をその日のテーマに沿って書く会なんだ。
どうして、みんなその会に集まるのかというとね。
仕事場ではできないし、自宅でもなかなか集中できないために、ある意味、自分をその環境(教室)に放り込んでなかば追い詰められながら楽しむという会だった。
coucouさんは、いつも頭を抱えていた。
その理由はね、coucouさんはモノを描いたり、書いたり、まとめたりすると時は一人作業。大勢で創作するという経験がない。
会場はシーンとしており、紙の音やペンの音、そしてみんなの呼吸しか聞こえない静けさだった。そうなんだ、みんな真剣勝負。そして最後にそれぞれが自分の句の発表を行う。
coucouさんはね、ここでも劣等生~
でも、面白い~
俳句はね、にっぽんの歌だよね。
その昔、まだ文字が存在しなかった時代、人々は国や一族の歴史を「歌」にのせて次の世代へ伝えていた。膨大な情報を、リズムと調べを使って記憶しやすくしたこの「歌」が、俳句や短歌のもとになる「和歌」のはじまりだという。
そう、ラップのようなリズム感がある。
5・7・5…と繰り返す音のリズムを使って、その世界を表現して、人の心を掴む。当時は、現代の歌だったのだと思う。そこに、「季語」という季節を表す言葉を加えることで情感や季節感とともに「俳句」が生まれた。
たとえば、「銀杏(いちょう)」という言葉を目にすると、思い浮かぶのは、秋のギンナンや風に揺れて道端に美しく、舞う黄葉を思い浮かべる。
黄色は幸せの色というイメージもある。
また、ギンナンの可愛らしさに赤ちゃんを思い浮かべるかもしれない。
いちょうの葉のハート形が、ある人を思い浮かべるかもしれない。
そう、人によっては様々でいい~
そう、自由でいいのだからね。
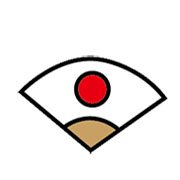
さて、いつも応援し続けてくれている、
coucouさんの大好きな、大好きな「ノートに神さま」
65番目(順不同)のかみさまのご紹介~
その人は、Kusabue〜現代俳句〜さん。
現在のcoucouさんとは対極の人、coucouさんは長文。
Kusabueさんは、5・7・5のリズムの短文。
でもね、その短文は5,000文字近い凝縮された文のような気がする。
coucouさんの想像や妄想力が広がる。
素敵な、素晴らしい日々の句。
言葉のかみさまのKusabueさんの作品をぜひ見てほしい~
Kusabueさんのワールドを~

Kusabue〜現代俳句〜さんの言葉より
俳句をつくっています/現代俳句協会会員/主に作品を投稿しています/今年もどうぞよろしくお願いいたします
三鬼は後年
「俳句で人生をムダにした」
というような意味のことを
言ったそうですが
俳句の世界に大きな功績を
のこした俳人です
驚きはジャブ、感動はストレート
そのワンツーパンチで、読者の方々のハートをノックアウトするといったことになるのかもしれません。
俳句の伝統がこの先もつづいていくとすれば、それは現在と何も変わらないということではなく、絶え間ない試行錯誤と、大小の革新の数々の積みかさねに拠るのかもしれません。
現代語を基本にした、現代俳句集です。
現代語・新仮名・現代的切れ字を基本にして詠んだ句を集めました。
お時間があるときにご覧になってみてください。

The Grassroots - Let’s Live For Today
coucouさんのおすすめマガジン①|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/mdf0316a88e8e
coucoさんのおすすめマガジン②|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/m295e66646c4c
coucoさんのおすすめマガジン③|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/mf98f9bd1801c
coucouさんのおすすめマガジン④|coucou@note作家|notehttps://note.com/note_yes/m/mf79926ee9bb1
https://www.theyesproject.biz/https://www.theyesproject.biz/
Production / copyright©NPО japan copyright coucou associationphotograph©NPО japan copyright association Hiroaki
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
