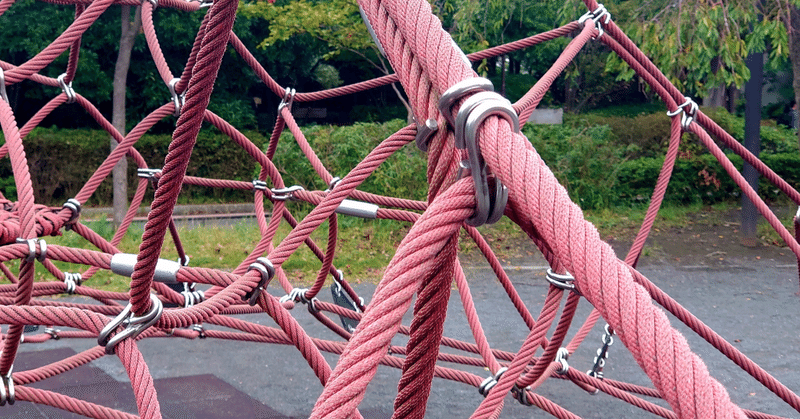
これまでの記事で書き落としたことのまとめ,2022年8月21日
https://note.com/meta13c/n/n7575b6c0826b
この記事の注意点などを記しました。
ご指摘があれば、
@hg1543io5
のツイッターのアカウントでも、よろしくお願いします。
https://twitter.com/search?lang=ja&q=hg1543io5
注意
これらの重要な情報を明かします。
特撮テレビドラマ
『ウルトラセブン』
『ウルトラマンティガ』
『ウルトラマンギンガ』
『ウルトラマンタイガ』
『ウルトラマントリガー』
映画
『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』
『劇場版 ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス』
小説
『ウルトラマンデュアル』
『二重螺旋の悪魔』
『心臓狩り』
『狂気の山脈にて』
『高度な文明』(星新一)
漫画
『ドラゴンボール』
『ドラゴンボール超』
『NARUTO』
『ULTRAMAN』
『SKET DANCE』
『左ききのエレン』
『ウルトラマン STORY 0』
テレビアニメ
『ドラゴンボール超』
『ドラゴンボールZ』
『ドラゴンボールGT』
『ドラゴンボール』
『NARUTO 』
『NARUTO 疾風伝』
アニメ映画
『ドラゴンボール超 ブロリー』
テレビドラマ
『相棒』
『下町ロケット』(TBS,第1期,第2期)
『下町ロケット ヤタガラス 特別編』
『ドクターX』
『A LIFE』
実写映画
『ターミネーター4』
はじめに
私がこれまで記したnoteの記事で、足りなかったところ、あとで気付いたところを、ここにまとめます。
節操のない書き方ですが、このように繋がるのが私の視点の特徴のようです。
強いところと弱いところの議論
私は以前から、「強い人」、「強い集団」などの区分や定義に、何とも言えない違和感がありました。
弱者と強者として扱っていた存在が、それぞれ逆のように見えるときもみられ、といってそのように逆転しているだけでは話の進まない感覚もあります。
そこで、人や集団を「強いところ」、「弱いところ」、それらが組み合わさる「こと」で説明出来ないか、と考えました。これは仏教なども踏まえています。
2022年8月21日閲覧
日本とアメリカの「弱者」
まず、日本よりアメリカの格差が激しいことです。
池上彰さんの書籍でしばしば言われますが、アメリカは「自己責任」の要素が強く、保険や教育に消極的で、『知らないと恥をかく世界の大問題 4』では、「国民皆保険がないのは、アメリカ以外ではソマリアとイエメンぐらい」という風刺画も紹介されています。キリスト教を信じるあまりに、進化論を教えさせないために子供を学校に行かせない家庭もあるそうです。
また、本川達雄さんの『ゾウの時間 ネズミの時間』では動物のサイズから様々な観点の考察がありますが、「小さな島では中サイズの動物が多く、大きな島では小さなサイズ、大きなサイズの動物も幅広くいる」という「島の規則」を、経済に適用しています。本川さんが訪ねたアメリカの大学には、きわめて優秀な人間が集中していたのですが、そこから少し離れると要領の悪い店員のいる店が多い、という説明で、大陸では経済格差が激しく優秀さにばらつきが多いということなのでしょう。
『ドクターX』では、フリーの外科医の大門が周りの医師と馴染まずに、優秀さで周りを苛立たせるところが多いのですが、「優秀な医師は1割しかいない。医者が助けるべきは患者であり、駄目な医者を助けている場合ではない」と主張し、「みんながあなたみたいになれるわけではない」と言われると「何で?」の一言で済ませています。
2022年8月21日閲覧
2022年8月21日閲覧
https://twitter.com/hg1543io5/status/1550425684283367424?s=21&t=cMQ7L-_--8tKU7IJcbsZpA
2022年8月21日閲覧
大門の主張は『左ききのエレン』少年ジャンププラス版で表現された「替えのきかない有能」のものであり、そのときの「替えのきく無能を自分と同じレベルにまで引き上げてくれる替えのきく有能こそ会社員に必要だ」というのが、おそらく大門に合わない日本流の経営、「分かりやすい指導」なのでしょう。
一方アメリカは大門に合った、優秀な人間はさらに優秀に、そうでない人間は能力の低いまま、という格差が激しくなり、それを「分かりにくい指導に追いつけない方が怠惰なだけ」で済ませることが多いのでしょう。
大門は「研究」に近い個人の能力による医療にこだわり、「教育」の視点が少ないのです。
前置きが長くなりましたが、つまりアメリカの国民は「大国の強い集団」ではなく、「強いところと弱いところが極端な集団」なのだと分類しました。
日本の中小企業の技術が高く評価される『下町ロケット』などは、日本に「そこそこ優秀な人間」が中小企業も含めて多い、その代わりにトップがアメリカには劣りやすい、まだアメリカより格差の少ない日本人の技術や経済の特徴を示していると推測します。
その意味で、アメリカの政府や経営者は「自分達の中の弱者の方が日本などの弱者よりも苦しんでいる」とみなして、アメリカの貧しい労働者などを、「守るべき弱者」とみなす視点が、日本などと噛み合わないのかもしれません。
絶対的貧困と相対的貧困と「ところ」
資本主義を肯定する木村貴さんは、「資本主義によって世界の絶対的貧困は減っている」と主張していますが、日本などは相対的貧困が増えているようです。
萱野稔人さんは、「今日本のリベラル派が問題視している、グローバル化による格差は、グローバル化により貧しい国と日本の格差は縮んでいるため、実のところ国内の格差であり、リベラル派もナショナリズムに基づいた主張をしている。だからといって格差を放置して良いわけではないが」と主張しています。
つまり、世界の絶対的貧困の解決は、貧しい国の「強いところ」である経済的に優秀な人間が、日本の「弱いところ」である経済的に劣る人間に「追いついている」ために、外国の労働者が日本に進出して豊かになっている意味で「平等」であり、それにより日本国民同士の格差による相対的貧困は広がって「不平等」になっているのかもしれません。
日本国民の大半は、世界的に見ればはるかに恵まれた賃金などを受け取りながら、国内の格差や物価などの相対的な基準に苦しむ「上の下」の生活をするからこそ苦しいのかもしれません。
ただ、『キミのお金はどこに消えるのか』の「経済の常識」を踏まえますと、日本人の貧困の原因を海外との差異だけでは説明出来なさそうですが。
「食の砂漠」などの「上の下」の苦しみ
たとえば、『食糧の帝国』では経済と環境について、アメリカなどでは貧しい人間ほど生活の時間や技術の余裕がなくなりジャンクフードなどで肥満になる「食の砂漠」という現象が問題視されています。
『リベラルとは何か』によれば、かつては貧困すら貧しい人の責任で社会問題として扱われなかったとされます。「食の砂漠」は、一見文明に依存した「ぜいたく」に見える「貧しさ」であり、今後はそういった、「文明や経済による上の集団の内の下」故の苦しさを「自己責任」で放置せず、「強いところ」と「弱いところ」で説明すべきかもしれません。
日本も、スマートフォンという30年前ならば著しく高性能なコンピューターを持ちながら、30年前の平均より苦しい暮らしをする人間はいるでしょう。「その機械を売ればどうか」のような論理は成立しません。
『A LIFE』での病院の副院長は、父親の代からの医師である以上は様々な意味で恵まれた「強者」だったかもしれませんが、小学生のときから「医者は100点を取らなければ0点と同じ」と父親に言われた苦しみや、自分より成績の悪い同級生が褒められていることへの嫉妬を持ち、それは日本国民の大半のような「上の下」かもしれません。
「上の下」の経済的な苦しみは、「強いところ」、「弱いところ」で区切った方が分かりやすいと私は推測します。
「自分の利益を全て捨てることは出来ない」
2022年8月21日閲覧
私は「相手に利益だけを与えることは出来ない定理」を踏まえて、利益はどこに発生するか分からないので、自分の利益を全て捨てることは出来ないとも考えています。
人助けのときに、『SKET DANCE』の主人公が死んだ父親に言ったように、「達成感などの利益目的だろう」などのように言われるのは、利益を100パーセント捨てることが、「身が持たない」、「感情に限界がある」以前に、原理的に出来ないためでしょう。つまり、相手への行動にも「相手が得をして自分が損をするところ」に「相手が損をするところ」、「自分が得をするところ」が伴い、完全には切り離せないのでしょう。
https://twitter.com/hg1543io5/status/1463136093293867018?s=21&t=cMQ7L-_--8tKU7IJcbsZpA
2022年8月21日閲覧
『相棒』シーズン10「アンテナ」で、杉下右京は引きこもりの青年に「人は100パーセント誰かのことだけ考えることは出来ません。必ず主観が入ります。それはあなたを裏切ったことにはならないんですよ」と話しています。もちろん杉下自身はどうなのか、杉下は犯罪者などの「100パーセント誰かのことだけ考えることは出来ない」限界を認めているのか、といった疑問もありますが。
「ところ」の混乱による、「下からのパターナリズム」
2022年8月21日閲覧
人は強いところと弱いところを持つというのを、私は仏教を踏まえて考えています。これにより、「下からのパターナリズム」と言うべき概念の説明も出来ると推測します。
パターナリズムは「強い立場の人間が弱い立場の人間の幸福を勝手に決めること」ともされますが、「強さ」の定義が、社会的な議論より実際には曖昧だと私はみなしています。
『A LIFE』では強者か弱者か割り切りにくい対立の部分がありました。
特に特撮や少年漫画では、一見「弱い社会的立場」の主人公の方が、戦闘能力や知識では上司や権力者を上回る「ところ」もあり、部下である主人公がパターナルに人助けをすることもあります。
女性向けの作品でも、弱い立場の主人公が、立場とは異なる知識や能力を独占して、独断で人助けをするパターナリズムはあるかもしれません。
物語における、人間以外による環境破壊
2022年8月21日閲覧
私は、「人間の環境破壊を批判する宇宙人も環境を破壊しないのか」と疑ったことはあります。
特撮などの宇宙人も、発達した科学技術で地球に来られる「強さ」があるからこそ物語が展開されるものの、見方を変えればそれ以外は人間と同じでも構わない多様性があり、むしろそれにより個人の能力が劣化している「弱さ」を抱えているからこそ、設備に依存したり、環境を破壊したりするねじれた部分もあるかもしれません。
『ウルトラマンデュアル』のウルトラマン及びヴェンダリスタ星人、『ULTRAMAN』(月刊ヒーローズ)のヤプール、『高度な文明』(星新一)などがあります。
特にヴェンダリスタ星人の中には、高い技術で圧迫しつつ、地球の限られた環境で苛立ち、ストレスを周りの人間にぶつける個体がおり、彼らは技術などの分野で「上の下」かもしれません。
サンゴとスカイドンの「動かざる動物の捕食」
2022年8月21日閲覧
サンゴは通常の環境の視点では弱者の生物なのが、周りには欠けている、特殊な栄養の摂取を行えるために、周りと競争しない水の澄んだ、栄養の乏しい場所を独占して、かえって炭酸カルシウムの殻で他の生物を助けて生態系に貢献していると記しました。
これも、「弱いところ」と「強いところ」が重要です。
2022年8月21日閲覧
人間とハチが、ウルトラシリーズで武器を生まれつき持つ宇宙人と人間が互いに争うのも、「強いところ」と「弱いところ」がばらばらで相殺出来ず、どちらが強者か割り切れず、「出来るところ」と「出来ないところ」が表裏一体とも言えます。
サンゴに話を戻しますと、サンゴに近代文明は「通常の強さ」を求める善意や善悪観を押し付けて、サンゴが海水温変化に弱いなどの弱さを尊重しないために、「強い」生物まで間接的に生態系ごと減らしてしまう危険があるのではないか、とも記しました。
これを連想させるのは、漫画『ウルトラマン STORY 0』のウルトラマン達です。
彼らは自分達が生き残るための人工太陽をバルタンが細工して、宇宙の生物を怪獣に変えたのに憤り、怪獣やバルタンと戦います。
しかし、怪獣の「異様さ」を批判したり憐れんだりするのが、人型生物の主観になっているところがあります。
たとえば、オリジナルキャラクターのゴライアンは、自分を待ち伏せして捕食しようとした怪獣(おそらくスカイドン)を「ふざけるな!口を開けて餌を待つなんざ、ムシが良すぎるんだよ!」と倒しました。
自分を狙う目的でなく、その手段も卑怯だという怒りがあったようです。
似たような怒りは、『NARUTO 疾風伝』「イタチ真伝」のイタチが大蛇丸に向けています。
しかし、それは言わば、「働かざる者、食うべからず」という人間社会の規範を、動物に適用した主観的で強引なものがあります。
おそらく彼は、「動かざる動物、食うべからず」と考えたのでしょう。
動物の定義は「多細胞で、自力で有機物を合成出来ないので他の生物から得る生物」だとされます。どのような動物でも、「食べる」ことはするはずです。
しかし、「動かない動物」は、先述したサンゴ、別名「サンゴ虫」がいます。この動物は海水に乗って来る有機物の粒子を「食べ放題」なので、動く必要がなく、植物のように幾何学的にユニットを繋ぐ構造で、そもそも海底に固定されて動けない時期があります。
サンゴは弱者か強者か曖昧ですが、強いところと弱いところがあり、「動かなくても食べられる強さ」は「動けない弱さ」、「それでも食べなければ生きていけない弱さ」でもあり、それに似ている怪獣を、前者だけから「ムシの良い」と捉えるのは、人間の主観を押し付けるところがあります。
ベムスターと『心臓狩り』
また、ゾフィーはバルタンによって生み出されたベムスターらしき怪獣が、惑星ごと捕食する大きさになり、さらにヒトデのような五角形の口が原典にあったところに、さらに手足も含めて頭部になった、5つの頭の体型になったのを、「自然物では絶対に有り得ない異形...ここまで命をもてあそぶなんて」と言っています。
しかし、実のところ、ヒトデも似たような生態があります。ヒトデやウニなどの棘皮動物も5つの部分に分かれ、その中に神経や生殖巣が均等に配置され、特定の頭はありません。ベムスターらしき怪獣は、その神経が発達して鳥類のような頭部に変化したとすれば、「異形」ではあっても、「自然物では絶対に有り得ない」とも言い切れません。棘皮動物の幼生は実のところ脊椎動物に近い左右対称の体型で、むしろそれがホヤなどの脊索動物、そしてサカナなどの脊椎動物の起源という説もあります。
その意味で、ヒトデのようなベムスターが5つの頭を持つのは、不自然だと言い切れず、そうみなしたゾフィーにも「人型生物の主観」があります。
ちなみに、『心臓狩り』では、ヒトとある棘皮動物の遺伝子が近いことを、この系統を踏まえたのか曖昧な表現の「謎」として扱い、ヒトの体に棘皮動物のある能力が隠れていたという設定で、一部の人間が異形になりましたが、それは棘皮動物への、ベムスターらしき怪獣のような「先祖返り」だったかもしれません。
クトゥルフ神話『狂気の山脈にて』にもヒトデ状の知的生物がいますが、人間の主観を超えてはいても異なる常識を持つ生物に過ぎないように描写されています。
「お前が言うな」と「差別」の問題
2022年8月21日閲覧
2022年8月21日閲覧
「お前が言うな」という台詞はしばしばありますが、たとえば「差別されそうなお前が何故似た特徴で差別するのか」というのもあります。
『ウルトラマントリガー』でメトロン星人であり人間の味方のマルゥルは、「笑顔」を重視する「人間」のマナカケンゴに「可愛い」と言われていますが、かなり人間から離れた容姿です。
そして、マルゥルよりは人間に近い容姿だった「闇の巨人」カルミラが変異して貝類やタコと融合したようなメガロゾーアに、マルゥルは嫌悪感を示しました。しかし、外見で差別されてもおかしくないマルゥルがそのように示すのは、果たして矛盾なのか、と言われますと難しいところがあります。
ちなみに、分かりにくいのですが、マルゥルの後頭部にも、タコの吸盤のような部分があります。
『トリガー』に関連した『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』では、主人公のダイゴが闇の巨人「ティガダーク」になりましたが、ダイゴの精神により味方のままでした。
それでものちの『ウルトラマンギンガ』で突然ティガダークが現れたときに、警戒されています。
『ウルトラマンタイガ』で、かつて『ウルトラセブン』で悪役だったゴース星人を主人公達は「差別するな」とかばいましたが、劇場版で闇のウルトラマンであるベリアルの「気配」を持つ「味方」のウルトラマンジードは警戒しました。
どこまでが「差別」なのか、線引きが複雑になります。
『NARUTO 疾風伝』で、アロエや食虫植物と人間が融合して緑と白と黒のピエロになったような白ゼツと黒ゼツがいました。彼は、蛇と融合したような状態の人間の大蛇丸が口から武器を出すのを見て、「ゲロゲロ気持ち悪い」と言っており、一見自分を棚に上げているかのようです。
特撮に比べて不道徳な言動を主人公もしやすい少年漫画として、主人公のナルトもゼツを「アロエ野郎」と言っています。
しかし、黒ゼツの正体は作品世界の根幹に関わる、動物と植物の両方の形態を持つ「十尾」=「神樹」=カグヤの息子であり、白ゼツはそこから生み出された兵士でした。ゼツにしてみれば、動物と植物の曖昧な姿こそ当たり前なのであり、動物の状態しかない「通常」の人間も、蛇と融合したような大蛇丸も、自分の半身や体の一部だけが動き回るような「気持ち悪い」姿なのかもしれません。
『トリガー』と『NARUTO 疾風伝』は植物に関して似たような気配もあります。
植物と動物のフラクタルと美感覚
植物と動物の形態の差異の原因として、食べる食べないよりも、動くか動かないかが重要です。
動くためには細胞の一部を分業させて機能を偏らせなければならず、そのためには一部の損傷を全体に警告する神経なども必要なため、損失を防ぐ痛みや非対称的な形態が必要です。
一方動かない植物の場合は、細胞があまり分業せず、一部が全体と同じ役割をしやすく、損失はあまり問題ではなく、むしろその一部を切り離してフローとして利用させやすく、対称的、幾何学的な形態として活動するようになります。
一部が全体と同じ形状の図形を「フラクタル図形」と呼び、植物はそれが重要です。
『二重螺旋の悪魔』には、フラクタルな「粒子と波動の生命体」の影響を受けた人間の主人公が、人間の姿を醜悪に捉え始めました。それは仏教の曼荼羅や、ダンテの『神曲』の神や天使のイメージとも比較されています。キリスト教と本来同じ神を信じるイスラムのアラベスクとも関係があるかもしれません。
そのフラクタルな「生命体」は、皮肉にも、戦うために醜悪な姿になっていますが。
『ドラゴンボール』とグノーシス主義の「下位の神」
2022年8月21日閲覧
2022年8月21日閲覧
『ドラゴンボール』とグノーシス主義について幾つか記しましたが、もう1つ気になったのは、「劇中で登場人物に接触する神は、神々の中で評価の低いことが多い」という繰り返しです。
グノーシス主義では、至高の世界の神々のうち最下層の女神のソフィアが産み落とした無知な神が物質の「この世界」を作り出したとされます。
これに似たものを、『ドラゴンボール』シリーズには感じます。
最初に登場した神である「地球の神」は、元々就任するために「悪の心」を切り離したものの、それが暴走してピッコロ大魔王として災いを起こしました。前任者にない能力で善意で地球人に与えたドラゴンボールも「ろくでもない使い方」をされています。
そのためか、少し機嫌を損ねただけで、上位の神である閻魔大王に「お前が死んだら地獄行きにしようかな」と言われています。元々神として評価が低い可能性があります。
また、閻魔大王より上の界王の中で、地球を担当する北の界王は、元々あの世で例外的な生きたまま暮らしていたのが、自分を超えるほど強過ぎる敵のセルの自爆から地球一つを守るために、孫悟空の瞬間移動によって巻き込まれて命を落とし、悟空だけのちに生き返っています。
また、アニメオリジナルでは、他の界王に死んだことを揶揄されているようです。
また、さらに上の界王神の中で、魔人ブウから生き残った東の界王神(シン)は、自分が界王神としてもっとも若く非力だったと認めています。
彼を無知だと批判する先祖の「15代前の界王神」も、その独自の能力は魔法使いと事故で合体して戻れなくなったためで、本当に単独の界王神として優秀なのか、と疑わしいところもあります。
『ドラゴンボール超』で界王神と対をなす破壊神のうち、悟空達の第7宇宙を担当するビルスも、その宇宙の人間のレベルが2番目に低いことから、強くても職務としての評価は低いようです。付き人である天使に呆れられるところもあります。
さらに、それ以上の存在のいないらしい全王も、タイムトラベルによって生じた並行世界ごとに複数存在しています。劇中に登場した本編世界の全王は、自分のいる並行世界のうちにレベルの低い宇宙を消したあと、唯一免れた第7宇宙の17号が約束の願いで復元しました。そのため、第7宇宙のレベルは上がったらしいですが、本編世界の宇宙全体のレベルは低いままになってしまったかもしれず、他の並行世界に比べて低いかもしれません。
また、「未来トランクス」の世界の全王も、部下の神々の争いを放置した結果として並行世界ごと消さざるを得なくなり、それによりどこにも行けず孤独だったのを悟空に助けられて本編世界に来ています。
破壊神のレベルも測られるならば、全王も「レベルの低い宇宙を消す」しか出来ず、実は天使にレベルが低いとみなされ、特に本編世界と「未来トランクス」の世界の全王は低いかもしれません。
なお、神として特殊ですが、ドラゴンボールから現れる神龍(シェンロン)は、少なくともナメック星と地球にいますが、地球のシェンロンは『ドラゴンボールGT』で「使い過ぎ」で暴走しました。劇中のシェンロンの中で、地球のシェンロンはレベルが低いと言えるかもしれません。
「地球の神」、北の界王、東の界王神、シェンロン、破壊神ビルス、本編世界の全王など、劇中の神々は、グノーシス主義のソフィアのように、評価やレベルの低い可能性のある存在ばかり登場し、だからこそ物語が盛り上がるのかもしれません。『ドラゴンボール』シリーズには、評価が「上の下」の神が多いかもしれません。
数学や物理は「神の一部」でしかないのではないか
2022年8月21日閲覧
チャペックの『絶対製造工場』では、いわゆる相対性理論の「E=mc^2」に基づいているらしい、物質を消滅させてエネルギーを最大限引き出す発明をした学者が、それを友人の工場経営者に売り込んでいましたが、経営者はその物理的な概念にあまり興味を示しませんでした。
その発明は物質からエネルギーだけでなく、宗教的に奇妙な影響を人間に及ぼす「絶対」も発生させ、それが社会を狂わせていきます。
そしてこの小説に、「みなが無限の神の有限の一部しか分からないからこそ、自分と同じ神の異なる一部を分かる人間が憎いのではないか」という推測がありました。これも、「ところ」の問題かもしれません。
序盤の開発者にとっては、「エネルギー効率」こそ「絶対の神」だったのではないか、と私は推測しました。物質から最大限のエネルギーを引き出せれば、工業は最大限の進歩を出来ると安易に数学的に推測し、それが彼にとって大事な意見だったのでしょう。
経営者は、「絶対」が勝手に製造を始めてかえって物流を狂わせて品切れにさせるなどを見て、「あの絶対は確かに偉大だが、人間の産業の仕組みを分かっていない」という趣旨の推測をしています。
産業は1つの数学だけでは動かないのであり、その数学を「神の一部」のように重視する人間にとってそれは耐えがたいかもしれません。
フリーザとサイヤ人の環境破壊
2022年8月21日閲覧
2022年8月21日閲覧
私は人間と他の生物の差異、環境破壊の原因として、「羊の肉など、資源の回復しない部分であるストックの消費をすれば環境を破壊する可能性は他の生物にもあるが、ほとんどの生物はそれで自滅するから直ぐに終わる。人間だけは他のストックの場所に移動するので、環境破壊を続けられる」と推測しています。
これで連想したのは、『ドラゴンボール超』のフリーザとサイヤ人です。
どちらも侵略を行う宇宙人でしたが、サイヤ人は元々あまり技術が発達せず、大猿に変身すれば我を失い周りを際限なく攻撃してしまう性質があり、それが分かっているからこそあまり変身しなかったらしい様子が、『超 ブロリー』にあります。
大猿になれば、惑星や衛星を破壊するほどのエネルギー波をさらに拡大して使えるのですが、宇宙空間に耐えられず、大猿の状態では宇宙船に乗りにくいので、自滅を恐れて大規模な破壊は出来なかったようです。
しかし、フリーザ軍に入ってからはさらなる破壊をしたと漫画版でベジータは推測しており、それは、軍の技術で宇宙空間を移動しやすくなったためかもしれません。
フリーザがいたからこそサイヤ人は、破壊する能力による自滅を避けて、環境を破壊「出来るようになった」と私は推測しました。
そして、フリーザの宇宙空間に耐える体質とサイヤ人の強さ、そしてナメック星人の再生能力を持つセルだからこそ、際限のない環境破壊が可能になったと私はみなしています。
フリーザとキリエル人の共通点
私は『ウルトラマンティガ』と『ウルトラマンダイナ』を『ドラゴンボールZ』と『ドラゴンボールGT』に比較させて考えたことがあります。
『DBZ』のフリーザとサイヤ人はキリエル人とウルトラマンに比較して考えたのですが、『DBGT』のフリーザは、キリエロイドと同じく氷漬けにされて砕かれました。また、このときのフリーザは既に死んであの世で活動していましたが、キリエル人に仕える人間も「既に死んでいた」ようです。
『ターミネーター』の英語と『二重螺旋の悪魔』の方言
2022年8月21日閲覧
『ターミネーター4』で、機械の反乱による核戦争で、人間をまとめ上げるジョン・コナーは「これを聞いている君は抵抗軍の一員だ」と呼びかけています。
しかし、彼の英語が通じさえすれば誰でも入れる多様性と、通じなければ優秀で真面目でも弾かれる単一性があります。これを私は英語ナショナリズムだと推測しました。
『ターミネーター』シリーズに似た、科学技術の暴走による戦争を描く1993年の『二重螺旋の悪魔』では、日本が核兵器で壊滅した東京の代わりに大阪に首都を移転しています。その軍人の間で、書き言葉と話し言葉の曖昧になる「音声認識ワープロ」により、「俺の報告書に大阪弁を入れるな!」、「悔しかったら東京、取り返してみい!」という会話がありました。
技術が発達しても、かえってそれにより残る言語の壁が、新しい対立を起こすのです。
『ターミネーター4』の世界でも、イギリス英語とアメリカ英語でそのような対立が起きているかもしれません。「何故、抵抗軍のアメリカ英語に、イギリス英語を使って来た我々が合わせなければならないのだ」と。かえってアメリカ英語を使う人間とイギリス英語を使う人間が分断され、国籍を超えて「アメリカ英語を話す集団」と「イギリス英語を話す集団」は統一されやすくなるかもしれません。
まとめ
幾つかの記事の補足を雑多にまとめたつもりが、予想外にあちこちで繋がったかもしれません。
参考にした物語
野長瀬三摩地ほか(監督),上原正三ほか(脚本),1967 -1968(放映期間),『ウルトラセブン』,TBS系列(放映局)
村石宏實ほか(監督),長谷川圭一(脚本),1996 -1997,『ウルトラマンティガ』,TBS系列(放映局)
アベユーイチほか(監督),長谷川圭一ほか(脚本),2013 (放映期間),『ウルトラマンギンガ』,テレビ東京系列(放映局)
市野龍一ほか(監督),林壮太郎ほか(脚本),2019,『ウルトラマンタイガ』,テレビ東京系列(放映局)
坂本浩一ほか(監督),ハヤシナオキほか(脚本),2021-2022,『ウルトラマントリガー』,テレビ東京系列(放映局)
映画
村石宏實(監督),長谷川圭一(脚本),2000,『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』,ソニー・ピクチャーズエンタテイメント(配給)
市野龍一(監督),林壮太郎(脚本),2020,『劇場版 ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス』,松竹
小説
三島浩司,2016,『ウルトラマンデュアル』,ハヤカワ書房
梅原克文,1998,『二重螺旋の悪魔(上)』,角川ホラー文庫
梅原克文,1998,『二重螺旋の悪魔(下)』,角川ホラー文庫
梅原克文,1993,『二重螺旋の悪魔 上』,朝日ソノラマ
梅原克文,1993,『二重螺旋の悪魔 下』,朝日ソノラマ
梅原克文,2011,『心臓狩り』,角川ホラー文庫
H・P・ラヴクラフト(作),大瀧啓裕(訳),1985,『ラヴクラフト全集4』,東京創元社(『狂気の山脈にて』)
星新一/作,和田誠/絵,2003,『ピーターパンの島』,理論社(『高度な文明』)
漫画
鳥山明,1985-1995(発行期間),『ドラゴンボール』,集英社(出版社)
鳥山明(原作),とよたろう(作画),2016-(発行期間,未完),『ドラゴンボール超』,集英社(出版社)
岸本斉史,1999-2015,『NARUTO』,集英社(出版社)
清水栄一×下口智裕,2012-(発行期間,未完),『ULTRAMAN』,ヒーローズ(出版社)
篠原健太,2007-2013,『SKET DANCE』,集英社
かっぴー(原作),nifuni(漫画),2017-(未完),『左ききのエレン』,集英社
真船一雄(著),円谷プロダクション(監修),2005-2013,『ウルトラマン STORY 0』,講談社
テレビアニメ
大野勉ほか(作画監督),冨岡淳広ほか(脚本),畑野森生ほか(シリーズディレクター),鳥山明(原作),2015-2018,『ドラゴンボール超』,フジテレビ系列(放映局)
清水賢治(フジテレビプロデューサー),松井亜弥ほか(脚本),西尾大介(シリーズディレクター),小山高生(シリーズ構成),鳥山明(原作),1989-1996,『ドラゴンボールZ』,フジテレビ系列(放映局)
金田耕司ほか(プロデューサー),葛西治(シリーズディレクター),宮原直樹ほか(総作画監督),松井亜弥ほか(脚本),鳥山明(原作),1996 -1997(放映期間),『ドラゴンボールGT』,フジテレビ系列(放映局)
内山正幸ほか(作画監督),上田芳裕ほか(演出),井上敏樹ほか(脚本),西尾大介ほか(シリーズディレクター),1986-1989,『ドラゴンボール』,フジテレビ系列
伊達勇登(監督),大和屋暁ほか(脚本),岸本斉史(原作),2002-2007(放映期間),『NARUTO』,テレビ東京系列(放映局)
伊達勇登ほか(監督),吉田伸ほか(脚本),岸本斉史(原作),2007-2017(放映期間),『NARUTO疾風伝』,テレビ東京系列(放映局)
アニメ映画
長峯達也(監督),鳥山明(原作・脚本),2018年12月14日(公開日),『ドラゴンボール超 ブロリー』,東映(配給)
テレビドラマ
橋本一ほか(監督),真野勝成ほか(脚本),2000年6月3日-(放映期間,未完),『相棒』,テレビ朝日系列(放送)
伊與田英徳ほか(プロデューサー),八津弘幸ほか(脚本),池井戸潤(原作),2015,『下町ロケット』,TBS系列(放映局)
伊與田英徳ほか(プロデューサー),丑尾健太郎(脚本),池井戸潤(原作),2018,『下町ロケット』,TBS系列(放映局)
伊與田英徳ほか(プロデューサー),丑尾健太郎(脚本),池井戸潤(原作),2019,『下町ロケット ヤタガラス 特別編』,TBS系列(放映局)
田村直己ほか(監督),中園ミホほか(脚本),2012-(未完),『ドクターX』,テレビ朝日系列
瀬戸口克陽ほか(プロデュース),平川雄一朗ほか(演出),橋部敦子ほか(脚本),2017,『A LIFE』,TBS系列
実写映画
マックG(監督),ジョン・ブランケットほか(脚本),2009,『ターミネーター4』,ソニー・ピクチャーズエンタテイメント(配給)
参考文献
本川達雄,1992,『ゾウの時間 ネズミの時間』,中公新書
木村貴,2022,『反資本主義が日本を滅ぼす』,コスミック出版
萱野稔人,2011,『ナショナリズムは悪なのか 新・現代思想講義』,NHK出版新書
田中拓道,2020,『リベラルとは何か』,中公新書
エヴァン、D.G.フレイザー(著)アンドリュー・リマス(著),藤井美佐子(訳),『食糧の帝国』,2013,太田出版
浅島誠(編),日本動物学会(監修),2007,『シリーズ21世紀の動物科学 7 神経の多様性:その起源と進化』,培風館
池上彰,2013,『知らないと恥をかく世界の大問題4 日本が対峙する大国の思惑』,角川マガジンズ
中村圭志,2016,『教養としての仏教入門』,幻冬舎新書
デール・S/ライト/著,佐々木閑/監修,関根光宏/訳,杉田真/訳,2021,『エッセンシャル仏教』,みすず書房
中村元,2003,『現代語訳 大乗仏典1』,東京書籍
金岡秀友/校註,2001,『般若心経』,講談社学術文庫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

