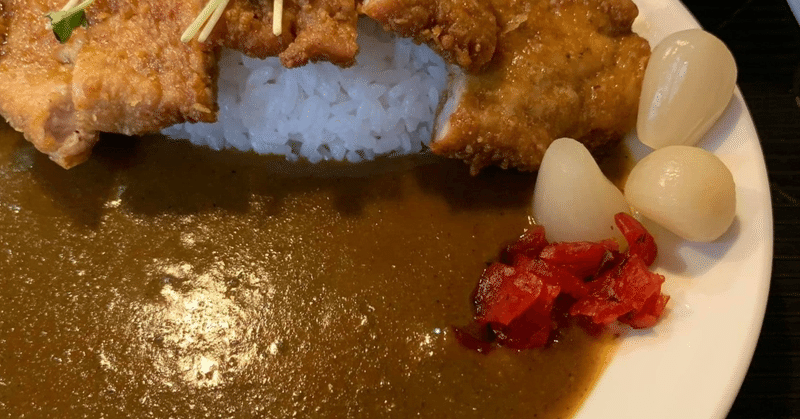#夏目漱石
三島由紀夫から見た夏目漱石の読者
三島由紀夫、安部公房だけではない。これまで見てきたように谷崎潤一郎も漱石の評価は低いし、太宰治に関しては「俗中の俗」と漱石を切り捨てている。三島由紀夫のこの発言も、夏目漱石というすでにこの世にない作家の死してなお消えない過剰な人気に対する反発の表れだ。
しかも芥川龍之介までスタイルは鴎外に近接し、漱石文学から何を継承したのかということさえ曖昧なので困る。
この三島由紀夫と安倍公房の対談は
「ふーん」の近代文学⑪ それにしたってさ
それにしてもこの「三四日等閑にしておいた咎が祟って」というところ、
この「三四日」に一体何が隠れているのかと『明暗』を改めてもう三回ほど読み直してみたけれど、驚くくらい二回目のなぞりがないね。この「三四日」に何が行われていたのかというところはどうも作品の進行する時間からすると過去になる。かなり意味深な書き方なのに、答えが見つからない。
今更非常線に引っかかる様な事でもなさそうだし、小林と
岩波書店・漱石全集注釈を校正する37 どす黒いちゃんちゃんは三週間以内に去る
どす黒くて竹輪の出来損できそこないである
このどす黒い蒲鉾はおそらく「じゃこ天」であろう。蒲鉾のつもりでじゃこ天を食べればそりゃ不味いと思うに違いない。
どういう了見か地方の練り物の東京進出速度は緩やかで、小倉織や薩摩絣は早々に江戸に根付いたものの、当時の東京では蒲鉾と竹輪とはんぺんと真薯くらいしかなく、さつま揚げでさえ書物に現れるのは、明治四十五年、家庭に普及するのは大正期であると考えら
岩波書店・漱石全集注釈を校正する29 蜘蛛手十字に宿世の夢、龕中に馳せかけた冷飯草履
「塔」の見物は一度に限る
何気ない書き出しで、ここに何かしかけられていると気が付く人もあるまいが夏目漱石全集を読み返すと、なにかわざわざそう書いていることが解る。
このさりげなさが漱石の仕掛けだろう。ふりを丁寧に、落ちはさらりと、それが江戸っ子の粋というところか。
蜘蛛手十字
岩波書店『定本 漱石全集第二巻』注解に、
……とある。蜘蛛手とは縦横ではなく蜘蛛の足のように胴体から四方八
サバイバーズ・ギルトのない風景
芥川龍之介が直接的に戦争について書いた作品は『首が落ちた話』と『将軍』のみであると言って良いであろうか。「東西の事」を書いた『手巾』が戦争に関して書いたのではないとしたら、そういう理屈になるのではなかろうか。
しかしこんな残酷な風景はむしろ付け足しである。芥川にとって戦争とは単なるプロットに過ぎない。芥川は『将軍』でも『首が落ちた話』でも戦争を材料にはするが、戦争そのものを云々する意図は見
夏目漱石『明暗』の技巧②会話の妙
谷崎潤一郎という作家は基本的に信用できない人だと思うんですが、それは単に嘘を言うということではないんですね。虚々実々の小説や戯曲を書きまくって、何が現実なのか分らなくさせた人だから信用できないわけです。
最初に谷崎について書いたのが、
この記事ですか。谷崎は『誕生』を書くにあたり『栄花物語』を読んだはず、『栄花物語』の語彙検索で調べてみると「國民」などと云う言葉が使われていようはずもなく
健三は何故健三なのか? あるいは三四郎は三なのか四なのか。
※今回も正式な文章読解ではないところで余談を書きます。
夏目漱石の『道草』という小説が自伝的要素を鏤めた私小説風ミステリー小説であることに異論の余地はあるまい。いや、ミステリー小説とは誰も思っていないかもしれないが、一々仕掛けの多い小説であることだけは確かなのだ。
しかしそうは云っても「健三は何故健三なのか?」と問われても、そもそもどういう種類の問いなのか解らない人が大半ではなかろうか。
『それから』は植物小説なのか?
『それから』が緑と赤の世界が対比される小説であり、植物が多く描かれる小説でもあるという程度の話は今更繰り返すまでもないだろう。しかし案外、何故植物が多く描かれる小説なのかということはこれまで殆ど議論されてこなかったのではなかろうか。(新聞小説なので露骨に書けないところを花で誤魔化しているのではないかという見立てが小森陽一氏にはあるように思われる。後は江藤淳が山百合にアレゴリーを見出しているぐらい
もっとみる