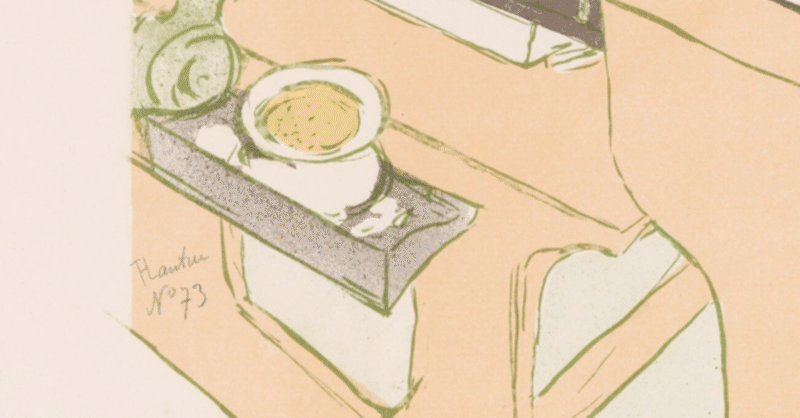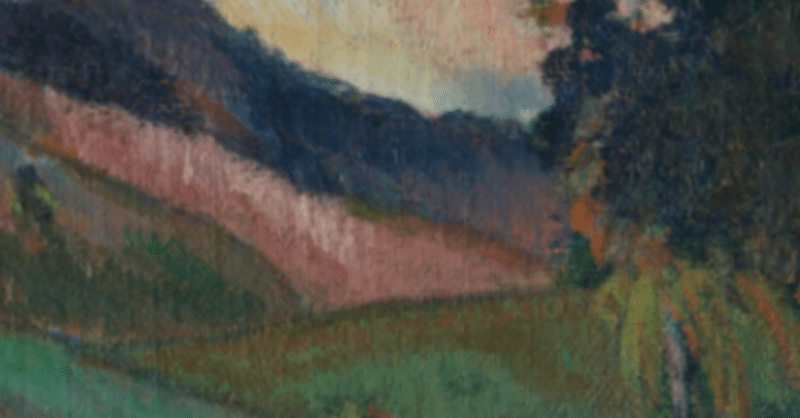記事一覧
瀬沼茂樹の『夏目漱石』をどう読むか⑨ 君はそんな風に学校で習ったか
そこで読点?
その「無口で、」はいつもそうやっているのかな?
それとこれだと誰と誰を同居させたのかよくわからないな。
養家からの仕送りを絶たれ、約一年半夜学校の教師を務めながら独力で生活し、時間的に余裕がなくなり神経衰弱になった友人のKを、先生は奥さんを説き伏せて宅に招くことにした。
こういうことだよね。奥さんは反対した。奥さんを説き伏せた。事情は奥さんにもお嬢さんにも話して聞かせ
瀬沼茂樹の『夏目漱石』をどう読むか⑧ 誰や君?
誰やそれ?
この人は真面目な人なんだろうと思う。ところどころ格好をつけて文章がおかしくなっているけれども、一応本人は真面目にやっているのだと思う。
だから何を言いたいのかよくわからないところも辛抱して、なんとか意味が分かるように修正したりもしてきた。
しかしいよいよ本当に解らないところに出くわした。
六十四年間、「『彼岸過迄』の宗蔵って誰や?」というものはいなかったのだろうか。
御館に振分髪も蜂巣くふ 夏目漱石の俳句をどう読むか151
古瓢柱に懸けて蜂巣くふ
ふくべとはひょうたんのこと。ふるいひょうたんをはしらにかけておいたらはちがすをつくっていたよと、冗談のような句。これはおそらく意図とは別に、というところにユーモアがあるはずなのだが、では本来の目的は何なのかというあたりの感覚が案外分からなくなっているのではなかろうか。
今柱にひょうたんが懸けられている家なんてまずないと思う。これは子孫繁栄の縁起物で、秀吉の千成瓢箪な
陽炎に筮竹もむや神の馬 夏目漱石の俳句をどう読むか150
陽炎に蟹の泡ふく干潟かな
ついこの前、
蟹の泡流れて白し朧月
という子規の句を見た気がする。
確か芥川の俳句の時に書いたと思うけれど、蟹が泡を吹いているときは苦しがっているので、小春かどうか、朧月かどうかは別にして、陽炎の立つ干潟はかなり暑かったのではなかろうか。
昨日のこともあるので何か含みがないかとあれこれ調べてみたが、結果として、蕪村に蓋をされたのか「蟹の泡」の句が案外少な
瀬沼茂樹の『夏目漱石』をどう読むか⑦ 鋭くはないな
日本語としてどうなのか
言いたいことは分かる。ただつまらないだけではなく日本語としてよれよれである。平野敬一郎の『三島由紀夫論』もそうとうあちこち文章がいい加減だったが、最近はそういうのが流行っているのかね。
まず、主述のねじれ、どころの話ではないか。
ええと「宗助は」がいらないな。
で、先に「家主」と書いて次に「家主の坂井」は順番が逆なんじゃない。
それから「交り」は今
岡部茂の『漱石私論』をどう読むか② 三度目はない
トンデモ説を疑いつつ、もう少し読み進めることにする。朝日新聞出版サービスの人が序文で「丹念な検証」と書いていたからだ。
岡部はやはり八月十四日の漢詩を比較する。
花間の宿鳥 朝露を振い
柳外の帰牛 夕日を帯ぶ
随所隨縁 清興足る
比較されているのはここである。
なるほど、この夕暮れの感じが漢詩と通じているということなのかな?
あかん。
あほやこいつ。
これは立派なト
那美さんの湯がいた芹のしたしかな 夏目漱石の俳句をどう読むか149
芹洗ふ藁家の門や温泉の流
この「温泉の流」と書いて「ゆのながれ」と詠ませる句は多分大正五年にもあるな。
橙も黄色になりぬ温泉の流
みたいな感じで多分。まだ読んでいないから、あくまで多分だけど。
岩波の解説には
とだけある。
ええと、「藁家」は藁屋根の家、または粗末な家か。それでも門があるのはまあいいとして、温泉で芹を洗うの?
それ、洗ってるんじゃなくて湯がいてない
岡部茂の『漱石私論』をどう読むか① 大塚楠緒が好き
瀬沼茂樹の『夏目漱石』は読みの凡庸さと文章の稚拙さでなかなか読みづらい本である。同時に熊倉千之の『漱石のたくらみ』というトンデモ説の極みのような本を読んでいたので頭がくらくらして、相当にしんどかったが何とかそちらは読み終えた。結論から言えばまともなことは一つしか書かれていなかった。それは「漱石作品の地の文の末尾は次第にタが増えていき、猫が14.19パーセントであったのに対して明暗は96.40パー
もっとみるK.Natsume "I looked at her as she looked at me"
I looked at her as she looked at me:
We looked and stood a moment,
Between Life and Dream.
We never met since:
Yet oft I stand
In the primrose path
Where Life meets Dream.
Oh that Life could
Melt in
夏目漱石『坊っちゃん』
今にして思えば、人生とは愛おしく思う誰かと本当に屈託なく笑い合えるような瞬間をどれだけ共有できたか、それがなければ自分が大切に思う人に対してどれだけ感謝できたか、そこに尽きると思う。
そう思えば私には人生などなかった。
しかし近代文学2.0はある。
瀬沼茂樹の『夏目漱石』をどう読むか⑥ 一生気付かへんのやろな
真面目に一生懸命生きてきた証がこれかと愕然とする。
おそらく瀬沼茂樹という人は真面目に漱石について網羅的に語ろうとしてこんなに大きなタイトルの本を書いたのだ。
幅と用意
この人は一生自分が訳の分からないことを書いていたことに気が付かないまま終わるのだろう。
東京大学出版局の岡本和夫も同罪である。
いい指摘をしかけて、言語化に失敗している。「実業家攻撃に終始してきた態度を転じて」
熊倉千之の『漱石のたくらみ』をどう読むか③ 小林は洗濯屋
これを読んで「へ―深いね」と感心する人がたった一人でも存在するものだろうか。
これはジョークでなければなんなのだ?
こじつけにもほどがある、と言えば済むことなのか。
例えばダミアン・フラナガンは導入部においては上手に事実関係を配置した。
小宮と森田の手元に『ツァラトゥストラ』がたまたま存在したのは、生田に助言するために再読していたため、という指摘はいかにももっともらしいものだ。
瀬沼茂樹の『夏目漱石』をどう読むか⑥ 無理せんでええがな
格好つけようとして失敗している
人文学系の論説が馬鹿にされるのは、こうした言い回しが放置されているからであろう。
まったく意味が解らない。
解らな過ぎて何故解らないのかと考えてみると、少なくとも「常にそうであるように」が「ほかならない」と同じように無理のある格好つけの言葉であり、この文においては完全に不必要であると気が付く。すべての告白が死と新生の宣言である訳もない。
次に「代助の