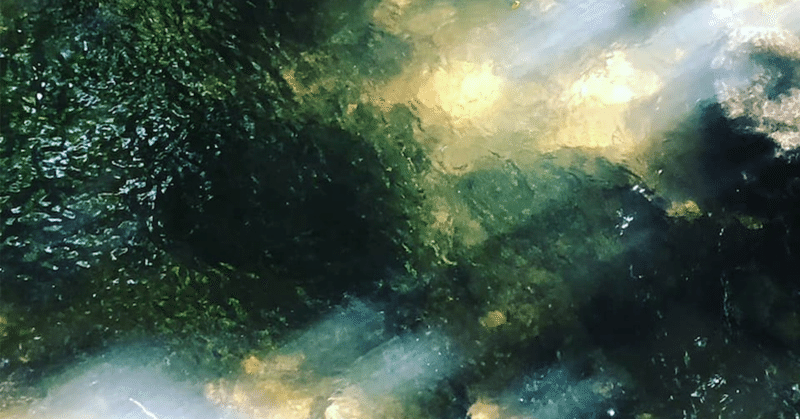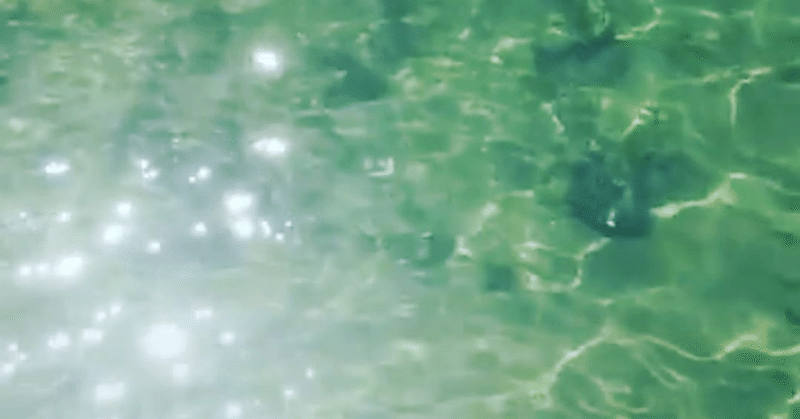#コラム
神社学的☆プロセスこそが随神道
この国に住んでいる人であれば、一度も神社に行ったことがない、というほうがめずらしいかもしれない。では多くの方の神社参拝はどんなきっかけが多いのだろうか?
お宮参り、七五三、結婚式やお葬式などの人生の節目には必ずという方もいれば、お祭りや初詣といったイベント的な時にしかというかたもいるだろう。または観光や出張の際に立ち寄るなどなど、そのきっかけは様々ではないだろうか。もちろん合格祈願や縁結びなどの
神社学的☆自然という神との出会いが“自分”となる
僕が20代のころ見に行った演劇があった。とても前衛的な演出で、舞台上は怪しい光のもと、霧が立ち込め「うわぁ、すげえな。超神秘的だ!」なんて感動していました。
それから20年以上たった数年前、同じ演出者の手掛ける舞台に出かけたのだが、さすがに時の流れとともにその演出も磨きがかかり、さらに神秘的な空間が広がっていた・・・が、どうしても僕は以前のような感動をすることができなかった。この光は照明であり、
神社学的☆億千万の命に溶け込む
幸せとはなんであるか。
これこそ人の数ほどその概念は様々で、これが幸せの型です!
と言える人はいないはず。
究極的には僕の幸せは僕自身にしかわからず、国に働き方を決められることでも、日本にオリンピックがやってくることでももちろんない。僕にとっては、今、この瞬間に生きていること自体を幸せなことだと感じていて、これ以上のテクノロジーの進化もライフスタイルの変化もあまり必要とはしていないのです。と、