2021年7月の記事一覧
君子は泰にして驕らず。小人は驕りて泰ならず(論語 子路)
(意味) 君子は自信を持ちながら、しかも謙虚である。小人は傲慢でありながら、そのくせ自信に欠けている。
人の上に立つ者は、特に謙虚でなければならない。「謙虚さ」は、孔子の理想とする人徳のうちの一つです。いかに才能に溢れ、アクティブで優れたであっても、履き違えて傲慢な態度でいると、いずれ諫言する人も居なくなり、かつてその優秀さで成果を上げていたものの、新しい考え方が周囲から入ることなく、やがてパフ
欺くこと勿れ。而してこれを犯せ。(論語 憲問)
子路君に事えんことを問う。子曰く、欺くこと勿れ。而してこれを犯せ。
(意味) 子路が、君主に仕(事)えるとはどういうことかを質問した。
孔子は仰った。「偽ってはいけない。しかし、いざというときは躊躇なく諌めよ。」
この言葉は、子路という弟子が講師に対して、君主に仕えることに対する考えの質問をした中の一節です。
基本スタンスは「誠心誠意」
嘘偽りを言うのは不義理であり、それは国を滅ぼす元凶
事を先にして得ることを後にす、徳を崇うするにあらずや。その悪を攻めて、人の悪を攻むることなき、慝を脩むるにあらずや。(論語 顔淵)
(意味) 自らがなすべき事を十分に行って、その報いを考えなければ、徳は自ずから積まれてくるものだ。
常に自ら顧みて自分の悪を攻めて取り除き、他人の悪を攻撃することがなければ、心の中のやましところはなくなる。
なんともストイックな言葉ですね。
まず、やるべきことを全うする
前半の言葉です。
あくまで関心の中心は自己鍛錬にあります。
自らを高めていくことで、その引力で、報いは後から付いてく
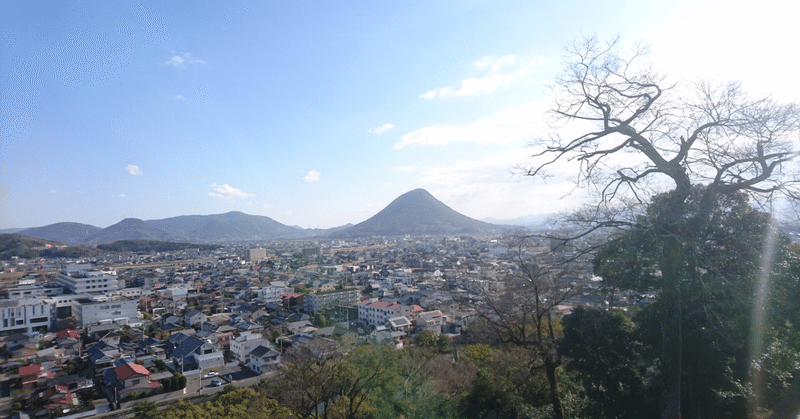


![[コラム] 孔子スタイルとソクラテススタイル](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/57324962/rectangle_large_type_2_1a1331e48858b02b29d35eca75e4e755.jpg?width=800)










