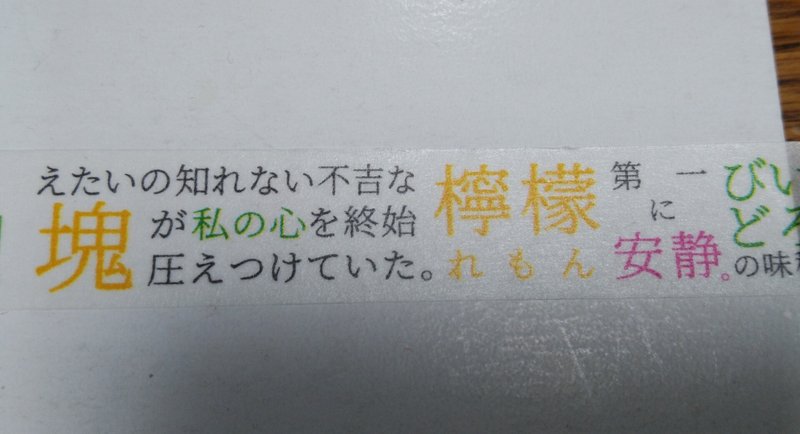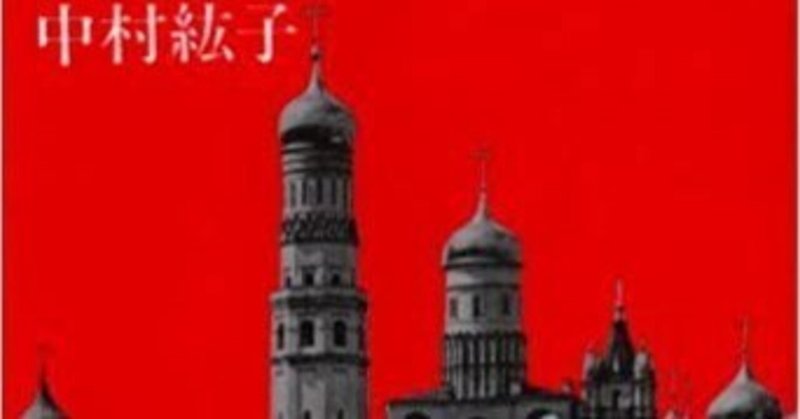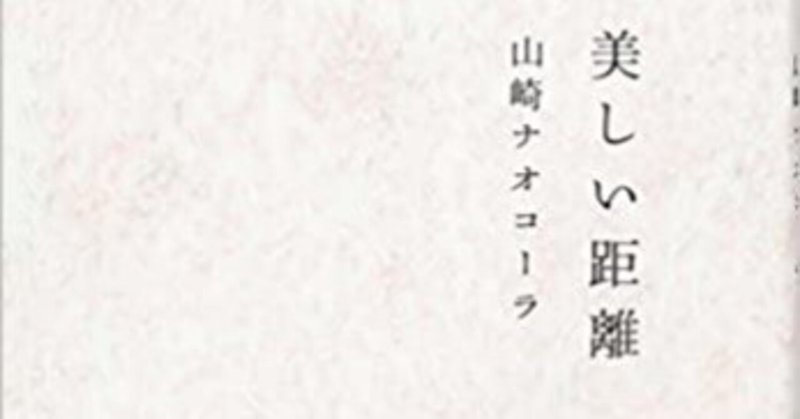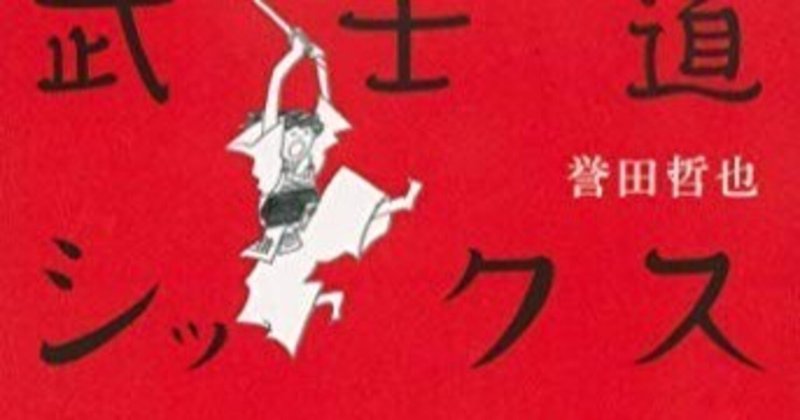2022年6月の記事一覧
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂7』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(354))
廣嶋玲子『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』シリーズ(jyajya絵、偕成社)7冊目。6巻目に続き、鳥かごに閉じ込められたままの、たたりめ堂のよどみから邪悪な駄菓子の素材を委ねられた赤ひげの怪童と勝負をすることになった銭天堂の紅子。たたりめ堂から委託された菓子を銭天堂に並べ、お客さまが紅子が作った菓子より沢山たたりめ堂のお菓子を選んでくれれば怪童の勝ち、という勝負。
もう見るからにたたりめ堂のお菓子が邪悪さを
中村紘子『チャイコフスキー・コンクール』(毎日読書メモ(353))
実家に来ているときに、少しずつ読んでいた、中村紘子『チャイコフスキー・コンクール ピアニストが聴く現代』(中央公論社、のち中公文庫)を1ヶ月位かけて読了。
父の本棚にあった本だが、父が亡くなってからの1年間、本棚の整理をしながら発掘して拾って読んでみた本とはちょっと性質が違う。この本をわたし自身も新刊だった時代に読んでいる。1988年10月に刊行された本で、奥付に父が書いたメモによると購入したのが
山崎ナオコーラ『美しい距離』(毎日読書メモ(352))
山崎ナオコーラ、続く。2016年に、5回目の芥川賞候補となった、『美しい距離』(文藝春秋、現在は文春文庫)。芥川賞は逃したが、島清恋愛文学賞を受賞している。先日『母ではなくて、親になる』を読んだ時(感想ここ)に、この『美しい距離』が芥川賞候補になって落選して島清恋愛文学賞をとったあたりの経緯が書かれていて、気になったので読んでみた。
生命保険会社に勤める夫と、サンドイッチ屋さんを経営している妻。
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂6』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(350))
廣嶋玲子『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』シリーズ(jyajya絵、偕成社)6冊目。これまでの巻より心持ち分厚い感じ。ライバルというか敵役のよどみは、第5巻のトラブルで鳥かごのなかに収監されていて、ぱっと見トラブルの種はなさそうなのに、銭天堂の紅子は原因のわからない不調で集中力を欠き、幸運のお客さまにお勧めする駄菓子を間違えてしまったり、カプセルトイを落としてしまって幸運のお客さまでない人に使われてしまった
もっとみる石井光太『ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか : マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える 』(毎日読書メモ(347))
2015年6月の読書メモより。石井光太さんの本は、その後『本当の貧困の話をしよう 未来を変える方程式』(文藝春秋)(感想ここ)も読んでいる。また色々読んでみたい。
読書SNSの書き込みを読んで気になった『ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか : マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える』(石井光太・ポプラ社)を読んでみる。最初にマララ・ユスフザイさんの国連演説が紹介され、それから作者の意見が書かれて
柳沢有紀夫『会社を辞めて海外で暮らそう―海外家族移住という選択』(毎日読書メモ(346))
友人でもある柳沢有紀夫君が2005年に出した『会社を辞めて海外で暮らそう―海外家族移住という選択 (クロスカルチャーライブラリー)』(スリーエーネットワーク)の読書メモ(2015年6月)。
『会社を辞めて海外で暮らそう―海外家族移住という選択 』を図書館の棚で見かけ、ぱらぱらとめくってみたりしたので、長く会っていなかった彼が、会社を辞め、オーストラリアで暮らしている、ということは10年近く前から
誉田哲也『武士道シックスティーン』『武士道セブンティーン』(毎日読書メモ(345))
誉田哲也『武士道シックスティーン』『武士道セブンティーン』(文春文庫)の読書メモ。この後更に『武士道エイティーン』、『武士道ジェネレーション』(文春文庫)と続くが未読。いい小説だったけど、スポーツ少年少女の物語には飽和量があるようです>自分自身。いつか読むかもしれない(人の評を読むと、後になるほどよくなるっぽいので)。
『武士道シックスティーン』:磯山のオレサマぶり、早苗の天然ぶり、どちらにも深
金哲彦『走る意味―命を救うランニング』(毎日読書メモ(343))
金哲彦『走る意味―命を救うランニング』(講談社現代新書)の読書メモ。新書は消耗品なので、2010年に刊行されたこの本を今から読む人はそんなにいないかもしれないが、金さんの本、ランニングを始めた頃何冊も読んで、走る上での指針となったのとは別の意味で、深く心に残った。
フルマラソンを走るより前に、ランニングのイベントで金さんに走りを見ていただいたことがあり、必ずサブフォー出来ますよ!、と明るい声で断言
『白洲正子自伝』(毎日読書メモ(342))
『白洲正子自伝』(新潮社、のち新潮文庫)の読書メモ。
単行本で買って、10年以上寝かせてあった本をついに読んだ。それは白洲次郎、正子の破天荒さの片鱗を知ったり、三島の『春の雪』や北村薫の英子・ベッキーさんシリーズに出てくるような圧倒的お嬢様世界の記録を読んだりという意味でも興味深く、また、白洲正子本人のセンスとか文才とかたくましさとか、そういうものを堪能する意味でも実に愉しい読書であった。読んで