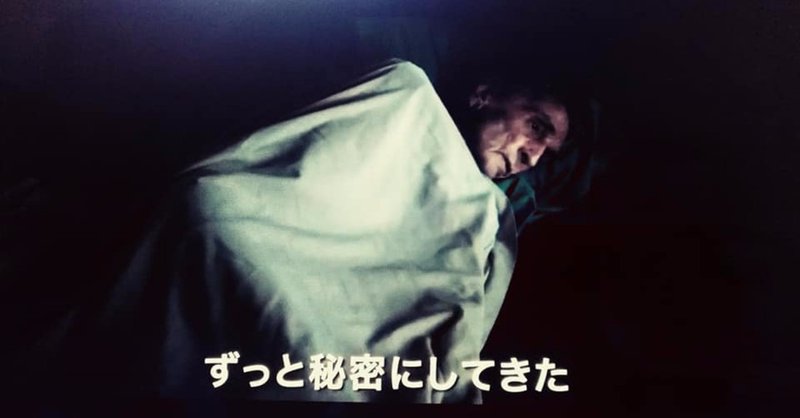#暦
まなかい;立冬 57候『金盞香(きんせんかさく)』
「金盞」とは水仙のこと。
「金盞」の「盞」…「戔」に「薄くて重ねたもの」の意があると『字統』に記されている。水仙の花は、3枚の花びらと3枚の萼に、副花冠が合わさっていて、確かに薄い盃を重ねたようだ。輝くように黄色い薄物の盃と見立てて「金盞」とついたのだろうか。
爽やかで苦味も効いた濃厚なあの香りに、お酒を注いで飲んだらどんな味がするのだろう。
漢名は「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、
寒露:第51候・蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)
晩秋ともなると、夜にあれほど鳴いていた虫たちの声が減る。
蟋蟀戸にあり、
虫の数が減って、合唱だった歌が独唱となり、その歌が侘しくさせるのだろう。
秋も、彼らの生も残り僅か。
離れていくから名残惜しい。
恋情は燃えるが、それを振り払って、引き剥がして生きていく。
「あき」はそうやって「あきらめていく」とき。「飽きる」も語源だともされるが、いずれにしても距離が「空いて」いく。
自分の何
夏至;第30候・半夏生(はんげしょうず)
夏至の三つの候は、薬効の高い薬の植物ばかり。
「乃東枯」「文目華」そして「半夏生」。
次候の「文目華(あやめはなさく)」のアヤメにサトイモ科のニオイショウブも含めているだろうと考えればだけど、とはいえ目でみて美しいとか、何か心地よさを感じるとしたらそれだけでもう薬だろう。そうするともう全て自然界には薬でないものはないということになる。
この時期までに田植えは終わらせておかないと収穫は期待でき
芒種;第25候・螳螂生(かまきりしょうず)
冷房が効かないので
窓を開けて車を走らせていると
どこからやってきたのか
蟷螂の子がフロントガラスを斜めに翔けていく
たった一匹
梅雨入り前の途方も無く広い空を眼下に
二つの鎌を立て
身を反らせて
三角まなこはみどりの粒で
あんなにも軽々とあらわれて
もう会えない
花を活ける仕事をしていると
稀に蟷螂の卵が付いている枝がある
捨てられないのでバルコニーなどに保管しておくと
小満;第23候・紅花栄(べにばなさかう)
中東あるいはエジプト原産と言われるベニバナ、本紅で有名な紅花の咲くのはまだ先。
「半夏ひとつ咲」ともいうから咲きはじめは夏至の末候。
まゆはきを俤(おもかげ)にして紅粉(べに)の花(芭蕉)
行く末は誰が肌触れむ紅粉の花(芭蕉)
と奥の細道巡礼で芭蕉が詠んだのは、今の日付に換算すると7月中旬となるようだ。
まゆはきは「眉掃き」「眉刷毛」で、おしろいを叩いた後 眉についたそれを払
小満;第22候・蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)
生まれ育った地域はかつて養蚕がとても盛んな土地柄で、小学生の頃は隣もお向かいも裏の家も田畑と養蚕を営んでいた。
隠し部屋のようになっていて使うときだけ降ろす階段が、土間続きに設えられていて、それを不思議な感覚で登った記憶がある。登ると蚕室は囲炉裏や寝室のある一階の上ほぼ全てという広さで、そんな板張りのガランとした「お蚕さん」の蚕室に何度か入れてもらったことがあるけど、何百匹といる蚕が草を食む音に
立夏;第20候・蚯蚓出(みみずいづる)
分解者の代表 蚯蚓。特にこの時期、彼らの役割を改めて思い出す。
場所は世田谷ものづくり学校。
ぽくぽくと土を耕してくれて、年々土は豊かになっていく。
人の手は最小限にしている都市では珍しい場所。足元に広がっている見えない営みが命を支えている。
蚯蚓もまた死んだら次の命の場所になる。