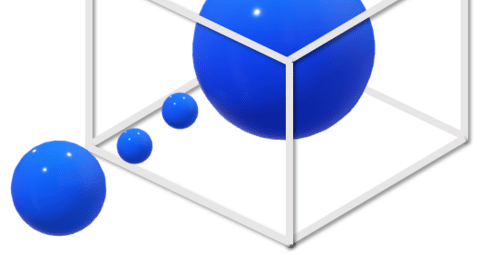2022年5月の記事一覧
しあわせに生きる基本はどこで作られると思いますか?家庭?地域?子どもたちはほとんどの時間を学校で過ごします。教室の影響はとても大きいのです。みなさんはどんな学校を自分の子に行かせたいですか?
「こんな学校に子どもを行かせたい」
「こんな学校を作りたい」
そんなことを考えたことはありますか?
そんなすごいことをやってる方々のお話を聞くイベントを準備しました。
あすキラLab vol.5 学校を創る。学びってなんだろう
2022/06/16 (木) 19:30 - 21:00
私は若い頃には、そんな思いはなかったんですね。学校って、どれもそんなに違うとは知らなかったから。そして、学校が
「シアワセってなに?」Denmark株式会社が新しい社員研修サービスを提供開始
これまで小中高校で行ってきた「シアワセって何?」と言う授業を企業研修として組み立てたのがこちらのサービスです。(ニュースリリースはこちら)
根底にあるのは、子どもたちも親(大人)もベースになるものが同じにならないと、共通言語で話ができない・分かり合えない、と思うこと。言葉の定義が違っているのに、同じ名詞・動詞を使っても、実は話はすれ違っている、、、そんなことありませんでしたか?それは親子・家族=最
コロナ禍で学びの機会を失った子どもたちにチャンスを!オンライン「世界一周スタディーツアー(World Immersion Tour)」4月22日提供開始
ちょっと前の話になりますがこんなサービスを開始しました。まずは動画でご覧ください。
ニュースリリースはこちら!
打ち合わせのたびにどの学校からも同じ声が聞こえてきて、そして先生方はまるで自分たちが悪かったように、「子どもたちが可哀想で、、、」と肩を落としていました。
世界一周スタディツアーでは生徒が選ぶ5大陸をオンラインで旅をしながら人生を考え今を学ぶと言う仕組みです。
私たちもそうですが
若き経営者たちは偉大だった。そして、思わぬ言葉がたくさん出てきてびっくりした。やはり、仲間を巻き込む彼らはすごい!
若いうち(若いって何歳から?)から経営者となったお二人のお話は本当に面白かった。このイベントに参加しなかった人は本当に後悔すると思ったし、やはり中高生に聞いて欲しい話だった。意外なことから人生は始まったりする。
大森峻太さんはジェイノベーションズ社の代表。大学時代から様々な団体が結果としてスポンサーとなり無料で海外旅行をしていた。その延長線上に今がある、と。これまでの流れがあまりにも爽やかだ。大
THINKING CLASSROOMS に関わる日々がスタート。
もう3ヶ月ほど前からだろうか、この書籍の翻訳出版と学校・授業への展開プロジェクトを開始した。と言っても、最初は二人。半年前に知り合った梅木卓也氏がこの本にある教え方でカナダで数学の高校教員をしている。話を聞けば聞くほどに、デンマークの小学校の「算数のドリルを複数人で行う理由」と重なった。
現在数学教育学の大学院生でもある梅木さんの恩師がこの本の著者リリヤドール教授だ。梅木さんには弊社のOut o