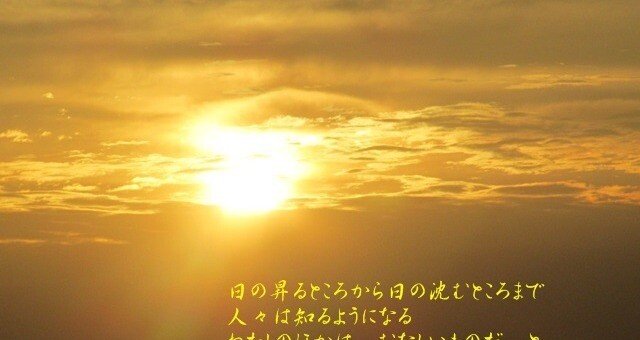
哲学も少しはかじっています。なにもそんなこと考えなくてもいいんじゃない、と言われるところも、でもさ、と考えてみる、それが哲学。独断と懐疑に終わらずに常に自分の至らなさを認めるあた…
- 運営しているクリエイター
2021年3月の記事一覧
人を数にしている私たち
連日、新型コロナウイルスの感染者の数が、ニュースのほぼトップに挙がってくる。新規感染者、死亡者が数字となる。それにより、非常事態宣言が発令されたり、解除されたりする。政策の上で、それはひとつの指標となっている。
思い出す。「一人の死は悲劇だが、集団の死は統計上の数字に過ぎない」
誰が最初に言ったのか、情報は錯綜している。しかし、次の言葉ははっきりしている。
「一人殺せば悪人だが、100






