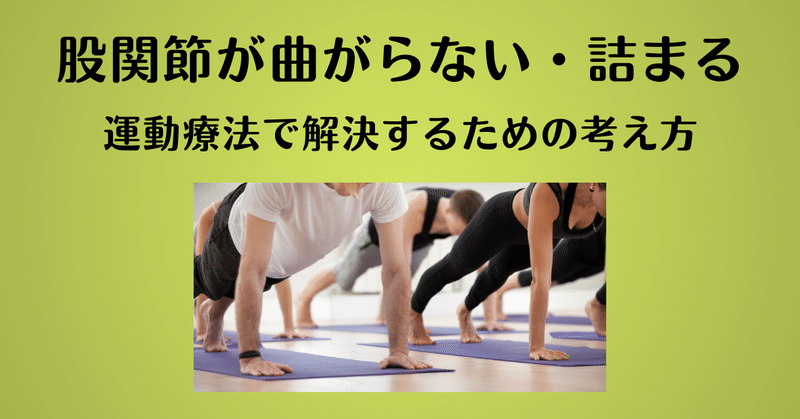
「股関節が曲がらない」「股関節が詰まる」運動療法で解決する考え方!
股関節が曲がらない。
股関節を曲げたら詰まる。
そんな方も臨床をやっているととても多いです。
そんな股関節の症状を改善するための運動療法の考え方というテーマで今回のコラムはお伝えしていきます。
機能解剖学をもとに股関節の可動域制限やつまり感の原因を解説して、自分自身の臨床経験からもアプローチのコツについて紹介をします。
股関節を曲げる時の条件

股関節を曲げる時の条件ですが…
腰椎
骨盤
大腿骨
この3つの骨の動きによって動きが構成されています。
骨盤大腿リズムとか言われたりもしますよね。
このどれかの部分の動きが過剰になったり、、
反対に動きが出ずに制限になったりするから股関節のつまり感・可動域制限になるケースが非常に多いわけですが…
このどこの骨の動きが上手く出てないのか?
どの骨の動きが過剰になっているのか?
それを動作や実際に触って動きを評価することが必要になります。

腰椎
骨盤
大腿骨
この3つの動きの協調性がなくなった際に、股関節のつまり感や可動域制限に繋がると解説をしましたが、、
じゃあ、この骨の動きを止めている部分はどこなの?
そういう原因を考えることが必要になってきます。
股関節が曲がらない制限因子

股関節を曲げる動きの際の骨頭の動きを考えた場合には、骨頭は後方に向かって動く必要性があります。
そのため、骨頭が後ろに移動する制限が掛かっている場合に屈曲制限に繋がってしまいます。

骨頭の後方移動を阻害する因子として、一般的な考えとしては股関節後方組織の硬さが挙げられます。大殿筋・深層外旋六筋・中殿筋あたりがタイトになっている場合であれば、当然ですが骨頭が後方に移動することができないので、股関節の可動域制限に繋がります。
この場合であれば、、
股関節後方組織のタイトネスを改善すれば股関節の屈曲可動域も改善するケースも実際に臨床で経験します。
反対にですが、、
骨頭の前面部分の軟部組織など、腸腰筋・大腿四頭筋・腹筋群・股関節内転筋群あたりの滑走障害があれば前方でインピンジメントの様な状態になるため挟み込まれてしまって可動域制限やつまり感に繋がるケースが多いです。
これはどこの制限因子を改善すれば…
可動域改善ができるかという話になりますが、、
今回のコラムではモーターコントロールの面からも少し話をして、運動療法の中で股関節の屈曲可動域・つまり感を変える方法を解説します。
動き方の問題を解決する運動療法

自分の臨床経験としても、、
徒手療法をゴリゴリに行って、股関節後方組織や前方組織の制限因子を改善しても改善しなかったケースも実際にあります。
股関節の制限因子を改善しても、、
そもそもの体の使い方や動かし方が悪い状態になっていると、それが要因で股関節の詰まり感などインピンジメントを作ってしまう状態になっている可能性もあります。
例えばですが、、

女性などで、腰椎が過度に前弯したアライメントが定着した方がいます。
そんな方の股関節前方因子・後方因子の制限因子の解決をしても、この方の中で股関節を深く曲げる動きをする際に今まで腰椎が屈曲したり、骨盤が後傾する機会が体にとってなかったわけなので、、
ここから先は

臨床マガジン【現場で使える機能解剖学・運動療法・ピラティス】
業界最大規模の購読者数700名以上●「現場でしっかり結果を出したい」セラピスト・トレーナー・インストラクターのためのマガジン●"臨床で本当…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
