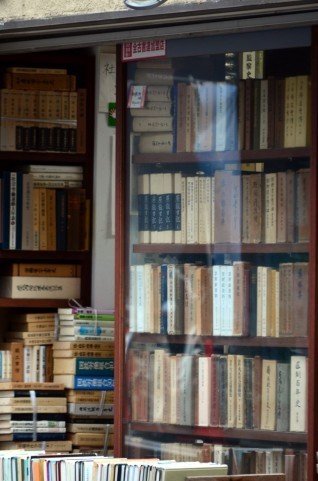
- 運営しているクリエイター
#国富論
「なぜ勉強をしなければならないか」への答えは「人間らしく生きるため」他
子どもの頃、よく、「ひょっこりひょうたん島」を見ていました。
あの中に「勉強なさい」と言う歌が出てきました。
子どもたちが勉強なんかしなくたっていいじゃないかと言うと、お返事が人間らしくなるためだと言うやり取りが、子ども心に印象に残った記憶があります。
今聞いてみると、ちょっとズレてるかなぁと感じる点はあるのですが、ただ、勉強する根拠=人間らしくなると言うのは、この歌の論旨とは別に「あってい
毛皮が「商品」になった事と日本の開国の関係など
アダム・スミスの国富論にこんな一節があります。
「人間が最初に衣服の材料として用いたのは、比較的大きい動物の皮であった。それゆえ、この動物の肉を主食としている狩猟民族や牧畜民族の間では、食料を自給することによって、各人の必要以上の衣料の材料を自給する事が出来る。
外国との貿易が全然なかったなら、この材料の多くは無価値なものとして捨てられたことであろう。
北アメリカの狩猟民族の間では、かれらが
「紙」マルチによるニンジン栽培のテスト。地代は原価+手間賃で決まる価格とは別の原理で成り立っている件など
アダム・スミスは国富論の中で、賃銀と利潤は価格の原因だが地代は結果だとしています。
「地代」について、制度や政策と言うことを離れて考えてみると、確かに「労働」によって実現される価値とは違う性格を持っていることは確かです。
価格や価値と「労働」の関係ですが、アダム・スミスは「労働価値説」、つまり、労働があらゆる価値の源泉だとしています。
たとえば、僕が大根を育てて、1本100円である飲食店に卸
国富論にみる徒弟奉公と半農生活の農家を生み出すための仕組み、温暖化には「上限」がある?など
アダム・スミスの国富論にギルドの徒弟修業のお話が出てきます。
「全ヨーロッパを通じて昔は7年と言うのが同業組合化された職業の大部分における徒弟修業の期間であったようだ。そういう団体は昔はみなユニバーシティと呼ばれた」
ユニバーシティは、今では大学を意味する言葉ですが、この点について、スミスは
「しかるべき資格のあるマスターのもとで7年間勉強したと言うことが、リベラル・アーツの場合も、マスター
備中鍬で雑草ごと掘り起こす畝立て法、「校庭の雑草」は手間のかからぬ農法開発に役立つ、ホウレンソウは南側畝から種まきすると長期収穫できるかもしれない、資本主義の特徴は投資すること等
「院政と武士の登場(福島正樹)」には、「都の貴族からみた奥州平泉は、金、馬、布などの奥州特産物や平泉を中心に行われたであろう北方交易によって入手したアザラシの皮、鷲の羽根などの、武具の材料になる貴重品をもたらす源であった」と記載されています。
「銭踊る東シナ海(大田由紀夫)」には、室町時代に大陸からの輸入品が「唐物」として珍重されたことが書かれています。
19世紀には中国の茶や日本の生糸を欧米
18世紀にアダム・スミスは中国は世界一豊かだが停滞しているから中国の労働者は貧しいと述べた。21世紀までの流れを思い返してみて、今後を考えてみる・・・
アダム・スミスの国富論には、中国のことも出てきます。
「長い間、世界で最も富んだ、すなわち最も肥沃で最も良く耕作され、最も勤勉で、そして最も人口の多い国の一つであった。
けれども、この国は長い間、停滞状態にあったようだ。」と述べています。
スミスは、中国の停滞状態を「たとえ国の富が大変大きくても、その国が長い間、停滞状態にあるなら、そこでの労働の賃銀が非常に高いと思ってはならない」
つまり















