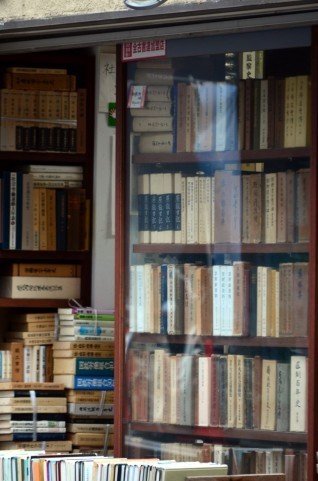
聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…
- 運営しているクリエイター
2023年2月の記事一覧
18世紀にアダム・スミスは中国は世界一豊かだが停滞しているから中国の労働者は貧しいと述べた。21世紀までの流れを思い返してみて、今後を考えてみる・・・
アダム・スミスの国富論には、中国のことも出てきます。
「長い間、世界で最も富んだ、すなわち最も肥沃で最も良く耕作され、最も勤勉で、そして最も人口の多い国の一つであった。
けれども、この国は長い間、停滞状態にあったようだ。」と述べています。
スミスは、中国の停滞状態を「たとえ国の富が大変大きくても、その国が長い間、停滞状態にあるなら、そこでの労働の賃銀が非常に高いと思ってはならない」
つまり
「原価と手間と利益を見込んでこの値段になる」と言う説明はヨーロッパ人が植民地を作り、先住民の社会と資本主義社会を対比して生まれたものだと言うこと
アダム・スミスの国富論は1789年に書かれています。
この中で
と述べています。
中公文庫の注釈は、この記述について、以下のように述べています。
現代の私たちは、例えば、自分が売っている商品について、「これ、もっと安くできないの?」と聞かれて「いや、手間がかかっているから無理です」と答えることもあると思います。
「手間がかかっているから、この値段になる」と言うのは、「労働」が価値を生んでいる
「外的な規範」で「自由な交易」を規制している例・・・農業との関係で
「外的規範」と交易、交換で、「自由な経済活動」が「霊の祟り」や「公共の福祉」等、「経済の外側」にある何らかの規範によって規制される例について述べました。
農業との関係で言っても、こうした「外的規範」による規制は、歴史的にも、現代でも割りと通常に行われていると言えます。
手元に本がないので正確な引用はできませんが、バルキッドゥ・サドルの「イスラム経済論」では、アメリカ流の資本主義でもソ連流の社会











