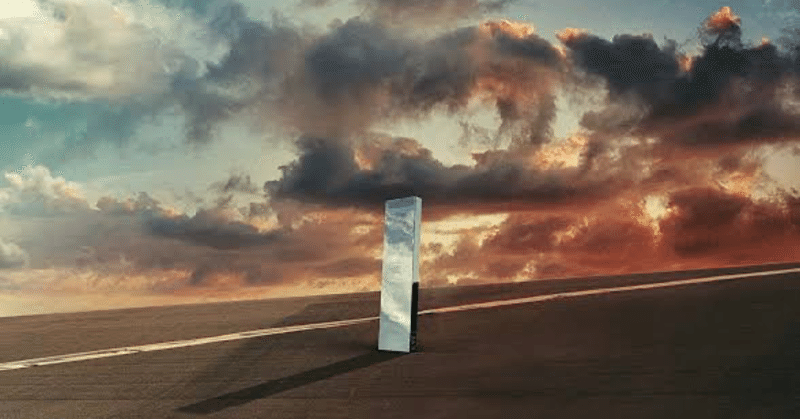
メリーバッドエンドの物語「星の子」を観て、映画を観る意味を考えた。
映画『星の子』を観た。
2020年に大森立嗣監督によって映画化された、芦田愛菜主演・今村夏子原作の、宗教二世のお話である。
『もし、自分が物心ついた時に、両親が宗教信者だと分かったら』
この映画を観るまで、私は、この状況を想定したことが一度もなかった。宗教二世問題が、旧統一協会の騒動で明るみになる前の鑑賞だった。自分の周りにも、親が宗教に熱心だと漏らす友人はいなかった。
もし、映画・星の子を、あの騒動の後に知って観ていたら、得た感想は、異なっていたのだろうか。ネットの声のように、
「自分とは無縁の世界の話」
「気味が悪い」
「頭のおかしな人たち」
「バカバカしい」
「関わりたくない」
そんなことを、思ったのだろうか。
私には、宗教が分からない。
分からないくせに、クリスマスには毎年ちゃんとワクワクするし、その1週間後には寺や神社に挨拶をしにいく。なんならそれが神でも仏でも構わない。"年末年始に何者かに手を合わせる行為"が欲しくて、それをやっているだけにすぎないのかもしれない。
この映画は、病弱だったちひろを救いたい一心に、ちひろの両親が "神秘の力を宿している" という水にすがり、次第に「あやしい宗教」にのめり込んでいくところから始まる。
そこからちひろが思春期を迎えるまでの心の移ろいや、宗教に心酔する親のもとに生まれた子供たちの生き様が物語られていく。
そして、そのちひろの両親が宗教信者になるきっかけを作っていたのが、実は“ちひろ自身“なのであるという皮肉さが、物語の肝となっている。
人は、弱い。
どうしても守りたいものがあった時、どうしても何かにすがりたくなった時、自分一人で背負いきれなくなってしまった時、何かのせいにしたくなった時、何かに、誰かに、その思いを託すことで、救われてしまうことがある。
幼い頃、ちひろは医師もお手上げ状態で治すことが難しいとされていた皮膚の湿疹が、全身に発症していた。愛する我が子が、痒みなのか痛みなのか、その不快感でずっと苦しみ続け、泣いている。耐えられなかった。どうしても、治してあげたかった。
そんな時出会ったのが「金星のめぐみ」という名の水だった。その水を使って、毎日丁寧に体を洗うことで次第に回復するという。両親にとって、もうその水がなんであろうとも、回復の兆しを予感させるものは、全て救いだった。言われた通りに毎日、体を金星のめぐみというきれいな水で洗った。優しく洗った。そしてついに、ちひろの皮膚は、健やかな赤ちゃんの肌そのものになった。この、治癒に至るというひとつの成功体験と、心からありがたいと思い平伏すことのできる存在への安心感こそが、両親を宗教にのめり込ませるきっかけとなったのだ。
ちひろが心の中でその事実をどう受け止めて咀嚼したのかというところは、この映画の中では詳細な描かれ方はされていなかった。
同じように、ちひろが心からその宗教を信じているとも疑っているとも、その答えを直接的に描写されるシーンもなかった。
心から信じてもいないし、心から疑ってもいないけれど、それでも、毎日金星のめぐみを飲むことだけは、ちひろの中で習慣化していた。生まれた時から、もう既に当たり前のように身近な存在になっていた“金星のめぐみ“という、水。その水を、ちひろは、不安な時、納得がいかない時、無意識のうちに、ごくりと音を立てて飲みこんだ。その、水を飲む様子だけが、描かれ続けていた。
ただ、2つだけ両親と異なっていたのは、決して宗教の『儀式』だけは、しなかったこと。そして、両親が金星のめぐみの効力が弱くなるからと飲まないコーヒーを、好んで飲んでいたということ。
両親のように熱心に『儀式』はしないのに、水は飲む。その行為が、本人は決して心酔しているつもりのない宗教に、不自然なくらい自然に浸透してしまっている二世としての宿命が、体現されているように見えた。
ちひろは思春期を迎え、新任の教師に恋をする。
そして、その恋を経て、次第に周囲が両親へ抱く違和感と、ちひろ自身が抱く両親への様々な感情の狭間で葛藤する場面が描かれるようになっていく。
たとえ親友が両親への疑念を口にしても、親戚のおじが宗教にのめり込む両親から引き離そうとしても、家がみるからにどんどんと貧乏になっていっても、ちひろは両親のもとを離れようとはしなかったし、強く咎めることも反抗するこもなかった。それでも、恋を知ったちひろは、両親のことを、恥ずかしいと思う自分がいることに気付く。その新しくも根深く古くからあった感覚が湧き上がってくる自分自身に耐えきれず、夜の街をただ、走ることしか出来ない。
ちひろの両親がちひろを愛する気持ちは、宗教とは関係ない。ちひろのことを、本当に心から、愛していた。家族として、愛していた。その愛を、ちひろも十分に感じていた。愛していたからこそ、「どうにかちひろの病気を治したい」というその一心で、すがる思いで宗教に救いの手を求めた。
親としての心理を汲めば、子供を救ってくれた神の恵みを信じるというその行為自体には、なんの違和感も覚えない。しかし、「金星のめぐみ」に関する商品をどんどんと購入し、しまいにはただの貧乏になっていくその姿には、大きな違和感を覚えてしまう。
何が正しくて、何が間違っているのか。
何を信じていくことが正義で、何に対する悪に疑いの目を凝らすべきなのか。
その正解を知るのは誰なのか。
学問を学び続けていけばその正解を得られるのか。
この長い長い人生を生きていけばいつか、辿り着くことができるのか。
「どうしたらいいか分からない」
人生には、そんなことが無限にある。
「訳わかんなくなること、あるよね」
両親から離れて暮らしていくことを決めたちひろの姉はそう言って、ちひろにコーヒーを淹れた。
金星のめぐみを心から信じる親は、金星のめぐみに守られている以上「風邪をひかない」と言う。
その親の子供であるひろゆきくんは不登校になった。その親の子供であるまーちゃんは家出少女になった。その親の子供である原山さんは保健室に毎日仮病で通った。
何を信じるかは自分次第。
その信じる先を、宗教を、強要しないことが大切だ。
そんな忠告を、よく聞く。
でも、その子供は?
生まれた時からの確固たる安全基地である両親が、宗教を信じていたら?物心のつかない頃から、それがこの世の当たり前だと育てられたら?
それが愛情であっても、正しく間違いだと言えるのだろうか。
宗教信者をバカにする親が子供の腹にアザを作ることもある。その親の心を救うものが何も無かったとして、もしその親が、金星のめぐみを飲み心が落ち着いて子供を愛することが出来たとしたならば、その子供を救ったのは果たして誰だと言えるのだろう。
親戚のおじさんが「金星のめぐみ」を公園の水と入れ替えた。入れ替えたことに気が付かず、効果があると言い続ける両親に、親戚のおじさんは「それは公園の水だ」と伝え、「水で清められることなどはない」と現実を突きつける。
憤慨する両親。
水の入れ替えに協力したのは、ちひろの姉だった。それなのに、親戚のおじさんが両親から子供たちを引き離そうとすると、ハサミを持って「帰れ!」と叫び止められる。その叫んだ相手は他でもなく、ちひろの姉だった。
「訳わかんなくなることってあるんだね」
ちひろの姉はただ、そう言って、コーヒーを淹れた。
「あさみ先生?
昨日ちょっとお水かかっちゃって、そのまま寝ちゃったんです。
私、風邪引かないんです。
この水飲むと、風邪引かないんです。
でも、やっぱり、風邪ですか?」
「風邪でしょう。」
保健室の先生とのこの会話が、この映画の中で、一番の悲痛さを感じた。風邪だと肯定されれば、これまでの、両親の全ての否定になってしまうから。
自分でもわかんないんだ。
ちひろが初めて両親を否定した日。
これまで、ずっとちひろは片思いしかしなかった。
いつでも自分の手の届かない人を好きになった。
むしろ届きたいとも、思ってはいなかった。
それが、両親が理想とする崇拝する教祖が、決して手の届かない存在であることと重なった。
ちひろは恋をしても、決して手を伸ばさないから、傷つかなかった。どうしようもないイケメンにしか恋心を抱かないちひろは、手を伸ばしても届かない相手だからこそ、ただ一方的に好きでいることができた。だから、傷つくことはなかった。一方的な好きは、いつまでも好きでいられるから。一方的な好きは、相手の美しい部分ばかりを捉えて美化し、いつまでも、のめりこめるから。
初めて傷ついて泣いた。
恋した相手からの、両親の存在否定。
どうしていいか、わからなかった。
そもそも両親が宗教に陶酔していったのは、自分の病気を治すためだったから。両親を信じたいと思う気持ちって、ちひろからしてみたら、自分が此処に存在することを認められる唯一の繋ぎ止めでもあったから。
両親の否定は、自分自身の否定だから。
親は選べないけれど、親は、親しかいないから。
その、とてもとても辛かった日の翌日も、ちひろは、水を飲んでいた。
「待ってる方がいいよ。じゃないとお互い行ったり来たりで、一生会えないかもよ。」
宗教団体の怪しいうわさが後を絶たなくなっても、ちひろたちは、宗教団体の長を信じていた。信じていた、というよりも、心のどこかで同じ境遇であるという強い繋がりをもつ仲間に会える集会に、参加しないという選択肢を選ぶ者がいなかった。
これまで自分が信じていたものを否定されるといことは、自分たち自身の存在を、そして自分たちのこれまでの全てを、否定されたような、そんな気持ちになるのかもしれない。
間違っているのかもしれないと心のどこかで感じても、それを否定してしまうということは、これまでの自分自身も、過ごしきてた時間も、きれいなはずだった思い出もぜんぶ、間違いだったと突き落とされる気持ちになるのかもしれない。
それは分からない。
当事者にしか、決して、分からない。
メリーバッドエンドの物語。
つまり、途方もなく現実世界に忠実な物語。
わけわかんない。
モヤッとする。
とてもよかった。
つまらない。
幸せになれたのかな。
なれたと思う。
なれなかったんだと思う。
この映画には、180度違う感想が散見される。
誰かの生きる人生は、他の誰かによってはものすごくつまらなく見えるだろうし、それのどこが幸せかなんて全く分からないものだ。
目に見えるような勝利や富や愛がなくとも、その人生を生きた当の本人は、あぁ、ものすごく幸せだとそう思いながら、死んでいくのかもしれない。また、その逆も然り。
本当の幸福なんて、その人にしかわからない。
私たちには、体験したことのない他人の人生は、想像もつかない。つくはずがないのだ。
他人の人生全てを想像できる人なんていない。
いたとしても、それは愉快な大間違いだろう。
ただ、その疑似体験が叶う場所があるとしたならば、それが、映画という世界なのだろう。たかが120分間で、他人の人生を疑似体験することができる。どんな魔法よりも精密だ。
人生にしおりは挟めない。
小説みたくしおりを挟んで一旦パタンと閉じてしまいたい時だってあるけれど、それでもページをめくり続けなければならない。自分のペースで読み進めたいと思うのに、それが許されないこともある。そんなとき、自分以外の誰かの人生に、密度高く深く落ちていく没入感を得られる時間、自分の人生を一時停止して、誰かの人生を疑似体験することが許される時間、それが、現代最高難度の映画体験という技術なのだと私は思う。タイムワープも入れ替わりも出来ないけれど、そんな危険なリスクを犯さなくとも映画の一本で知ることのできる世界が今日も、私のすぐ手の届く場所に広がっている。
私が映画を観たくなる理由なんて、そんなものだ。
♢♢♢
政治と宗教の話だけはするなと言われそうだけれど、これはつまりただの映画感想文だということにしておきたい。
その人が信じたものがたまたまアーティストだったか恩師だったかはたまた何かの宗教だったか、そんな違いだけでその子供もそのまた子供も苦しむかもしれないこの世界で、それでも今日も何かを誰かを信じていたいと願ってしまう、もしかしたらそれが人の弱さでもあり、ひとつの強さでもあるのかもしれない。
私が信じていたい、音楽のことばを。
俺達が生きてる間に差別も犯罪も戦争もなくならねぇ
今日も何処かで飢えて死んで行く子供達を平気でシカトしてる神様が 俺達の夢に興味持つ訳ねぇだろ!
願う以上に自分で変えろ!
本日の #読売新聞 滋賀県版朝刊に #UVERworld の広告が。
— 読売新聞社広告局 (@yomiojo) December 18, 2021
ニューアルバム「30」の収録曲 #EN の歌詞が掲載されています。
今の時代を生きる私たちへの強いメッセージをご覧ください。 pic.twitter.com/OtAAZqaADa
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 このnoteが、あなたの人生のどこか一部になれたなら。
