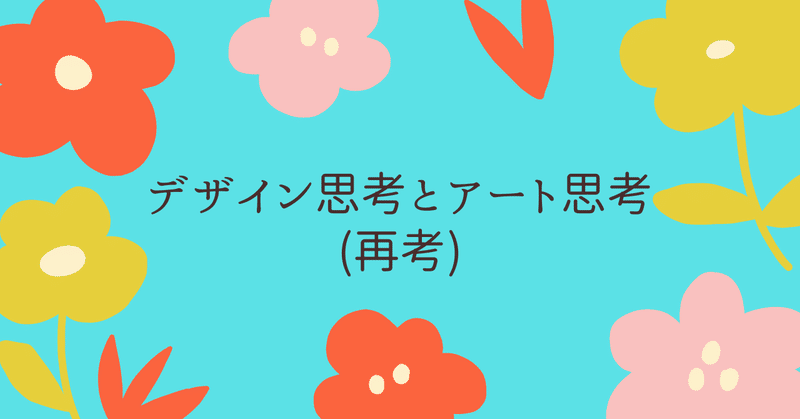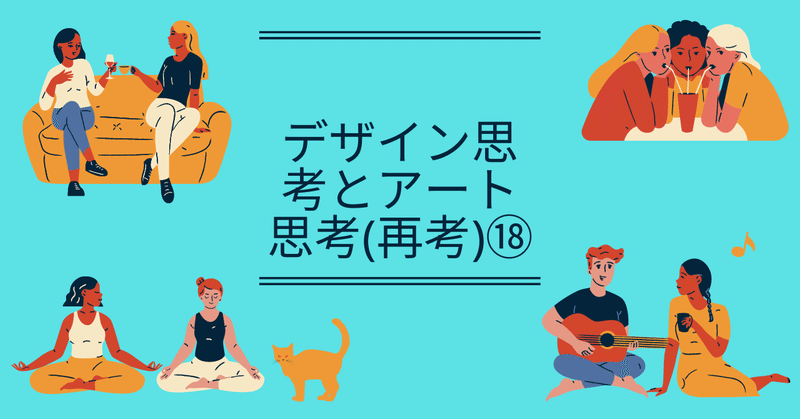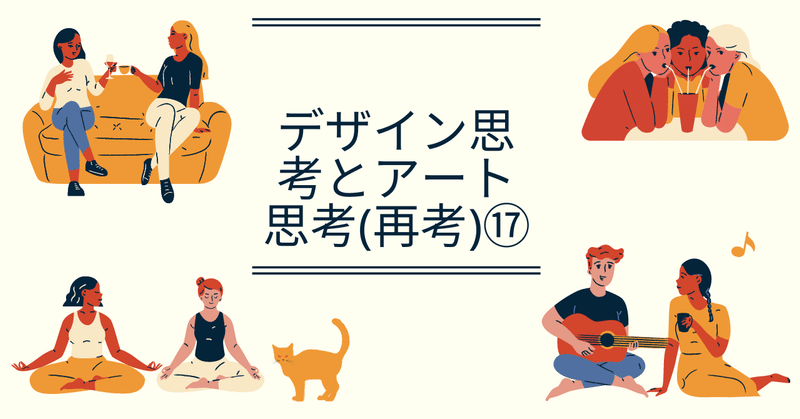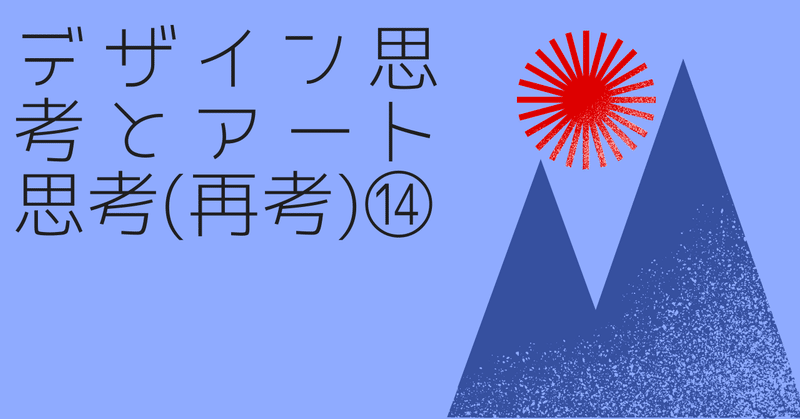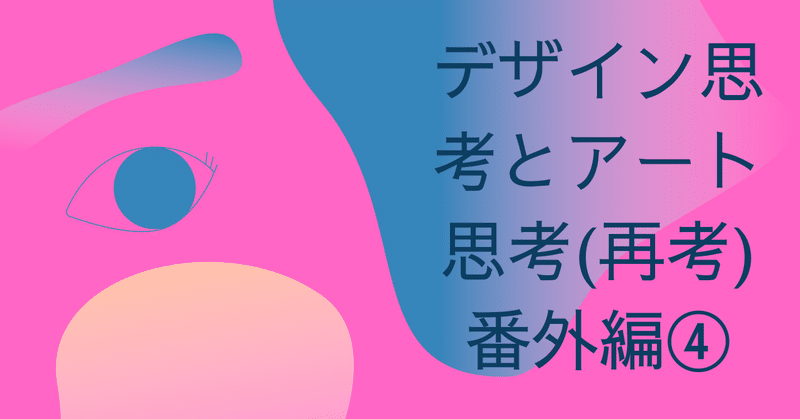#デザイナー
デザイン思考と組織文化PARTⅣ
本編⑱のところで見たように、Dums and Mintzberg(1989)やCooper, Junginger and Lockwood(2009)は、デザイン思考にとっての理想的な組織文化とは「組織全体にデザインの考え方が浸透した状態である」と述べているが、これは言い換えると、デザイン思考がロジカルシンキングのように当たり前のノウハウとして組織内で広く認識され、多くの人々がそれを使いこなすた
もっとみるデザイン思考と組織文化PARTⅠ
今回からは最後のテーマとして、デザイン思考と組織文化との関係について考えてみたい。本編⑧のところで述べたように、欧州ではデザイン思考とは、クリエイティブ・コンフィデンス(creative confidence)のことであるとの論調があるが、そのような理解の仕方は本当に正しいのであろうか。
そもそもクリエイティブ・コンフィデンスとは、個人が持つ創造的なマインドセットや思考パターン、あるいはそれ
デザイン思考とエフェクチュエーションの関係
ここでは「デザイン思考と起業行動」に関して、もう少し寄り道してみたい。本編⑬~⑯でも見たように、近年、デザイン思考はアジャイル開発やリーン・スタートアップなどと共に語られることが多くなっている。また、その結果として、デザイン思考は起業やベンチャー創出のためのアプローチとして注目されるようになっており、エフェクチュエーション(effectuation)との関係についても関心が寄せられるようになって
もっとみるデザイン思考と起業行動 PARTⅡ
前回述べたように、欧州勢の先行研究にいうスプリント(以下、広義のデザイン思考とする)とは、創造的な問題解決(以下、狭義のデザイン思考とする)にリーン・スタートアップやアジャイル開発などの考え方が足し合わされた拡張された概念であるが、そもそも狭義のデザイン思考と、リーン・スタートアップやアジャイル開発との関係はどのようなものなのであろうか。先行研究には様々な見解が見られる一方で、それらの関係性につ
もっとみるそれぞれの思考法の間で重なり合うところ
拙著『デザイン、アート、イノベーション』ではどちらかと言えば、デザイン思考、デザイン・ドリブン・イノベーション(以下、DDIとする)、アート思考、それぞれの間にある「違い」にスポットライトを当ててきた。そこでは、デザイン思考は「あなた」に焦点を当てた(イノベーション創出のための)アプローチであるのに対し、DDIは「人々」に焦点を当てたアプローチ、アート思考は「私」に焦点を当てたアプローチであるこ
もっとみるインクルーシブデザイン
本編⑫では、デザイン思考の実施に際して、これまでターゲットとされてこなかった少数派の狭いニーズや、極端な行動をとる人々の深いニーズを優先的に探し出そうとすることがよくあると述べた。そうすることで、誰も気づいていないニーズ(指摘されて初めて気づくような潜在的なニーズ)や、今はまだ小さくても将来大化けする可能性のあるニーズを探り出すことができるためである。
このような“これまで排除されてきた人々