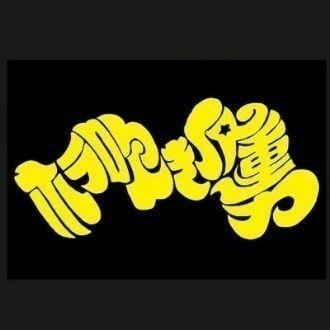2020年3月の記事一覧
私はなぜ昔のタモリを評価するのか
みうらじゅんが以前新聞で、自分で質問を考えて自分で答えるという連載記事をやっていた。
この中で「小説の登場人物が覚えられない」というものがあって、回答は「映画化されて自分の知っている俳優が演じる事を考えたらいい」だった。「ただし、俳優の選び方で原作と全く印象が違う話になったり、シリアスな話がシュールなお笑いコントになったりする可能性があります」(うろ覚え)ということだった。
とても解りや
自分の才能は隠れているものである
あの「ドラえもん」に登場するのび太が、いつも射撃とあやとり以外はダメなヤツと勘違いしている人(=あまり読まない人)には、「のび太の結婚前夜」で、のび太がオープンタイプのスポーツカーを乗り回しているのを不思議に思う人がいる。
でもこれ、「ドラえもん」を読み込んでいる人には不思議ではない。「ミニカー教習所」というエピソードでは、のび太は性格が変わったように、いや、本来の性格が出たかのようにオープ
1984(昭和59)年の「夏の氷カルピス」のCM
(この記事は拙ブログ「俗世界の車窓から」とほぼ同じ内容です)
1984(昭和59)年、カルピスのCMが斉藤由貴になる前年の夏(だと思う)、すごく印象的なCMが流れた。印象的というのは自分にとってなんだけど。
https://youtu.be/c1Kiq5dayIY
昭和を思わせる夏の海の風景、白い帽子にセーラー服を着て髪をおさげに結び(当時でも「少し懐かし」になっていた)、かき氷を持った
メモ 「オタク的とは何か」
・多分「マイナーな物事を掘り下げて調べたり取り組んだりする人」と「最新の(深夜)アニメ、ゲーム、マンガなどを追いかける人」の二種類の使われ方がある
理屈はよくわかるんだけど
鉄道関連の撮影会や運転会というやつがある。参加費を払って撮影させてもらう。払ったお金は鉄道会社とか保存活動をしている人の所にいく。理屈はよくわかる。
南部縦貫とか尾小屋とか、かなり面白い。行ったことはないが片上も面白そうだ。
ただ、時として「俺、なんでこんな所にいるんだろう」と思ってしまうイベントもある。
誰が悪いというのではない。大盛況の撮影会だからこそ、「俺が写真を撮って何になる
続 鉄道ブームと言っても
そういえば「日経レイルウェイ」とか「鉄道ニュータイプ」とかは出なかった。ホビージャパンやモデルアートから鉄道模型本が出たけれど、特に新しい部分があった訳ではないように思う。
誠文堂新光社も参入するものの、各種「ガイドブック」や「子供の科学」の経験を生かしきれず長く続かなかった。実際、「なんかイマイチ」の本だった気がする。
「アニメと鉄道」や「寅さんと鉄道」など、鉄道雑誌以外から出てくるよう
生まれる前に無くなっているものだから興味無いだろうというのは間違い
マーケティングみたいなものというか、単純に、趣味をやっている人を対象にした場合、「多分年齢的に接点が無いだろうから、興味も持てないだろう」みたいな考えは間違えだと思う。
自分自身、ブルートレイン目当てで買った鉄道雑誌に「足尾のフォード」、「南筑のブタ」、「根室の銀龍号」を見つけて興味が湧いた事があった。各車両、知らない人がいたら検索してね。国際的にはそんなに珍しくもないのには、もう一回たまげ
趣味は小さい「好き」の積み重ねでいい
よく趣味に関して、硬く考えすぎている人がいる。生きていきやすくするのが趣味なのに、難しく考えすぎなのかもしれない。
一番の原因は「既に存在する趣味業界の共通の価値観」とか、ひどいのになると「オレの正しいやり方」を押し付けてくるのがいるからだ。これでは生きづらくなるばっかりだ。
だから自分のおすすめは「何となくバスとかに乗って海とか山とかに行ってみる」とか「適当な本を読む」とかだ。第一歩は