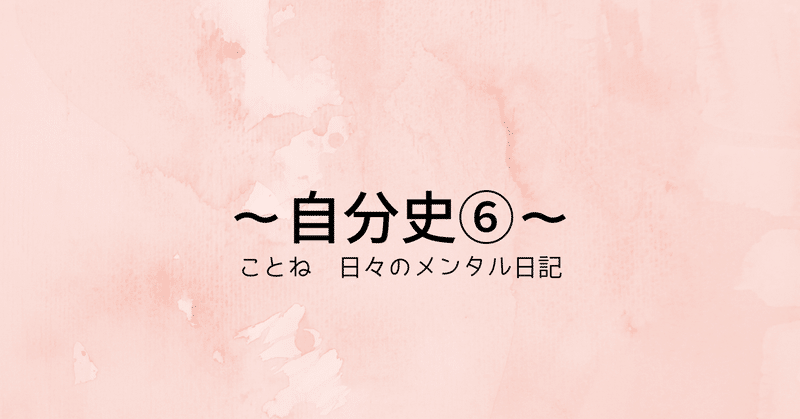
自分史〜⑥〜
マガジンに過去の投稿あります
少し戻って、仕事事情について書こうと思う。
何も成し遂げずに
以前投稿で少し触れたが、2022年あの当時28歳の影響で夜職を始める前に、少し契約社員をしていた時期がある。
室内で作物を育てる仕事だった。1つの大きな倉庫の中に色んな一般企業の障害者雇用の障がい者が働いている、という感じであった。一般企業の障害者雇用では'あるある'なシステムだ。
私はこの仕事を1週間ほどでやめた。研修期間中に。
理由は『雰囲気が好きではない。自分の実力に合わない。』だ。
これは私の感じ方であり障がい者を差別するわけではないが、障がい者しかいない建物に1日いるのが辛かった。それは「私も障がい者なんだ」と思いたくなかったからだった。
もっと健常者の仕事がしたかった。
そしてこの時期に夜職を始め、夜職の方がもちろん稼げるのでなんかもう嫌になって、やめた。
この契約社員を辞めたときに、その会社の上司に辞める日に言われた言葉。
『あなたは大学中退して、この仕事もすぐ辞めて、何も成し遂げていない。』
公務員
そして次に仕事をしたのが公務員であった。
私は公立学校の教職員だった。そこの事務補助をしていた。
なぜこの仕事を選んだかというと、自分が大学時代に教育学部であったくらいには学校で働きたかったからだ。学校の事務をするのが、大学1年生の私の夢の1つだった。
だからこの教職員の募集を見たときに「これだ」と思った。
面接と試験があった。
試験は1位だった。1位と聞くとすごいと思われるかもしれないが、この試験はただハサミで点線に沿って紙をくり抜いたりとか、プリントを指定された順に並べてクリップでまとめるとか、そういう試験であった。
面接は、何も考えずに挑んで、喋って帰った。でもこの面接で少し傷ついた出来事があった。病気についての話の時間、とある面接官に『つまり、あなたはかまってちゃんなんですね』と言われた。
その面接官に、のちにパワハラ(のようなこと)される。
公務員に無事になれて、嬉しい気持ちも数日で冷めた。
思っていた仕事と違った。その「違う」は1ヶ月1ヶ月経つごとに大きくなっていった。
人事課は何も言わない。説明が遅い。お役所と同じだ。
休みの仕組みや有給の仕組み、生理休暇や病休など、何も言われなかった。
私は働き始めて3週間たった頃に体調を崩して2日休んだ。でもそれが有給扱いだと知らないでいた。
それで休み明けに人事課の係長と部下が私の職場にわざわざ電車に乗ってやって来た。そして私は校長室に呼ばれた。
『これ以上休むと、懲戒処分になって名前も所属先も全て新聞に載る』
『教育委員会には記者クラブがあって、記者が常に張り込んでいるんだ』
色々と、淡々と、言われた。懲戒処分の長ったらしい規則の紙を渡されて、懲戒処分について説明された。
当時私は片道2時間かけて通勤していた。
この日、泣きながら帰って、家族LNEで両親に1通送った。
『もう無理。片道2時間はきつい。お金ないけど引っ越したい。』
結局引っ越したのだが、この係長の威圧的な言動がトラウマになり、『休んだら懲戒処分』が怖くて怖くて、2ヶ月休職した。
私の職場には私専門のジョブコーチのような人がいたのだが、その人がとても細かい人だった。印刷の1ミリのズレすら許さない人であった。
でも、それ以上に、私は『障がい者』という扱いをされているのが苦手であった。
「いつでもトイレ行っていいですからね」と言われたり、教育委員会の本部の人が見学に来ると「琴音さんはいつもこんなことをしてくれるんです〜」と私がただ印刷した用紙を、授業参観かって感じで本部の人に見せたり。
ジョブコーチがというよりも「教育委員会が」、『障がい者』扱いをすごいしていた。正月とお盆に教育委員会本部で「研修」があるのだが、それは5時間ひたすら折り紙であった。何が研修だよ。
少なくとも、私には合わなかった。
公務員の規則は窮屈すぎる。自由に過ごしたい私には合わない。
障がい者として扱われすぎいていた。そのように扱って欲しくない私には合わない。
仕事内容が私には低レベルだった。成長を感じられずこの仕事を続ける未来が見えなかった。
結局1年も続けられず、ずっとずっと係長の言葉がトラウマで、いつも出勤がプレッシャーで、辞めた。でも、これでよかった。
ちょっと後悔しているのは、普通に教員している先生たちともっと話したかった。
『先生方は忙しいから…』『私たちは教員じゃないから…』とジョブコーチにずっと言われていて、普段先生と話すのをやんわり禁止されていたり、せっかく先生たちから行事の打ち上げに誘われたのに行かせてもらえなかったりしていたから。
放課後の職員室が私は好きだった。先生方が放課後働いている姿を見るのが好きだった。かっこよかった。それだけは、この仕事について良かったこと。
今回はここまで。
次回はまたいつか。
琴音
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
