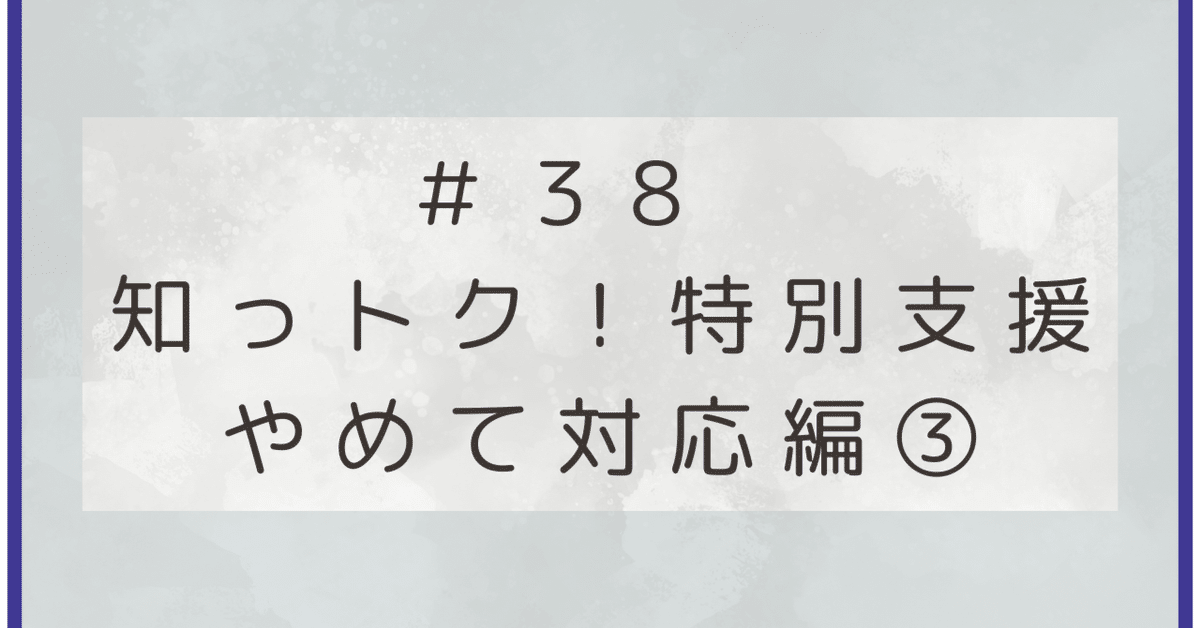
#38 特別支援教育:事例から学ぶ!子ども同士のトラブル解決法と「やめて」の重要性
今回は、事例紹介です。
Aさんが椅子に座ろうとして椅子を引いたとき、後ろの席でノートに何かを書いているBさんがいました。
勢いよく椅子を引いたため、Bさんの机に強くぶつかりました。
AさんはBさんの机に自分が引いた椅子があたったことに気づいていません。
B「A,やめて」
A「はあっ?」
と言ってから、Bさんの筆箱を床に投げつけました。
B「Aさんが何もしてないのに、私の筆箱を床に投げつけました。」
と担任に訴えてきました。
さて、どう対応していくとよいでしょう?
間違っても、いきなりBさんの話を鵜呑みにして、Aさんを注意してはいけません。これでは多数派擁護の学級経営となってしまいます。
詳しくはこちらを↓
まずは、Aさんに、Bさんの筆箱を投げた理由をききます。
T「どうしてBさんの筆箱なげたの?」
A「なんかわからないけど、やめてって言ってきたから、腹立って投げた。」
T「じやあ、Bさんはどうしてやめてって言ったの?」
B「Aさんが椅子を私の机にぶつけてじゃまをしてきたから言いました。」
A「じゃまなんかしてないし、ぶつけてもないし、うざっ」
T「ぶつけてないっていったけど、どんな感じで椅子をひいたかやってみてくれる?」
Aは、ゆっくり椅子をひいて座る。
C「そんなゆっくりじゃなかったよ。もっと勢いよくひいてたよ」
T「Bさんの机に椅子は当たってた?」
C「あたってた。」
と近くにいたCさんが言います。
T「じゃあ、知らないうちに引いた椅子がBさんの机にあたったかもしれないね?」
A「まあ、あたったかもしれない」
T「はっきりとは覚えてないけど当たったかもしれないんだね。でもわざとやったんじやないよね。Bさんは、わざとじゃなくても椅子が当たったから書いてるのをじゃまをされたと思って、やめてと言ったんだと思うよ。でもそれは、誤解だね。いずれにしても椅子が当たったのであればわざとじゃなくても一言ごめんって言ったほうがいいよね。」
A「ぶつけてごめん」
T「Bさんも誤解して、やめてと言ったことは謝った方がいいよね。」
B「やめてって言っちゃってごめんね」
Aさんは、机といすの距離感がつかめなかったのです。空間認知に課題のある子であることがわかります。このような子は、よく友達とぶつかります。
うまく自分のしたことや考えたことを言語化できないことも多いので担任が汲み取って通訳してやる必要があります。
特に、支援を要する子どもは、相手から「ごめん」という謝罪の言葉がないと、許すことができません。許さないというよりかは、状況を理解できないといった方がよいかもしれません。だから、面倒ですが、お互いに「ごめん」と言わせる行為は必要です。間違っても、「Bさんの表情みてごらん、強く言ってしまったこと反省しているじゃないか。だからもう許してあげなさい。」などと言ってはいけません。ASD傾向の強い子であれば、この言葉の意味は全く理解できません。お互いが理解できるユニバーサル用語として「ごめん」を使うのです。少数派(支援要する子ども)の意見に耳を傾けて対応していかないと学級は荒れるか、もしくは不登校やいじめが起きやすくなります。
大変ですが、新学期始まって2ヶ月近くはこのようなトラブルをいくつも丁寧に処理することが大切です。
支援を要する子どもが多い場合はなおさらです。
そのうち、クラスの子の中に、担任と同じ目線で、通訳できる子がでてきます。そうしたら、担任がでていかなくてもトラブルがおさまるようになります。
支援要する子どもたちへの対応を、学級経営の中核と位置付けていけば、一学期後半には、居場所のある空間となり、落ち着いて学習できる集団に育ちます。
それまでは、辛抱です。根気よく丁寧に対応していきましょう。
参考になる方がいたら幸いです
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
