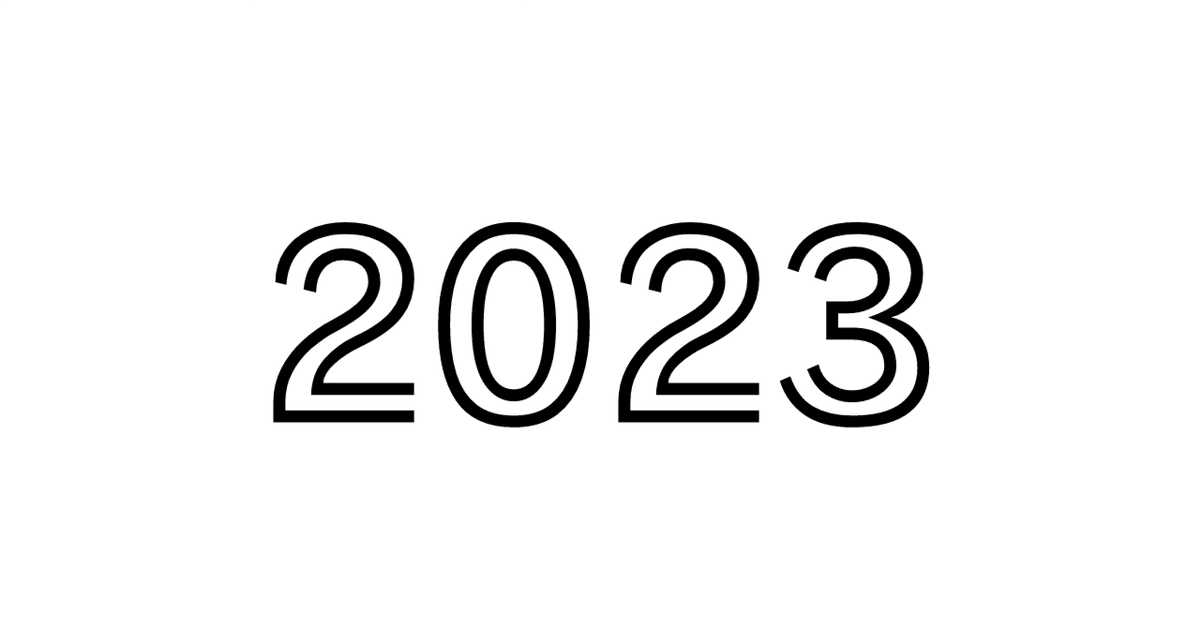
【2023年ふり返り】ああ「100周年」が過ぎていく 大震災、虎ノ門事件、快楽亭ブラック
ああ、2023年が終わってしまう。
今年、書きかけて完成しなかった原稿のなかから、今年でなければ意味がない記事を、メモ風になるが、いちおう形にしておきたい。
*
今年2023年は、3つの「100周年」が重なった年だった。
100年前と言えば、1923(大正12)年だ。
1923(大正12)年
9月1日 関東大震災
9月19日 (初代)快楽亭ブラック死去
12月27日 虎ノ門事件(のちの昭和天皇が狙撃された事件)
すなわち今年は、
関東大震災100周年
初代ブラック没後100年
虎ノ門事件100周年
の年だった。
三題噺のようだが、この3つを関連づけて記事にしたかった。
関連があるのである。
「朝日・毎日」時代の始まり
そのためには、もう一つの「100周年」をくわえなければならない。
それは、
「朝日・毎日時代」
の100周年だ。
今年は、いまの「朝日・毎日」中心のメディア体制ができて、100年目の年であった。
もう「朝日・毎日」の時代ではないよ、と言われそうだし、新聞の部数だけを見ればそうだが、テレビなどふくめた大枠はそれほど変わっていない。
明治に起こった多数の独立系メディアがしのぎを削っていた時代から、少数寡占のメディア体制になった。その画期が100年前だった。
関東大震災で、東京に基盤をもつ「読売」「報知」などの新聞社が壊滅状態になったため、大阪発祥の「朝日・毎日」がメディア業界を席巻した。そのときできた業界構造が、いまに続くのである。
東京大学の関谷直也准教授が「関東大震災とメディア」で書いている。
なかでもメディアとして最も大きな影響を受けたのが、震災当時の主たるマスメディアの新聞であった。当時は、『東京日日新聞』『報知新聞』『時事新報』『東京朝日新聞』『國民新聞』という東京5 大新聞が大きな部数を誇っていたが、他にも様々な新聞社が数多く存在した。
関東大震災により、多くの新聞社は壊滅的な打撃を受けた。被災した新聞社は新聞活字を収集することと、印刷所の確保に奔走した。だが、取材を継続することや、東京近辺で新たに印刷所を確保することは容易ではなかった。その結果、この大震災を原因として、5 大新聞のうち、『報知新聞』(『読売新間』に合流)、『國民新聞』(現『東京新聞』)の部数は大幅減となり、その勢いを失っていった。そして、『時事新報』『やまと新聞』『中央新聞』『萬朝報』など、明治期から続く伝統のある新聞が消えていく契機となった(大広、1994)。
その中で、大阪出自の2つの新聞社が台頭してくる。大阪毎日新聞社の傘下にあった『東京日日新聞』(現『毎日新聞』)と大阪朝日新聞社の傘下にあった『東京朝日新聞』(現『朝日新聞』)は、関西の支社や他の新聞社と協力して情報収集や印刷を行うことで、この危機を乗り越えたのである。
実際には、朝日・毎日は、東京勢の弱みにつけこみ、あくどい商法で覇権を握る。
そのことは、以前書いたことがある。
虎ノ門事件・難波大助と「読売新聞」
当時の皇太子、のちの昭和天皇が狙撃された虎ノ門事件と、関東大震災の関連は、ある程度知られていると思う。
関東大震災時の亀戸事件(社会主義者10数名が警察と軍に殺された事件)が、犯人の難波大助を憤慨させ、動機の一つになった。
そのことは、難波の官選弁護人で、社会活動家・衆院議員の松谷与次郎が書き残している。(昭和6年刊「世界犯罪双書」)
面白いのは、もう一つ、犯行のきっかけになったのが、難波が1923年のメーデーの日に読んだ、「読売新聞」の記事であることだ。それは大震災の4カ月前で、「読売」はまだ健在だった。
上記・松谷が記した、難波の供述によると、以下のとおり。
難波は、住んでいた現在の江東区から、銀座にあった新聞社を通って、メーデー会場の芝公園に行く(仮名遣いは現代風に改めた)。
難波大助の供述
大正十二年五月一日のメーデーには私は深川区富川町(現・江東区森下)の第二煙草屋(木賃宿)におりましたが、同日七時頃友人と共に徒歩にて坂本公園に参り、その日の新聞を読んでおりますと、自由労働者の群れが赤旗を掲げ、メーデーの歌を唄うて公園に立ち寄るのに出会いまして意気大いに揚(あが)り、徒歩にてその行列に従って行きました。読売新聞、朝日新聞、国民新聞各社の前を通り芝公園に入りました。その日の新聞には二三千も集まるであろうということが書いてありましたが、実際には一万人以上の労働者が集まっておりました。
私も一つ演説してみようと思った時、ふとその日の読売新聞に出ていた記事を思い浮かべました。それは日本のある富豪が巴里(パリ)で亡命中のレーニンと話したところ、レーニンはそのとき日本を倒すには十億の金(かね)と十人の血で沢山だと申したところ、その富豪は時のたつのにしたがい、その外(ほか)にレーニンの言ったことで当ったことがあるので恐れを抱き、明治神宮にて国家安泰を祈るため神灯を献じたという記事でした。私は十人の血ということに大いに感じましたので、それを演説にしようと想をまとめ・・
このときの難波の「演説」は、官憲に妨害されてできなかったのだが、このメーデーの日の読売新聞に載ったレーニンの言葉「十人の血」が、難波の脳裏にとどまり、彼の「過激思想を刺激した」ことは、松谷も記している。
この難波が読んだ読売の記事を確認していないが、レーニンがパリにいたのは1910~12年ごろで、そのころに会った日本人の話と思われる。
なお、この1923年のメーデー時点では、読売新聞本社は銀座一丁目にあったが、その3カ月後に銀座三丁目に移転する。
読売新聞ホームページの社史にこうある。
1923年(大正12年)8月19日 読売新聞社、本社社屋を、現銀座一丁目から、東京・京橋区西紺屋町(現・中央区銀座3丁目)に移転
1923年(大正12年)9月1日 関東大震災で本社社屋が炎上
すなわち、移転から半月たたず、読売の新しくできたばかりの本社は崩壊するのである。
虎ノ門事件と皇室の「自閉」
この虎ノ門事件の影響として、あまり語られないのは、開かれようとしていた皇室が、これで閉じてしまったことである。
その2年前、1920(大正10)年に、のちの昭和天皇、皇太子裕仁親王は、半年におよぶ欧州訪問をおこなった。
これは、当時としては非常に大きな出来事だったが、メディア史上も重要だった。
東京日日新聞(のちの毎日新聞)が欧州訪問に同行し、それを映像におさめて、劇場で一般公開したのである。
この映画は大成功をおさめた。ほとんどの日本人にとって、「動く皇族」を見る初めての機会だった。
ぼうず頭で日本を発った皇太子裕仁は、帰国時には長髪になっていた。当時は大正デモクラシーで、リベラルな雰囲気があり、皇太子もその雰囲気を浴びていた。
欧州訪問後も、皇室はメディアを皇居内に入れて、皇族を撮影させていた。ロシア革命(1917年)で皇帝ニコライ二世が家族と共に処刑されたのを見て、皇室も、国民に親しまれなければならないと考えただろう。
しかし、皇室と国民の距離を縮めようとする、そうした動きは、この「第二の大逆事件」で止まってしまうことになる。
「ブラック新聞」と快楽亭
では、初代快楽亭ブラックとの関連はどうか。
初代快楽亭ブラックは、大震災の衝撃のなか、脳卒中で白金の自宅で亡くなる。64歳だった。

初代快楽亭ブラックは、日刊新聞「日新真事誌 (にっしんしんじし)」を発行したオーストラリア人(当時はイギリス領なのでイギリス人)、ジョン・レディー・ブラック(1826ー1880)の息子だ。
「日新真事誌」は、東京で発行される日本初の日刊新聞になるはずだったが、おそらくは政府の画策で、「東京日日新聞」にその座を譲らされた。
いずれにせよ、ジョン・レディー・ブラックは、日本に「新聞」というものを根付かせた、メディア史上の「偉人」の一人である。
大佛次郎が1947(昭和22)年に「新大阪(新聞)」に連載した「幻燈」は、維新で将来の目標を失った旧士族の若者が、当時「ブラック新聞」と呼ばれた日新真事誌の記者になる話だ。
主人公が、銀座のブラックの新聞社を訪ねると、そこにはブラックと談笑する福沢諭吉がいた、という場面が描かれている。なお、「日新真事誌」本社は、のちの服部時計店、現在の銀座和光である。
しかし、ジョン・レディー・ブラックの息子は、メディアにはむかわず、青い目の芸人になる。
今年、初代の100周忌供養をおこなった二代目快楽亭ブラックは、以下のとおり、初代を「偉人の道楽息子」だと語っていた。
今年は、9月19日が初代快楽亭ブラックの没後100年ということで、8月15日、日本橋の会は、昼夜ともに初代快楽亭ブラック没後100年「ブラック祭」ということでやらせていただきます。
初代はどういう人かというと、まあ早い話が日本の外人タレント第1号でございます。明治から大正にかけて活躍した人で、グローバル化した今と違って、ついこの間まで日本は鎖国をしていた。その直後に日本にやってきて、外国人が流暢な日本語をしゃべるのだから、もうこれだけで話の内容はともかく、もうただ日本語を喋ってるというだけで一世を風靡した人でございますね。
父親が、江戸時代は瓦版しかなかったのに、新聞というものを発行して、日本人に新聞というものがあるんだよというのを教えた偉人でございまして。そのせがれのブラックは、父さんは明治の偉人なのに、芸人になっちゃうぐらいですから、まあ落語によく出てくる道楽者の若旦那でございますねえ。そういった性格でございまして、あの有名な初代三遊亭円朝の門人となって活躍をしたんでございます。
外国で売れている小説を翻案して、それを発行したり、噺にしたりしました。犯行現場に残っている犯人の指紋、この指紋っていう概念を日本で初めて教えてくれたのがこの初代快楽亭ブラックなんですね。「岩出銀行血潮の手形」という、指紋から犯人が割り出される噺を、イギリスの小説を翻案して作っております。
それから、レコード録音を日本に導入いたしまして、明治時代の名人の音源を、残念ながら名人と言われた初代三遊亭円朝(1880没)の音源は間に合わなかったんですが、それ以降の名人の音源、もちろん初代快楽亭ブラックの音源も残っております。今我々がCDレコードで落語を楽しめる、これ全部初代快楽亭ブラックが元でございますから、そういった意味で落語界に大変に貢献をしてるんでございますね。
二代目快楽亭ブラック★初代快楽亭ブラック噺&『もう半分』枕(7月3日)
私自身は、初代快楽亭ブラックの生き方は、日本のメディア事業でつまずいた父親の「屈折」を引きずっていたのではないかと感じている。
そして、その反骨の精神は、二代目快楽亭ブラックが引き継いでいる。
ともあれ、私は、100年前、1923年の東京を舞台に、
・皇太子摂政宮裕仁
・初代快楽亭ブラック
・難波大助
の3人が登場する物語が書けないか、とぼんやり考えていた。
この年のメーデーの情景から始まって、関東大震災、虎ノ門事件まで。
もう一人、だれか当時の新聞記者を狂言回しにして、この近代日本の転換期を描けないか、とか思ったのだ。
思っただけで、何も書かずに、2023年は終わってしまった・・
しかし、2024年は、難波大助の死後100年でもある・・。
1924(大正13)年
2月25日 正力松太郎が読売新聞を買収
11月15日 虎ノ門事件の難波大助処刑
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
