
コロナ禍で音楽家を辞めて一般企業に就職→異例のスピード出世、それでも夢を諦めきれなかった私が取った行動とは? ヤマモトダイキ~過去編②~
前回までのあらすじ
ジプシージャズという激レアジャンルにはまる→高卒認定試験に合格し高校を自主退学→10代で音楽学校に通いながら初めてプロのバンドで演奏を経験→しかし音楽家としての独立は難しく、地元福岡へいったん帰ることに
2009年 福岡
福岡へ帰ってきた私は、19歳にして「一旗揚げようと上京したが、夢に破れて地元へ帰ってきた中年」の気分でした。
そんな私になんとか社会と繋がりを持って貰いたかったのか、両親はなにかと外部との接触機会を設けようとしたり、アルバイトをさせたりしました。
しかしどれも長くは続かず、私は当時まだ真新しかった言葉で指すところの所謂「ニート」状態になりました。
夜中にPCでかつてのように音楽を聴き漁ったりする時間が以前より長くなったせいか、それとも親の活動時間帯に起きていることが何となく気まずかったせいか、私の生活は昼夜逆転し、部屋にこもりがちになりました。
地元の友だちなどは勿論おらず、また孤独な日々が始まりました。
八木輝明教授との出会い
その頃の私の興味は、音楽よりもむしろ政治や哲学、そして文学にありました。三島由紀夫や福田恆存といった、単に作品を世に発表するだけでなく、人文学系の知に通じ、国民全体を啓蒙していくような、昭和の中ごろに遂に途絶えてしまった旧き良き「知識人・文化人」としての作家・文学者像に強い憧れを持っていました。
私の興味が学問の世界にあることを感じた母親は、当時ちょうど慶應義塾大学の通信課程に在籍しており、その母を通じてドイツ近・現代文学とドイツ史を専門とされる慶應義塾大学経済学部の八木輝明教授とよくメールのやり取りをするようになりました。
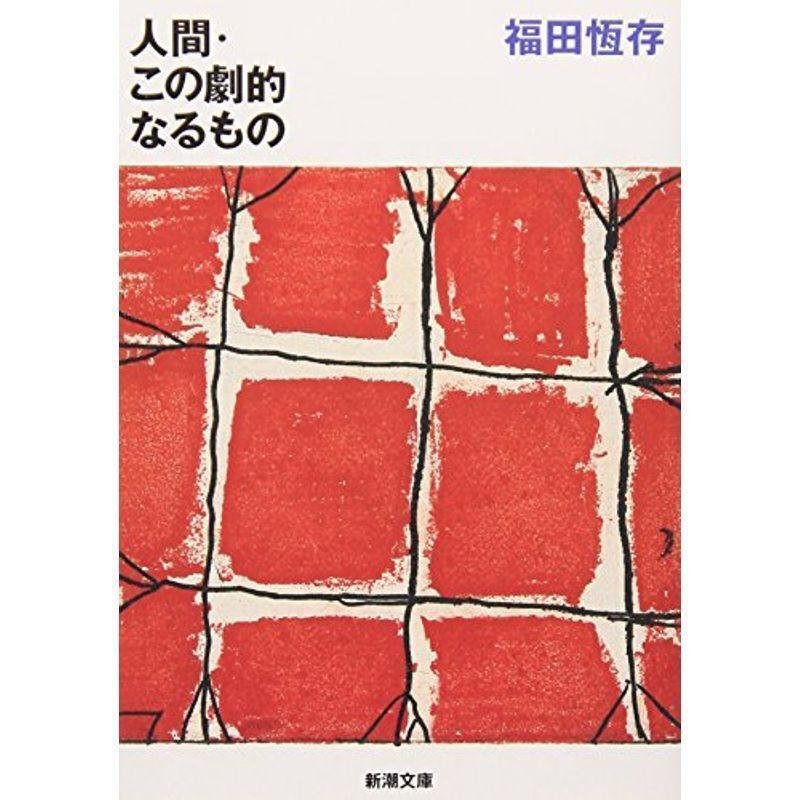
それは外から見ると「ニートと大学教授の文通」という大変奇妙な関係性でした。
私は八木先生に時候の挨拶もそこそこに時事問題や当時の国際情勢についての持論を述べ、それどころか生意気にも先生の専門領域である文学・哲学についても私見を書き連ねたメールを送り、先生は暖かくそれに返信を下さり、同じ第二次大戦の敗戦国であるドイツと日本の今後の在り方についてや、ニーチェ、ゲーテ、そしてヘルマン・ヘッセと何人かのドイツ近・現代作家について私に手ほどきを加えてくれたのでした。
確信的な会話は何もなく、自然と「学問上の師弟関係」のようなものが結ばれていったのを覚えています。
先生とはメールのやり取りだけでなく何度か会食もし、会うたびに私の事を「将来が楽しみだ」と褒めてくれるので私は先生が大好きでした。

現代ドイツ文学界の重鎮マルティン・ヴァルザーによる、文豪ゲーテ〈最後の恋〉といわれる文学史上の実話をもとにした長編小説。
その後、先生の退職を機にやり取りが疎遠になったのち、母を通じて先生が鬼籍に入られたことを知らされました、当時の孤独な私の魂を救ってくれた先生の墓にいつか手を合わせたい、一言御礼を申し上げたいと思いつつも、私は慶應義塾大学の学生でもなく部外者ということもあり、なかなかきっかけが掴めずにいます。この場を借りて先生や先生のご家族へ感謝を述べたいです。
國學院大學へ入学
学問への興味を捨てきれなかった私は、よくある「モラトリアム期間の延長」や「就職の為」「皆行ってるから」などという動機は一切なく「いずれ世界へ出た際に、自分の育った国の文化やルーツを説明できるようになりたい、その為には國學院大學が適当であり、今から勉強すれば間に合うので大学に行かせて欲しい」と理路整然と述べて親に援助を願い出ました。
意外にも両親はこれを快諾、喜んでいた理由としては「高校を辞めて家を飛び出した時はどうなるかと思ったけど、2年遅れでようやくまっとうな進路を選んでくれた」といったところだったろうと思います。
しかしその頃の私はジャンゴ・ラインハルトと三島由紀夫という絶対に両立し得ない二つの存在が自分の中で日増しに大きくなっていく分裂症のような感覚に悩まされており、将来の展望などほぼないに等しい状況でした。
大学で初めて人生を謳歌する
そろそろタイトルの本題に入りたいので私の大学時代については端折りながら書いていこうと思いますが、結果として國學院大學で過ごした日々は。私にとって初めて居場所を得た人生の春でした。
大学というのは「きちんと授業に出て学問をしていて、人に迷惑を掛けない限りであれば、たいていの個性は受け入れてくれる理想的な空間」でした。

私は春・秋は着流し、夏は浴衣、冬は着流しにインバネスコートと革手袋という出で立ちで毎日和装で通学し、演劇部に入り戯曲を書くようになり、自分では「和装倶楽部」という部を立ち上げて、毎週末は仲間たちと和装で川越に出かけて過ごす日々を送りました。
「毎日和装で大学構内をうろついて、どうやら週末はジプシージャズギタリストとしてライブ活動をしているちょっと変わった人」として同期や後輩たちの間で知られていました。とにかく、趣味全開でした(笑)

大学卒業後、ほんの一瞬「音楽収入だけで生活」することが叶う
卒業が近づくと、毎日のように政治や文学や哲学について熱い議論を交わしていた仲間たちも、名前を聞けば誰もが知っている大企業にどんどん就職が決まっていきました。
在学中、大使館街の広尾にあるイタリアンバールでアルバイトをしていた経験から私は英語が喋れたので(客はほぼ欧州・中東の大使館職員でした)、六本木にある外資系のギタースクールで講師をしながら、週末や平日夜は都内のホテルバーなどで演奏の仕事を得ており、それにプラスして自分個人のレッスンやライブ活動の収入があり、なんとか音楽による収入だけで生活をすることが出来ていました。
教務課から卒業後の進路を問う電話が来た際は、少し自慢げな口調で「ミュージシャンです」と答えたのでした。
コロナで音楽の仕事を失い一般企業へ就職
音楽の仕事が上手く回っていたのも束の間、すぐにそれだけでは生活できなくなり、私は友人のベーシストから(定時前に終わることも多く、シフトも自由で音楽活動と両立しやすい)と聞いていた警備員のアルバイトを始めました。
この時点で私は(誰かが元締めとなっている仕事の下請けを自分の収入の柱にしていると、急にその仕事がなくなった時に対処できない)という教訓を得ることになります。
2021年、やがて都下一帯にコロナによる緊急事態宣言が発令され、音楽の仕事はほぼ失われます。私はこれでついに(週末音楽家のフリーター)になったのでした。
この時の私はライブもギターの練習も思うようにできず、雨の日も、雪の日も、猛暑日も、毎日中央区晴海のオリンピック選手村の建設現場に警備員として立ち続けました。一日12時間の立ち仕事で、帰宅して別のことをする体力はかけらほども残っておらず、酒に酔うことで明日が来るのを早めるような毎日でした。

きつい、汚い、危険、3Kと呼ばれる類の仕事でした。辛いときはStardustの美しいメロディと歌詞を、誰にも気づかれないほど小さな声で歌いながらやり過ごしました。
警備員のアルバイトに慣れてきたころ(ウチで営業をやらないか)と正社員に誘われました、私は大学時代から交際の続いていた女性と婚約したばかりで、結婚の為にも安定した収入が必要だったので二つ返事でその誘いを引き受け、人生で初めてスーツを仕立てました(といってもイージーオーダーですが)
異例のスピード出世
これを読んでいる方が「警備会社の営業」と聞いてイメージが沸くかどうか…ざっくりと言ってしまえば私の場合は建設現場や施設の責任者に防犯カメラや警備サービスを提案営業する、というような内容の仕事でした。
私は飛び込み先の建設現場の監督に大声で怒鳴られても「これはタイミングが悪かったか会社の商材が批判されているだけだから私自身は傷ついたり動揺する必要はない」と割り切って考える無限のタフネスと、業界紙に載っていた会社の番号リストに当てずっぽうで電話営業していくつも見込み案件のアポを取る運の良さ、そしてパソコンが苦手な元役員の部長のエクセル仕事や会議資料作りを裏で代行して恩を売り、代わりに彼を通じて上層部に自分の昇進を早める口添えを頼むような、強かな政治力を発揮しました。
結果、私は入社して1年半で課長に抜擢され、月40万と歩合給を貰うようになりました。当時の業界の相場や景気を思えば破格の待遇でした。
こんな風に書き過ぎると、まるで本当に運が良かっただけのように思われるかもしれませんが、一応、私なりの仕事の流儀というものがあり、真面目に正攻法で取った契約もありました。
上手く説明できるかわかりませんが、
まず、身だしなみはいつも完璧に整えること。
とにかく初心のうちは真面目に、誠実に、マニュアル通りに、当たり続ける。リピーターになってくれる大口のお客さんを二三見つけたら、それらを業績のベースにして安心できる状況を作ったうえで、日々の業務の色々なトライ・アンド・エラーを行う、これらのサイクルを繰り返し、顧客の課題を見付ける提案能力を高め続ける、というものでした。
相手の役職・年齢や性格、現場での働き方を熟知していれば、どの時間帯に電話をかければ相手の仕事を邪魔せず気分良く出てくれるか分かったし、高齢の担当者がガラケーからスマホに変えたばかりで初期設定に困っていたのを助けた御礼に防犯カメラを買って貰ったこともありました。
そうやって時にはデータが、時には情が、それぞれ功を奏することもある、正解のない人対人の仕事でした。
定量化できないものを無理矢理に定量化し、それを効果測定する過程が楽しくもありました。
これは「演技」だから いつか音楽家に戻れる
なんとなく、音楽以外のコミュニティに身を置いているときの自分に「目の前の相手や属している組織が求める人間」を巧みに演じているような感覚が常にあり、会社での出世はあくまで営業職という「演技」がうまくいっているような感覚でした。「演技」だからこそ仕事の辛い面にも耐えられたのかもしれません。
そういった考えの根底にあったのは「自分は音楽が本分だから」という認識でした。
大学卒業→就職→結婚と、ライフステージを経る間も、ずっと音楽活動だけは辞めずに続けていました。
しかし、最初は子どもの頃から変わらぬあの根拠のない自信に裏打ちされて「今は昼の仕事もしているが、そのうちチャンスをつかんで音楽家として成功するだろう」と思っていたのが、段々「演技」の自分が本当の自分にすり替わっていくような不安を感じていました。
それに、顧客には夜の現場で働く担当者もいて、深夜に「防犯カメラが動かなくなった」とクレームの電話対応に追われることもあり、確実に生活が蝕まれていました。
課長の次は支店長、その次は部長、そして役員、常務・専務・社長。
あのまま進めば更に上に行けたかもしれません、しかし同時に「ここから先へ行くには仕事=人生というレベルの犠牲が必要になる」という険しい感覚も確かにありました。
妻「ああ、悔しいなぁ」
ある日の朝の事でした、リビングで出勤前に慌ただしく朝食を済ませながら、テレビをYoutubeに接続して、私の憧れのギタリストRocky Gressetの演奏する「Groovin High」の映像を観ていると、妻が「悔しいなぁ」と呟いたのでした。
イマイチ文脈が読めなかった私が「どういう意味?」と問うと
「だって、悔しい、あなただって本当だったら今頃こうしてRocky様みたいにバリバリギターを弾いて活躍しているはずだったのに…」
そういう妻の表情は真剣そのもので、目に涙さえ浮かべていました。
「そういう意味か、ありがとう。でも、僕も夢を諦めたわけじゃないよ」
なんとなくはぐらかすような感じで家を出たあと、私は仕事が殆ど手につかなくなりました。
自分が夢から遠ざかっている事を、自分の愛する人が心の底から悔しがっている、こんなに想ってくれる人が側にいて、自分に噓をついて生き続けて良い訳がない。
もう演技はやめよう。
妻に「私を養うためにあの人は夢を諦めた」と思われたくない。
本当になりたかった自分を、もう一度目指してみよう。
私はその日のうちに会社に辞表を提出しました。
続く
いいなと思ったら応援しよう!

