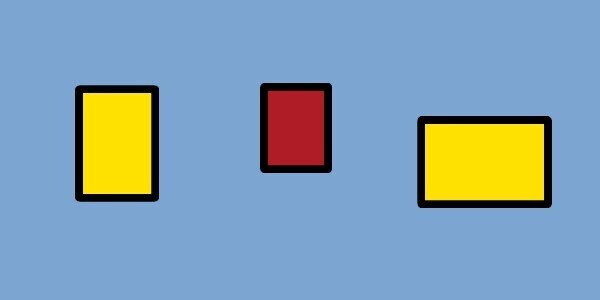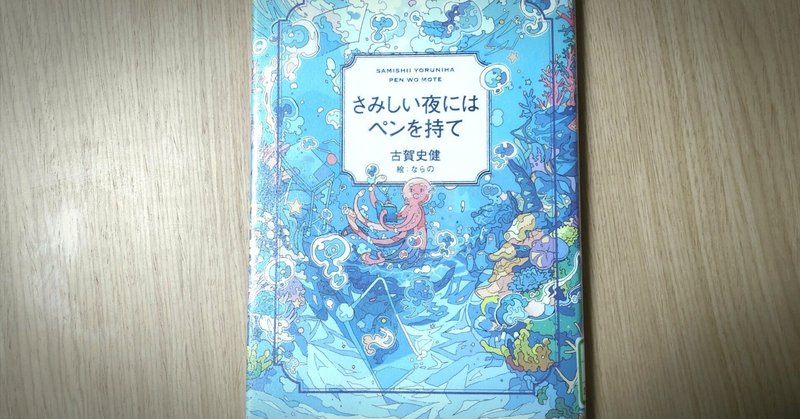#徒然日記
『じぶん時間を生きる』佐宗邦威
図書館で予約して、だいぶ待ってようやく順番が来ました。
コロナを機に(ほかにも色々重なって)東京から軽井沢へ移住した佐宗さんが、内的要因による変化(本では「トランジション」と呼んでいます)を語った本です。
まだ途中ですが、面白いなと感じた箇所を。
この感覚は、自分でも感じたことがあります。
自分ではうまく言葉にできなかったけれど、本に明文化されていてスッキリしました。
たぶん、自分がうまく言語化
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』アンディ・ウィアー
数日前に下巻を読み終わりました。
専門用語が難しいところもあったけれど、長い映画を見終わったような読後感で、宇宙に行って帰ってきた気分でした!
主人公の男性は気づいたときには見たこともない宇宙船のようなところにいて、なぜか記憶が途切れている…という場面から始まるストーリーですが、読み進めていくと過去と交錯しながら話が展開して、彼がなぜここにいるのか、いまどういう状況なのかが分かってきます。
途中
ゼロ秒思考も同じだった
最近読み始めた本『ゼロ秒思考』、ゼロ秒思考は何と同じだったのか?
それは『さみしい夜にはペンを持て』と同じだったんです。
どこが一緒かと言うと、頭の中のモヤモヤを書いて外に出してしまうところ!
メモか日記か、の違いはあれど、書いて頭をすっきりさせるのは王道なんでしょうね。
実際にゼロ秒思考のメモ書きを試していますが、書くことで頭は多少すっきりします。まだ始めたばかりなのでこれからもっとすっきりす
『さみしい夜にはペンを持て』古賀史健
ずっと気になっていた古賀史健さんの本。意外なきっかけで読むことができました。
末っ子が学校の図書室で借りてきたのです。
自分が本が好きなので、子供たちが本好きになれはいいなと昔はよく読み聞かせたり絵本を買ったりしましたが、大きくなってからは、みんな自発的に図書館や図書室に行かないので、子供が本を学校から借りてくる姿を見たのは小学生以来?そこまで遡らないかな。
それくらい久しぶりです。
どうして