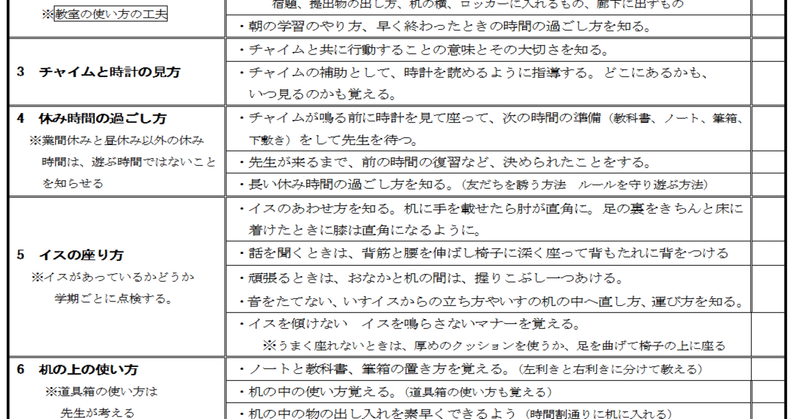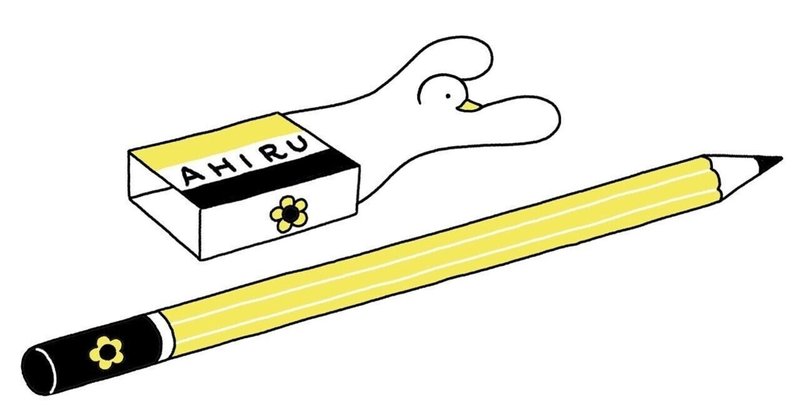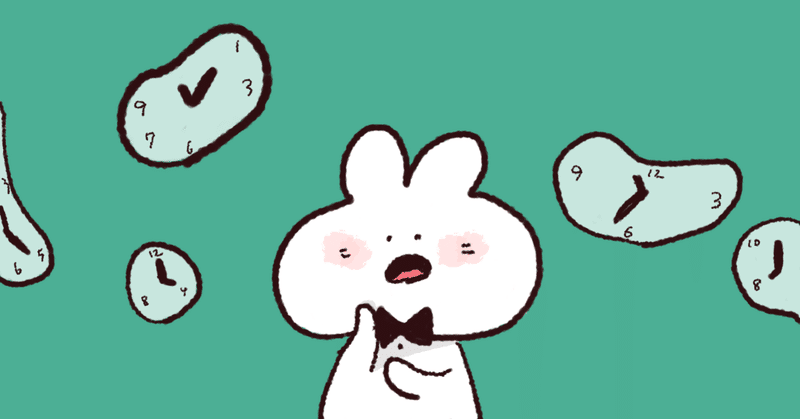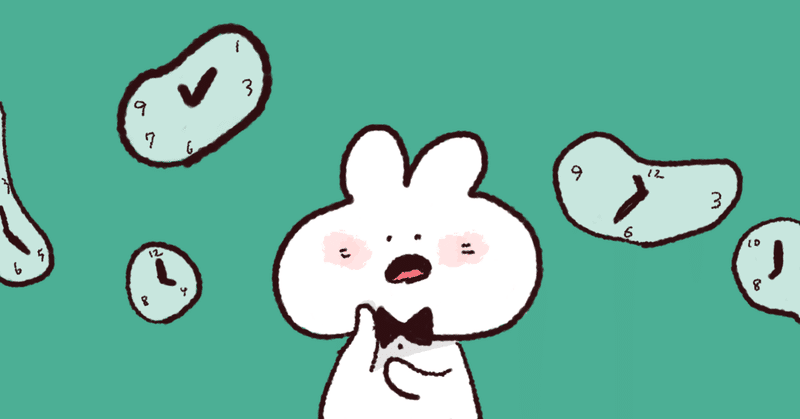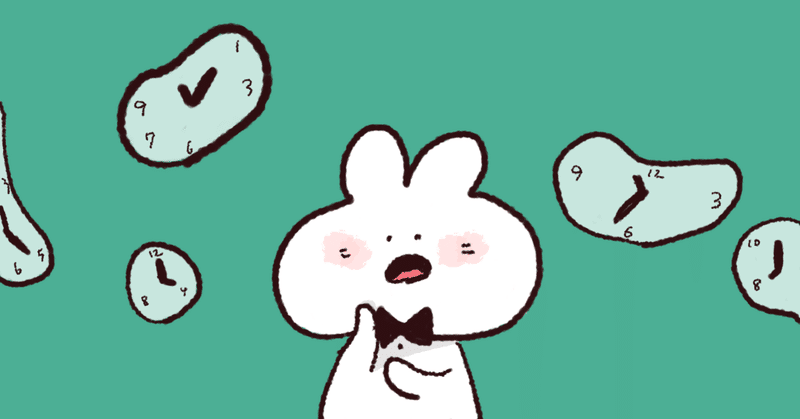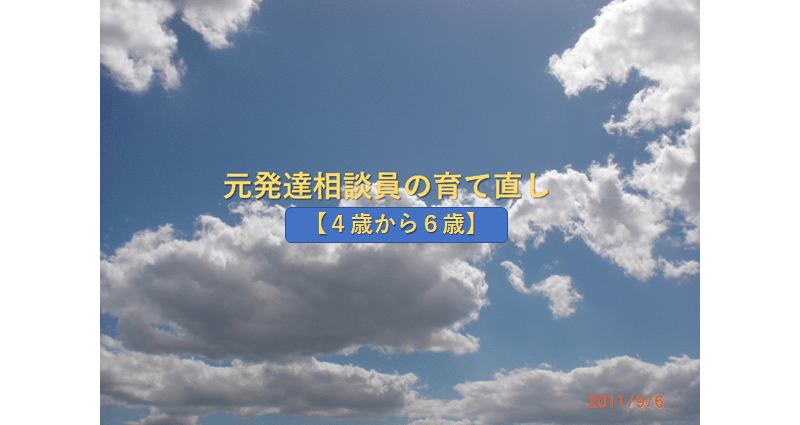
- 運営しているクリエイター
#発達凸凹
4歳から6歳までに『何をどう育てるのか』を、ものすごく具体的に書きます
「これから、何を書こうとしているのか」の説明編です。少し長いですが、読んでください。
1.4歳から6歳までの間に「どんなこと」を教えていけばいいのか 小学校に向けて、4歳から6歳までの間に「どんなこと」を教えていけばいいのでしょう。考えながら、子育てしているでしょうか?
平均タイプなら心配いりません。子どもから出てくる要求に合わせて子育てすれば、普通に小学校に適応するような子どもに育ちまま
『低学年で覚えて欲しいルールとスキル 30』の紹介
まず、『低学年で覚えて欲しいルールとスキル 30』の全項目を紹介しておきます。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備
2 登校から1時間目までの過ごし方
3 「チャイム」と「時計の見方」
4 休み時間の過ごし方
5 イスの座り方
6 机の上の使い方
7 筆記具の正しい持ち方 と 書くときの正しい姿勢
8
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備 今後の書き方の説明
この項目には、4つの補助項目が付いています。まず、それを紹介します。
1️⃣ 朝起きてから学校に行くまでのルーティーンを確立する。
2️⃣ 時間割や連絡ノート・お便りを見ながら、明日の準備ができるように
なる。
3️⃣ 筆記用具の準備ができる。
4️⃣ ランドセルへ、教科書、ノート、筆箱などをきちんと詰め込むことがで
きる。
Ⅰ家庭での学習準備その1から、1️⃣の【解説】そして、Ⅰ
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備 その1
1️⃣ 朝起きてから学校に行くまでのルーティーンを確立する 【解説】
発達の凸凹タイプは、自分の思いを優先させます。そのため「日常生活のルーティーン」を日によって変えます。つまり「日常生活のルーティーン」が定まらないということです。だから、保護者が「日常生活のルーティーン」を確立するのを手伝ってあげないといけません。
子どもにとってよい日常生活のルーティーンは、夜9時までに寝ることに始まり
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備 その3
2️⃣ 時間割や連絡ノート・お便りを見ながら、明日の準備ができるように
なる。 【解説】
現在の小学校では、時間割だけを見て明日の準備できません。毎日のように時間割変更があるからです。連絡ノートやお便りなど複数の情報を読みこなして、準備する必要があります。
その他、月曜日に決まって持っていく「給食エプロン」や「上靴」があります。また、特別に持ってこないといけないもの、例えば工作用の牛乳パ
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備 その5
2️⃣ 時間割や連絡ノート・お便りを見ながら、明日の準備ができるようになる。 【育て方】
⑵ 書いてあることを見て、その指示通り動くこれを育てる「いい方法」は、2つあります。「お使い」と「クッキング」です。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備 その6
【育て方】
⑶ 複数の情報を組み合わせて正解をする
これを育てるには、次の2つの方法をお勧めします。なぞなぞとブロック遊びです。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備 その8
3️⃣ 筆記用具の準備ができる 【育て方】
発達に凸凹があるタイプの子どもは、えんぴつを削ってこないことが多いです。理由は3つあります。
1.えんぴつを削る方法知らない。
・・・親が教えていないか、親が削って上げていた。
2.できるが、面倒くさいからやらない。
3.単に忘れている。
だから、6歳までに、次の3つのことを育てておく必要があります。
1.
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 1 家庭での学習準備 その9
4️⃣ ランドセルへ、教科書、ノート、ふでばこなどをきちんと詰め込むこと
ができる。 【解説】
ランドセルに、教科書、ノート、ふでばこ、連絡袋、連絡帳を詰め込むのは、案外難しいことです。視覚が発達してこないとなかなかうまくできません。ある一定の枠の中に、ものをきっちりと収めるスキルが必要です。
そのスキルは、学校で多用されます。子どもが個人ですることには、次の3つがあります。これがで
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 2 登校から、1時間目までの過ご し方 その2
1️⃣ 持ってきたものを片付ける。 【解説】
・宿題と提出物を出す。
・机の中に教科書などを入れる
・机の横に体操服、赤白帽などをぶら下げる
・ロッカーの水筒を上に置く
・給食袋を教室の横にぶら下げる
・ランドセルや手提げ袋をロッカーに入れる
1年生になると、登校してから1時間目までに、こんなにたくさんのことをやらないといけません。もちろん、5月末を目処にできればいい
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 3「チャイム」と「時計の見方」 その1
この項目には、2つの補助項目が付いています。まず、それを紹介し【解説】します。
1️⃣ チャイムと共に行動することの意味とその大切さを知る。
【解説】
小学校は、自立にむけて育てていく方針があります。そのため「自分で時間を見て行動すること」を求められます。しかし、各自が時計を持つのが難しかった慣習が残っていています。つまり「時計を持っていないので、チャイムで時間の変わり目を知らせます
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 3「チャイム」と「時計の見方」 その3
2️⃣ チャイムの補助として、時計を読めるように指導する。どこにあるか
、いつ見るのかも覚える。【育て方】
数字を覚えているのでデジタルでいいかと思わないで、アナログの時計も教えて教えていきましょう。その理由は、2つです。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 4 休み時間の過ごし方 その3
2️⃣ チャイムが鳴る前に時計を見て行動し、次の時間の準備をして座って先生を待つ。 【育て方】
Ⅰの2や3で、「登校してから先生を待つ方法」や「時計を見方」の
【育て方】については書きました。その記事を参照してください。
一つだけ付け足しておきます。「教科書とノートを時間割通りに並べて、机の中に入れておく」を育てるための方法です。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 4 休み時間の過ごし方 その4
3️⃣ 長い休み時間の過ごし方を知る。 【育て方】
「友達に一緒に遊ぼうと誘うスキル」と「ルールを守って、最後まで楽しく遊び切るスキル」を育てるためには、大人と遊ぶ必要があります。大人が2つのスキルを育てる意識を待って、遊んであげることです。大人と遊べないのに、子ども同士ではなかなかうまく遊べません。