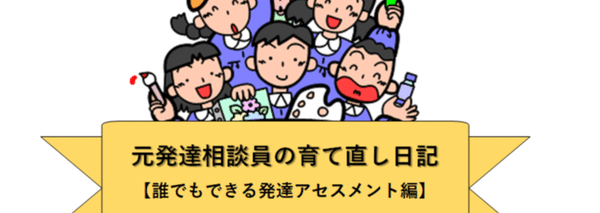やまと たける
一番書きたかった、発達に凸凹のある子どもの育て方の《0歳から3歳》を再掲していきます。最初の頃に書いた記事なので、書き直しつつ再掲します。その間に「ハヤカワ・ポケミス完全収集」という記事や、難航している太極拳の記事(少しずつ書けてきました!)なども挟んで掲載していきます。
最近の記事
- 固定された記事

育て直し 1988年 1月12日(火) 2歳3ヶ月 今していることに満足させて場面転換するか、次に興味あるものを持ってきて、場面転換するかの2つの方法がある
【日記】 最近、りんごなど「お父さん、これ食べ」と気を使って勧めてくれたりする。👍 とてもうれしい。 失敗したときに、「ごめんね」が素直に言えるようになった。👍 「これしてから、あれしよう」ともよく言う。👍 だから、自分で場面切替ができる。「~してから~する」と場面切り替えにずっと取り組んできたことが、やっと実ってきたようだ。 数字が「4」まで理解できている。だから、ブロックや自動車、チョウチョなどいろいろなものを4つまでよく数えて遊んでいる。👍 梓は、よく歌