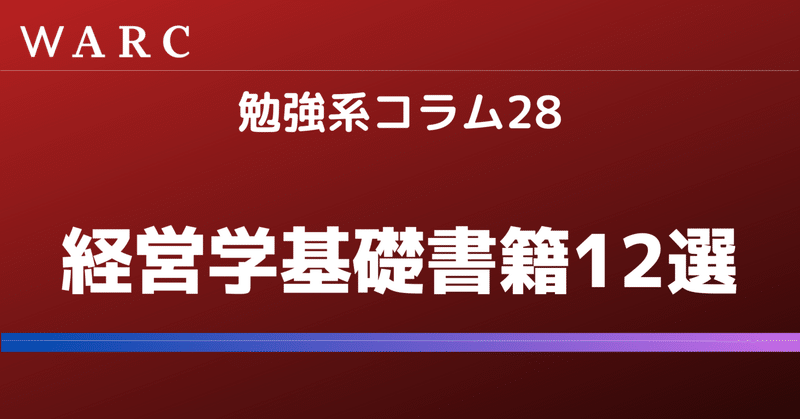
【勉強系28】ビジネスマンが経営学を学ぶ際に読んでおくべき書籍12選(書籍紹介)
【SYNCAオープン!】
経営管理部門・バックオフィス特化型の転職サイト「SYNCA」(シンカ)がオープンしました😁
皆様是非ご活用ください!
はじめに
今日も書籍紹介です😁
世の中もある程度落ち着いては来ましたが、まだまだ外出は控えないといけない時期だと思うので、ここで一つ気合を入れて、学問に勤しんでみましょう!
今回は経営学系の書籍を12冊ほどご紹介させていただきます。
ここ数年いろいろあって、社会が不安定になってからというもの、社会人のMBA(経営学修士号)の人気が爆発しているようで、倍率も高くなっているようです。
国内MBAにどこまでの価値があるかは未知数ですが、経営学を学ぶこと自体は強く推奨したいと思っています。
ただ、いきなりMBAに入ったとしても、下の方の大学院だとほとんど何も学べずに終わります😱
2年かけて入門書籍数冊分の知識しか学べないところもあるので要注意です。
社会人が集まってあまり意味のない雑談をして終わる授業等もありますから、どうせ学ぶならハイレベルの大学院に行くべきでしょう。
一方で、ハイレベルの大学院だと、経営学基礎はすでに頭に入った状態であることを前提に講義が進んでいく傾向があるので恐ろしいところです。
特に国立のMBAはその傾向が強いので、もし京大・一橋・筑波・神戸などの名門MBAに行こうとしている方がいれば、ここで挙げた書籍くらいはサクッと読みこなしておくことをオススメいたします。
その上で、海外の権威ある経営学者の書籍にも目を通し、概要を理解した上で入学した方が得るものも大きいと思います。

【初級編】
初級編は、大学の学部レベルの書籍をいくつかご紹介します。
ここでご紹介する書籍に記載されている内容はある程度深く知っていた方が良いと思います。
そのため、初級編で学んだこと、出てきた理論は、原典を読むようにすると良いです。
なお、MBA等に行く予定がない方については、初級編だけで十分ではないかと思います。
1.大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる【図解】
2.大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる【文庫版】
こちらの2冊は同じ著者の同じタイトルですが【図解】の方はフルカラーで図が非常に多く、楽しんで読み進めることができます。
そのため、文字を読むのが苦手な方にはちょうどよいかもしれません。
一方で【文庫】の方は、基本的に白黒で、解説もある程度あります。
その分安いです。
どちらも経営学の基礎的なところをざっくり学ぶことができます。
東大の有名な経営学者である高橋先生が書かれた書籍なので安心してお読みください😁
※高橋 伸夫 教授:東京大学大学院経済学研究科教授
3.今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」
こちらの書籍はちょっと変わったタイトルになっていますが、初学者にとっては逆にありがたい書籍だと思います。
著者の佐藤准教授は防衛大学校で教鞭をとっていますが、防衛大学校は自衛官を育てる機関なので、経営学に興味がない学生が多いのです😱
そのため、授業や言葉に工夫が必要で、その苦労の集大成がこの書籍なのだろうと思っています。
そのため、他学部の出身者でも読みやすい内容で書かれていて、身近な例で経営学の基礎が学べるようになっています。
佐藤 耕紀 准教授:防衛大学校 公共政策学科 准教授、北海道大学(経営学博士)
4.ゼミナール経営学入門(新装版)
こちらの書籍は、経営学部のゼミ用テキストとして指定されることもあるくらい有名な書籍です。
第3版が出て長いこと改定されていなかったのですが、ありがたいことに2022年3月に新装版が出ました。
しかし、新装版(ソフトカバーになって安くなった)というだけで、中身は変わっていません(笑)
記載内容は古いままですが、今でも経営学をこれから学ぼうという方にとっては最適な入門書となっています。
幅広い記載内容で、かつ、ある程度詳しく載っているので全体を学びたい人にとっては有益な書籍だろうと思います😁
著者は伊丹先生と加護野先生です。
伊丹 敬之 学長
国際大学学長
元一橋大学商学部教授
カーネギーメロン大学経営大学院(Ph.D)
加護野 忠男 教授
神戸大学社会システムイノベーションセンター特命教授
元神戸大学大学院経営学研究科教授
神戸大学(経営学博士)
5.1からの経営学<第3版>
4.でご紹介した「ゼミナール経営学入門」は内容としては2003年頃に書かれた内容なので若干古い部分もあります。
もし、最新版の入門書の方が良い!という方がいれば、同じ加護野先生(共著・編集)が書かれた本書を読むと良いと思います。
2021年に出版された本です😁
ただ、共著なので様々な先生が各章を担当なさっているタイプの書籍です。

【中級編】
続いて中級編です。
このレベルになってくると、学部レベルを超えてMBAで学ぶ内容も含まれてきます。
ただ、私が思うに、MBAに入学する前に、MBAで学ぶ範囲は一通り学んでおくべきだと思っています。
そもそも、上位の国内MBAに行くレベルの人たちの一部(1割くらい)は、最初から博士号を取るつもりで入学してきます。
そういう人たちは、全ての科目で成績上位者になろうとしますし、そのまま博士後期課程又は海外大学院に進学します。
そういうハイクラス層は、大学院修士課程で学ぶ程度の経営学は既に修めた状態で入学してきます。
上位校に行くならそのくらいの学力があって然るべきだと思いますし、MBAで良い成績を取るには最低限そのレベルに到達していないといけません。
そうでないと、授業で習うこともチンプンカンプンになりますし、レポートや課題をこなすことも難しくなります。
博士課程に進学する又は海外大学院に留学する場合、GPAが4.0(満点)に近ければ近いほど良いので、できれば中級編までは軽く読みこなしておくことをオススメいたします。
なお、中級編の書籍の内容は簡単です。
ビジネスマンであれば比較的容易に読みこなせると思いますし、数日で1冊読めると思います。
重要なことは、これらの書籍に書かれている基礎的な理論をどこまで深く理解しているかなので、取っ掛かりとして活用してください。
自分がMBAで研究したいと思っている領域の理論は別途深めておくことをオススメいたします。
6.ビジネスマンの基礎知識としてのMBA入門
7.ビジネスマンの基礎知識としてのMBA入門2 イノベーション&マネジメント編
8.MBAのアカウンティングが10時間でざっと学べる
9.MBAの経営戦略が10時間でざっと学べる
上記4冊はすべて早稲田ビジネススクール(通用WBS)又はその教授が書かれた書籍です。
WBSはおそらく今では日本でトップクラスに人気があるMBAで、毎年多くの人が受験し、散っていきます😱
倍率でいうと3~4倍くらいだと思っていただければよいかと思います。
舐めた状態で受験すると面接でボコボコのボコにされます🤣
早稲田の教授陣は実務でも活躍なさっていた外資コンサル出身者が多いことに加え、研究者出身の先生もバリバリの論者なので面接が鋭いことで有名です…。
心に深いダメージを負って二度と受けたくないという方もいるほどです。
中級編と書かれていますが、先生方からすると入門書ですらないというレベルなので、確実に読みこなしておきましょう。

【上級編】
最後に上級編です。
ここでいう「上級編」とは、普通のビジネスマンにとっては上級編というだけで、MBAを目指す人にとっては初級編だと思います。
ここまで紹介してきた書籍は全部「ビジネス書」の範疇だと考えることもできるので、ここからがやっと経営学らしくなってくるという感じです。
大学院で真面目に研究を行うつもりの方は、ここに書かれている書籍からスタートして、そこからどんどん論文に広げていくことをオススメ致します。
殆どがアメリカの論文を読むことになるとは思いますが、本気で良い成績で修士号・博士号を取ろうと思うのであれば頑張ってくださいませ👍
10.世界標準の経営理論
11.考える経営学
12.ケースに学ぶ経営学 第3版
このレベルになってくると、やっと『学問だなぁ!』という感じが出てきます😁
MBAにも様々な種類がありますが、大きく2つの種類に分かれます。
一つが実務的なケースメソッドを重視する専門職大学院で、
もう一つが研究を主体とする研究者養成大学院です。
専門職大学院では、修士論文は比較的簡易なものでよく、誰でも修士号が取得できるような仕組みになっています。
一方で研究者養成の大学院は、修士論文でもしっかり審査が入りますし、ガッツリ指導されます😱
社会人が通える夜間のMBAはほぼすべてが専門職大学院です。
しかし、その中でも、早稲田等の私立は比較的簡易な修士論文でよいので実務側に寄っていますが、筑波・一橋は結構厳格な審査の上で修士論文を書き上げないといけないので、研究者養成側に寄っています。
それぞれの大学院で特色があるのでよく調べたほうが良いです。
もちろん、プロフェッショナルの中では修士論文をしっかり書いている人の方が評価が高いです。
上級編の書籍は、専門職大学院(簡易な修士論文の学校)に行こうと思っている方にとっては単に読むだけで十分だと思います。
理解しておけばそれで足りるかなと。
一方で、専門職大学院の中でも研究者養成側によっているところに行こうと思っているのであれば、読むだけではちょっと心許ないかもしれません。
上記の上級編を読んだ上で、自分が2年間でまとめようと思っている修士論文のテーマに関係する理論については原典を読み込み、現在までの先行研究を把握し、研究計画書内に落とし込めるようにしておくべきかなと思います。
おわりに
今日は大きく「経営学」という括りで基礎的な書籍を12冊紹介させていただきました。
30代のビジネスマンにとっては非常に勉強になる書籍ばかりだと思うので、お休みの日に読んでみてはいかがでしょうか😁
結構面白いですよ。
次回は、経営学の中でも経営戦略に特化した書籍を紹介してみようと思います。
お楽しみに!
では、また次回🎵
【お問い合わせ】
この記事は、株式会社WARCの瀧田が担当させていただいております。
読者の皆様の中で、WARCで働きたい!WARCで転職支援してほしい!という方がいらっしゃったら、以下のメールアドレスにメールを送ってください😁
内容に応じて担当者がお返事させていただきます♫
この記事に対する感想等もぜひぜひ😍
【WARCで募集中の求人一覧】
【次の記事】
【著者情報】
著者:瀧田 桜司(たきた はるかず)
役職:株式会社WARC 法務兼メディア編集長
専門:法学、経営学、心理学
いつでも気軽に友達申請送ってください😍
Facebook:https://www.facebook.com/harukazutakita
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/harukazutakita/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
