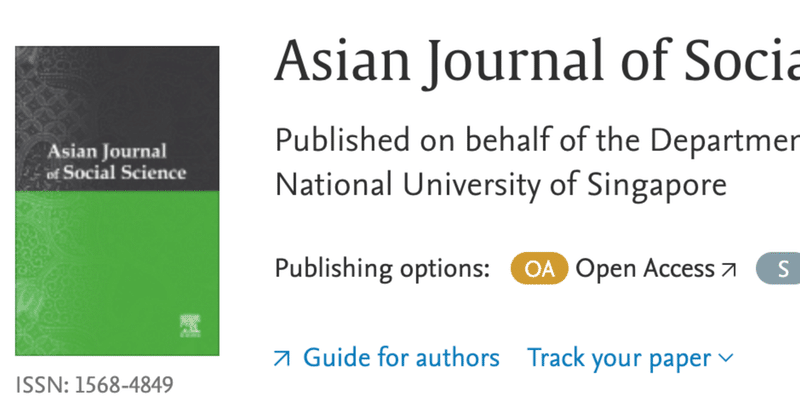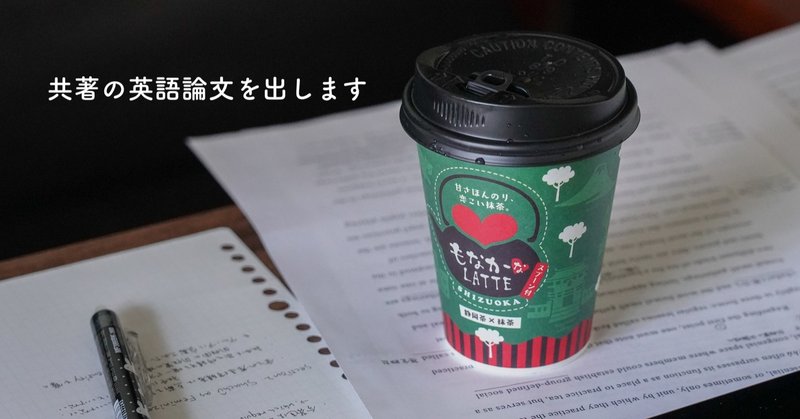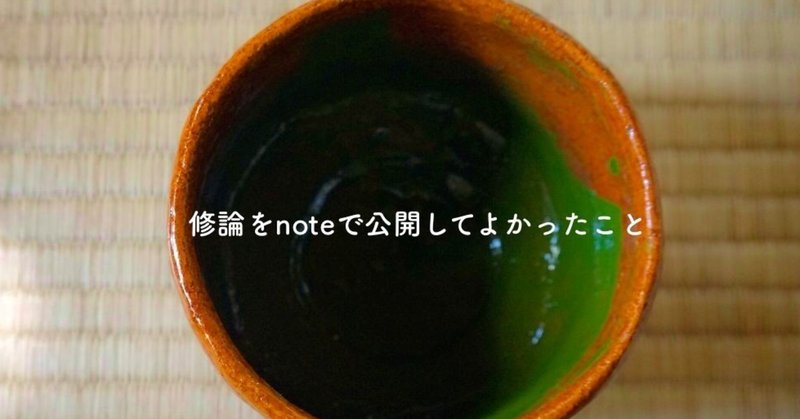- 運営しているクリエイター
#論文
共著の英語論文が公開されました。
大学院時代の指導教官との共著論文が先日ようやく公開されました。
論文の概要掲載されたのはNational University of Singaporeが発行する『Asian Journal of Social Science』で、
タイトルは「Body-mind discipline for life: The non-conformity of contemporary Japanese t
共著の英語論文を出します
ニュートンの三大実績は全てペスト禍の18ヶ月で為されたらしいが、論文を書くのはいい「おうちじかん」の過ごし方だ。
たとえば過去のGW、2017年は修論締め切り前(6月卒業)で排泄以外は部屋から出ず、2018年は修論をnoteにアップし続けるだけで連休を終え、2019年は祝日休みではない職場で普通に連勤だった。
今年は尻から根を生やしつつ論文を書いていたが、世界中の人が一緒に自粛してくれていたの
修論をnoteで公開してよかったこと
修論をnoteで公開するまで修論が完成したのは去年で,学術誌に載せるように指導教官に勧められ,査読が通って2018年の春に出版されることになった。
いざ春になると,出版された学術誌3部と,自分の記事部分だけが印刷された抜き刷り30部が送られてきた。
「30部も!」と思ったが,ふと我に返る。
学術誌は全国の大学図書館などに置かれるはずで,興味のある人には読まれるはず(現代の一般茶道修練者の研