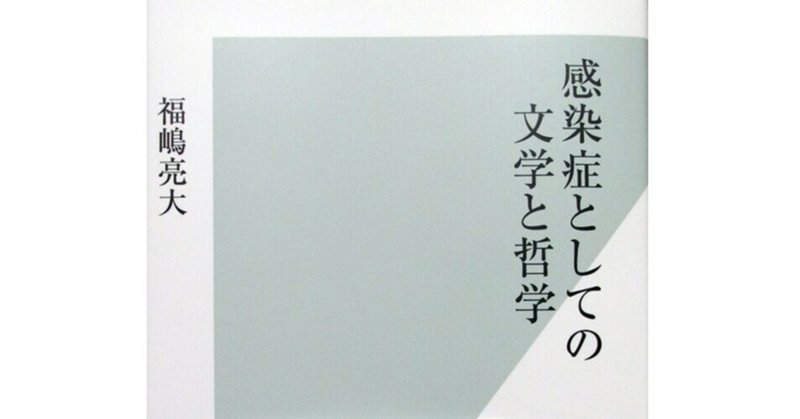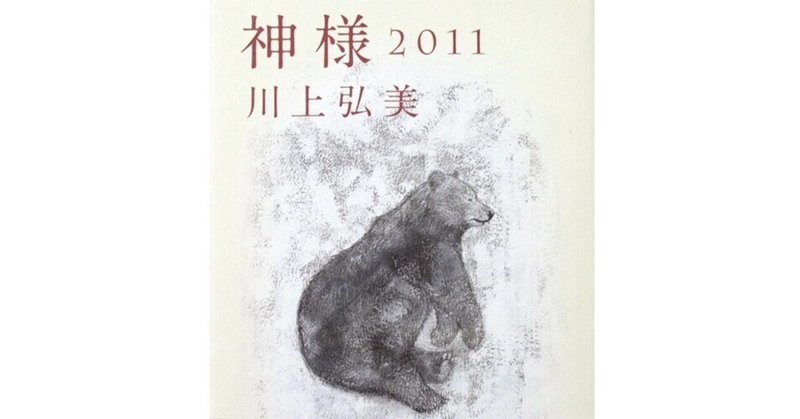- 運営しているクリエイター
2022年3月の記事一覧
『いつもの言葉を哲学する』(古田徹也・朝日新書)
2021年12月発行。ウィトゲンシュタインについての分かりやすい本を書いた人だと後で気づいた。言語についての堅い話がお得意である。が、これは至って分かりやすい。「いつもの言葉」なのだ。なにげなく広く使われている言葉遣いだが、ふと考えると、何かおかしい。違和感が消えない。そんな言葉があるものだ。私は実はかなり多い。こだわる必要のない場面もあるし、事実使っているのだが、何か引っかかる。抵抗がある。そん
もっとみる